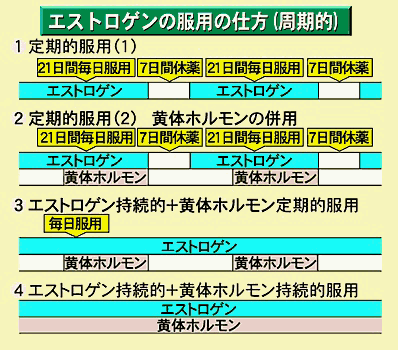男性に更年期障害はないの?
女性のものと思われがちの更年期障害ですが、けっして男性も無縁ではありません。男性も加齢に従って男性ホルモンの分泌が減っていくうえこの時期は男性もストレスが増える時期です。女性ほど急激な変化が見られないので見過ごされがちですが、女性と同じような更年期障害の症状がみられれば、専門医に相談しましょう。
更年期障害の治療はどうするの?
ホルモン療法
更年期障害を抑えるエストロゲンと、エストロゲンの働きを抑える黄体ホルモンを用いた治療が行われます。ホルモン療法は、のぼせ、異常発汗、冷え症、肩こり、腰痛、関節痛などに有効で、高齢者になると一層進むコレステロールの増加による動脈硬化や心臓の病気の発病,骨粗しょう症の予防にも有効です。
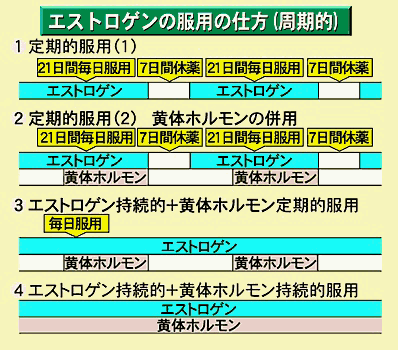
1,単独投与法
エストロゲン(女性ホルモン)のみを21日服用し、その後7日間休薬します。この方法はすぐに効果が現れるのですが、エストロゲンのみを長期に服用すると、子宮がんの発生する危険性があり、あまり長くは行われません。
2,周期的投与法
エストロゲンを28日間使用し、そのうち後半12日間はプロゲステロン(女性ホルモン)を併用します。その後7日間休薬します。この治療はもっとも広く行われている方法です。
この方法は、女性ホルモンを補充しはじめてから30日目くらいに月経様の出血が起こります。年長者では出血を嫌うため、閉経後10年以内の、比較的若い年代に向いています。
3,エストロゲン持続的+黄体ホルモン周期的投与法
エストロゲンを持続して服用する一方、黄体ホルモンを定期的に服用します。この治療は重症な人に行われます。
4,持続的併用投与法
エストロゲンとプロゲステロンを毎日、持続的に併用します。
この方法は、すでに子宮が萎縮し、女性ホルモンに対してあまり子宮が反応しない、閉経して10年以上たった年代に使うので月経様の出血は起こりません。
たとえ少量の出血があってもいずれとまります。
ホルモン療法の副作用
経口薬では胃腸障害肝機能障害が現れることがあります。
また経口薬、貼り薬ともに、血液の粘度が高くなり血管詰まりやすくなることがありますので糖尿病で薬を使っている人、血栓のできやすい人は元の病気を悪化させる恐れがあり、行われません。
5年以上使用を続けている場合は、乳癌や子宮体癌の発生率が高くなると言われています。
1年に1回はホルモン療法の影響をチェックしてください。
非ホルモン療法
非ホルモン療法には、薬物療法とカウンセリングがあります。薬物療法は、頭痛、不安、イライラ、不眠、うつ状態、手足のしびれなどに有効で、抗うつ剤や自律神経調節剤漢方薬が用いられる事があります。薬物に頼る事なく、カウンセリングを受け、生活に張りや目標を定め、自信を持つだけで、症状が軽快する人もいます。
.gif)
.gif)