

 イラスト 井上奈緒子
イラスト 井上奈緒子
新自由主義批判の、アメリカを素材にしたすさまじくリアルな一冊である。ニューヨーク州立と市立の両大学に学び、アムネスティのニューヨーク支局員、米国野村証券を経ている著者の具体的なアメリカ報告は、読む者の心にヒリヒリと痛みを与え続ける。二一世紀に生きる者に、このようなことでは人類の未来は暗いぞとのメッセージを与えるものとなっている。プロローグはサブプライムローンの本質から入る。カードも持てない貧困層に住宅取得の夢を与え必死で高利のローン支払をさせる。この債権の担保証券にヘッジファンドや銀行が目をつけ、そこに投資資金が集まった。貧困層が破産などで手を挙げれば崩れるシステムであり、現に崩れて担保証券の格付けが下がり世界的金融危機が来たが、著者が書き、読者に気づかせる点は、アメリカの金融システムの基礎の一つが貧困者を食い物にする性格のものである点である。一章は肥満と貧困の関係。貧困層は家庭でも学校でも一番安いジャンクフードしか食べられず太ることのすさまじい実証である。二〇〇五年のハリケーンカトリーナ被害の被災者がみんな太っていたことを思い出す。ルイジアナ州ニューオーリンズが最貧困地域である。二章はそのカトリーナの被害が人災であった実証である。私が一九九五年の阪神淡路大震災時の研究で、前年のカリフォルニアノースリッジ地震での活躍を注目した強力な権限と予算を持ったFEMA(Federal Emergency Manage-ment Agency)は、二〇〇一年ブッシュ政権の発足時にすぐさま変質させられ、弱い一民間団体化され、予測されたルイジアナ洪水のための堤防強化の資金をカットした。被災者は全米に棄民され今も復興していない。黒人とともにヒスパニックも棄民されている。いい就職先は軍しかない。三章は医療保険がなく、高額な医療費で破産していく中間層が貧困層に転落して行く実態である。医療過誤、過誤訴訟の悪循環でますます医療は高額化している。製薬会社が跋扈している。四章は修学困難、修学ローンからの脱出、就職困難、そして医療保険をもちたい若者をねらう軍の勧誘実態とほとんど詐欺のような軍隊での扱い、イラク送りなどの実態である。五章は貧困層が民間の派遣として戦争に送り込まれるおそろしい状況である。彼らの戦場の死は、軍人でないから統計にすら出ない。エピローグで著者はこのアメリカの状態に日本が近づく可能性と、それを防ぐための報道の自由の必要性を強調する。本書を読み、そして深く考えるならば、悪化する現実への抵抗は澎湃として読者の心に湧いてくるであろう。日本人必読の本である。★★★
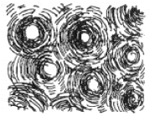 中島聡「おもてなしの経営学 アップルがソニーを越えた理由」(アスキー新書、2008年)。
中島聡「おもてなしの経営学 アップルがソニーを越えた理由」(アスキー新書、2008年)。
アップルとマイクロソフト、グーグル、ソニー、任天堂などを比較検討しながら、いまアップルがuser experience(これを「おもてなし」と訳して本書のキーワードとする)の面で抜きん出ているとし、その根拠を描き出す。マイクロソフトのOSの開発に長く関わっていた著者が、アップルが当面すごいというのだから、一貫したアップル党である私など興味津々と言うところである。マイクロソフトはOS(ウインドウズ)とウェブプラウザの両方を制覇していたのに(アップルは三%程度のニッチ商品になりさがっていた)、熱烈なファン度において従来からアップルに負けており、社名をアップルコンピューターからアップルに替えipodで息を吹き返したアップルに、iTunesでデジタル・ミュージック・ビジネスでのリーダーの座を奪われた。ipod nanoにシリアル番号をつけていることも顧客の気持ちを考えてのこと。ウインドウズのサービスは床屋の満足だという。つまり床屋としての誇り高い髪型にして客を送り出すが、客がそのときどのような髪型にしてほしいかを考えていないという意味である。ソニーは出井伸之というマーケティングの天才を社長に据えていたのに、ハードウェア・エンジニアの発想が強すぎて床屋の満足に陥って、ウォークマンというすぐれたブランドをまたたくまにアップルに破壊された。アップルにはマーケティングのスティーブ・ジョブスが再加入して指導した。ソニーと対照的な日本企業はゲーム機の任天堂で岩田聡社長の子供たちの目線に立った発想、その先端のソフトWiiは有望であろうとする(この著者の予言は的中したようで、私がこの本を読んでいた四月二五日の各紙によれば任天堂がWii効果で二〇〇八年前期の営業益が二・二倍になったと報道している)。そして当面のアップルの好調を支え持続するすごい商品、芸術品がiPhone(タッチパネルのフルカラー液晶携帯電話機能のほかipodとしての音楽動画再生、ダッシュボード・ウィジェット、インターネット環境を備えたている綜合装置)だそうである。加えてApple TVが改良されていくと地上波デジタル化などの税金食い方式でなく、すでに普及している光ファイバーを使いテレビ、コンピューターを一体となったサービス(テレビ番組、音楽・ビデオの配信)が可能となるというのである。つまりipodにはまるとアップルのここまでの戦略に顧客は熱烈に乗ることになるであろうというのである。すごい話である。まさにマックワールドといえるであろう。本書には後半、ITビジネスに関する旬の論客との対談がある。中でも興味あふれるのは私が本誌六五号で評論した「ウェブ進化論」の著者、Google派の梅田望夫とのそれである。二人で欠点をみつけようとしているが、まだ決定的なものはなく、帝国のようなGoogleが世界の優れた小さなベンチャーを買収し、いまのところますますおおきくなっている(Google自体がシリコンバレーのようになっている)とのことである。私の理解度には限界があるが、実におもしろいITビジネス論であった。★★★
1976年に創刊され、シティボーイのためのライフスタイルマガジンとして、ヌードと劇画は登場させないとして一世を風靡した雑誌POPEYE(平凡出版、マガジンハウス)を、私は当時全く寄せ付けなかった。私が三〇歳であり同誌がめざした読者層からするとやや薹(とう)が立っていたのと、同誌の編集方針である軽スポーツでカラダを楽しませたり、物欲をかっこよく満足させる路線の対極に私が立っていたことが原因である。私が読んでいた雑誌は「朝日ジャーナル」であり、「世界」、「前衛」、「文藝春秋」、「ビッグコミック」であり、やっていたのは労働事件の弁護、不正行政追求弁護であった。しかし今、歴史的視点で同誌をその発行の中心にいた著者の筆で鳥瞰すると、実に重要な雑誌だったことが理解できる。サーフィン、スノボ、スキューバ、VAN、デカラケ、バイク、超合金ロボット、吉田カバンなどを流行らせ、アメリカ西海岸への日本青年の大進出を組織した。また文芸、音楽、映画評論、ファッション、広告、デザイン、建築、写真、コピーの面で著名人となる人士(安藤忠雄、阿久悠、荒木経惟、小林信彦、原田真人、今野雄二、マドンナ、アイルトン・セナ、鈴木亜久里など)を育てた。すぐ近くにいたビル・ゲイツの開拓には失敗したと言っている。この雑誌は戦後民主主義を、消費的大衆主義に変貌させようとした立役者であったと思われる。編集長木滑良久の存在も大きい。反米主義から親米主義、物欲主義への若者の転換に果たしそうな役割、現に果たした役割を見て、アメリカ政府上層部、CIAからの援助があったと著者は推測している。ソニー、ホンダをはじめとする日本の大企業も広告の形で全面協力した。CIAエージェントだと言われた読売新聞社社主正力松太郎もPOPEYE発刊に協力している。電通との結びつきも強い。ナチスグッズ、ソ連の武器を礼賛するなど、世界の民主主義的常識からは噴飯ものであった。しかし、本書はこれらの内容を魅力的な筆致で書き、飽きさせない。POPEYEのような特殊な雑誌の歴史的意義をリアル且つ内幕的に書いたものとして価値ある作品である。★★★
非常に優れた著作が世に出た。ラジオが戦前の日本社会に有していた異常な影響力を著述したうえで、太平洋戦争の始まりも、進行も、終戦(混乱防止)もすべてラジオの力によるところが大きかったと結論づける。戦前日本、ラジオ台数では世界五位で、人口一〇〇〇人あたりでは二五位であったが、家屋が開放的で、家屋内では家族で一緒に聴き、家屋外、近所にラジオ音声が流れることを日常としていた。運営は日本放送協会だけで、統制の強いものであった(米仏では民間放送が大いに発達した)。著者は世界最強のマスメディアだったと結論づけている。このような基本条件のもとで、軍部がこれを大いに利用し、東条英機もだがとりわけ英語力も抜群で演説のうまかった松岡洋右はラジオで諸外国との交渉、国際連盟脱退模様を放送させ、戦意を煽り英雄となった。敗色濃厚になった時、天皇をラジオに出させて終戦の宣言をさせようと各方面を説き、それを妨げるクーデターも起こったがうまく軍により鎮圧させ、「玉音」放送を実施し、混乱を防止した立役者が情報局総裁下村宏であった。法的終戦は八月一四日のポツダム宣言受諾で、外国とのミズーリ艦上での調印は九月二日であるのに、誰でもが天皇の放送のあった八月一五日を終戦記念日と認識し、その後いくつかの法律でもこの日を終戦日とし、最終的には一九八二年、この日を「戦歿者を追悼し平和を祈念する日」とすることが閣議決定された。一五日の正午の放送は三七分半続いた。天皇の声はわずかな時間で、あとはアナウンサーが詔書、内閣告論、ポツダム宣言などを読んだ。一億総玉砕を叫んだラジオから、天皇の声が流れ、終戦か否かと言う点では何の混乱もなくマッカーサーが驚いたように終戦処理と占領が始まった。著者はラジオのこれらの功罪を事実で丹念に追っている。貴重な書物である。★★★
内山節「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」(講談社現代新書、2007年)。
高卒の哲学者で東大をはじめさまざまな大学で教鞭をとり群馬県上野村と東京を往復する著者の力のこもった読み物である。キツネにだまされたと言う話がなくなったのは一九六五年頃であると調査をとおして認識した著者は、まずその原因を人間側とキツネ側から分析する。高度成長期の人間の変化、科学認識の優越、情報化(生活における自然とのコミュニケーションの消滅)、受験教育化による伝統教育の駆逐、家の断絶と死生観、自然観の変貌(やがて自然に帰るという精神の消滅)、人工林の増加、焼畑の消滅による老獪なきつねの消滅!、などと。これらを基礎にして、歴史学、哲学の基本的概念を解説する。私があらためて勉強になったのはヨーロッパの自然観(人間の知性による文明が自然を切り開く)と日本人の伝統的自然観(生まれ、穢れてやがて自然に帰り清められる、その自然が神であり仏であるという伝統意識、民衆意識)の違いである。★★★
若い密教僧(三二歳)であり写真家でもある著者の渾身の一作である。諸外国を多く撮り続けている著者が、我が国の過疎の村を訪ねている。文もいいがやはり写真が秀逸。下手な写真を何十年も撮り続けている私のようなヘボからみて、なぜこのような深い味わいの写真ができるのか謎である。そこで、わが編集次長の香取が関学写真部に属した経験を持つので聞いてみると、まずいい三脚を買い、じっくりと撮ればいいのではないかと言う。いい三脚は容易に手に入るだろうが、じっくりが私には難しい。加えてじっくりというのは心の持ち様をも意味するだろう。一〇年以内に四二三の集落が消滅するのではないかと著者は言う。語られ撮られているのは、経済原理には適用しない農作業、水田、棚田、漁業、そして小さな集落、墓、古い小学校、そしてきびしい自然、美しい自然、老いである。そこに生きている人に想いを語らせ、それ以上に何も付け加えない。ノンフィクションの叙情である。★★★
保母武彦「『平成の大合併』後の地域をどう立て直すか」(岩波ブックレット、2007年)。
政府が誘導し自治体の数を三二三二から一八一七に減少させた。そしてそれを財政面で理由づけたのが「三位一体の改革」である。国から地方への税源の移譲、国庫補助負担金の改革、地方交付税の改革の三位は、実際には、東京に代表される大都市は税源は集中し豊かだが、過疎の地域には財政を逼迫させる効果しか生まない。本書は、わかりやすい論述で、これらの実施の生け贄に使われた夕張市、模索する佐渡市、住民とともに敢然と自立度を高める矢祭町等の事例を分析して、地域立て直しを励ます。貴重な本である。★★★
安保徹「自分ですぐできる免疫革命」(だいわ文庫、2007年)。
良い本にめぐりあった。人並みに歳をとってくるとこのような本が実に嬉しい。私の哲学というか人生観として、薬、サプリメント、化粧品などは体にとって異物であるから、できるだけ利用しないことにしてきていたが、そのことを励ましてくれるとともに、さらに徹底させてくれ、かつ生活態度を改良させてくれる貴重な内容である。著名な免疫学者として、一番すごい話から始める。これでかなりに衝撃を受ける。現代社会はガンにかかりやすいが、手術、放射線、抗ガン剤の三点セットが一番いけない、免疫力を高めてガンと闘うのが重要であるというのである。三点セットは最も免疫力を弱め、体を弱め、ガンに負ける要因となる。免疫力を高めるとは次のようなことである。過度はだめだが一般にはリンパ球、顆粒球が多い方が良く(リンパ球は顆粒球では処理できないウイルスなど小さな異物の処理を担う)、のんびりして楽観的な方がよい(病気は必ず直ると自分を信ずる。体を動かして、笑ってほがらかに生きる)、頑張り屋は交感神経が優位で、リンパ球を増やさない。副交感神経優位にするには深呼吸しよく噛んで食べる。悩み、ストレスで自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが乱れると免疫力は低下する。免疫力を高める基礎体力としては、自分で食べられる、散歩できる、入浴できるという三点が目安と言う。
以下では項目ごとにまとめると次のようになる。
食べ物・食べ方=野菜抜きの肉はガンになりやすいが、野菜だけでは活力は出ない。玄米が最も良い(食物繊維が多い、生命体としての過不足がない)。高血圧は現在では塩分よりもストレス。キノコは消化しにくく消化管を刺激続けるので良い。お茶もコーヒーも飲み過ぎはよくない。少量の酢は排泄反射を促し、少量のショウガやニンニクは血流が良くなるので良い。体を動かさず食事制限すると血流障害になる。日本酒一~二合、ビール一~二本は副交感神経を刺激し百薬の長で、脳梗塞もむしろ少ない。休肝日は根拠がない。一〇本以下のタバコも問題ない。発ガン物質で発ガンする例は少ない
体の使い方=四十をすぎたら体を鍛えるより持久力を鍛えること。ウォーキング、ハイキングがよい。冷えが残らない程度の水泳は良い。ゴルフは楽しみなら良い。筋肉トレーニングは良い。温泉はカルシウム、マグネシウムが吸収できるから良い。体が温まる(リンパ球が増える)から良い。何度も一日に入るのは良くない。足を温めるのも良い。サウナも温まるから良いが体力の消耗は激しい。朝明るくなると起きる。七~八時間睡眠が良い。
心の持ち方=仕事など活力ある世界とリラックス世界のバランスが大事。歳とっても前者も大事。悲しみや怒りを反芻させると免疫力を下げる。笑いが良い。やりたいことだけをしていてもだめ。音楽でリラックスできるのは副交感神経を、激しいのは交感神経を刺激する。美術鑑賞は良い。無理のない時々の旅行は、適度の刺激とリラックスをもたらすから良い。
薬、病気=消炎鎮痛剤は使うな(血流を悪くする。あまりに痛いときは二、三日に限る)、睡眠薬、解熱剤、抗生物質も使うな。糖尿病、心臓疾患は働き過ぎが原因。漢方薬は排泄反射が良くなるので良い。便秘と下痢は便秘がより悪い。鍼灸は血流促進。整体に頼らず姿勢を良くする。ビタミンは不足が良くない。ボケは生きる必要があると意欲を持てば可能性は少なくなる。体温が三六度台が重要。★★★
北原保雄編「KY式日本語 ローマ字略語がなぜ流行るのか」(大修館書店、2008年)。
新書判である。その場の雰囲気、空気が読めない人のことをKYと皮肉る表現が流行っていて、なかなか面白いと思っていたところ、四〇〇近くこの種の言葉があるのだと聞いて、本書を手にしてみた。要するに隠語なのだが、それぞれの人間関係、年齢に応じて無数にあり得ることがわかった。当然と言えば当然である。何かの文章で理解不能のKY的用語が出て来た場合のための辞書として活用したい。★★
偶然に田中が最高裁により石原産業手形詐欺事件で有罪確定され収監されることが決まった日、注文していたアマゾンから本書が届いた。田中は元特捜検事で弁護士を経て裏社会と付き合い前科者になった。九〇年前後には私の周りのマスコミ人で弁護士になったばかりの田中のファンがたくさんいたことを思い出す。宮崎は元共産党員で早稲田時代、全共闘と闘ったが、その後雑誌記者を経て、裏社会と付き合い、三億円強奪犯人と疑われたことをきっかけに「突破者」として売り出した。この裏社会と通底する二人がバブル、司法官僚、裏社会の三つをテーマに、それらに関連する人物、企業の実名をふんだんに明らかにしながら対談するというので、関係者からは言うに及ばず、一般的にも注目された本である。しかし薄汚く、志低く、陳腐な内容であった。社会進歩や人の感性の陶冶とは関係のないものである。私にとって真新しいことは事件屋、暴力団、同和関係の氏名、事件の内容くらいであるが、そもそも裏社会に身を置きながら、上記三テーマと向き合ってみても、語られる内容を誰が信用するだろうか。引用もできない人物たちの対談というのは所詮無意味であり唾棄すべきものであろう。しかも宮崎のことはわからないが、田中に関して言えば、語っている内容はもう現在の一級の法実務知見ではないところがあわれである。★
心温まる市井の男女三人の物語である。良い芝居は、見終わって感動し明日へ勇躍突き進もうと思う作品、人生は辛いけれどがんばろうと思う作品、こう言う人々もいるのだ人生捨てたものではないなと思う作品の三種に分かれる、と私は思う。この作品は三番目の類型である。親切な大家にかわいがられて古物商を営む孤児でお人好しの小太郎、大家の娘で小太郎を幼い時からお兄ちゃんと慕う出戻りのめぐみ、小太郎の家を窺いながら塀から転落して記憶を失ってしまった男、大垣が闖入。小太郎家に居候しながら、めぐみとも交流していく。大垣は何をしに来たのかがミステリーである。このミステリーが徐々にわかっていく。小太郎は小学校時代、かわいい順子ちゃんと庭の木の根元にタイムカプセルを埋め、将来結婚しようねと誓い、その約束を四〇を過ぎる今も守って、めぐみが秋波を送っても全く気づかない。大垣の記憶が徐々に戻りわかったことは「悲劇」であった。順子ちゃんは大垣と結婚して、癌で死ぬ前に小太郎との約束を話し、小太郎の様子を見、自分のことを伝えて欲しいと頼み、大垣は見届けてくる約束をしたというのである。これだけの話である。観る者は、最終場面で小太郎と大垣が半ば泣きながらタイムカプセルを掘り当て、中から出て来たかわいい作文を読み聞かされながら思う。いい芝居だったなあ、いろんな場面でこの役者たちの名演は心に焼き付いて離れないなあと。何重もの二人の約束である。小太郎の中井貴一。ますます演技に磨きがかかった。映画「壬生義士伝」で映画俳優としての頂点を極め、以後主として演劇で名を挙げている。お人好しのコメディタッチが無類に巧くなっている。遊眠社出身の段田安則は日本の名優である。「贋作・罪と罰」、「ロマンス」などで達者ぶりを観た。京都出身だから関西弁が自然だ。この二人が劇団ふたりを旗揚げしている。モデル出身のりょうは、歯切れの良いセリフで魅力的だ。福島三郎劇作・演出である。★★★
見逃していたが、WOWOWで。野田英樹作演出であるから言葉遊び、語呂合わせが全篇を貫くが、この作品のは上品で大いに笑えた。キルは「着る」、「切る」、「kill」と掛けられて、物語の縦糸となっている。羊の国モンゴルの有名なテーラー、デザイナーの息子として誕生したテムジン(妻夫木聡力演)は、母(高橋恵子)から生まれたが本当の父は別にいる。父はファッション戦争で命をおとすが、父の開発した型紙を尊重し羊毛素材の服「蒼き狼」というブランドを立ち上げファッション世界の制覇をめざす。その途中で絹の国(中国)を攻めシルクという美貌の女に恋し、文字の読める側近の結髪(ケッパツ、勝村政信力演、好演)の援助で恋文を書いてもらい妻にする。バンリ(野田秀樹)という息子が生まれ、病弱だが才能豊かに育つうち、テムジンは息子に自分の地位を奪われるのではないかと疑心し、勢力を増して来た麻素材のパッチもの「蒼い狼」の征伐と息子自身を潰す目的で遠征に派遣する。バンリは行方不明となり、やがて「蒼い狼」が攻め込んでくる。バンリへのテムジンの仕打ちに悩み、ケッパツの優しさに魅かれシルクは彼の子を身ごもる。バンリも不義の子ではないかと疑うテムジン。ケッパツは処刑され、テムジンの味方はいなくなり、最期を迎える。今わの際に夢見る祖国羊の国は、母の羊水のように温かく、しっかりと蒼かった。生まれることも死ぬことも同じなのではないかと思わせる道行きは成功している。布を多用した舞台装置、ファッション性の高い衣装は華やか。モンゴル、中国の特性を皮肉っぽく盛り込みながら、いい作品に仕上がっていた。妻夫木は単なる二枚目でなく役者だ。★★★
チェーホフ(一八六〇年〜一九〇四年)の「かもめ」である。沼野充義東大教授の新訳を用意して原作に忠実に栗山民也が演出した。前号でチェーホフの生涯を井上ひさしが演劇化した「ロマンス」を評論したが、その演出も栗山だった。若き劇作家トレーブレフ(藤原竜也)の恋と挫折が縦糸だが、横糸は重層且つ複雑である。しかも時代背景がある。まず時代。チェーホフの死去した翌年にロシア革命が勃発する。要するに彼の生まれた年はナロードニキ(人民農村運動)が始まる直前だったが、その運動も鎮圧され、かもめが書かれた一八九五年は皇帝圧政の最後のあがきが激しかった。プレタリアートが形成され都市化され(モスクワが都市の象徴である)、やがて農村とプロレタリアが結束して皇帝を倒すのであるが、その直前の進行形の暗さが支配していた。演劇のかもめは一定規模の農村旧家出身のモスクワ女優アルカージナ(麻美れい)の華麗なモスクワ生活と湖のほとりの実家で劇作家をめざす息子トレーブレフ、二人の周辺の愛憎劇である。湖のかもめが地方を象徴し(しかも狩りで剥製になっている)、その環境から抜け出そうとする若者たちの憧れが都市モスクワである。都市で成功した小説家トリゴーリン(鹿賀丈史)は書き続ける重圧の中で地方生活に憧れてアルカージナの恋人となり、その彼にトレーブレフの想い人ニーナ(美波)は魅かれ、農村からモスクワに彼と女優業に憧れて出るが芽は出ず、死産の後トリゴーリンに捨てられ、心も病みみずからをかもめと呼ぶ。トレーブレフを想うマーシャ(小島聖)は恋破れて歳の離れた教師と結婚しアヘンに頼って後悔の日々を送る。その他すべてはこの短評では書けないが、入り組んだ人間関係が描かれ演じられる。暗い。結末も暗い。かもめと自らを呼ぶ売れない女優ニーナが自立して歩み出すのに対し、彼女を慕い続けて遂げられぬトレーブレフは母をはじめとする取り囲む環境に失望し破滅する。舞台装置は秀逸であった。正面から見た舞台そのものが斜めに切られ、遠近感が出やすいように作出され、手前は部屋で奥は庭と湖という風に狭い空間を最大限に奥行きあるものとして活用していた。文芸の欄で評論する黒川創「かもめの日」は、随所にチェーホフの「かもめ」を織り込む。★★★
作井上ひさし、演出蜷川幸雄、主演阿部寛、助演筆頭木場克己とくれば面白いことに間違いない、と思ったがそうでもなかった。作井上ひさし、演出蜷川幸雄の作品は「天保十二年のシェークスピア」(本誌六二号で絶賛)、「藪原検校」(私は木村光一演出のものしか観ていない。本誌三六号で絶賛)に続く三作目だそうである(三作とも初演は古い)。道元が開いた簡素な仏教の一つ禅宗(曹洞宗)に対する既成仏教代表の比叡山天台宗、それに帰依する朝廷、鎌倉幕府の妨害、道元の悟り修行のきびしさ(日本仏教に飽き足らず南宋にわたる)、悟り後も離れない懊悩(性欲への悩み)を描く。音楽劇でもある。井上作品の特徴である該博な歴史、仏教研究に裏打ちされた言葉遊び、蜷川作品の特徴であるコロス的集団劇、大胆な舞台廻し、スピード感はすべてそろい、役者も上述の二人のほか栗山千明、横山めぐみほか実に巧い人々が揃っている。しかし二級なのは、やはり脚本に問題があるのだろうと私は思う。道元の観る夢が現代とつながり、道元と二役の阿部が演ずる劇中劇で婦女暴行犯の中年男、彼に施される心理的、医学的治療という重要な設定がやはり違和感なしには観れないからであろう。笑って楽しみながら、心は空虚感が残った。★★
久しぶりに新感線芝居を観た。「阿修羅城の瞳」(本誌五六号=二〇〇四年で評論)以来である。いつもの大音響に加えて、本作はロックがナマで多用されたから、耳と神経の疲労は極に達した。新感線をまた観ようと言う勇気を持つまでに四、五年はかかるということかもしれない。その間に私は歳を取り客席は若い人で溢れると言う構図である。本作も作=中島かずき、演出=いのうえひでのり、座付役者の古田新太、橋本じゅん、高田聖子、粟根まことのほかに、北大路欣也、松雪泰子、江口洋介、森山未来、川平慈英らを客演で呼んでいる。秀吉の時代、京都所司代警護の岩倉(江口)に捕縛され釜茹で処刑された五右衛門(古田いつものようにクサク力演)が手下やお竜(松雪)に助けられ、船で脱走するうち南の島(タタラ島、バラバ国)に漂着。五右衛門から盗物を巻き上げるためにくっついているお竜は、早速この島を実効支配するクガイ大王(北大路)にくっつく。大王は、バラバ国の正統な王子(森山)=大王の息子の挑戦を受けている。クガイ大王には神秘の宝=月生石の製造を任されているインガ(高田)が愛を誓っている。そこに五右衛門が乗り込むわけだが、大王もインガも織田軍にまつわる倭人。インガは五右衛門と同じ忍びの仲間で恋仲だった。複雑な人間関係を基礎に月生石(塩とアヘンの混合物)をめぐりスペインの死の商人(川平)たちとのせめぎ合いと、大王の本質が徐々に明らかになる。舞台の変転は幕でなく、観客席にライトを向けることにより眩しさの中で終始するなど目に耐えがたい方法によりやりきった。いのうえの歌舞伎的現代様式美に若者たちは喜び、私は疲れた。セリフが高性能インカムで語られるから、役者によっては聴き取りにくい。感動はないが、こんな芝居も在って良いと思いながら、帰路についた。★★
若い作者、竹内介による、深刻なテーマ満載の芝居である。家庭を顧みず新薬開発に人生を捧げた淀山(北川隆一)は、妻(藤田千代美)の死により、これまでの自分の人生を否定的にしか見えなくなった。妻にも息子にも、新薬開発での被害者にも悪いことをしたという慚愧から記憶を消し去る薬を秘かに開発し、自らに投与する。優しく優秀な息子誠一(倉内恵)とその妻翔子(高平万希枝)に励まされ、何より淀山がたたずむ公園のホームレス三人(松田勲、藤島淳一、山口雅美)に優しく包まれて淀山は正常と異常の間を行き来する。妻の面影が常につきまとうが、淀山の悔いの深さに対し、妻の思い出亡霊は彼を恨らまず愛している。ホームレスの三人のそれぞれの出自も描かれ、公園を訪れる高校生間のいじめ、OLの職場いじめを絡ませ、現代の貧困、若者や勤労者がおかれた惨い現状を相乗的に描き込む。みんなの愛情に依拠し、淀山はアルツハイマーのための新薬開発に再び情熱を注ぐハッピーエンドがやってくる。我らが高平は屈折した息子の嫁としての微妙な立場を演じて見事であった。論点が多すぎる嫌いはあるが、真剣に現代社会と向き合った優れた作品である。★★★
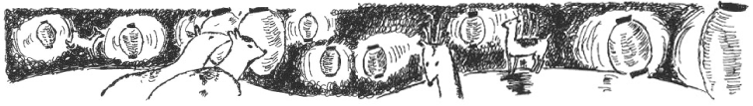
ロバート・レッドフォードが監督をし、重要な役割で出演もした作品である。原題が「LIONS FOR LAMBS」で、子羊のためのライオンたちと直訳できるのに、このような邦題には驚く。解説パンフによると原題は通常の日本人が知らない第一次大戦の戦史にもとづく。対独戦、ソンム川の戦い。つまらない司令官の下で果敢に戦って死んでいったイギリス兵たちの逸話である。それを考えても邦題は適切でない。私なら「勇者への責任」くらいかと思う。本作品は、九・一一後、ビンラディンを追ってアフガンに入った米軍が、その後のイラク戦争の影に隠れながら、なお引き上げることができないでいるばかりか、多大な人的被害を被っている現実を描き、ブッシュの誤りを正面から描く。二〇〇八年に入ってのアフガンの治安の悪化を予感させるような作品である。アメリカ国内における二カ所でのディベートとアフガンでの作戦での兵士同士の生死をかけた会話とが同時進行し、相互に関連する。ワシントンでは著名な女性ジャーナリストであるジャニーン(メリル・ストリープ)はブッシュの次の大統領の有力候補である共和党アーヴィング上院議員(トム・クルーズ)のオフィスに呼ばれ(彼女は昔、彼をタイム誌で若きホープと紹介した因縁があった)、アフガンでのアメリカ特殊部隊による新しい作戦についての特ダネを与えられ、激しいディベートが持たれた。見返りは作戦への紙上での好意的意見の表明であった。ジャニーンの鋭い質問(なぜ今か、失敗は全くないのか、成功したとき、失敗したときのそれぞれの犠牲者予想)にアーヴィングはたじたじとなりながらも、ジャニーンのジャーナリストとしての加齢からくる地位の不安定を特ダネで補わないかとの誘惑も与える。成否もその意味も明確でない作戦を特ダネ報道すべきかどうか彼女は悩みに悩む。ディベートの間にすでにアフガン現地では作戦が始まり、刻々とその恐るべき場面が組み込まれる。この場面の制作費は膨大であろう。カリフォルニア大学では歴史学のマレー教授(レッドフォード)が優秀なのにさぼっている学生トッド(アンドリュー・ガーフィールド)に、一年上の二人の優秀な学生アーネストとアーリアン(マイケル・ベーニャ~ワールド・トレードセンターで好演とデレク・ルーク)が大いに勉強した上で、現実に起こっている重要な事象に参加することの意義を感じ、アフガンの自由回復に志願兵としてでかけたことを話す。アメリカが良きことをする努力に参加したいと望んだのである。教授は自らのベトナム戦線での苦い思い出を語り、戦場に行くことはない、アフガンへの参戦が正義かどうかわからないと止めたが二人の勉学と実践への意欲が並はずれていたことを話し、まず勉学に勤しむようにトッドを説得する。その場面に、何度も上記のアフガンの作戦が映し出され、なんとアーネストとアーリアンが、無謀な作戦の犠牲となり、敵地で孤立し、負傷し、救助を待っている。そして三番目の会話はその二人による。命をかけた友情の発露である。作戦機から打ち落とされたアーネストを助けるためアーリアンは自ら飛び降りる。負傷したアーネストを助けたいが、アーリアンは雪に埋まって足が抜けない。敵は二人を生け捕りにしよう、米軍の無法作戦の証拠をつかもうと接近する。衛星を活用した最新鋭計器を持つ米軍は爆撃機で敵を爆撃しつつ、救助ヘリを向かわせるが、二人にはそのことはわからず、孤立感の中、励まし合いながらやっと雪から脱出し、砲弾の切れた銃を敵に向け、信ずる祖国アメリカのために覚悟の上で砲撃を受けて散る。これらの戦場での出来事を知るよしもないジャニーンは、記事へのこだわりを胸にタクシーでアーリントン墓地を通りかかり、思わず落涙するのであった。重い作品である。映画パンフには分析はないが、堤未果「ルポ貧困大国アメリカ」(岩波新書)に詳しいように、学生は学費ローン返済のために多く入隊し、戦場に送られて命を落としている。登場する三人の若者たちに、学費ローンの重圧があったことを作品は丁寧に描いている。アメリカの世界戦略の行き詰まり、政治、ジャーナリズム、大学の現実を描いて必見の秀作である。★★★
タイの子供たちの人身売買の実態と日本との関係を描いた同名の梁石日の小説(幻冬文庫、二〇〇四年)が映画化された。阪本順治監督作品。日本人の男はタイまで行って幼児買春し、臓器不全を持つ家族はタイの子供の生体臓器を買う。後者は日本の子供がタイの子供の命を買うと言っても良いであろう。タイの子供たちは貧しさの中、自分の親に売られているのである。この心の凍るシチュエーションをノンフィックションのようなタッチで作品は描いて行く。これを世界に告発したい新聞記者南部(江口洋介好演)、助手となるカメラマン与田(妻夫木聡)、タイの子供を助けたいボランテティアの音羽(宮崎あおい力演)が、それぞれの立場でタイマフィアの仕切る監禁部屋からエイズ感染のためにゴミとして捨てられる子供を助けようとしたり、手術寸前(つまり臓器を抉りとられる寸前)の映像をカメラに収めようとする。買春場面は醜悪であり、エイズが発症し捨てられ脱出し実家に長い距離を歩いて帰った子供が、親の家に入れてもらえず、庭の小屋でハエまみれとなって死に、小屋ごと親に焼かれるシーンなど、観る者の心と身体に悪いシーンの連続である。そしてラストがまた衝撃である。人身売買反対の集会にマフィア集団がなだれ込み、警官隊と銃撃になり、戒厳令のような状態になる中で、南部は生体臓器売買暴露では追求の側に立っていたが、買春をしていたことが暗示され、自殺か銃撃戦に巻き込まれるかで命を落とす。私は、最後の場面の理解がうまく出来なかったので、上記原作を勝って読んだ。すると映画は原作をこの点においては大きく変えていた。原作は、混乱の中で南部は音羽に外国人だからもう日本に帰れと迫り、音羽はここが私の居場所だと拒否してタイに残るところで終わる。逃げ帰るところのある善意とそれを捨てた性根の対比である。映画も原作も秀逸である。多くの世界の人々に観て欲しい名画が誕生した。★★★
原題はINDIANA JONES and the KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL。このシリーズをずっと観て来た。「レイダース 失われたアーク<聖櫃> 」は一九八一年、「魔宮の伝説」は一九八四年、「最後の聖戦」は一九八九年だった。「最後の聖戦」は本誌一八号で評論している。小三の娘と観たことを書いているから、一九年ぶりの四作は観る者も加齢したことになるが、何よりも興味があったのはハリソン・フォードのインディとしての加齢である。歳をとった。役者本人は一九四二年生まれ六五歳であり、物語では四〇代後半を演じ、レイダースで恋人役だったマリオン(カレン・アレン)が息子マット(シャイア・ラブーフ)とともに登場し、写真だけ登場する亡父ヘンリー(ショーン・コネリー)を偲んでいる。父と知らない間にはマットはインディをジジイと呼んでいた。しかしハリソンはなかなか若々しく演じている。物語はいつものパターン(考古学、冒険、悪の手から神聖な地を守る)で新味はないが、一九四六年生まれのスピルバーグ監督、一九四四年生まれのジョージ・ルーカス総指揮・脚本コンビのSFX寅さんである。三作は一九三八年が舞台でナチとたたかったが、一九年ぶりのこの四作はそれから丁度一九年経った一九五七年を舞台としソビエトのKGB(かの美女ケイト・ブランシェットが猛々しいKGB大佐を演じている)、スターリンの陰謀とたたかうのである。ルーカスの脚本はネバダでの核実験が頻繁な時代も描き、華麗な作品を作っている。SFX、時代考証もしっかりしている。まだ続くと公式サイトは示唆しているが、果たして何年後か。インディはハリソンなのか、監督や総指揮や一九四五年生まれの私は生きているだろうか。★★★
|
見逃していた二〇〇三年作品。篠田正浩の最後の監督作品と言われる。ソビエトのスパイ、ゾルゲ(「トゥームレイダー」などに出たイギリス人俳優イアン・グレン好演)と協力した日本人マルキスト尾崎秀実(ほつみ、本木雅弘好演)を中心と、結論めいた最後の場面もゾルゲの活動を肯定的に描いているから、批判を浴びるべき作品であるが、驚くほど丁寧に昭和前半の日本政治、社会、とりまく国際情勢を描くから、歴史の勉強、整理になる。知らなかった史実の学習にもなる。作画としては上海租界、銀座四丁目の再現など見事な映像技術が光る。大阪朝日新聞記者の尾崎は赴任先の上海でナチス党員であるジャーナリスト、ゾルゲと会う。ドイツ人でありドイツ共産党の優等生としてコミンテルンの指示でモスクワに行き、上海に派遣されていた。ソ連は国土をナチスドイツと日本軍の脅威から守るための両国の情報収集をゾルゲに命じた。尾崎は朝日新聞幹部として得た情報を上海でも東京でも与え続ける。尾崎も自らの思想として共産主義に到達していたのである。ゾルゲはフランクフルター・ツァイトゥンク紙の特派員として来日し、ドイツ大使館に入り込み、また近衛内閣の顧問となった尾崎から、それぞれ確度の高い情報を得ていく。その情報の最大のものは、日本軍が南進する点であり、それによりソ連はシベリアから精鋭をヒトラーに備えてヨーロッパ戦線に移動し国を救ったのである。戦前の世界におけるマルクス主義を正義と同視化する力をあますことなく描いた作品である。出演者も豪華で、上記二人の他、椎名桔平、上川隆也、葉月里緒菜、小雪、夏川結衣、榎木孝明、大滝秀治、岩下志麻など。一見の価値ある作品であった。★★ |
小林多喜二「蟹工船」(定本小林多喜二全集四巻、新日本出版社、一九六八年
一九二九年(昭和四年)に発表されベストセラー的に高い評価を受けたが結局発売禁止となったこの作品が、いま派遣などの奴隷的労働を論じる際に、「そっくり」だとして注目を集めブームとなり、文庫本のベストセラー五位に入っているという。私はあまり全集を買わない質だが、多喜二のこの一五巻全集を学生の時に買って今も持っている。小さな活字の二段組でこの作品を何十年ぶりに読んだ。驚くほどの濃い内容であった。私は読書の際、評論のための備忘に注目箇所に小さな紙片を挟むのだが、ほとんどの頁に挟む結果となり、本が変形するほどだった。物語は特定の主人公をおかず、群像として、カムサッカ海峡に浮かび、国家的事業として、ソビエト領海に侵入しての蟹漁に従事し缶詰をつくる工場船での過酷な労働と自然発生的な抵抗、サボタージュ、ストライキ、帝国海軍による弾圧、再びのストライキの成功、殺人的労働を強制していた監督たちの資本家による馘首などを描く。搾取、企業と国家、労働者の抵抗などという社会科学的概念を小説の中で如実にリアルに語りかける作品である。ボロだが四五〇人も乗り組む船の組織・実態、船員、漁夫、雑夫の年齢(一四、五歳から中年まで)、出身(北海道、東北中心で、夕張炭坑ガズ爆発の恐怖から新しい地獄へ来た者も多い。貧困層が人買い周旋屋により運び込まれるのである)、出稼ぎの実態(食費や宿泊費名目で給料から控除され、結局金は残らないシステム)、健康状態(糞壷と言われる船室の不衛生〜月二回の入浴、虱、蚤、南京虫、反吐、精液〜、荒れる極寒の海での長時間労働の過酷で三年働けば死ぬだけ)、監督が拳銃で脅しながら強制する奴隷作業(船内逃亡は虐待死で応報)、同じ蟹工船がSOSを発して沈没しようと、いわば子船である川崎船が帰還しまいと母船は救助しないなどの非人間性を克明に書きこんでいる。食事、酒、性欲処理なども克明である。文学の力を感じた。リアリズム文学の粋であろう。多く本作への現代評が出たが、吉本隆明「『蟹工船』と新貧困社会」(文藝春秋七月号)が現代の若年層を指して「本当の問題は貧困というより、何か人間の精神的な抵抗力が弱くなってしまったこと」と論じる点を、斎藤美奈子は寝ぼけた論だと批判するなど(朝日新聞六月二五日「文芸時評」)喧しい。★★★
大江健三郎の短い文章を二つ扱う。
「ソレデ世界ノ順番ガ下カラ変ル」の副題が付いたわかりやすい名文である。連載している「定義集」の一つ。小田実の死を悼む。核兵器問題の原点を扱った小田の作品「HIROSHIMA」を通して、小田の平和への志=根本思想と人間への深い悲しみの心を綴る。小田がギリシャ古典の研究から現代海外文学の動向までをきちんと押さえていたことも紹介しながら、三歳年上だった巨人の死に静かにかつ情熱的に向き合っている。★★★
「原理としての『人間らしさ』」(自由と正義、二〇〇八年二月号)
本誌前号で、私が浜松の日弁連の人権大会にこの講演を聴きに行ったと書いたその講演が文字になった。あらためて大きな感動を受けた。編集部の何人かにコピーを差し上げた。まず日弁連で話そうと思ったきっかけを教育の国家管理への危険を訴えた教育基本法改悪反対の声明に教えられたからだと切り出し、自らにとって改悪前の教育基本法は、子供はみな、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間として育成されることになったという条項を母に話して東京に行き大学教育を受けることを許してもらったかけがえのないものであったことに話しを進める。そして偉大な母は国や地方公共団体の責務を規定する教育基本法三条の二を書いた大江のメモを持って農協の組合長に学資を貸してもらいたいと言って行き、そのメモをみた組合長が共鳴して貸してくれたというのである。そして本題に入る。渡辺一夫の薫陶から理論、思想としてのユマニスム、人間らしさを一生勉強して行こうと考えた若き日、重い障害児が生まれた。有名な光君である。その憂鬱を抱えたとき、渡辺は大江に「いまの君を見ると、根本のところでは絶望しているように感じられる。しかし、希望を持ちすぎず、絶望しすぎずというのが、ユマニストたちの態度だった」と言った。そして渡辺から寛容ということも学んだと言う。そして大江は自分の表現は自分で行きどまりで光君には伝わらないと思っていたとき、光君には音楽で自己を表現する能力があることがわかった、そして光君は生きる方向で、その肉体が意志していることもわかって来たと言う。光君から教育された根本に人間が生きていくこと、その中心に人間らしさがある。大江は渡辺から理論としての人間らしさ、光君から体験としての人間らしさを教えられたというのである。才能と不幸があって今の大江があるのだろうが、不幸を絶望しなかったことから人間らしさが湧いて来ているように思える。それが大江に更なる才能を身につけ続けていると言えよう。★★★
本誌11号で巻頭言をもらった野坂の戦争童話集沖縄編である。黒田征太郎の絵。吉永小百合が朗読して話題になっている。沖縄の浦添の海岸で毎年産卵する歳とった大きなアオウミガメが感じた太平洋戦争末期の海の異常、人々への異変と、一人の少年哲夫の最期の模様が描き出される。カメと哲夫の接点は、哲夫がカメの産んだ卵を、アメリカの軍艦の砲撃から守るために自分がひそむガマに砲撃のこわさもわすれて運んでやるところから始まる。六月二三日沖縄戦が終わったのにそれを知らない哲夫は、ひもじさのあまり、そんな気持ちはまったくなかったのに卵を食べてしまう、しかしそのことを悪いと感じる力はもうない、死んだ父や死んだに違いない母、祖父母のことも考えられない。海、空、雲をながめながら、フッと、満ちて来た潮にすべり入り、底へ沈んでいった。そして、海の水をあったかい、甘いと思うのである。少年が沈んだあと、歳とったウミガメは、二か月前の騒ぎも忘れ、いつものように卵を産みに来て海に漂い、こどもかもしれない小さなアオウミガメとすれちがう。辛さ悲惨さが淡々と描かれる。「火垂るの墓」と同じである。視点を少し後方に引けば、それが戦争の現実である。淡々とした表現に込められた作者の万感の想いが胸を打つ。私はこれを大山の山小屋で読み、独りだったのでずっと涙をこぼしていたが、哲夫の(それを感じる力も奪われてしまったであろう)悔しさを思い、怒りと名状しがたい勇気が湧くのを感じた。すぐれた作品である。★★★
私は本誌前号にも著者の「第三の時効」を絶賛評論したほか、これまでもたくさん読んではその度に唸ってきた。本作品も唸った。ゆっくり読むことはできない。一気に読み通すしかない。「第三の時効」は県警本部の刑事部捜査一課の三つの係のしのぎの削りあいであったが、本作は県警本部長、警務部長(この二人が警察庁キャリア)、警備部長、刑事部長、生活安全部長、交通部長の公私の関係を描く(住居である官舎、公舎も隣り合わせであり、何人かは婦警出身の妻を持ち、プライバシーも何もあったものではない)。キャリア同士、キャリアとノンキャリ、ノンキャリ部長間の出世欲、せめぎ合い、かなり乱れた私生活を扱うから、読者は本作でも他の著作では読めない世界を味わえる。将来警察庁長官と嘱望される若いキャリア警務部長の部下でノンキャリの人徳ある警務課長不破が、阪神・淡路大震災当日、警察手帳も返上して突然失踪する。マスコミに気づかれないままに発見しようとする幹部達の必死ぶりが物語の縦糸である。刻々と伝えられる神戸の惨状も二本目の縦糸かも知れない。横糸は不破の過去から現在までの実像が暴かれていく過程である。若き日の婦警との恋愛のもつれとそれに尾を引く中年になってからの女性関係、地域有力者との警察業務にからむ貸し借り、上司からの無理なもみ消し依頼などで潰れていった優秀な警察官。この警察本部では身内の「始末」=激震処理に必死で、阪神・淡路の救援、援助の激震対策がおろそかになっていくことから題名は付けられている。★★★
|
新しい感覚をもった女性作家が誕生した。一三八回芥川賞を受賞した。町田康の女性バージョンの誕生である。同じく大阪出身で、同じくミュージシャンでもある。町田の文体の魅力の頂点は本誌六二号で絶賛した「告白」だが、川上はおそらく公然と町田の真似をしているのではないか。大阪弁を基礎にして。文体は真似ても心は似ないと川上は言うだろう。もちろん心は似ていない。その意味は町田には女は書けないというか女にはなりきれないのであって、川上は男は書けないだろうと思うほどに似ているのである。川上は本作で、女を描く。女の、広義と狭義の生理を描く。心と血である。大阪から出て東京で働く夏子のもとを、姉の巻子とその娘緑子が二泊三日で訪ねる。離婚しホステスをしながら緑子を育てる巻子は豊胸手術をしようとしている。初潮期に達した緑子はそんな母親に反発し、口をきかなくなり、ノートでの筆談に終始する。胸を大きくするのは男のためなのか自分のためなのか、そんなことを言うなら化粧はどうなのかと辛辣に問いかけつつ物語は進む。そんな問答には阿呆らしやの鐘が鳴るとも言う茶化しの作者本人もいる。反発しつつ愛し、愛しつつ反発する母娘をリアルに追いながら、この初々しい作家は人間そのものを描いている。★★★ |
|
沖縄発音で「みるくゆー」。人気作家だが初めて読む。一九七二年の沖縄返還直前の沖縄人(うちなーんちゅ)のアメリカへの抵抗、様々な矛盾(日本への屈折、本島内でも地域ごとにある差別心、周辺の島々、奄美に対する優越感、父親不明の多くの混血子、占領軍内の黒人と白人の対立)を基本にしての問題小説である。アメリカに占領され、アメリカ兵によりありとあらゆる犯罪や無法地帯形成が行われるが、生活のためにうちなーんちゅはそれに迎合し、核と毒ガス兵器がなかば公然と保有され、琉球政府は当然に無力、施政権返還後もどうせ日本政府はアメリカとの関係で無責任であろうと予想される時、沖縄人はどうするのか。作者はアナーキストジャーナリストの伊波尚友と天然のマルキストで三線弾きの比嘉政信という正副主人公を登場させ、とりわけ憎しみが強い尚友はCIAに協力してまでも情報を集め、彼らはすべての鬱屈を沖縄にいるアメリカ人(アメリカー)、基地へのテロに集中させる。アメリカ基地から兵器を盗んでの実行である。沖縄ヤクザ(アシバー)の頭目も加わる。琉球共和国軍を名乗る。彼らは日本人(やまとーんちゅ)を全く信用せず、沖縄の革新共闘、復帰協、全軍労その他の運動(それらの幹部たちの名は実名で登場する)をお祭り主義、ガス抜きだと軽蔑している。全員が孤児の施設で育った尚友と照屋仁美(黒人との混血)、政信と當銘愛子(白人との混血)の胸迫る恋情、それぞれの心の闇の描き方、愛の末路の寂しさは胸を打つ。週刊ポストに連載した作品であるからか、脇役として登場する人物たちの途中からの不登場(長編連載をしていると忘れてしまうのだろう)は多くある。北海道出身の作者が沖縄の心への渾身のレクイエムを書いた。主人公たちの心情、とる行動には批判もあろうが、沖縄を深く描いていると私は思う。藤川覚の装丁も良い。★★★
「無人島に漂着した三一人の男と一人の女」というセンセーショナルなキャッチフレーズにまんまと乗って買ったが、いま一つだった。南の島なので、生存を保つ動植物はあるが(ごちそうの野豚のほか、蛇、トカゲ、コウモリ、小魚、バナナ、タロイモ、椰子など)、男女比が極端なので片面的乱交又はホモである。しかし著者が力を入れて書いたのはその面ではなく、支配者としての資質、孤独、脱出競争(狂騒)、諦めからの人格変容、環境順応、日本人と中国人の違いである。日本人たちは島を東京島と名付け、地域ごとにコーキョ、オダイバ、ブクロ、トーカイムラなどの地名を付けて暮らした。ロビンソンクルーソーなども参考に書いたとどこかの新聞で著者は語っていたが、一人二人の孤独でなく、一定人数の中でもたらされる孤独と葛藤がテーマである。ほとんどの男と接し、誰かの子を妊娠した女の扱い、生まれた子の運命など話題、題材満載に広げてある。著者のねらいは何であろうか。本当の東京にいる現代人と、東京島にいる人々とどちらが幸せなのか、いわゆる文明は人を幸せにしているのか、文明なき孤島はそのことの故に不幸せなのかの問い詰めであろうか。世間の大騒ぎと違って、私はあまり成功したようには思えない。ただこれの続編はいくらでも書けるだろう。★★
本誌四九号でこの作者のデビュー作「お眠り私の魂」を絶賛し、加えて「作者が覆面だと本の帯は言うが、言われなくとも我々法律関係者が読めば、裁判官が書いたことがわかるし、私と親しい人であるようにも思う」と書いた。思い当たる人がいたのである。しかし、徐々に明らかになったのは女性刑事弁護士だとのこと。全くの思い違いだった。思い違いをしたから評価を下げるわけではないが、本作は成功とは言えない。法律家でない読者は、きわめて正確な刑事捜査実務、裁判実務を理解することができるだろう。しかし、主人公(犯人の女性)にも、語り手の私(毎朝新聞社会部遊軍記者)にも、人間的深みがない。陳腐な描写、作劇とも言えよう。前掲作品とえらい違いである。すでに一〇本近い発表作があるようだが、今後のいい作品を期待したい。★★
「かもめ」と言えばチェーホフ作品と一九六三年の女性初の宇宙飛行士ソ連のワレンチ・テレシコワがヴォストーク六号から「ヤーチャイカ」と叫んだ声とが思い浮かぶ。ヤーは私、チャイカはかもめである。テレシコアのコードネームがかもめだったから、「私はテレしコアだ」と言ったに過ぎないという説、それはそうだが、ソ連と言う暗い世界で花形デビューしたテレシコワはチェーホフの「かもめ」のニーナ(本稿演劇欄参照)を彷彿とさせるという説、彼女は後に別の宇宙飛行士と結婚して出産したが、それは宇宙で浴びた放射能の人体実験であったので、「かもめ」なのだと言う説、体制の中にありながらテレシコワのコードネームをかもめにしてそのように彷彿させた命名者は反体制の人物だったのだという説などを本作品は織り込んでいる。物語は、上空から東京のいくつかの地点を鳥瞰すると(確か作者が「週刊ブックレビュー」で言っていたと思う)、思いもよらぬ人間関係が見通せるというような叙情的な話しである。舞台は都心のFMラジオ局。そのAD(アシスタントディレクター)、気象、交通、ニュース担当のフリー女子アナ、その夫の作家、フリーのナビゲーター、そのインタビュー相手の交通博物館学芸員などの男女関係を含む人間模様、ADの学生時代の行状と暴行被害を受けた女性、その父、彼女を助けた駆け出しの大学研究者。これらを作者は人工衛星から見おろすように淡々と場面ごとに書いて行く。ところどころに作者の結婚観、労働観などを散りばめながら。それぞれの人々が意外なところで出会っている。1回読んだだけでは容易にわかりにくい物語が、読後にペラペラと早送りで頁をめくると、人工衛星で同じ地点を少し時間をずらして飛んだ趣で理解できてくるというような作品である。これも文学であろう。★★★
|
この作者の作品は「砂のクロニクル」(本誌二八号で絶賛)以来だが、うって変わった駄作。クルド問題を悠久の歴史の中で熱く語りいい知れぬ感動を与えた作品を書いた、同じ作者かと疑う心境であった。東京の興信所の社員高倉が社長岸谷の命令で、山口県の山間部のさびれた赤猿温泉郷に潜む若宮淳次の監視のために東京から赴く。淳次は母親と姉が自殺したその温泉郷に復讐のために帰省していると聞かされる。調査すると、二人の自殺の原因は郷の男たちとの交情のもつれ、悩みと思われ、また郷が幕末に須佐で起きた殺人事件の下手人たちが隠れ住んだ村で、下手人たちの子孫が今の住民の大半であることがわかる。そして高倉の近くで連続的に殺人事件が起っていく。淳次は豪華なジャズバーを開き、ブードゥ教の怪しいマディ・マッドネスを流し、姪沙耶の裸自慰行為踊りで、郷の人々の性的感覚、暮らしを狂わせて行く。そして土地を売って郷から出ようとする人々が続出する。そして、陰謀が明かされる、淳次は岸谷の子であった。二人はつるんで須佐から赤猿温泉郷を通り津和野に抜ける歴史にちなんだ維新街道建設のために、温泉郷の土地を手に入れるための芝居であった。淳次は最後は岸谷を裏切る。思わせぶりで、あとで様々な薬味の意味を解明するのであろうと思いつつ読み進めたら、最後まで何もなかった。あるのは異常なセックスと殺人だけである。こんなつまらない作品だが、表紙はわれらが西口司郎である。表紙が気の毒だ。★ |