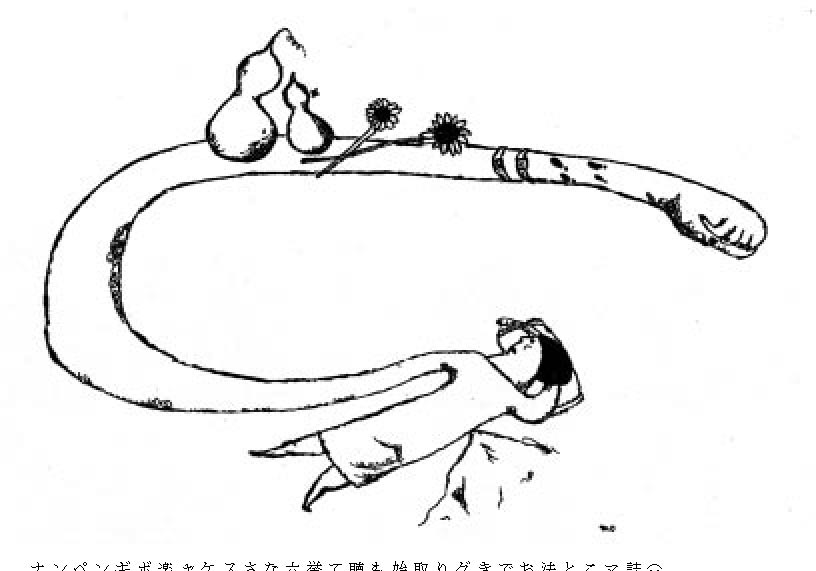★★★ 是非一度ふれてみて下さい。おすすめマーク。
★★ 機会があればふれればいいように思います。
★
時間の無駄です。ふれるなマーク。
「日本の」の意味の変化を恐れ、
引き続き「民族」と戦前の外交の意義を考える
あの鈴木宗男にいじめられ有名になったNGOピースウインズ・ジャパンの大西健丞が非常に面白い逸話というか事実をコラムで紹介している(毎日新聞三月一九日朝刊「私はこう考える」欄)。イラク北部スレイマニアで四月からの時期、氷売りが「日本の氷!日本の氷!」と声を響かせて街を練り歩くという。「日本の」の意味は、日本から輸入したと言う意味でなく、「完ぺきな」とか「奇麗な」とかを強調する形容詞なのだそうだ。日本はこれまで憧憬の対象になってきたのである。これを読んで私は衝撃を受けた。小泉首相が国連の新決議なしでの米英軍のイラク武力行使を支持したのが三月一八日だったから、この日以後、イラクで一つの言語が変化したのではないかと思えるからである。「日本の」は氷などを表現する美しい言語から、「ずるい」、「自分のことばかり」、「不甲斐ない」という意味を有する薄汚い言語へと。
★★★
酒井直樹「死産される日本語・日本人 『日本』の歴史―地政的配置」(新曜社 一九九六年)。本誌前号で評論した姜尚中・森巣博「ナショナリズムの克服」のなかでしばしば引用された理論家の論文集である。不明にしてこの人のことは名前も知らなかった。日本のマスコミ、論壇紹介などがいかに特定の人々にしか言及していないかがわかる好例であろう。突然だが、故中筋修が、私の聞いたことのないような人々の本を濫読しており、私はしばしば彼の読書から自分の読書の幅を貰っていたが、彼はもういないので自ら気をつけねばならない(中筋への追悼文は本誌四九号を参照されたい)。本書の名となった基本論文のなかで著者は、日本語、日本人というものが生まれると同時に死んでいた理由を説き起こす。考えてみれば確かに日本語の起源は過去への無限溯行である。時期の特定は不可能かつ無意味であるから、次に著者は国民語としての日本語を考察し、国民文化の生成過程との類似性を辿る。国民共同体、国民文化、国民語、社会、国民経済、民族、人種という統一体が一致するように作られていくのは近代である。そしてそれらは国際的には他の国民共同体との比較と区別を媒介にして構想される。つまり他との排他性を前提とする。近代は分割不可能な「個人」主義を発達させたが、分割不可能な「国民」共同体または「国民」全体主義を同時に共犯的に内在させたという。そしてそのように成立した日本語の起源として非言語との区別、そのなかのどのような要素がいわゆる日本語として取り上げられたかを考察している。前者すなわち言語と非言語の区別は常にタウトロギーに落ち込み難しい。その区別を言語で考えるからである。多言語主義は国民国家の分裂につながるから反発する動きも強いが、これがまさに近代化進行過程であると分析し、その反証に日本の一八世紀の状況を上げている。そこでは人々は漢文、和漢混交文、いわゆる擬古文、候文、歌文、俗語文、地方別俚言などのなかに重層的に帰属し、ひとつの言語共同体に無媒介的に同一化するとは思いもよらなかったことをあげている。そしてその一八世紀に日本語を古代に仮設し生み出す作業がおこなわれだす。日本語の誕生は日本語の死産としてのみ可能であったという。これは中国においても同じだと筆者は言う。つまり古代に日本語が存在したかどうかは実証できず、仮設するのみで、これを外国語のように「真似び」=学んでいく必要があり、制作されていく。著者は日本語と日本という国の成り立ちを一八世紀においており、一九世紀、明治政府にはおいていない。一八世紀を日本の近代への始まりと捉え、やがて最も成功した近代国家日本が生まれ、成功した国民主義は帝国主義になっていったという。もちろん著者は、近代の分析として平等の二面性も考察している。既存の社会体制内での同じ待遇を受ける権限としての平等、社会体制そのものが産み出す差別の撤廃を要求する平等である。この分析に見られるように著者の立場は近代悪論ではない。結論としては、過度の国民国家観、日本のような国体意識を持った国民国家観の脱構築が主張される。このほか、丸山真男批判も面白いのだが、あまりに長くなりすぎるので、他日評論したい。
★★★
小倉和夫「幻の史料『日本外交の過誤』を読む」(論座六月号)。本誌前号で城山三郎「落日燃ゆ」を取り上げ、広田弘毅を中心に据えた日本の外交の特徴と軍部との矛盾をいささか検討した。本論文は、前駐仏大使で青山学院教授の筆者が、一九五一年に外務省課長クラスが吉田茂首相の命により作った「日本外交の過誤」を分析している。今年四月に初めて公表された貴重史料の分析である。五一年に課長クラスであるということは、作成者達は戦争末期に外務省にいて、幣原外交、広田外交など城山が描いた外交を直接体験した人々である。この史料は、幣原外交の消極性を批判し、広田外交の軍部寄り姿勢を批判する。また国際連盟脱退、ワシントン海軍軍縮条約破棄、日独防共協定、日中戦争などを各論的に全て批判し、反戦の立場から戦前の外交を総括している。ただ、この史料もこれをコメントする筆者の言及にも、その外交上の誤りを産み出さないためには、どのような動きが可能であったかの立ち入った検討がないので、底が浅いと感じるのは私だけではないのではあるまいか。むしろこの史料を、城山に分析してもらったほうが、よほど成果が上がるのではないかと感じるのである。
★★
シェエラザードで軍国主義を
半落ちでヒューマニズムを学ぶ
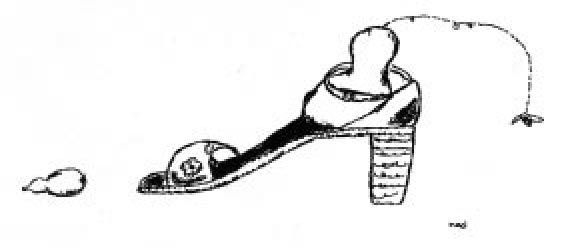 石田衣良「スローグッドバイ」(集英社 二〇〇二年)。作者の初めての短篇集で恋愛小説集だそうである。男の気持ちを描いた一〇篇を収録。標題の「スローグッドバイ」は、別れることになった恋人達が最も素敵な時を過ごす「さよならデート」という友人間のしきたりに従っておこなう不思議な経験を描く。同棲前にプレリュードを駆って彼女を迎えに行っていた思い出を辿ったり、いつも行った横浜の中華街でゆったりと昼食をしたり、元町を散歩しながら、七時間もかけて、たくさんの物語を紡ぐ。しっとりとした味わいが残る。「You look good to me」は、ネットの世界の喫茶店「パラダイスカフェ」で出会った醜い「アヒルの子」と名のる本当に自分が醜いと思っている女の子と現実の世界で出会い、恋人になっていき、美醜が関係なくなるまでの道行きをサラリと描く作品。なかなか切ない作品が「フリフリ」。女友達の一方清香が結婚した途端、独身の潤子にどんどんと男を紹介する。紹介された男が潤子と恋人のフリをして楽しみ感情移入しつつあるうち、清香が離婚する。すると潤子は男をサッと捨てバイバイをして清香の方に向かって歩くという。レズの話か、女の友情の話かはよくわからないが、力が抜ける。「真珠のコップ」は、仕事と恋愛が最も煩わしいと思っているソフトウエアのマニュアルづくりを生業とする男が、デートクラブの女性と本当の恋をするすばらしい道行きである。「夢のキャッチャー」はシナリオライターとして才能ある女に、納得する仕事をするまで結婚をじっと待っている男とそのことに心から感謝する女の単純な愛情物語。どの篇もさらりとうまくまとめられているが、石田のような才子にして、恋愛物語には苦労しているなという感が強い。男と女の肉体的交わりの描写で読ませず、心や感情の物語で読ませるのはたいへんである。
石田衣良「スローグッドバイ」(集英社 二〇〇二年)。作者の初めての短篇集で恋愛小説集だそうである。男の気持ちを描いた一〇篇を収録。標題の「スローグッドバイ」は、別れることになった恋人達が最も素敵な時を過ごす「さよならデート」という友人間のしきたりに従っておこなう不思議な経験を描く。同棲前にプレリュードを駆って彼女を迎えに行っていた思い出を辿ったり、いつも行った横浜の中華街でゆったりと昼食をしたり、元町を散歩しながら、七時間もかけて、たくさんの物語を紡ぐ。しっとりとした味わいが残る。「You look good to me」は、ネットの世界の喫茶店「パラダイスカフェ」で出会った醜い「アヒルの子」と名のる本当に自分が醜いと思っている女の子と現実の世界で出会い、恋人になっていき、美醜が関係なくなるまでの道行きをサラリと描く作品。なかなか切ない作品が「フリフリ」。女友達の一方清香が結婚した途端、独身の潤子にどんどんと男を紹介する。紹介された男が潤子と恋人のフリをして楽しみ感情移入しつつあるうち、清香が離婚する。すると潤子は男をサッと捨てバイバイをして清香の方に向かって歩くという。レズの話か、女の友情の話かはよくわからないが、力が抜ける。「真珠のコップ」は、仕事と恋愛が最も煩わしいと思っているソフトウエアのマニュアルづくりを生業とする男が、デートクラブの女性と本当の恋をするすばらしい道行きである。「夢のキャッチャー」はシナリオライターとして才能ある女に、納得する仕事をするまで結婚をじっと待っている男とそのことに心から感謝する女の単純な愛情物語。どの篇もさらりとうまくまとめられているが、石田のような才子にして、恋愛物語には苦労しているなという感が強い。男と女の肉体的交わりの描写で読ませず、心や感情の物語で読ませるのはたいへんである。
★★★
横山秀夫「半落ち」(講談社二〇〇二年)。ベストセラーである。私はこの本を表紙絵を担当した西口司郎さんからいただいた。アルツハイマーで壊れつつある妻から頼まれて殺した元警部を、取調、取材、弁護、裁判、刑務の立場から描いた周到な内容である。息子を一三歳の時、骨髄性白血病で亡くし、アルツハイマーに苦しむ妻を愛するが故に頼まれて殺したとき、誠実な警察官であったこの男は、絶望の連続線上で自殺をせず、謎の二日間を過ごして自首した。嘱託殺人までは素直に自白したが、その後の二日間の真相を頑としてしゃべらない。これを半分自白して半分否認と言う意味で半落ちという。この真相が、本作のもっとも優れた点であり、感涙を誘う。茨城県の水戸が舞台であろうか。警察幹部の妻殺しの真相がどのようにして隠ぺいされていくかを章ごとの主人公の生き様を交えて多様に描く。刑事の章ではたたき上げの優れた警視志木(県警捜査一課強行犯指導官)が捜査を知らないメンツばかり固守するキャリア組と暗闘する。誘導して自白を取る方式(向けて調べるという)に抵抗するが、結局身の保全から屈服していく様が描かれる。検事佐瀬の章は、東京地検特捜を経験したエリート検事が、小さな地検で、圧倒的な物理的捜査能力を持つ警察と対決し、警察からの捜査妨害、上司の事なかれ主義に疲れ果てていく様が描かれる。志木との友情に似た交流も描かれる。法曹である検事と非法曹である事務官との根深い不信も挿入されている。周到である。記者中尾の章では、新聞社間の特ダネ競争の熾烈、報道の危険性、警察発表と違うことを書く勇気と孤立化が描かれる。弁護士植村の章では、大都市での弁護士の競争と小都市での弁護士の伝統的不要性(争いは親族、地域共同体が解決)を対比させつつ、この事件での警察のウソを暴こうと必死に活動するものの、迫りきれず、自沈していく様が描かれる。判事藤林の章は秀逸である。キャリア判事は非常識との風評に抗い、名判事であった実父のアルツハイマーの介護を妻の献身的な愛情と自らの努力で補いながら、必死で良い判決のために努力している。本件では検事も、弁護人も、刑事も被告人である警部に心から同情しつつ裁判が進むという非日常に判事も真相のかけらを発見するようになる。同じくアルツハイマー病の義父から殺してくれと頼まれ必死にその激情に耐えた妻から、殺した犯人は優しい人なのだと教えてもらいながら、どれほどこの警部が優しい男であっても、人を殺すことはいけないと改めて剛直な結論を出している。刑務官古賀の章で、押さえに押さえた本件の謎が志木警視との共同行動で解かれていく。刑務官としての受刑者に対する絶対的権力行使の危険も描かれてる。名作である。文学形式として、同じ主題を立場の異なる章ごとの語り手を作って深めていく方式で、丸山健二「千日の瑠璃」(本誌二九号で絶賛)などが開拓した独特のものである。ところが、この作品が受賞最有力視されていた直木賞選考委員会でクレームが出て、受賞はなかった。次に有力視されていた石田衣良も含めて、今回の同賞は該当者なしとなった。クレームとは、作者が、受刑者には実際には骨髄性白血病のドナーとなることが認められていないという事実を見逃している点であり、それが本作品の決定的弱点とされた。ミステリー作品としての未完成とも評された。しかし受刑者をドナーにしないのは運用であり(確かに受刑者から必要なものを取りだす環境は良くはないことは事実である)、法律上の基準ではないのだから、そのクレームを過大視することはなかったのではないか。競争相手の出版社か何かの強引なアピールが奏効した例とも言えるのではないか。私としてはこの本と、石田衣良作品との同時受賞が順当だったと思う。
★★★
 浅田次郎「シェエラザード上・下」(講談社文庫 二〇〇二年)。一九九六年から七年に新聞各紙に連載されたものの文庫化。一九四五年四月一日にアメリカの潜水艦によって撃沈された「阿波丸」事件をかなり忠実に下敷きにしながら、浅田は明確な帝国陸軍批判を追加して本作品を世に問うている。徴用された世界最高の豪華客船を「弥勒丸」と名を変えて。各地で日本軍が捕えた連合国の捕虜へ連合国からの支援物資を運ぶ目的を与えられ、安全航行が保障された船(これを安導券を持つ船と言う)がなぜ撃沈されたかの謎はなお解明されていない。浅田は、判明している史実に加え、昔から謀略の典型として出てくるM資金の話しを合体させた。軍部が中国支配を続けるための金塊をシンガポールを拠点としてマレー半島で地元金満家から騙してかき集め、船に積み、国際約束の航路を無断変更して上海で降ろそうとして、完全に
浅田次郎「シェエラザード上・下」(講談社文庫 二〇〇二年)。一九九六年から七年に新聞各紙に連載されたものの文庫化。一九四五年四月一日にアメリカの潜水艦によって撃沈された「阿波丸」事件をかなり忠実に下敷きにしながら、浅田は明確な帝国陸軍批判を追加して本作品を世に問うている。徴用された世界最高の豪華客船を「弥勒丸」と名を変えて。各地で日本軍が捕えた連合国の捕虜へ連合国からの支援物資を運ぶ目的を与えられ、安全航行が保障された船(これを安導券を持つ船と言う)がなぜ撃沈されたかの謎はなお解明されていない。浅田は、判明している史実に加え、昔から謀略の典型として出てくるM資金の話しを合体させた。軍部が中国支配を続けるための金塊をシンガポールを拠点としてマレー半島で地元金満家から騙してかき集め、船に積み、国際約束の航路を無断変更して上海で降ろそうとして、完全に
★★★
観劇の幅を広め、フォルクローレに酔う
「KERUMANTU CONCERT」(神戸市産業振興センター)。本誌前号に登場してもらったケルマントゥのコンサートである。このフォルクローレのグループとの本格的出会いは、本誌発行法人FASが二〇〇二年秋「おおさかミーティング」(五二号でその内容は掲載)を開いたとき、読者の鳴海幸代さんがこのグループの三枚目のCDを下さり、それを聴いた私が感動して取材を申し入れたということに始まる。編集部も、読者の方々も、梅田や京橋のストリートで聴いたことがある方が多い。さてこのコンサート、編集部が大挙して押し寄せた(と言っても六名)。失礼な言い方かも知れないが、想像を越えるすばらしさであった。ボーカル・コーラスとインカ楽器(大きく分けてケーナという笛類、サンポーニャという吹くオルガンのような楽器、チャランゴという弦楽器、ボンボという太鼓などに加え、ギター、ベース、パーカッション)の双方が良く、心地良いスペイン語の曲に包まれた。メインボーカルのエフライン・エルナンデスの声と楽器演奏能力の水準の高さは図抜けている。とりわけ、「El Condor Pasa(コンドルは飛んでいく)」では、導入部のエフラインの吹くケーナで地球規模の感動が私を訪れ、不覚にも涙が出た。自分のこれまで送ってきた人生、多くの会った人々、別れた人々が、瞬時に走馬灯のように私を通過していったのである。そんな音楽である。三枚目のCDにも収録されている「カリニート(可愛い人)」も良い。また聴きに行きたい。
★★★
東京乾電池公演「雨上がりの夜空に……」(近鉄小劇場)。長く演劇を観ているのに東京乾電池は初めてである。ベンガル、柄本明、綾田俊樹が二七年前に結成している。本作はベンガルと綾田が、関西の藤山直美を招いてつくった、記憶を失った人々が、元の生活を取り戻すために生活する青森県下北郡菩提温泉での共同浴場が舞台のドタバタ喜劇である。言うまでもなく、「雨上がりの夜空に」は、忌野清志郎作詞作曲でRCサクセッションが歌った「こんな夜におまえにのれないなんて こんな夜にはっしゃできないなんて」のフレーズで一世を風靡した曲の題名である。曲は、ポンコツながら当然にいつも動くことが前提になっていたバイクがつぶれた焦りをセクシーメイドで表現するから、この演劇作品との関係では、曲のバイクが人間の頭とか記憶とかということになろう。突然過去の記憶を失い「誰だ私は」という状態になったとき、人はどのような行動をするのか、肉体も記憶以外の精神も普通なのだから、過去をなくしても今を生きる位のことはできるだろうと考えることの愚かさ、記憶を失えば過去へのわだかまりがなくなってその時の能力に合わせて生まれ変わり何にでも誰にでもなれるのかという積極的な疑問などをドタバタの中で考えさせる。つまり人間というものそのものへの正面からの問い掛けである。主演の上記三人のアドリブの多いセリフ、アドリブ演技がみものである。ベンガルのアクの強い演技、綾田の軽妙なノリ、直美の迫力(顔、声、存在自体)と意外な可愛らしさとの落差、緩急をつけた演技は見事である。映画「顔」(本誌四七号で評論)以来、二度目の直美「作品」を観た。
★★★
「SLAPSTICKS」(シアター・ドラマシティ)。どたばた喜劇という演題である。ケラリーノ・サンドロヴィッチ(私は不勉強で知らなかったが演劇界の売れっ子。演劇ユニット「ナイロン100%」を主宰する四〇歳の日本人)作・演出。サイレント映画の終焉を思い出で綴る喜悲劇である。サイレントコメディの助監督ビリー(オダギリジョー)の周辺のハリウッドでの登場人物達と作品そして時代(一九二〇年代)を、一七年後の配映会社社員ビリー(山崎一)の思い出として呼び覚まし再現する構成。後のビリーの時代、トーキー全盛の時代では、サイレントは世間から忘れられかけているかに見え、映画興行主は容易に上映してくれない。サイレントはそもそも限界を持っていたのか、人気俳優だったアーバックル(古田新太好演)の強姦容疑のスキャンダルのせいなのか。しかしビリーは自らの若き日の恋(相手役マリーをともさかりえ)、情熱をかけて映画制作に取り組む仲間達の顔々を思い浮かべては、それらをすべて込めたすばらしい思い出総体の魅力をアピールする。ついに興行主が上映の承諾をしてくれて物語は終わるのである。舞台装置は超シンプルだが、巧みで機能的である。サイレントでもトーキーでも同じだと思われるが、映画制作の現場は特定の人々が濃密な時間を共有するから、いい役者いい制作マンになりたいと思いながら、あらゆる人間関係、社会問題はそこに反映し、恋、コカイン、出世欲、自殺などに取り囲まれ、時に自由恋愛か強姦かがわかりにくい事件も起こる。これらのことをすべて飲み込んだうえで、映画人は好い映画づくりに情熱を傾けていたことを切々ともちろん多くの笑いをとりながらアドリブの多い舞台は進む。女は時と環境に順応でき、男はいつまでも不器用であるという定理?も含みながら、しんみりと舞台はフェイドアウトするのである。カーテンコールが止まなかった。
★★★
「黒蜥蜴」(大阪厚生年金会館芸術ホール)。長年演劇に親しむものとしては、美輪明宏を一度観ておきたいと思って行った。「黒蜥蜴」は言うまでもなく江戸川乱歩の原作で、女賊と名探偵明智小五郎との知恵比べである。私は幼いころ江戸川乱歩の大ファンであったから粗筋はもちろん良く知っているのだが、本作品は脚本を三島由紀夫に拠っているので、単純な話しではなくなっている。つまり才色兼備の女賊と剛柔兼ね備えた名探偵が、自らの誇りを尽くして知恵比べをするうち、互いに相手の出方、考え方を予測し、自らのそれにかける情熱を自己分析し、互いのやり方に慣れ親しみ、やがて愛するようになるという設定なのである。そして更に怪しい雰囲気になるのは、美輪の男女両有的感性が観る者を幻惑するからである。もちろん三島の男女観は明確に示され、愛は同時でなく女をして先に告白させ、男を優位に立たせ、女は犯罪の失敗だけでなく、愛を同時でなく先に告白してしまったことを恥じて自死するのである。なにせ演出・美術・音楽・衣装をすべて美輪が担当する、美輪個人のエンターテイメント舞台なのだが、明智役の高嶋政宏も力演している。舞台、衣装も見事である。歌舞伎と宝塚をミックスした趣の娯楽である。
★★★
007の本質の復権
文学と映画の違い
「マイノリティ レポート」(ナビオ阪急)。原題もMINORITYREPORTスティーブン・スピルバーグ監督。二〇五四年という比較的想像可能な未来を想定しての都市における犯罪予防システムとその欠陥原因探しの物語。コンピューターと人間との関係、システムの欠陥はどちらの原因かを突き詰める展開である。いくつかの評論が、スピルバーグにしては駄作だと言っているが、私はそのようには思わない。未来予知能力者(プリコグ)三人により、未来に起こる犯罪の原因をその未来(時間)までに取り除くというこのシステムのおかげで、ワシントンD.C.は殺人事件がゼロにまでなっている。そのかわり都市住民は網膜ですべてコンピューターにより認識され、プライバシーなどなきに等しいまでの監視・管理下に置かれている。予防局の主任刑事ジョン(トム・クルーズ力演)は、幼い息子を誘拐され妻とも別居状態のもとでも、捜査の先頭に立っていた。しかしプリコグの中心であるアガサ(サマンサ・モートン好演)の未来と過去との混同したかに見える行動に疑問をもち調査するうち、システムはジョン自身が三六時間以内に見ず知らずの男を殺すと予知する。驚愕のうちジョンは逃走し、システム発明者に聞くと、プリコグ三名の予知は一致するとは限らず、多数決でシステムは進行し、切り捨てられた少数意見(マイノリティレポート)があることを知らされシステムの信頼性に大きな疑問を持つ。起こすと予告された自らの犯罪に迫ることでシステムの欠陥に肉薄し、愛息誘拐事件の犯人に近づき、予告された未来を変えたかに見えたが、アガサが予知した外形は起こってしまう。その決着を探るうち、上述のアガサの混同認識は、実は混同でなく、未来を予知していたのだがマイノリティレポートとして無視されたものであることがわかってくる。その予知は意外な男の殺人行為を正確に認識していた。依拠した予知が複数あることがわかり、重大な人物が犯罪にからんでいたことのために、このシステムは廃止される。空中の交通網、空中移動手段、大都市の光景、車の組立工場などに見られるVFX(視覚効果)は、スターウォーズシリーズなどからよりも更に進んだもので、息を呑む迫力がある。監視社会の近未来図も卓抜な出来である。都市と放置された周辺の対比も生々しい。一見の価値ある映画として、丁寧に作られている。
★★★
「壬生義士伝」(角座)。私が本誌四七号で絶賛した浅田次郎の同名小説の映画化。二〇〇二年の正月にテレビが八時間ほどかけて原作に忠実な作品を作っていて、渡辺謙、内藤剛志、岸田今日子がうまい演技を見せていた。原作のイメージが壊れるのが嫌で、この映画は観ないという人もいるのだが、本作品は、大胆な省略と再構成により、短時間の映画という場面でスケールの大きな原作を生かそうとしている。監督滝田洋二郎、音楽久石譲。壬生(みぶ)は京都の新選組の元の屯所(盛時は西本願寺)を指す。吉村貫一郎(中井貴一好演)という南部盛岡出身の文武を最高級に修めた下級武士が、飢饉の生活苦から逃れ家族に送金するために脱藩し、新選組に入る。吝嗇を極める生活をして金をため送金する吉村。しかし心の美しさと腕の確かさとで、近藤など幹部からも隊員からも愛される。幕府が倒れ、新選組が朝敵になる段階で、勤皇の志を守ろうとする者は離脱していくが、吉村は勤皇の心は篤くしつつ幕府に義を立て、瀕死の重傷を受ける。南部藩大坂北浜蔵屋敷に辿り着き、帰参を願うが、心の友である家老大野次郎右衛門(三宅裕司好演)から切腹を命じられ果てる。映画はこの筋立ての細部を、明治三五年の東京、夫婦で開業する大野の息子千秋と吉村の娘みつの医院で、吉村の新選組でのライバルで生き残った斎藤一(佐藤浩市好演)が、病気の孫を連れてやってき、受診中に、千秋と斎藤に交互に吉村のことを語らせることによって進めている。テーマは明治維新前後という動乱の中での家族愛、男女愛、属した集団への義とは何かということであろう。女優の夏川結衣、中谷美紀も好演。実に二人とも美しい。原作が良いから映画も良いという典型のような作品だが、映画は独自の世界で吃立している。途中からずっと泣いていた観客がいたが、貫一郎脱藩時の、娘みつとの別れの場面がとりわけ秀逸である。五歳だったか、みつが「とと、とと」と父にすがる。父も声を殺して泣くが、とと、とと、とと、と泣くみつの間歇的な弱々しく悲しい叫びは、久石の重厚な曲にリズムとして溶け込む。演じた子役の悲しみの表情は脳裏から離れない。名演名演出である。また貫一郎の死を知らされた一五歳の息子嘉一郎(藤間宇宙好演)が、函館戦争に死地を求めて旅立つ際の親友千秋、妹みつとの別れも良い。小川の水を互いに汲みあい水盃にしつつ千秋が問う。「なぜお前のような若い者が死ぬのだ」と。嘉一郎は答える。「大好きなととさが一人で三途の川を渡るのは可哀想だから、俺も一緒に行くのだ」と。川のせせらぎと音楽が分けがたく調和し観る者は感極まる。映画ならではの映像と音楽と演技とが結合した至福の一瞬である。邦画もよい。
★★★
「ボーン アイデンティティ」(センタープラザ)。原題はTheBOURNE IDENTITY。記憶を失ったボーンがボーンであることという程の意味が込められている。地中海に浮かぶ死体と見えた人間は、ピストルの弾丸二発とチューリッヒ相互銀行の口座番号が書かれたプレートが尻に埋め込まれていた。救助したイタリアの漁師たちの友情で快方に向かうが、自分が誰であるかを健忘している。ボーンである(マット・デイモン力演)。チューリッヒで貸金庫を開けると、アメリカ人ボーンのほか五カ国ものパスポートに別の名前で自らの写真が貼られていた。大金も入っていた。自らが容易ならざる身分であることを知ると同時に、殺し屋が次々と彼を襲う。しかし彼は超人的戦闘能力でこれを切り抜けていく。アメリカ大使館で見た金欠の女マリー(フランカ・ポテンテ好演・ドイツ女優でハリウッドに招かれている)に一万ドルを渡し、自宅があるとされるパリまで彼女の車で逃走するが、そこでも襲われる。観客は徐々に彼がCIAのエージェントで、戦闘ロボットのように文武に渡って徹底して鍛えられた男であること、そして彼が組織の命令でアフリカの独裁者を抹殺しようとしてある要因(この作品が連作になるとすればキーポイントになるのではないかと思われる幼い子どもへの優しいまなざしである)で失敗し、ピストルで撃たれ、海に投げ込まれたことがわかってくる。そして失敗したエージェントは知りすぎているから、CIA自体から抹殺されようとする。原作は八〇年代のものらしいが、アメリカが気に入らない独裁者を抹殺しようとする構図は超現代的である。殺し屋とCIAの機関自身から追いつめられていく過程で、ボーンとマリーに愛が生まれ、押さえた調子のラブストーリーにもなっている。アメリカ国家及びCIAの本質が赤裸々に描かれて息を呑むが、観客はパリ、マルセーユ、チューリッヒ、ギリシャなどの映像の美しさにも同時に息を呑む。「スパイゲーム」(本誌五〇号で絶賛)に続き、スパイもので、アメリカ国家の危険性を描く手法である。優れた作品である。ダグ・リーマン監督。
★★★
「007 ダイアナザーデイ」。原題もDIE ANOTHERDAY。英国作品。前作「ワールド・イズ・ノット・イナフ」(本誌四七号で評論)に続き、ピアーズ・ブロスナンのボンドである。二〇作目で四十周年というからすごい長寿作品である。マドンナがテーマ曲を歌っている。今作の監督はリー・タマホリ。今作はソ連崩壊後のボンドの敵創造の苦労から開放されて、正面から北朝鮮を据えたから、久しぶりに明快なメッセージを出せたかも知れない。一九作までの名場面のオマージュが埋め込まれているというからマニアには魅力であろう。ボンドガールは黒人のハル・ベリーと白人のロザムント・バイク。動と静の異なる魅力がある。いつもながら北朝鮮、香港、ハバナ、ロンドン、アイスランドのそれぞれの情景は、目をみはる美しさと迫力で撮られている(もちろん北朝鮮はセットである。北朝鮮にサーフボードで乗り込む際の山のような波は、ハワイマウイ島のジョーズ波現場で、とりわけ大きい波が来るのを待ちに待って撮影したという)。さて、本作のテーマである北朝鮮の高級軍人の危険な戦争冒険と世界征服野望について、北朝鮮がアメリカ(イギリスではない!)を非難している。北朝鮮の政権自体を非難しない点では「シュリ」と同じで迫力はない(本誌四七号でこの点は少し立ち入って述べた)。しかるに北朝鮮が怒るのは主として二つの理由であろう。一つはダイアモンドの不正取引により巨額な冨を稼ぐ点が麻薬取引を彷彿とさせる点、二つは高級軍人が立派な父将軍を抹殺する点が、金正日が金日成に及ばないことを暗示する点ではなかろうか。別にどちらも独裁者で変わりはないが。娯楽作品ながら、機敏に世界情勢を見据え先取りする姿勢は、評価に値しよう。★★★
美しくすごすことはできない
棟方志功展(滋賀県立近代美術館)。久しぶりにこの人の作品をかためて観た。板画の世界である。生誕百年記念とのこと。私の理屈なしですきな作家の一人。明治三六年(一九〇三年)に青森県で生まれ、一九七五年に没した。この人の板画作品は、私の父(明治二六年生まれ)も好きで、私も幼いときから見慣れている。記憶が確かとすれば、昭和三〇年代の文藝春秋に毎月この人の作品が掲載されていた。一七歳(大正九年)のときに青森地方裁判所の弁護士控室の給仕に雇われ二一歳で絵の修業のために上京する。二十代前半で苦労するが、その後は特定の師を持たず意欲と感性で日本と世界に出た。わが国では、保田興重郎、谷崎潤一郎、草野心平などの作品の挿し絵を飾る。難しい美術論はさておいて、棟方の作品の特徴は何であろうか。まず人物画は宗教画も含めてほとんどが女性であり、そのほとんどの顔は豊満で平安美人と言われる下膨れであり、大半はヌードであるか、着衣から胸がこぼれ落ちるように描かれる。男が描かれるときは戯画化されユーモラスである。色彩は朱か黒で極めて扇情的である。動物は意外と写実的であり、目が悪いのでデッサンができないと嘆きながら、実は心の目で本質に迫っている。太い刻線は力強く、描かれる対象は躍動する。この人はふるさとを愛し、ねぶたを毎年愛でたという。この人は、感性のまま生き、女性をこよなく愛したのであろう。菩薩も吉祥天も女性というすばらしい属性の極致だと棟方は捉えている。これほど天真爛漫に女性を賛美した美術家も珍しいのではないか。私はそこに惹かれる。
★★★