

 イラスト 井上奈緒子
イラスト 井上奈緒子
恐慌の時代に冷静にわが国と世界を分析したい 井上久男・伊藤博敏編「トヨタ・ショック」★★★ |
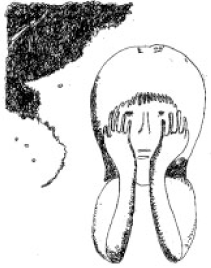 |
演劇 井上ひさし、蜷川幸雄、野田秀樹を讚える NOSAMAP「パイパー」(シアターコクーン)★★★ |
|
映画 現代映画よりも黒澤作品を 「わが青春に悔なし」(NHK衛星第二)★★★ |
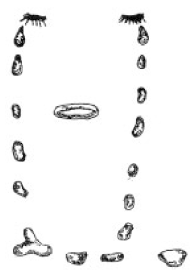 |
文芸 すばらしい天童荒太、飯島和一、鶴見俊輔 天童荒太「悼む人」★★★ |
★★★ 是非一度ふれてみて下さい。おすすめマーク。 |
美術・写真 武藤と小西に出会えた幸せ |
井上久男・伊藤博敏編「トヨタ・ショック」(講談社、2009年)。
元朝日新聞経済部記者などの非常に奥深いドキュメンタリーであり、資本主義、産業構造についての優れた分析書である。〇九年が二兆円の赤字となる予測のトヨタの底なしの泥沼化を誰が予想しただろうか。私が最も関心を持ったのはトヨタのアメリカでの不振は〇七年一〇月期には現出していたのにその対策を間違ったという点である。その時点でもアクセルを踏み続けた。リーマンショックを軽く見た。それら外的要因に合わせて、それまでの成功から現場主義を忘れ、グローバルマスタープランに縛られる利益中心主義に陥り、カローラでなくレクサスに代表される高級車などにシフトした企業体質の変化、幹部の官僚化もあった。もちろん円安を前提にした輸出体質である。トヨタの成功はグローバル経済に組み込まれ、結局はアメリカの金融資本主義で浮利を追うマネーゲームにすぎなかった。ショックの影響は系列企業を襲い、地域経済を壊滅させ(中部経済圏の失速―豊田市の税収は九割減、愛知県も交付税交付団体転落の危機。九州、東北、アメリカ各地も大影響)、車関係の部品メーカー・鉄・ゴム・保険・海運・マスコミ広告がマイナススパイラルの波をかぶり、トヨタ関連の失業者は八万人に達する。プリウスに象徴されるエコカー技術を中心としたスモール・トヨタとしての再生が期待されるとの結論である。多くの人が読むべき内容である。★★★
神谷秀樹「強欲資本主義ウォール街の自爆」(文春新書、2008年)。
住友銀─ゴールドマン・サックスを経てニューヨークで小さな投資銀行を経営しながら、アメリカ経済、追随する日本経済への警告を続けて来た著者の、今次経済危機についての渾身の原因分析書である。読む者は、第二次大戦後の世界復興を支えたアメリカの健全性の減少、変質の歴史を辿る。モノづくりの国から金融の国へ、そして強欲資本主義への歴史を辿る。後掲「エコノミック・ヒットマン」がアメリカによる新興国への搾取・支配システム分析とすれば、本書はアメリカ強欲資本主義による内外市民からの究極の税金搾取システム分析である。本誌前号で取上げた堤未果「ルポ 貧困大国アメリカ」と同じ状況を、被害者の側でなく加害者の側で分析した著作と言えよう。読む者は、ウォール街の主流の投資銀行の実態に驚く。現行法で犯罪にならないことを研究しつくされた倫理的には詐欺にあたる行為のオンパレードで、儲けを追求する経済体制ができている。傭兵のように各金融機関を渡り歩いて投資業務を担う主流の人物たちは例えばサブプライムローンを流通化させればいずれ破綻することはわかっているから、早く稼いで売り逃げるのであり、そのツケは金融機関本体に残り、それを政府が税金で救うか、破綻させるかが今選択されている。市民、企業という顧客のための銀行業務は片隅で息をひそめ、主流の投資銀行は自らのために飽くなき追求をする装置である。そして崩壊しつつある。著者はモノづくりに回帰しないとアメリカが回復する道はないとする。アメリカとの経済同盟を切り、日本古来のモノづくり、道徳観を取り戻さないと日本の生きる道はないとする。日本のモノづくりの伝統に期待と確信を込めて 呼びかけている。会社は株主のためだけのものでなく、従業員、社会のためのものと言う。グローバルスタンダードという名の金融的手法で一時日本経済を活性化したかに見えた小泉│竹中路線への究極の批判書でもある。私は、資本主義の大きな揺らぎである今日、資本主義内部にあって健全な資本主義のあり方を説く本書のリアリズムに感銘する。★★★
ジョン・パーキンス「エコノミック・ヒットマン」(東洋経済新報社、2007年)。
古草秀子訳。原作はConfessions ofan Economic Hit Man。二〇〇四年の著作。
アメリカの国際的コンサルティング会社に所属しながら、特に選抜され訓練を受け、発展途上国に恩恵を施すそぶりをしながらその財政を完全にアメリカの利益(世界帝国を推進する動きの中で、大企業、大銀行、政府の集合体を「コーポレートクラシー」と著者は呼ぶ)に組み込むために活躍したエコノミストが、反省を込めて書いた告発の書とされるノンフィクション作品である。このような者たちをEconomic Hit Man=EHMと略称する。EHMが計画をたて、途上国政府がそれを採用すれば、米大銀行が融資し、米大企業が仕事を請負い、儲けを得ながらその国の外見を近代化、先進国化する。途上国政府は財政で米銀行への元利返済をする。元利返済は通常不可能であるから途上国は代償としてアメリカの属国化される(国連での票、軍事基地設置、資源への権益)。途上国の指導者がこの道を採用しなければ、次はジャッカルと呼ばれる殺し屋が暗躍し、それもうまくいかなければ武力攻撃(侵略)という定式があると著者は言う。
インドネシア、パナマ、サウジアラビア、イラン、コロンビア、エクアドル、イラク、ベネズエラを著者は経験し、分析する。パナマのトリホス大統領はパナマ運河の自主権を主張し続け飛行機事故で死に、後継者のノリエガは腐敗堕落した上でCIAと結んだが米州学校の設置期限の延長に反対したことで、アメリカはノリエガを捕まえるためにパナマを大規模都市空爆し、アメリカに連行し裁判にかけ追放した。
エクアドルのロルドス大統領は自国の石油をアメリカの石油会社から自立的な位置におく政策を取りヘリコプター事故で死に、その後この国はアメリカの手中に落ちた(本書以後、二〇〇七年コレア政権となり反米路線に転じた)。サウジの王家は他の産油国結束を破る盾となる役目を引き受け、オイルダラーをアメリカに還流させ、自らの立場をアメリカから守られ続けている。イランでは国王を失脚させたが、民衆の心を読み違い、イスラム原理主義の宗教指導者が支配する国となった。イラクのフセインは一時アメリカと良好だったが、EHM路線には乗らず、湾岸戦争とイラク侵略で打倒された。ベネズエラのチャベス大統領もアメリカの路線に乗らず対抗したが、フセイン攻撃の合間でアメリカは余力が無く助かった。
そしてブッシュ親子、マクナマラ、シュルツ、ベイカー、ワインバーガー、チェイニーなどの企業人としての顔が明らかにされる。父ブッシュとビンラディンの裏取引も示唆される。著者は言っている。ドルが基準通貨でなくなり、債権国(日本、中国など)が債務返済を迫れば、コーポレートクラシーは崩壊すると。アメリカは大英帝国の操作、騙し、奴隷的仕打ちから独立したのに、今はそれ以上に汚い存在になっていることを嘆いている。
迫力ある内容であり、今後私の様々な研究等において、引用素材として貴重なもので、とりわけ中南米の状況がリアルに描かれて、得難い内容である。しかし、なお描き切れていない弱点があるように思われる。それはEHMを統合するアメリカのコーポレートクラシーの統合意思がどこにあるかを明言しない点である。CIAと暗示しているようにも思えるが、まだ不分明である。もっともこれ以上書くと生命が無いのかも知れない。★★★
町山智浩「アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない」
(文藝春秋、2008年)。
続いて、アメリカ分析の優れモノである。長くアメリカに在住して、日本の雑誌や週刊誌に書き続けた著者(コラムニスト、映画評論家)の評論集である。
アメリカ人にはニューヨークを知らず、天動説を信じ、聖書以外は読まない人々が多いことから始め、宗教が大きな影響を持ち、反知的影響が大きく、格差は広がるに任せ、老後の生活を含む社会保障を株式で運用させていることを述べる。有力メディア(FOXニュース、NYポスト)がネオコン支持者のマードックに買収され、ウォールストリートジャーナルも危うく、マスコミのブッシュ批判の弱さも取上げられる。政治、経済、文化にわたる、身近な話題からのアメリカ再検証(事実に基づくアメリカ批判)となっている。★★★
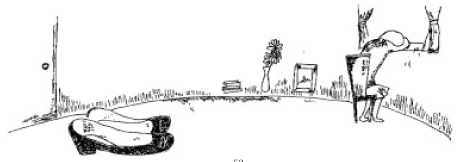
雨宮処凛「生きさせろ! 難民化する若者たち」(太田出版、2007年)。
自らも弟もフリーターの辛酸をなめ(一番辛いのは貧しいことだが加えて誰からも信用されなくなることの辛さ)、リストカットを経験しつつ、自らはたまたま文筆で身が立ったし、弟は実家が税理士だったのでその道に脱出することで、かろうじて死を免れた。しかし、そのような家族福祉的な偶然が無かったら、今の若者が高校又は大学を出た時に就職できなかったり、できても転職することにより、派遣、アルバイトと順を辿り(フリーターとも言うであろう)、企業の使い捨ての道、ワーキングプア、漫画喫茶・ネットカフェ難民、ホームレスまでまっしぐらに落ちて行き、人間としての尊厳を保つ生活はできず、過労死、自殺を含め、生存が危ぶまれるところまで行き着くことをリアルにレポートする。その状態の人々をプレカリアートと呼ぶ。Precario(不安定な)とProletariato(労働者)との合成語だ。若い時にそうなれば歳を取って正規に戻ることはあり得ない。本誌六九号で評論した堤未果「ルポ 貧困大国アメリカ」が、アメリカの貧困を他書にないリアルさでレポートしているのと双璧感がある。必読の書である。(これ以前のところを二〇〇八年秋に書いたが、今更に加える。本書は今世界を襲っている経済大津波のなか、我が国の非正規労働者に起っていることを、二〇〇七年時点で予告し警告した作品として後世に残った。政府、経済界はこの人の言うことを早く学び対策をとるべきであった。否、これまでの政府、経済界はそのような対策をしないことをもって存在したものであるから、本書の警告と現下の対策は別な政府、経済人によっておこなわれることになるのであろう)。そして私はこの著者をインタビューした。★★★
今の恐慌的事態からの脱出と再生を考えるための最適の書を読んだ。
井上ひさしの作品だから文芸に分類されるべきかも知れないが、対象がボローニャと言う都市のすばらしい自治的都市運営の話なので、ここにこの評論を置く。オール讀物に二年ほど前に連載された。ボローニャは北イタリアの都市で二〇世紀ではナチス、ムッソリーニへのレジスタンスで知られる。しかし、作者の関心はレジスタンスにもあるが、中世からの都市の歴史とヨーロッパ規模の文化的、知的伝統にある。その歴史と伝統が自治を生み出している。自治組合的伝統が知と文化を生んだとも言える。自治都市共同体(コムーネ)である。作者は大学、法、映画、映画の修復、演劇、ファッション、サッカー、街並保存、産業博物館、製造業、銀行などのボローニャ的特徴を、じつにわかりやすく、面白く紹介し、日本の政治、経済、文化への警鐘を鳴らし、住民がやる気になればいい例があるよと呼びかけている。★★★
日本人の心を考察する一冊。
山折哲雄セレクションの「生きる作法」全三巻の一冊である。新聞とかの短文は良く読むが、この人のものをまとまって読むのは初めてだと思う。家系は本願寺派だが、本人は宗教学者と言って良いのであろう。国際日本文化研究センター所長をつとめる。最澄、空海、日蓮、親鸞、道元、源信など代表的仏教人の思想の特徴を簡潔に解説した部分と、自らの宗教観、浄土観を披瀝した部分とに大きくは分かれる。前者は便利であり、百科事典と異なり一人の宗教学者が仏教巨人たちを解説するのだから読者には極めてありがたい。しかし迫力があるのは圧倒的に後者である。前者で興味深い記述を少し上げておく。
最澄は変革、転換の時代に顧みられ、空海は安定と発展の時代に蘇るという特徴付け。比叡山対高野山+東寺。/織田信長に破れた石山本願寺から、秀吉による再興と家康による東西本願寺分断支配、体制と本願寺との一体化。西本願寺による維新即応、東本願寺の追随。廃仏毀釈を乗り越えて、改革のきざしはあったが頓挫して現在に至る。/道元の北条政権との接近と在家伝導へのあきらめ、永平寺に帰参してからの出家伝導専一。/法とは仏の教えだが、親鸞は正法、像法、末法と区分し彼の生きた時代の法を末法と呼んだのに対し、道元は法はいつの時代も正法のみと考えた。さて著者が自らの宗教観、浄土観を披瀝する後者であるが、まず自然葬を説く。告別ではなく自然へ、涅槃へ、出発(たびだち)である。身体と離れた不死・仏心を観念する。そのためにラサのセラ寺で死者のからだをハゲワシに食べさせる風習、ヒンドゥーのベナレスの遺体焼却炉と眼前のガンジスに骨灰を流すのみの風習、カルカッタで路上に転がる死体への無関心(非人情)の日常、インドの香の甘ったるさ、宗教音楽の明るさなどを押さえた上で、日本の仏教とインドなどの仏教との違いをまず考察する。非人情の極致でもなく無限軌道をいく慈悲路線でもないというのである。マザー・テレサのような徹底した慈悲路線は非人情の極限に近づくという。これは根本的な現代日本仏教批判ではないであろうか。そして日本人にとっての浄土を考察する。それは山だと著者は言う。日本人の自然観(自然に還る)に裏打ちされていると言う。どこの山にも阿弥陀ヶ原とか浄土ヶ峰があり、谷には地獄谷、賽の河原があるのはそれをあらわすと言う。この日本人の自然観に親鸞なども影響を受け、親鸞は山に加え海も浄土と考えたと考察している。著者の立場は前述の仏教の巨人たちをつつむ日本と言う自然、世界の習俗を踏まえて、日本独特の浄土観を摘出している。★★★
ジョー・オダネル(写真)、ジェニファー・オルドリッチ(聞き書き)「トランクの中の日本」(小学館、一九九五年)。
そして日本人は侵略戦争とそれによる日本国民自体の犠牲を検証すべきである。そのような作品を読んだ。
「米従軍カメラマンの非公式記録」という副題がついている。写真と解説である。凄まじいリアリズムの世界。
オダネルは、一九四五年九月から七ヶ月間、従軍カメラマンとして日本に滞在し、福岡から長崎、広島を撮った。そして帰国して四五年間ネガをトランクに詰め、封印した。それぞれの都市の終戦直後の有り様は、悲惨を通り越しているが、私が最も心を打たれた写真二枚は次のようなものである。
一つは長崎の焼け残った校舎での生き残った児童と先生の授業風景。誰も米軍カメラマンを意識せず(無視して)授業が熱心に静かに進められていく一葉。窓の外は廃墟であるが、教室は塵一つなく磨かれている。児童たちの机の上にはほとんど教科書は無い。教師の言葉を一言も逃すまいと聞き入っている児童たち。カメラマンは疎外されて撮影後教室を後にしたという。
もう一つは死んだ弟を背中におぶって、焼き場の炎の前で気をつけをしている少年。これは何度か見たことのある有名な作品である。彼は係員が死んだ弟をおろして炎に焼べ、脂の焼ける音がしても、一時背中が気落ちしたように丸くなったのに、すぐに直立し背筋を伸ばし、火の中を見ずにじっと前を見続け、そして回れ右をして歩み去ったと言う。
オダネルは、マッカーサーの「老兵は消えゆくのみ」、キング牧師の「私には夢がある」、ジャックリーン夫人の血に染まったスーツ姿など著名な写真を撮り続けた。★★★
藤本威宏「ブーゲンビル戦記─海軍主計士官死闘の記録」(光人社NF文庫、二〇〇三年)。
私は母の晩年親孝行とは言えなかったような気がしているので、母が一九九三年に死去した時、彼女が心残りだったことの一つを実践しようと思い立った。その心残りとは、母が愛してやまなかった弟、私から言えば叔父(柴原次郎)の供養が不十分であったことである。戸籍では、彼はインドネシア、ニューギニア、ブーゲンビル島方面で戦死したとある。母が死んでから一〇年経った頃、ブーゲンビルに叔父の墓参と骨集めの旅に出たいと真剣に思った。しかし調べてみると、今はパプアニューギニア領の自治政府の支配下で内戦は落ち着いているが、マラリアを中心とする風土病が多く、また最も困るのは何度も飛行機を乗り継ぐ必要がある日本からの訪問困難地であり(成田─ポートモレスビー─ラバウル─ブカ─ブーゲンビル)、実現させなかった。いつも心の片隅にブーゲンビルのことがあるが、そんな時本書に出会った。
この文庫は二〇〇三年出版だが復刊で、単行本としては白金書房から一九七四年に出ている。東京商大を出て東芝に就職していたが召集され一九四三年から終戦までブーゲンビルで士官として戦い、珍しく生き残り、現地の終戦処理にも参加した。書き残した日記とともに帰国したので詳細な本書が可能となった。戦後は経済人として活躍した。ブーゲンビルで戦ったと言っても四二年末からはすでにニューギニア戦線は敗色濃く、制空権制海権は奪われ、四三年四月には山本五十六連合艦隊司令長官が、ブーゲンビル島上空で戦死しているのであるから、圧倒的な連合軍の攻撃からジャングルを利用して体力のある限り逃げ続けたと言うことであり、六万の兵士の多くは死んだ。死んだと言っても戦死と言えるかどうかわからないと著者は訴える。食料不足、結果としての栄養不足による病死と餓死が大半であった。「ふるさと」の曲を「うさぎ追いし…」と唄いながら、「お母さん」と言いながら。この悲惨な戦場報告は、何よりもリアルに戦争の実態を描ききっていることにより、日本人のみならず世界の民衆に貴重な宝物を残したと言えるのである。これをどの方向で活用するかは読み人に任せられる。★★★
飯田進「地獄の日本兵 ニューギニア戦線の真相」(新潮新書、2008年)。
上の「ブーゲンビル戦記」が一つの島に絞った報告であるのに対し、本書はニューギニア戦線、日本兵二〇万人全体の報告である。著者はニューギニア島で戦い捕虜となり重労働二〇年の刑を受け、巣鴨に送られ六年服役した。
「ブーゲンビル戦記」と同様、飢えにより死んでいった兵隊たちの記録である。★★★
黒人大統領がアメリカで誕生した。本来はこれに連動すべき中国は、今も官僚的共産主義者によって統治されている。
「都合のいい全訳」(朝日、一月二八日)。新華社がオバマの就任演説の中国語全訳をウェブサイトに掲載したが、中国当局に都合の悪い部分は除いた「全訳」だった。一つは「公金を扱う者は……説明責任を求められる」から「説明」を抜いた。二つは「イスラム世界に対し、私たちは共通の利益と相互の尊敬に基づき、新たな道を模索する」はすべて抜いた、三つは「腐敗と謀略、反対者の抑圧によって権力にしがみつく者たちは、歴史の誤った側にいることに気づくべきだ」もすべて抜いた。これが朝日のコラムである。第一は中国政府の人民への責任放棄である。第二は新疆ウイグル自治区への強圧を意味しよう。第三は中国政府そのものへの批判への恐れである。辛い現実を読む。★★★
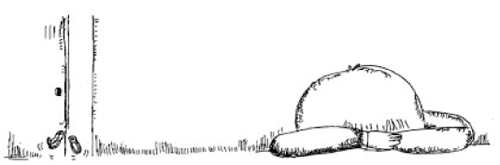
本誌前号で高評価した「キル」に続く野田秀樹作演出の作品である。
「キル」は時代を遡ったが、本作品は千年後の火星、地球から移住した火星での人類の経験を描く。パイパー(コンドルズというダンス集団が演ずる)とは、人の悪意を吸収してエネルギー源とする人類の守護ロボット。移住者のリーダーは野田秀樹が演じ、民主主義と数字を崇拝している。舞台は火星のよろず屋「ストア」。ファボス(宮沢りえ)、ダイモス(松たか子)姉妹(ちなみにファボス、ダイモスは火星の二つの衛星の名)と父親のワタナベ(橋爪功)が住み、ワタナベがムネの大きな女マトリョーシカ(佐藤江梨子)を連れ込み、それに息子のキム(大倉孝二)がついてくる。
移住当時からの人間には、〈パイパー値〉と呼ばれる幸せの単位を計るための装置が鎖骨に埋め込まれている。ファボスにはあるが、火星で生まれたダイモスにはない。死ぬと鎖骨が取り出されておはじきにして保存。そのおはじきには生きた時代の記憶が詰まっており、生者が鎖骨に当てるとおはじきの時代の記憶を見ることができる。なぜかワタナベはおはじきを処分し過去を見せたがらない。ダイモスが無理に見ると、パイパーはある時代から悪意を吸いすぎて悪に転化し、人を襲うようになっており、父と思っていたワタナベは父でなく、ファボスは異父姉だった。どんどんとパイパー値は悪くなり、火星は食料にも事欠く状態になっていく。この地域で食料があるのはストアだけであり、食料調達のための襲撃も増える。地球は核戦争で滅亡し食料船は来ない。薬状食品以外には食料はない。それならストアにある食物とは何なのか。これらの真相が鎖骨とおはじきの組み合わせからわかってくる。その食物を食べて生き残るのか、食べずに死ぬのか。
姉妹の母(松たか子二役)の壮絶な最期も描き出される。人類は追い立てられて金星に移住するしかないが、そこには絶望しかないと暗示される。
野田はこれまでのややドタバタの言葉遊びから、言葉遊びは適切に配置しながら、今の世界の混迷を千年後の火星で象徴してみせた。役者層が厚く、とりわけ、りえと松ちゃんは見事である。りえは艶っぽく、松ちゃんは巧い。二人の膨大なセリフだった。私はこの二人を観に東京での仕事後一泊した。直後、りえの結婚と妊娠六ヶ月が発表された。かなり激しい動きを作中でしていたのに、役者は丈夫なのだと妙に感心した。
大江健三郎の高質な評論が発表されたが(朝日新聞二〇〇九年三月一七日)、低質といえども私もあえて評論する。★★★
作井上ひさし、演出蜷川幸雄のコンビ作品。このコンビの作品は「天保十二年のシェークスピア」(本誌六 二号で絶賛)、「藪原検校」(私は木村光一演出のものしか観ていない。三六号で絶賛)、「道元の冒険」(六九号で評論)に続く四作目(三作は初演は古く、本作も戯曲が書かれたのは一九七〇年である)。
ともかく長い。休憩二〇分を入れて四時間一〇分だったので、BRAVAの椅子では限界である。シアターコクーンの椅子でもエコノミー症候群寸前であろう。作品は江戸中期の享保から安永にかけて生きた平賀源内の一生である。長さは井上の戯曲そのもののせいよりも、井上戯曲を扱う蜷川が最善の理解度をそう定めたということであろう。
才能豊かな(今で言えば医学、薬学、電気工学、画家、作家、貿易商などに精通する)源内が立身出世を求めて様々な分野、地域で苦渋の旅をし、ことごとく中途半端に終わり、のたれ死するのだが、それぞれの風俗を蜷川は丁寧に丁寧に描く。性風俗もとりわけ詳細である。蜷川ワールドの舞台はシンプルのなかに豊かさが表現され、やはり一級品であった。
表裏というのは、人間の積極消極両面を表し、戯曲は役者を二人使う。ハムレットのように一人の役者が複雑な葛藤を選びつつ進むのではなく、表が上川隆也、裏が勝村政信とわける。両者ともに熱演だが、とりわけ勝村は巧い。才能豊かでない観客でも、源内の歩みのどこかの場面に自分を重ね、失敗の思い、人生の難しさの念を共有する。
蛙合戦とは、蛙に意味を持たせているのであろう。蛙の子は蛙ということわざにあるように、蛙は凡人を指そう。才能の豊かな非凡の人も、あれこれと戦っても、徹底して枠を越えなければ、結果は凡人のドタバタと同じという意味であろうか(蛙合戦とは一人の女・メスを巡る男・オスたちの戦争なのだという説もある)。もちろん現代に生きる我々としては、封建と言う制約の時代でもがいた天才へのレクイエムとして源内を見なければならない。高岡早紀は艶かしさで、六平直政はアクの強さで輝いていた。★★★
小さなライブハウスでの音楽芝居である。
Sei ten rai buとルビを振り、副題をSOUL of the SKYというこの芝居は、商業主義に徹した芸能会社ゴールドマンエンタープライズのもとでのタレントたちの使い捨て状況とそれに反旗を翻した女性ボーカル青空あゆみ(小牧芽美)の生き様を描く。あゆみは公園、青空の下で練習を重ね、使い捨てタレントたちとその場所で友情を育む。ゴールドマンの内部抗争、社長とあゆみの血のつながりなどの物語を織り込んで進行する。出演者のダンスはかなりの水準だが、歌はさらなる向上が要ろう。われらが高平万希枝は永津真奈、伊藤恵理子とAripeとして出演、熱演した。三人のつくる劇団ユニット「アライブ」(本誌五五号に登場)を変形させた名であろう。作、演出フランキー仲村。★★★
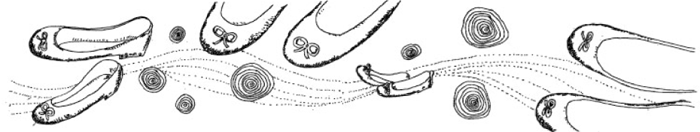
黒澤明没後一〇年記念でNHKが様々な特集を組み、彼の全作品を順次放映したから、できるだけ観ることにした。
一九四六年の作品。終戦直後にこれだけのセットとロケがおこなわれているところにも、我が国の奥深さを見ることもできよう。
京大滝川事件とスパイゾルゲ事件に想をとった久板栄二郎のシナリオを黒澤が撮った。京大教授八木原(大河内伝次郎)、弟子たち、妻、娘幸枝(原節子)が吉田山を散策する明るく清々しい場面から始まるが、昭和八年満州事変の影は学問と大学に暗雲をもたらしていく。八木原は大学を追放され、無料法律事務所を開設し、貧しい庶民の弁護士となる。弟子のうち野毛(藤田進)は抗議の退学、糸川(河野武秋)は大学に残り検事となる。野毛は左翼運動に進むが逮捕され、転向し、八木原家に卑屈な調子で挨拶に来る。野毛に魅かれていた幸枝はすっかり失望し、自活するため上京する。キャリアウーマンの走りである。糸川検事から野毛の転向が本物と思いますかとサジェスチョンされた幸枝は、確かめるために野毛の住まいに押し掛け同居し、妻となる。野毛は自らの本当の立場を幸枝に明かしたわけではないが、幸枝は野毛が反戦自由のために働いていることを確信する。野毛が再び逮捕され、八木原が弁護を申し込むと、未決のまま獄死したことを知らされる。観る者は小林多喜二を思い起こし、野毛の虐殺を確信する。
幸枝のその後の行動が作品封切りから現在まで、識者の中で論争の種となった。自立した女への評価の差である。彼女は野毛の実家の農家に押し掛け、歓迎もされないのに嫁として農作業に従事する。「スパイの家」と迫害されている両親を励まし、来る日も来る日も身体を壊しても高熱のまま慣れない農作業に従事する。両親の信頼を徐々に獲得し、両親も元気になって行く。そして終戦である。八木原は京大に歓呼で呼び戻される。お祝いのために京都に帰った幸枝は、京都に住むよう勧める両親に別れを告げ、吉田山に別れを告げ、野毛の実家農村に帰り、農村文化指導者としてその地で人生を送るのである。直球勝負の反戦自由の作品である。
原節子の、他の作品では見られないきりりとしたほとんど笑顔を見せない表情が清冽である。また糸川検事が幸枝に、野毛の転向への疑問を笑顔で伝える場面などは、検事という権力中枢の役職にも、日本の知識人の自由ぶりの痕跡を伝えようとしていると思われる。脚本に規定されているとはいえ、黒澤のこのような作品を鑑賞することは幸せと言わねばならない。私は京大の反戦自由の伝統に憧れて入学し大学生活をやはりその伝統のもとで謳歌したが、この作品を観るのは初めてであった。★★★
初めて観る。一九四九年のモノクロ作品で、戦後四年目の東京の景色、風俗が克明に作られており、黒澤が最後まで変わらなかったリアリズムの姿に息をのむほどである。
その年のその日は特に暑かった。警視庁捜査一課の新米刑事村上(三船敏郎)は、混み合ったバスでコルトを掏られる。追跡した男は取り逃がし、スリ係に聞いて仲間の女を割り出し、闇市でピストル屋を探すよう示唆される。復員兵の姿でうろつく村上の闇市徘徊シーンが長い。これでもかと東京の終戦直後を映し出す。所轄のベテラン刑事佐藤(志村喬) とコンビを組み捜査するうち、村上のコルトが強盗や殺人に使われていく。辞表は受理されず、犯人検挙を命じられる村上。佐藤の先輩としてのあたたかい指導のもと捜査は続けられる。犯人遊佐(木村功)を割り出し、その女ハルミ(淡路恵子)に張り付き、二人は遊佐を追いつめる。佐藤が撃たれ、非協力だったハルミが遊佐との待ち合わせ場所を教え、村上は撃たれながらも格闘の後、逮捕する。佐藤の一命は取り留められていた。村上に犯人逮捕による警視総監賞が贈られる。
社会風俗のリアリズムのほか、黒澤の哲学も色濃く出る。それは社会と犯罪の関係である。遊佐は復員後、全財産を入れたリュックサックを国内で盗まれ、悪の道に走る。戦争で苦労を重ねやっと復員した下級軍人の大事なものを盗むような日本になっていたことへの遊佐の怒り。黒澤は佐藤刑事の口をとおし、悪を環境のせいにすることは許されないと語る。現に村上も同じ経験をもつが、自暴自棄を乗り越え、悪を取り締まる警察官になったではないかと佐藤は言う。環境は確かに人を過酷な目に遭わせるが、そこで負けたらやはり自らへの負けなのだと黒澤は言うのである。★★★
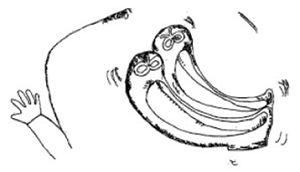 |
一九五四年、モノクロ作品。私の年齢では封切りは観ていないから、名画座や記念上映やテレビ、ビデオ画像で何度も観ている。SFXなどのコンピューター技術を使わない映像として、ナマの迫力を堪能させてくれる。それは騎馬野武士たちの疾走場面、戦闘場面に現れる。それまでの時代劇、その後しばらくの時代劇が持ち得なかったスケールの作品である。ただちにアメリカによりリメイクされ一九六〇年、ユル・ブリンナー主演の「荒野の七人」になったことは有名な話である。 |
一九五八年のモノクロ作品。鉄砲が多用されるから戦国時代の後半か、ただ群雄割拠で合従連衡はあらわれないので時代は結局不特定とするのが良いであろうか。
山名に破れた秋月家。猛将真壁(三船敏郎)は雪姫(上原三佐)とともに隠し砦に籠る。砦の随所に膨大な軍資金が隠され、それを使ってお家再興をめざす。そこに敗残兵となり欲だけがつっぱる百姓の太兵(千秋実)と又七(藤原鎌足)が通りかかり、偶然に木の枝に巧妙に隠した金塊をみつける。真壁は彼らを利用して金塊を運び出す計画に着手する。三人が姫を守りながら敵の囲み、関所をどう脱出するかの様々な方策が延々と展開する。
敵の中の味方づくり、味方の姫の勝ち気の危険さ、槍の一騎打ち、馬上決闘などを織り交ぜ、スリル万丈の物語に仕上がっている。姫と太兵、又七の道行きはスターウォーズのレイア姫とC-3PO、R2-D2ロボットのアイディアにジョージ・ルーカスにより転用された。★★★
久しぶりに一九六一年封切りのモノクロ作品を観た。ヴェネチア映画祭やブルーリボン賞など広く国際的に評価された。もちろんモノクロームだが決して古びていない。時代劇だから古くて当たり前というような意味ではなく(最近時代劇専門のケーブルテレビチャンネルで毎日流している東映作品で、いかにも古いと感じるものが多くある)、映画としての手法が五〇年近く経つのに斬新なのである。モチーフを一九二八年発表されたダシール・ハメットの「血の収穫」(創元社推理文庫)に求めたと言う。ピストルやマフラーが登場するから幕末期ではなかろうか。
冬の上州の小さな宿場町。賭場の開帳権をめぐる二つのヤクザ集団の争いで町は寂れ、棺桶屋だけが繁昌する状態となっている。そこに、問われて明らかな偽名とわかる桑畑三十郎と名乗る素浪人(三船敏郎)があらわれ、二つの集団の双方に自らを用心棒として高く競り売りして、実は対立を利用してヤクザを野だやしにしようと目論む。狙いは的中しそうになるが、それを阻止する人材がヤクザ集団に現れる。一方の集団の親分の弟(仲代達矢)が短銃と知恵を備えて帰って来たのである。ヤクザのパトロンの女狂いを微妙に絡ませながら、三十郎も生死を彷徨う事態を越えて、当初の目的を遂げ、働く全うな町人に町を渡して立ち去る三十郎。筋、殺陣、遠近を巧く使ったカメラワークの色あせぬ新鮮さは見事である。
イタリアで「荒野の用心棒」、アメリカで「ラストマン・スタンディング」とリメイクされた。黒澤作品としては「椿三十郎」に続いていく。仲代、司葉子は今も元気だが、三船敏郎、山田五十鈴、加東大介、志村喬、東野英治郎、藤原釜足、西村晃など他界した出演者の多さには年月を感じるのである。放映としては重要な場面がカットされていてやや残念ではあった。★★★
一九六二年モノクロ作品。劇場でもテレビでも何度も観た。
「用心棒」の桑畑三十郎も景色を見ながら咄嗟に名乗るから偽名だとわかるが、椿三十郎も椿を見ながら名乗る。しかも「もうすぐ四十郎だ」と笑わせ方も同じである。同じ着物、一本指しであるから、続編として作られたことは明らかだが、時代は逆に遡り、戦国がやっと終了した徳川初期ではなかろうか。二〇〇七年に森田芳光監督、織田裕二主演でリメイクされた。
汚職はびこる城内の正常化をめざした九人の若侍が、城代家老に意見書を出したが破られ、次は大目付に出そうとしたところ賛成され、仲間を集めよと指示された。希望を見出した九人が寺で喜んでいるとき、うす汚い浪人(三十郎・三船敏郎)が現れ、岡目八目で見ると大目付の方が怪しいと言う。若者が反発しているとき、寺は多数の侍に取り囲まれていた。縁の下に九人を隠し、追っ手の多数を叩きのめす三十郎。討手の頭目室戸半兵衛(仲代達矢)は三十郎にいつでも訪ねてくれば仕官を世話すると約束する。城代家老は捕われ、その妻娘も幽閉されていた。九人のリーダーは城代家老の甥(加山雄三)で、三十郎は彼等を指導して城代家老救出作戦を練る。妻と娘を救出したが家老の行方はわからない。妻(入江たか子)は三十郎におっとりとした口調で「あなたは、少しギラギラし過ぎます。抜き身みたいに。本当にいい刀は鞘に入っているもんですよ」と言い、イライラさせる。紆余曲折の後、三十郎は「用心棒」と同じく、敵の本拠地を訪ね、味方になる振りをし、家老の居所を探る。大きな立ち回りで敵を多数斬り殺す三十郎を見て、九人は心から三十郎を信頼する。そのうち、三十郎たちがいる屋敷の泉水に隣の椿屋敷から家老が破った意見書の一部が流れてくる。破ったと見せかけて家老は意見書を保存しており、それを千切って泉水に流し、自らの居所を知らせたのである。何と家老は隣家の椿屋敷にいるらしい。三十郎は確認するために単身乗り込み、泉水に椿を流したら救出のために九人で斬り込めというのであった。三十郎は捕縛されるが、九人の集結地は遠くだと言い、出払わせた後で、残った大目付ら老人たちに、実は九人は隣家におり、すぐに斬り込む手はず、中止は椿の花を泉水に大量に流すことだと騙す。斬り込んで来た九人に悪人はつかまり、家老は救出される。そして仕官を断って旅立とうとする三十郎の前に室戸が現れ、凄まじい、しかし一瞬の居合い勝負が展開される。三十郎は「こいつは俺とそっくりだ。抜き身だ。お前達、ちゃんと鞘に収まってろよ」と九人に言い残し、旅に出る。娯楽に徹した作品である。★★★
いくつかの現代映画も。
邪馬台国九州説に立って地元長崎県島原の観光発展に尽くした宮崎康平夫婦の愛の物語である。実話を元にしたフィクションと、字幕にあった。
島原鉄道のワンマン社長康平(竹中直人)はNHK福岡放送局で講演番組に出演し、相手を務めた局員和子(吉永小百合)を一目で(康平は疲労による失明状態であるので声と雰囲気でと言うべきであろうか)気に入り、会社のバスガイド指導員として勧誘し、和子は逡巡の後それに応える。和子は妻に逃げられ、幼い子をあやしながら唄う(これが康平作詞作曲の名曲、島原の子守唄である)康平の優しい面、隠された芸術的側面を見る。
バス事業は順調に発展し観光客は増えたが、諫早大水害のため鉄道もバスも大打撃を受ける。その過程で康平は土器を発見し考古学にのめり込み、社長を解任された。
職を失い福岡に帰ろうとする和子に康平は涙ながらにプロポーズし、和子は受ける。康平は和子を目として魏志倭人伝を始め書物を研究し、各地を調査する。和子は幼い男女児を育てる。高校生に成長した男子が実の母を訪ねて離婚届を書かせ、二人は婚姻届を出す。考古学と観光による地元発展に尽くす康平夫婦は有明銀行頭取江坂(江守徹)など良き理解者がいた。第一回吉川英治賞を受賞し、邪馬台国ブームを生み、ゆとりをもって邪馬台国跡発掘に取り組むようになってすぐに康平は脳溢血で六二歳で死去する。昭和三二年から五五年の物語である。
吉永は加齢したが美しく、九州各地のロケーションも美しい。康平を尊敬するさだまさしの「関白宣言」のヒントになったと言う。作品中ではセリーヌ・ディオンが吉永のために劇中歌「卑弥呼のテーマ」を日本語で唄っている。★★
栗原奈名子監督作品。本誌三七号、一九九五年に登場願い、以後交流のある監督の二作目のドキュメンタリー。前作
のウーマンリブから一転、お年寄り、移民問題を扱う。
紺野堅一氏。一九一二年生まれで、貧困対策として一九三一年にブラジルに移民として渡り、様々な職業を辿りしぶとく彼の地で生活し、一定の安定を得た後、訪日を開始し、妻が死去した一九九五年からは毎年一ヶ月は日本に滞在し、各地のブラジルからの出稼ぎ移民を訪ねる。矍鑠(かくしゃく)として若く、クリアな言動に驚く。
彼が滞日中にすることは、戦前の移民政策の記録を辿りある種の検証作業が一つである。戦前政府の政策の第一は朝鮮満州への移住であったが、自分はブラジルを選んだ。逆だったら自分はどうなっていただろうと回想しつつ、無謀な大陸侵略を静かに批判する。老人ホームで自分よりも若い老人たちに自らの体験を語り、身を以て励ます。
しかし彼が最も力を入れるのは日本各地のブラジル移民たちを励ますことである。日本社会の外国人への差別、異端視といじめに立ち向かい日本社会に根を張る努力の重要さを説き、日本の学校に対しても配慮を求めていく。帰るなら子供が一〇歳になるまでにブラジルに帰らないと、言葉を通じて日本人になってしまうと彼はアドバイスする。帰らないなら社会に奉仕し、日本国籍を取るよう努力し、やがて国境がないような時代が来るから世界市民として生きるんだよと日系二世ブラジル人サッカー少年に優しく説く姿に、観る者はスケールの大きな庶民の存在に涙する。この人が辿った道の厳しさとその道が鍛えた珠玉の言葉と笑顔が心にしみる。
栗原監督はまたも優れた作品を世に送った。監督が上映前に特別挨拶をし、その中で、現在の派遣切りのうねりの中で、この映画を見る目が、完成した二年前とは全く違ったと話したが、私も更生管財人としてブラジル人派遣社員の雇い止めをした者であり、重い気持ちで聞いた。
久しぶりに第七藝術劇場に行ったが、変わりなく優れた作品を上映し続けている。★★★
|
22作目で、六代目ボンドのダニエル・クレイグ主演の二作目である。本誌六六号で評論した「カジノ・ロワイアル」に次ぐ。 |
 |
|
京阪電車で最後の涙を隠しながら読み終わって帰宅すると、ニュースがこの作品の一四〇回直木賞受賞を伝えていた。新幹線のように全部前を向いた座席で読むことを奨める。対面席電車では、流れる涙が異様に写ろう。 天童は一月三一日のNHK週刊ブックレビューに出演し、この作品での死者の考察の基礎には、9・11WTCのテロによる多数の死、その報復として10・7からのアフガニスタン攻撃による多くの市民の死があったと語った。なぜ死を迎えるのかわからない人々の死がとりわけ心をとらえるという。
|
またまたすばらしい作品に出会えた。天童荒太といいこの作者といい、実にヒューマンな作品を生み出してくれる。この時代に生きる者として感謝する。
この作品は一六三七年(寛永一四年)の通称島原の乱と言われる民衆蜂起を題材とする。題材とするがテーマではない。テーマは実に巨大である。究極的には人間の生と言うべきであろう。
幕藩体制とその末端大名である島原松倉家の年貢取り立ての苛斂誅求が描かれる。これに対し蜂起した農民たち、土豪たち。キリシタン(イエズス会のカトリック)の伝統が強かったので、支配への抵抗の精神的紐帯としてキリスト教があったことが描かれる。作者は支配層の強盗的腐敗堕落を詳述し、蜂起層の蜂起がやむを得なかったこと、倫理観の高さを強調する。
しかし作者は分析をここで終わらせない。犯罪的支配層に対し恥辱に耐えよとのキリストの教えに基づき忍んできた農民たちは、貧困と栄養不足から来る病のために自らと子供たちの命が奪われる段階になって蜂起するわけだが、これはとりもなおさず支配層の支配の転覆、現場における敵の殺戮である。やむを得ない蜂起でありその倫理観は高いけれども、蜂起は敵の命を奪うことでしか継続できないのである。この乱は鎮圧されるから逆だが、蜂起が成功したら革命と呼ばれたかもしれない。倫理観の高い蜂起側がやることも殺戮しかなく、その行為は依拠する倫理観と矛盾する。またはその行為を許す倫理は倫理と言えるのかを作者は問いかける。江戸初期の歴史に題材を求めながら、作者は宗教の矛盾、ジハード、テロリズムにも思いを馳せているのかも知れない。
作者は蜂起に火をつけながら離脱し医業で庶民の命を助けるために働くイスパニアの血を祖父に持つ寿安を対置する。寿安も完成した人間ではないから、蜂起勢を皆殺しにした幕閣へのテロを企てるが、患者が医術者としての寿安を求める願いの大きさに「負けて」思いとどまる。そして大坂で医学者として生きる。
ストーリーの大きさと志の高さをもって、作者は読む者へ問題提起をしている。答えは困難且つ永遠の疑問として残るかも知れない。私には答えは今ない。★★★
肉親を含む一二三人に関する一九五一年から二〇〇八年、つまり五七年間に書かれた哀悼の辞である。少しでも知っている人の五九人分を精読した。衝撃を受けた。
第一は思索の広さと悼詞の対象である個々の死者の本質把握の深さとあたたかさにである(傷つけた相手のは書いていないとあとがきにある)。第二は第一の裏のようなことだが私のこれまでの思索の狭さと不勉強への自覚を鋭く突きつけられたことにである。内容を少し記しておきたい。
冒頭の池田成彬に関しては維新人と明治人との区別をし池田もその一人である前者は変革感覚を持していたという(ちなみに後者は順法感覚と言う)。
バートランド・ラッセルは四〇歳位のときの仕事が最も重要なものだが、それから六〇年近くを若い人の業績を謙虚に学びながら業績を上げ、平和運動にも情熱をもった。
高橋和巳は一貫して全共闘運動を支持しながら彼らから攻撃を受け、しかし内ゲバを克服するように上級下級の命令の論理でなく、直接民主主義的に個を尊重するよう訴え続けた。
多くのマルクス主義者が抽象にさいして何か大切なものを落としていると自覚していないのに、梅本克己は自覚していた。マルクスもそうだった。
寺山修司は流行歌評論を得意としたが短歌も秀逸だった。
寿岳文章、寿岳しず夫婦は戦争時代をしなやかに耐え、ともに英文学者として明るく生き、家庭共和国を築いて娘
の寿岳章子を戦争の影響から守った。章子も国文学者として反戦の生涯を送った。
長谷川町子はサザエさんで強い女性とそれに家の指導をゆだねる器量のある男を描いた。
岡本太郎は一貫して「思想の科学」とベ平連を支援した。
司馬遼太郎はノモンハン事変では共感する人が見つからず小説にならなかったが、「草原の記」でモンゴル人の側からそれを書いた。
久野収は滝川事件から「週刊金曜日」まで、私権を守る、自主的な組織を作る、平和の問題を追究する点で一貫していた。
都留重人は鶴見の哲学の教師だった。
小田実は最期の時までギリシャ語を保ち、ホメロスを訳し続けた。
後藤新平の長女だった母鶴見愛子は激しく自分に干渉して育てたから、母を避け、精神も病み、人生に絶望し、不断に闘争したが、どんなに悩んでいた時でも、母が自分を愛していることに確信を持っていた。自分は、一生分の愛情を受けたと思っている。
当然入っていないが二年先輩の加藤周一への悼詞も読みたい。
本書のあとがきに黒川創が選んだとある。本誌前号で評論した「かもめの日」の作者である。黒川は「思想の科学」で鶴見の薫陶を受けた人であった。★★★
本誌前号で小林多喜二「蟹工船」を取り上げた際、朝日新聞で「文芸時評」を担当している斎藤美奈子が吉本隆明批判を鋭く展開していることをとりあげたが、またも痛快な時評である。
村上春樹がこれまでの業績でエルサレム賞を受賞した。選考委員会は「日本文化と現代西欧文化を独特の方法で融合させている」という。そこで彼は、イスラエルのガザ攻撃のさなか、受賞反対が多くあったのでむしろ来たと言って、「もし硬い、高い壁と、そこに投げつけられて壊れる卵があるなら、たとえ壁がどんなに正しく、卵がどんなに間違っていても、私は卵の側に立つ」とスピーチして、好意的な話題になっている。
しかし斎藤は受賞を拒絶すべきだったと思っていると言い、加えて、「こういう場合に『自分は壁の側に立つ』と表明する人がいるだろうか」と言い、「作家はもちろん、政治家だって『卵の側に立つ』というのではないか。卵の比喩はかっこいい。総論というのは、なべてかっこいいのである」とたたみかけた(二月二五日朝日朝刊)。痛快ではないか。
村上がノーベル賞に向けてパフォーマンスをするのは苦々しいと思う人は多いであろう。
朝日のカイロ特派員の平田篤央は、アラブは村上が誤りを犯し許さないと考えているが、彼を愛してもおり、困惑がある模様を伝えている(朝日三月九日)。★★★
丸谷才一「蝶々は誰からの手紙」(マガジンハウス、2008年)
書評の名手、我が国現代書評の確立者である著者の一二〇ほどの書評である。
読む者は、本書のあまりに該博な知識と対象の広さに圧倒され、読みの前進意欲を失うほどである。
まあこの種の本の読み方としては順番に頁をめくり、知っている本か作者、興味のあるテーマが出てくると読むという程度が良いのではないだろうか。全部読もうなどと思うと却って頓挫することになり、私の場合「途中ギブアップ書物」というパソコン上のアイコンに題名だけ収用されることになりかねない。
まず現代書評の基礎的土俵となった毎日新聞の「今週の本棚」、週刊朝日の「週刊図書館」の意義を確認し、戦前の書評を概観し、書評の国とも言えるイギリスの優れた伝統を述べてから、本題に入っている。
少しだけ書評への感想を。
半藤一利「[真珠湾]の日」について誉めながら、昭和天皇の戦争回避決断の無さ、日本国民の戦争支持と戦争嫌悪との心理研究が抜けていると指摘する。
松本健一「評伝斎藤隆夫」について、この戦前の日本の良心とも言える代議士と軍部から攻撃を受けながらも彼を最高点当選させる選挙民を讃える評伝を評価しながら、松本の斎藤評価がなお薄っぺらいことを批判している。
中村稔「私の昭和史」は、私は知らないが著名な詩人であり弁護士である著者の自伝だとのこと。中村の父のことが胸を打った。裁判官だった父の戦前の仕事を軽蔑しながら、調べると父はゾルゲ、尾崎秀実などの予審を担当しかなりの真実に迫っていた。だのに時勢に屈服していた。その心境を生前聞けなかったと中村は悔やんでいると言う。丸谷はこのことを静かに評価している。
大野正男「弁護士から裁判官へ」について、最高裁判所判事の生活がどれほど過酷なものであるかを丸谷は驚き、大野の論理の高さを絶賛し、職業裁判官で多数を占める最高裁が憲法判断をすることの困難を指摘する大野を讃える。
大野晋編著「源氏物語のもののあはれ」につき、大野が本居宣長を越えていると評価する。このような勇気ある評価に読者は快感を得る。
「日本国語大辞典」への評論は内容よりも、このような全一三巻の辞典があることを知らなかった自分を恥じる。
坪内稔典「柿食ふ子規の俳句作法」は、本誌前号に登場した坪内の代表作の一つである。坪内の「三月の甘納豆のうふふふふ」を誉め、同書の構成と坪内の遊び心を貴重とする。
辻原登「ジャスミン」につき丸谷は、奇才ぶりを絶賛しながら、主人公の心の中が覗けないと注文をつける。
丸谷は太平洋戦争から六〇年特集の毎日新聞で、そのテーマを扱う書物を九冊あげ、小説では大岡昇平の「野火」、戯曲では井上ひさしの「父と暮せば」をあげ、村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」のノモンハン描写を誉める。
山口瞳「忘れえぬ人」が三島由紀夫、田中角栄をよく料理しているのを評価し、山口の文章力、話術を教育勅語と対立するアーリーモダン的思想、都市性に求める。
山崎正和「歴史の真実と政治の正義」につき丸谷は、山崎の柔らかい国家観を評価し、著書名が石部金吉だと皮肉を言っている。山崎のこの本が丸谷の評価するような内容なら私も嬉しいが、そうなら山崎が権力から重用されていることと矛盾は無いのだろうかとやや疑問がわいた。まあしかし私はこの本を読んでいないのだから言う資格は無い。
「日本の歴史一巻」への推薦文につき丸谷は自己批判している。藤村新一の遺跡捏造問題である。ひどい内容なのに編集委員が回収、絶版にしないのを怒っている。本書は疲れたが、読後の徒労感はもちろんない。★★★
さるすべり。江戸風俗をしっかり組み込んだ漫画である。私はほとんど読んだことが無かったが、さっぱりした好感のもてる読み切り作品。漫画サンデー連載の文庫化。男性作家のような趣がある。
長屋の葛飾北斎とその娘お栄の二人暮らしに、弟子や居候が加わりドタバタと進むが、遊郭など柔らか系の話題が多い。其角の句や代表的浮世絵風枕絵風の作者の絵が満載の粋なコミックである。北斎と言う天才の世俗的生き様が面白い。そして娘と父、弟子と師匠、版元と作家など様々な人情が溢れる。このような作家が四〇歳台で死去したのは惜しまれる。★★★

本誌六七号で絶賛した「悪人」の姉妹編のような作品である。数段劣る出来であるがやはり水準は越えている。
「悪人」がそうであったように、この作品も実際に起った事件をアイディアにしながら現代を描く。今回は母親の子殺しと学生による女子高生への集団暴行を組み合わせた。後者がメインストーリーである。その上にストーリーテラーとしての週刊誌記者自身の家庭崩壊の生育過程、現在を据えて、いわば順調でない者から、さらに順調でない者を観察するスタイルになっている。
集団暴行事件を起し有罪となった男たちの色々な生き様、被害にあった女性の社会からの扱いをこれでもかと描き、加害者と被害者が許し合えることはできるのか、その条件や心の葛藤を描く。救いの無い世界であり、しかしこのような現実はあるであろうと読者を引きつける暗い魅力を持つ。★★★
初出は昭和五三年から五四年にかけての「週刊文春」。弁護士の松尾直嗣君が長年出している素敵な「とても私的な〜CINEMAGUIDE」誌に面白かったと書いていたので読むことにした。著者唯一の伝奇長編小説だそうである。確かに面白く、電車、新幹線、飛行機の乗車時間合計約四時間くらいで三七九頁の二段組を一気に読んで、終わりたくない、もっと続けて主人公とともにいたいと思った。
徳川十代将軍家治の時代(宝暦、天明。一七六〇〜八六年)のうちの約五年に起る将軍継嗣をめぐる暗闘。三代家光の継嗣後滅ぼされた弟大納言忠長の末裔を将軍にと望む闇の戦闘集団八嶽党、それを利用して家治の世子を殺し、自らの子を家治の養子とし、十一代家斉にしていく一橋民部、それに田沼意次、松平正信が絡む。舞台廻しをする主人公は御家人の身分を捨てた無限流の達人剣士鶴見源次郎である。政治、文化、男女の愛・機微、市井の暮らし、多くの剣士、武闘を時代考証をしっかりとして描くから、得難い娯楽小説となっている。★★★
本誌で「浪速人物往来」シリーズを連載で担当していただいている詩人である著者の小説である。帯に本誌六九号に登場願った俳人・坪内稔典さんの賛がついている。現代に生きる少年竜太と大助が鎌倉時代の地獄草紙を見ることでその時代の民衆の苦しみ、自らを人間とも自覚できぬほどにひもじく苦境にある民衆に思いを馳せ、竜太は父に法然、親鸞の教えの概要を教えてもらううち、夢で竜太丸となり鎌倉時代へスリップする。そこで大助丸に会い、親鸞の弟子から直接教えを受けた大助丸の祖父から親鸞の一生を教えてもらうという構成になっている。法話でなく、親鸞を現代人にわかりやすく理解させるための巧みな方法である。法然を心から敬愛する親鸞はその思想を一歩進め、身分、性別、生業を問わず、またいわゆる悪に身を置く者こそ、また親鸞を苦しめ迫害する敵(古来仏教、それと一体となった朝廷、貴族など)も、他力(釈尊のみを頼る)で念仏すれば救われる(浄土に生まれる)と説いた。自分の学識、徳を高めることで救いを得ようとする自力の道、人を導こうと言う立場を捨てることもその内容に含まれる。当然儀式は廃され、儀式と報酬を結びつけ寺や指導者が肥えることを禁じた。これらは一種の革命思想である。この境地に至るまでの迷い、迫害、たたかいを描く。
著者本来の学識と深い調査に基づき、親鸞の一生、思想がよくわかることは言うまでもないが、著者が本作品に込めたモチーフを考察してみたい。
山折哲雄「日本人のゆく浄土」を読んだばかりの知識で言うならば、始祖親鸞の思想と江戸期以後の本願寺の隔絶がそのひとつであろう。また純粋の仏教の持つ革命的思想の検証もあげられよう。しかし無心論者を公言する著者をしてここまでの作品を書かせたのは、親鸞の思想が持つ永遠の自己分析の厳しさへの共感ではないかと思う。親鸞は自分で説く境地に自らが立ち得ていないことを悟りつつ、死ぬまでその境地を説き続けたという絶対矛盾への共感ではないか。★★★
私は読んでいないが「鴨川ホルモー」、「鹿男あをによし」(いずれも映画化)で人気のこの作者の第三作。舞台が大阪である。 NHKの週刊ブックレビューで、京都、奈良、大阪とご当地歴史物を書いたので、次は別のジャンルに挑みたいと語っていた。
さて、この作品は、大阪には、明治維新時の明治政府との条約により大阪国と言う正式な政府が目に見えないが存在しており、日本国の国家予算を最近では年に五億円程度各種社団法人などを通じて使い、運営されているとする。大阪国の存在は大阪出身の男子に伝承され、その目的は豊臣家末裔の女子を王女として護ることだけであり、王女の危機には大阪国のすべての男子が起ち上がるというのである(危機には大阪城が赤く染められ、通天閣も赤電飾し、伝達はひょうたんを並べておこなわれ、大阪のテレビ局が合図を伝え、大阪は全停止する。それぞれの機関の中枢部は大阪国国民で構成されているから混乱は起きず、全国には伝搬しないそして男たち一二〇万人が大阪城に集結する。しかし暴力はふるわない)。豊臣の大阪城を徹底的に破壊して徳川が作った現在の大阪城の真下に、明治期に、辰野金吾の設計で建設された大阪国議事堂がある(日本国の国会議事堂と同じ辰野の設計で、それよりも古いと言う)。この議事堂と王女を護るための電算機技術の保全更新のためだけに国家予算は使われている。物語はこれだけである。この構想を作品にするために、大阪国を検査する日本国の優秀な会計検査院職員を配置し、市井の中に生きる普通の男、真田幸一を大阪国総理大臣とし、王女橋場茶子は女子中学生とする。王女は代々自らがその地位にあることを知らない。私は読んで、とんでもない話だが心が騒いだ。集結の場面には高揚した。楽しいエンターテインメントである。歴史、法制度、地理をよく調べて作品は出来上がっている。もちろん、王女の危機の平板さ、王女と彼女を取り囲む人物たちの不自然さが払拭されず、構想の壮大さ、奇抜さと比べ残念なレベルだが、読者はその未完成を許すであろう。特に大阪の読者は好感を持って、この稀代のストーリーメーカーに拍手を送るだろう。登場人物の名字は、会計検査院職員も含め、すべて戦国、豊臣時代に活躍した歴史的英雄たちのそれになっている。落ちもある。大阪国は男子により継承されてきたとされるが、大阪の女たちはすべてを知って知らん顔をしているのだと。★★★
第四〇回日展(大阪市立美術館)。武藤初雄「扉」を観に行った。日展の常連となった。前年度特選受賞者である武藤は無鑑査という地位が与えられて作品説明にその刻印がある。「扉」は私がいつも評論している廃ドックの鉄製の巨大な扉である。錆と塗料剥げで赤茶色に変色している様が克明かつ艶やかでさえある。その左横に石製の門柱があり、そのさらに左横にレンガ積みの壁がある。扉の右手前には背の低いドラム缶があり、木片などが入れられている。これらの登場するものは武藤の常用物であり、この茶色の多様さが武藤の若き日からの特徴であるが、初期の作品と比べ明るくなっている。水彩であることをいつもながら忘れてしまう程の色彩の厚さがある。私はこの画家の作品を見続けていられる幸せに浸った。★★★
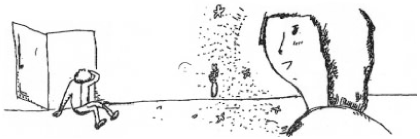
CHu写真展「葉ちるるわ。すぐぐる春の命」(ギャラリー箱/2)
小西忠男こと忠さんの個展である。前の個展は雲が主題だった(本誌六八号で評論)。本来商業カメラマンの忠さんは、資生堂などの仕事をこなしながら、私と知り合う前にはインドを旅し、知り合ったのはニューヨークにいた。その後、尻無川で男のヌードを撮り、舞州と淀川で雲を撮った。そして家の前の公園で今度は葉っぱを撮っている。彼の関心が身近に狭まったわけではない。時にラオスを旅している。そして、ついに岡山の瀬戸内海に近いところに居を構える準備をしている。都市の先端を走った中筋修・安原秀がつくった都住創の住宅から田舎へ行こうとしている。都市と辺境、華美と素朴の両方を愛した写真家が撮ったモノクロとセピアの作品がそこにあった。葉は落ちて春の準備をしていると忠さんは考え、シャッターを押したのであろう。私はこの写真家の作品を見続けられた幸せに浸った。★★★