
★★ 機会があればふれればいいように思います。
★ 時間の無駄です。ふれるなマーク
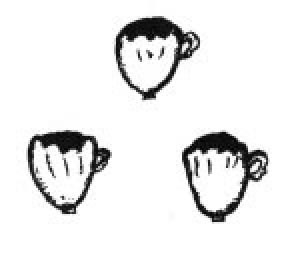 日本の過去と現在、在日朝鮮人、ナショナリズム、民族問題
日本の過去と現在、在日朝鮮人、ナショナリズム、民族問題
立花隆「戦艦大和と第二の敗戦」(文藝春秋二〇〇二年一二月号)。
戦後の人間にとっては、「大和」は図体だけ大きく中身が伴わなず、戦闘において使い物にならなかった代物という感じがあるのではないか。しかし立花の趣味と夥しい調査により、読後読者は大和像を全く異なるものとして形成するのである。「戦艦大和は技術的側面からいうと、…あの時代の技術の粋を集めて造られた世界最大最高の超弩級戦艦」ということである。三万メートル先のどのような軍艦でも(四二センチの鋼板でできていても)沈没させられる。砲塔とその操作機器も、自動装填装置、水圧式駆動装置、照準・発射管制装置、光学式距離測定装置、自艦の揺れを電気機械式自動計算機で判断して砲身角度と砲塔の旋回角を決める装置など高度技術のかたまりで、精査した米海軍もこれは造るのが不可能というほどの精巧なものであった。これらの装置は今のニコンが開発していた。このように技術的優秀さを押さえたうえで、立花はこの戦艦が主砲をほとんど撃つことなく、昭和二〇年四月、撃沈させられた原因として、すでに制空権、制海権がなかったことを上げ、それがどのような原因でいつ起こったかを克明に検証し、単体としての戦艦がどれほど優秀であっても、無保護であれば簡単に撃沈されることを結論づける。しかしそれでも敗戦に至るまで大本営は勝っていると宣伝し続けてきた様を立花は検証している。その上で、バブル崩壊後の日本経済の破綻は、第二の敗戦であるのに、メディアは官庁
★★★
今の日本をどう見るかについて、久しぶりに山崎正和に注目した(一二月三〇日朝日新聞朝刊「経済潮流」)。「バブルの後始末と重なっている日本では構造変化が見えにくいが、不良債権問題が解決しても、人はモノの消費より充実した時間の消費に向かうだろう」というのである。つまり、大量生産、大量消費社会からの脱却という文明的変化が、日本で最も先鋭的、先端的に表れている。失われた一〇年どころか、「大進歩の一〇年」だと思っているというのである。この見解は、バブルの建て直しを意図的に小さく見せている特徴を持つが、日本の通奏低音にモノ社会からの離脱傾向があることは確かであろう。
★★★
台頭するナショナリズムと民族問題を考えるのに便利な本が出た。姜尚中・森巣博「ナショナリズムの克服」(集英社新書〇二年)。東大教授で政治学者の姜が在日朝鮮人の立場で、作家の森巣が若いときから在外生活をし今はオーストラリアでイギリス女性と結婚生活をしているという立場で、それぞれの特別な視点から日本のナショナリズムを考察している。一八世紀頃から民族概念ができあがり、そして分けられた諸民族がそれぞれ国家と結びつくことで、国民国家ができ、ナショナリズムができた。その場合の牽引力として優越感を内容とする人種意識が密接にかかわる。要するに民族概念は、西欧近代の発明物であり、フランス革命やナポレオン以降の国民国家創出に深く関与した。自由、平等、博愛の理念は、フランスの境界線の中だけでしか通用せず、植民地ではひどいことをくり返した。サッチャーは、南アフリカ人種差別支持の理由に、私たちの中にも、アジアやアフリカからきた人たちへの差別があるじゃないかと言っていたことが紹介されている。マックスウエーバー(平和的な資本主義を理念型とした)を基本とする大塚久雄の経済史研究の影響力は大きかったが、アジア的人間類型(民族のエートスなど)がスターリニズムを招来するというような差別意識を基本とする無内容で有害な代物であった。要するに、民族とは文化を同じくするものと言われるが、現代社会の文化状況をみればそれを同じくすることで民族が定義できるはずもなく、また言語を同じくするものと言われても、在日は日本語をしゃべり、標準語からは佐渡の言葉は理解できないという説明不可に陥る。人類学、生態学も差別に結びついている。日本の場合は、これらに加えて国体概念が加わる。国体とは日本民族の本質であると言われ、結局は天皇制と結びつく。天皇制ナショナリズムであり、天皇制があるかぎりアメリカのような国家には脱皮できない。戦後はアメリカの傀儡国家であるがゆえに、ナショナルな純粋性の言説が欲望されてきた。アメリカが日本のためにアジアの問題をかき消してやり、日本は技術力もあり国際関係の大再編成に有利に乗っかった。流れは政治的ナショナリズムから経済ナショナリズムへと変化していった。しかし九〇年代になると政治的な部分にかかわらざるをえない。なぜならグローバリスムの中でなんらかのバーゲニング・パワーを持たないと経済ポジションが維持できないところに行き着いており、そこからネオ・ナショナリズムが強くなっている。これに対抗するのは現状維持では福祉国家イメージで進んだが、それを放棄し治安維持国家イメージに転換しつつある。在日はもともと福祉国家の外にいたから治安管理の対象だったが、これからは全国民が治安管理の対象だから、日本人の在日化という現象が起こると皮肉っている。ヨーロッパ王家は国民国家の原理を元々越えており(ハプスブルグ、メディチ、ブルボン、ウインザー家)、これが一番インターナショナルであった、難民がこのまま増えれば、国境は消えていくとも言っている。国体、国家、民族、人種などの概念のあいまいさと本質を解明しながら、現在日本の新しい民族主義の中身と危険性を考察している。頭の中を色々と整理できる有益な内容である。
★★★
 ここで在日作家の優れた文芸作品一冊を紹介したい。梁石日「終りなき始まり 上・下」(朝日新聞社 二〇〇二年)。本誌四七号に巻頭言をお願いしたのに、今までこの作家の作品をちゃんと読んだことがなかった。もちろん本誌三四号で評論した映画「月はどっちに出ている」の原作者である。四七号に載せたプロフィールをあらためて読むと、本作品のストーリーは主人公の年齢を含めて完全に重なる。自伝の気持ちを込めていよう。タクシー運転手を生業にしている詩人、四四歳の主人公文忠明(朝鮮籍)が光州事件のテレビを東京で見るところから物語は始まる。従って一九八〇年五月一七日から始まるのである。南北両方の在日一世、二世それぞれの複雑な苦悩と、国や民族共通の人間としての悩みとが絡み合い、混とんと澱んだ状況が文忠明を中心にした人間関係を通して紡ぎだされる。その中でも、淳花という女性が物語の縦糸である。忠明は、大阪の高校を卒業し、日雇いに従事し、結婚後ケミカルシューズ雑役などを経て、零細のゴム練り工場で働くが、そこでの悲惨な労災死亡事故もリアルに描かれている。忠明はその後平版印刷事業を自営し、二六人を雇う社長にまでなるが失敗、夜逃げして東京で運転手をしているのである。忠明が愛欲に溺れているのが淳花である。淳花は、父親と諍い、誰とも挑発的に喧嘩するが、文学的素養をもち、伽耶琴など韓国伝統芸の深さに陶酔している。韓国に対する感性の違いから忠明と別れ、小説を書き、様々な著名な賞を取った後、ソウルに行き、ソウル大学国文科を卒業し、韓国舞踊にのめり込み三七歳で死亡する。解説を読むと、淳花は芥川賞作家李芳枝をモデルとしているとのことである。作者は李芳枝の鎮魂のためにも本書を書いたという。物語は二〇年前の忠明の大阪での生活が挿入されながら進む。忠明は、スターリニズム、北朝鮮の権力を否定する人物として描かれ、五〇年代後半から六〇年当時の日本と北朝鮮の関係(帰国事業協定五九年調印、北朝鮮に反対する「組織違反者」は帰国できない問題、六〇年は日本は安保闘争、韓国は李承晩追放闘争、六一年軍事クーデター)、北朝鮮と日本共産党の関係(忠明の八歳年長の詩人金基洙は、五四年頃日本共産党員で総連の関西地区青年文化部長、サークル誌チンダレを発行していたが、総連に離反し忠明らと新しい同人誌をつくることなどの記載から多くのことが暗示されている)が象徴的出来事で語られている。解説によると金基洙は金時鐘をモデルとしているという。さて、本書の題名はどのような意味であろうか。気だるい筆致の中で、作者は上記のような政治関係、人間関係を描くと同時に、在日の心の葛藤と将来展望を描いている。すなわち、本作品では言葉と名の問題が掘り下げられている。まず、日本語と朝鮮語に関し、在日二世が日本で覚えた朝鮮語で文学を書くのは難しい、言葉はその土地の文化の総体のようなものなので、日本にいて学んだだけの朝鮮語で文学は書けないという立場や、これに対しては翻訳文学にも感動するし、日本人でも源氏、近松、西鶴をチャンと読める人も少ないのだからという反論を他の登場人物達に言わせながら、作者の立場が金基洙(金時鐘)の考えとして語られる。「植民地人としての日本語は肉体の中に深く刷り込まれた敵性の言葉であるが、その引き裂きの深淵の中から込み上げてくるもう一つの日本語がある。隠された言葉、歴史の闇に埋もれて呻吟しているもう一つの日本語は、在日朝鮮人の苦悩と重なる。たとえ敵性の言葉であろうと、言葉の力は普遍性を持っているのだ」と。この金時鐘の考えは深い。次に在日同胞が日本人名で演芸やスポーツで有名になっても、在日であることがわかると人気が急落することから、女優李明淑もメジャーになるため改名を要求され、しかし断る場面を作者は用意する。親の考えで帰化していた淳花が韓国籍になりたいと苦吟する場面もある。言葉と名、人にとって本質的な二要素を作者は掘り下げている。これらのことを考え抜くことは在日にとっては終りはないし、その中から淳花や明淑のような突き抜ける人々が出てくることがいつも始まりなのだと作者は言っていよう。なお作者の日本に対する評価は、同時代批評という雑誌を主宰する文芸評論家岡田敬造の言葉として語られていると思われる。水俣病のいいかげんな扱いを論じて、日本の企業、行政、裁判所をきびしく批判し、今の体制が続くかぎり、この国は亡びると断言している。私にとって読みやすい文体ではなかったが、珠玉の思想とこよなき真摯さを発見した。作者には次第に明らかになる北朝鮮の拉致、核問題などを聞いてみたい。
ここで在日作家の優れた文芸作品一冊を紹介したい。梁石日「終りなき始まり 上・下」(朝日新聞社 二〇〇二年)。本誌四七号に巻頭言をお願いしたのに、今までこの作家の作品をちゃんと読んだことがなかった。もちろん本誌三四号で評論した映画「月はどっちに出ている」の原作者である。四七号に載せたプロフィールをあらためて読むと、本作品のストーリーは主人公の年齢を含めて完全に重なる。自伝の気持ちを込めていよう。タクシー運転手を生業にしている詩人、四四歳の主人公文忠明(朝鮮籍)が光州事件のテレビを東京で見るところから物語は始まる。従って一九八〇年五月一七日から始まるのである。南北両方の在日一世、二世それぞれの複雑な苦悩と、国や民族共通の人間としての悩みとが絡み合い、混とんと澱んだ状況が文忠明を中心にした人間関係を通して紡ぎだされる。その中でも、淳花という女性が物語の縦糸である。忠明は、大阪の高校を卒業し、日雇いに従事し、結婚後ケミカルシューズ雑役などを経て、零細のゴム練り工場で働くが、そこでの悲惨な労災死亡事故もリアルに描かれている。忠明はその後平版印刷事業を自営し、二六人を雇う社長にまでなるが失敗、夜逃げして東京で運転手をしているのである。忠明が愛欲に溺れているのが淳花である。淳花は、父親と諍い、誰とも挑発的に喧嘩するが、文学的素養をもち、伽耶琴など韓国伝統芸の深さに陶酔している。韓国に対する感性の違いから忠明と別れ、小説を書き、様々な著名な賞を取った後、ソウルに行き、ソウル大学国文科を卒業し、韓国舞踊にのめり込み三七歳で死亡する。解説を読むと、淳花は芥川賞作家李芳枝をモデルとしているとのことである。作者は李芳枝の鎮魂のためにも本書を書いたという。物語は二〇年前の忠明の大阪での生活が挿入されながら進む。忠明は、スターリニズム、北朝鮮の権力を否定する人物として描かれ、五〇年代後半から六〇年当時の日本と北朝鮮の関係(帰国事業協定五九年調印、北朝鮮に反対する「組織違反者」は帰国できない問題、六〇年は日本は安保闘争、韓国は李承晩追放闘争、六一年軍事クーデター)、北朝鮮と日本共産党の関係(忠明の八歳年長の詩人金基洙は、五四年頃日本共産党員で総連の関西地区青年文化部長、サークル誌チンダレを発行していたが、総連に離反し忠明らと新しい同人誌をつくることなどの記載から多くのことが暗示されている)が象徴的出来事で語られている。解説によると金基洙は金時鐘をモデルとしているという。さて、本書の題名はどのような意味であろうか。気だるい筆致の中で、作者は上記のような政治関係、人間関係を描くと同時に、在日の心の葛藤と将来展望を描いている。すなわち、本作品では言葉と名の問題が掘り下げられている。まず、日本語と朝鮮語に関し、在日二世が日本で覚えた朝鮮語で文学を書くのは難しい、言葉はその土地の文化の総体のようなものなので、日本にいて学んだだけの朝鮮語で文学は書けないという立場や、これに対しては翻訳文学にも感動するし、日本人でも源氏、近松、西鶴をチャンと読める人も少ないのだからという反論を他の登場人物達に言わせながら、作者の立場が金基洙(金時鐘)の考えとして語られる。「植民地人としての日本語は肉体の中に深く刷り込まれた敵性の言葉であるが、その引き裂きの深淵の中から込み上げてくるもう一つの日本語がある。隠された言葉、歴史の闇に埋もれて呻吟しているもう一つの日本語は、在日朝鮮人の苦悩と重なる。たとえ敵性の言葉であろうと、言葉の力は普遍性を持っているのだ」と。この金時鐘の考えは深い。次に在日同胞が日本人名で演芸やスポーツで有名になっても、在日であることがわかると人気が急落することから、女優李明淑もメジャーになるため改名を要求され、しかし断る場面を作者は用意する。親の考えで帰化していた淳花が韓国籍になりたいと苦吟する場面もある。言葉と名、人にとって本質的な二要素を作者は掘り下げている。これらのことを考え抜くことは在日にとっては終りはないし、その中から淳花や明淑のような突き抜ける人々が出てくることがいつも始まりなのだと作者は言っていよう。なお作者の日本に対する評価は、同時代批評という雑誌を主宰する文芸評論家岡田敬造の言葉として語られていると思われる。水俣病のいいかげんな扱いを論じて、日本の企業、行政、裁判所をきびしく批判し、今の体制が続くかぎり、この国は亡びると断言している。私にとって読みやすい文体ではなかったが、珠玉の思想とこよなき真摯さを発見した。作者には次第に明らかになる北朝鮮の拉致、核問題などを聞いてみたい。
★★★
戦争と戦犯を描く文学
城山三郎「落日燃ゆ」(新潮文庫)。激しく感動した。七四年出版のこの作者の代表作を二八年も経って読む不明を恥じた。いくらでもチャンスはあったろうにと残念である。また読んでいれば当時から何程か私の人生観が変わっていたのではないかと思えるほどの衝撃を受けた。広田弘毅と一国の外交を描く。「軍部、右翼団体の支持を得て外相、首相をつとめ、A級戦犯で絞首刑になった人物」というのが私の広田に関する基礎知識であり、八一年にでた平凡社の世界大百科事典二六巻にもそのような記載があるから、あながち私の常識を唾棄すべきものとは言えない。このような人物の評伝風小説に私の興味が延びなかったのは当然ではあった。しかし城山は全く異なる広田を描いた。夥しい参考文献を読み込んで、わが国の外交官として軍国主義に身を挺して戦い、それでも軍国主義の昂進を防げなかった責めに殉じて、東京裁判で一言の弁解をすることなく、「自ら計らわぬ」生き方を貫き、文官としては唯一人刑場に消えた広田に、城山は本作品で渾身の力で鎮魂の辞を述べている。城山には様々な名作があるが、この一作をして文豪の域に到達したと言えるであろう。広田は石屋の長男として生まれ、貧しく、進学は難しかったが、父の友人が父を説得し、一高東大を経て外務省に入った。同期に吉田茂がいる。努力型の人で座禅、柔道にも親しんだ。この柔道場が自由民権の流れを組むが後に右翼団体と目された玄洋社であり、大きな影響を広田の運命に与える。中学を出ると論語の一節から考を得て丈太郎から弘毅と自ら改名。日清戦争後の三国干渉を見て、広田は外交官を志す。不世出の外務官僚と言われた山座円次郎に東大時代から可愛がられ、満鮮シベリア調査を委託されたりしている。広田のような有望な外交官には名望からの縁談があったが取りあわず、同郷の自由民権の貧しい志士の娘静子と結婚する。指輪は貝細工であった。生涯爵位、位階勲等に関心を持たなかった。遊ばずに勉強につとめ、若き日に北京、ロンドンと赴任する。山座と親友が突如死んだが、悲しみの中でも必死で勉強し、徐々に政治力の必要性も自覚していく。支那、東洋との友好発展が山座の教えを守る広田の基本的考えであった。地味に徹していたが、早くから広田は省内で「大臣」と目されるほどの力をつけていく。昭和五年の駐ソ大使赴任以来、昭和八年外相、二・二六事件直後の昭和一一年三月首相、昭和一二年外相などを通じて、広田は関東軍、軍部の侵略的行動と一貫して命を懸けてたたかい、和平の道を探った。もちろん清貧であった。中国、アメリカ、イギリス、ソ連を引きつけながら、軍部に対抗したのである。結果的には破れたことになろうが、このたたかいの様が本書の圧巻部分である。城山は主観的に広田を好むゆえに広田擁護の作品を作っているのではない。凄まじい決意で、資料に基づき事実を発掘している。この事実の摘示で誤った広田像が瓦解するのである。広田の実績からすると東京裁判では、いくらでも無罪の弁論ができたであろうのに、広田は弁護人の奨めを拒否し、全く弁明しなかった。弁明には他者への非難が必ず入ること、またこの裁判は勝者が敗者をさばく政治であるとの確信からであった。死刑執行直前の手紙、発言に至るまで一切不満や愚痴を残さず、ただ面会に来てくれた人々との思い出や感謝、不自由な房生活での楽しみなどに専一されていた。城山は広田の死生観を詳しく書く。まず広田の母タケは、八〇歳になり病状が悪化したとき一目弘毅に会いたいと願ったが、オランダ公使だった広田の帰国が無理だと知ると、一切食事を受け付けずに餓死同然の死を選んだ。その時から広田は死はいつでも選び取って見せるという気になり、母がそれを励ましてくれていると感じた。次男忠雄の自殺からも広田は死を身近なものとする。また東京裁判の後半、広田の運命を察した妻静子は、六二歳で自ら命を絶ち、後に続く広田を励ました。広田はそれを知って、意図を理解し、感謝しながら、留守宅に出す手紙には最期まで「シズコドノ」と書いたという。その文字が見られなくなったとき、すなわち広田が死ぬとき、はじめて静子も本当に死ぬのだと考えたと作者は書いている。昭和天皇像も興味深く描かれる。関東軍の跳梁には不快感を示し、統帥としては不拡大方針なのに、軍部がその統帥権を侵していると怒り、天皇機関説の正しさも理解していたが、広田に首相を命じたとき「名門をくずすことのないように」と特に注意し、官僚、軍部への配慮を指示している。軍部の理屈は、天皇の御意向に背いても日本の利益になったら大忠で、背かず従うのは小忠だと言うのであった。軍部の侵略拡大方針を国民世論が支持した点も書き加えている。短い首相時代、文化勲章を制定した。先輩である名門出の幣原喜重郎との若いころからの確執やある種の信頼も書き込まれている。吉田茂の人生も脇役ながらしっかり描かれている。吉田茂が元々は軍部と親しく若き日には中国侵略の旗振りであった。松岡洋右が元外務官僚であり、シベリア出兵などには反対していた事実など知らなないことが多く勉強にもなった。後半生の座右の書がまた増えた。
★★★
吉村昭「プリズンの満月」(新潮文庫)。九五年の作品である。城山の「落日燃ゆ」が戦犯側から東京裁判と戦争責任を描いたのに対し、この作品は巣鴨プリズンの刑務官から東京裁判と戦争責任を考察している。旧東京拘置所(巣鴨プリズン)の跡地は、池袋地域の再開発の中心地となり七八年には、当時日本で最も高いビルとなったサンシャイン六〇が建てられた。その側の公園にスガモプリズンの処刑場があったことを示す、石碑が建っている。主人公鶴岡は巣鴨プリズンにも勤め、定年まで各刑務所等を廻り、定年退官した元刑務官である。定年まもなく、元の上司からの誘いで、サンシャイン六〇となるビルの現場事務所の責任者を頼まれ着任し、巣鴨プリズンを思い起こすのである。彼は熊本刑務所勤務の刑務官であったが、占領軍の意向で全国から優秀なものを集めるとしてプリズン勤務をしたのである。作者のアメリカの占領政策や東京裁判に対する主張は明確である。「戦争裁判は、勝利者が敗北者をさばくという、基本的に公正さを欠いたもので、A級戦犯に対しては国家指導者としての平和に対する罪を問い、多くを極刑に処した。しかし、非戦闘員の大量殺害を目的とした都市への相次ぐ焼夷攻撃、さらに広島、長崎への原子爆弾の投下こそ平和への罪とすべきであるのに、それは全く無視されている」と、作者は鶴岡を通して信条を語っている。そのうえで、作者はプリズンの管理体制、刑務官の立場、戦犯の様子、国民の感情などを詳しい調査に基づいて克明に描く。「管理体制」の面では当初の銃剣での過酷な管理から、徐々に緩み、管理が日本に移管され、面会所の金網も撤去され、一時出所も許され(これにより家族の本当の窮状を知ることになる状況も克明である)、職業補導のための臨時外出、後楽園球場での野球見物(第一試合は大映・大洋、二は国鉄・毎日、三は巨人・東急)にまでいたる。刑務官の仕事が徐々になくなるのである。「刑務官の立場」の面では、当初米兵がおこなう管理の補助要員として日本の刑務官が銃を持たされた時点では、戦犯達の刑務官に対する反発、戦勝国にへつらうものとしてきびしいものがあった。しかし刑務官は日本人であり、その前に人間であるから、公然とアメリカ軍の行為に反発し、炎天下、戦犯の日除けをたたき壊した米兵を平手打ちにする刑務官も出現するようになる。処罰されながらも屈しない刑務官、その行為で戦犯に麦藁帽子が配られるようになり、戦犯との関係が和らいでいくのである。歴代巣鴨プリズン所長は気骨ある人物として描かれている。「戦犯の様子」としては、A.C級にわけて叙述があるほか、国際情勢が戦犯にあたえる影響も克明に描かれる。米ソ戦争の危機、講和の動き、講和条約の発効などに一喜一憂する戦犯。もちろん詐病、偽の精神かく乱を装うものも出る。父母のためには透徹した心境の遺書を書きながら、教誨師にはアメリカに対するうらみを語る死刑囚も描かれる。極刑の戦犯の前ではただ泣くだけの住職、教誨師田嶋も登場する。しかし彼は世界宗教会議に提訴し、世界的な署名運動に走り回り世界的共感を受けたのである。「国民感情」の面では、自発的慰問の申し入れが描かれる。当時の日本の一流の舞台人による慰問から始まる。所長、刑務官らは最初はアメリカ人でもわかるバレーなどから徐々に日本の芸能に広げていっている。釈放運動が徐々に広範に起こり、日弁連も「戦犯釈放特別委員会」を設置し解放運動に手を付けたとある。「題名」は、夜の警備で鶴岡が見た驚くほど大きい満月が、庁舎の上に昇っており、それが鶴岡には、血のついた鶏卵の黄身のように朱の色をおび、月面の陰翳も浮き出ているように見え、戦犯が鉄格子越しにこの月を見て、なにを考えるだろうと想う場面から採られている。作者はプリズンにかかわる様々な立場の人間に克明に焦点を当て、戦争の悲惨と国家の行為の誤りと身勝手を淡々と描き、読む者に濃密な感慨を与えている。
★★★
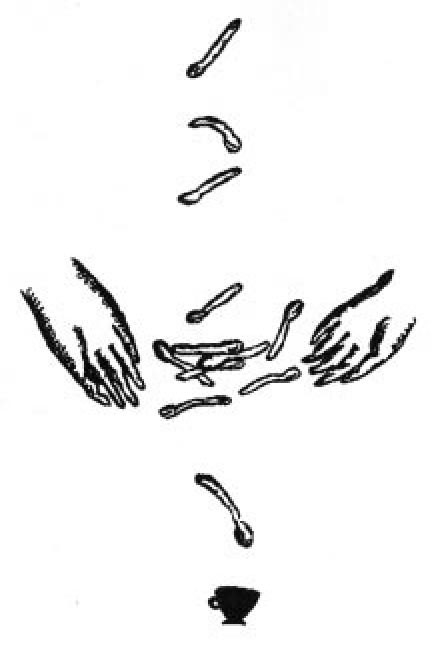 気分を変えて他の文芸を。
気分を変えて他の文芸を。
石田衣良「うつくしい子ども」(文春文庫)。本号の巻頭言をお願いした著者の九九年の作品。初めての長編とのこと。九七年の酒鬼薔薇事件を題材にしている。題材という意味は、少年の心に残酷な殺人意識が生まれる経過とそれを社会と肉親がどう受け止める可能性があるかの考察であって、実際の事件とはシチュエーションも人間関係も似たところはない。非常に優れた作品に仕上がっている。ぼく、こと三村幹生は人工のニュータウンのなかにあるエリート校、夢見山中学の二年で、ニキビヅラでジャガと呼ばれ美しくないのに対し、中一の弟和枝(カズシ)は美少年、小三の妹瑞葉(ミズハ)は美少女である。ミズハの同級生女児が夢見山の奥の山山中で惨殺され木に吊るされていた。これをぼくと新米の新聞記者山崎の両視点から追求する。現場には「PRINCE OFTHE NIGHTこれが最後ではない」との銀スプレーによる暗号が残されている。カズシが犯人とわかってから、報道攻勢は嵐のように迫り、家族のプライバシーが過度に流出され、市民感情が犯人の家を押し潰す。家族は転居、父母は離婚に至る。しかし、兄のぼくは弟の気持ちをすこしずつ明らかにしようと努力を始める。山崎記者もそれに打たれ協力する。数少ないが協力してくれる友人も配置される。その結果、エリート校の問題点が次々と明らかになる。建築賞をとった建物だが、設計は監視システムの思想が組み込まれており、超エリートの松浦という生徒の専制支配が隠然とまかり通っていた。弟を支配したエリート松浦も美しい少年であった。読書量もすごく、一年で二〇〇冊も読み、その内容はフランクル、ニーチェ、内田百に及ぶ高度のものであった。ぼくは同時に、ホラー映画を弟がどのような気持ちで見ていたかも考察し、平凡な日常の退屈との対比にぶちあたる。作者は事件が決してぼくの家庭に問題があったのではないと力説している。むしろたたき上げの警察官で署長にまでなった松浦の父親の教育方針などに因果関係を求めている。ぼくが真実に接近するに連れて、松浦はミズハを狙うが、前述の人々の協力で事無きを得て、衝撃の終りに至る。該博な植物の知識を織り交ぜて、著者は少年の心に生まれる闇の深さと真剣に向き合っている。名作であろう。
★★★
「倉橋健一詩集」(現代詩文庫一六六、思潮社、二〇〇一年)。本誌に「浪速人物往来」を連載していただいている氏の若い時代からの詩集の主なものがこの権威ある文庫に納められた。めでたいことだ。当代の名のある詩人がすべて収録されている文庫である。いただきながらじっくり読もうと思って置いてあり、やっと二〇〇二年の暮れに読んだ。「浪速人物往来」のすばらしさは定評のあるところで、ファンも極めて多い。単行本にする日が待たれるところである。これまで私は氏の作品については、本誌四一号で絶賛した「藻の未来」を評論したにとどまっているが、本文庫にもそれは収録されている。しかしそれを除く、若いころからの詩は、難解で私には全体としてわからなかった。解説にも難解で有名とあるから安心したが、徐々に親しんでみようと思う。しかし本書において氏のことはよくわかった。わからぬまでも詩作品から、評論から、諸解説からもである。一本気で激しい生き方である。三〇歳までくらいは政治的人間で、それ以後はそれを極端に嫌いつつ(と松原新一が解説している)、政治的に激しい動きや激しい人間に関心を抱き続けている。マルコムX、チェ・ゲバラ、エリナ・マルクス、レオン・トロツキー、樺美智子、ロバート・キャパなどが繰り返しうたわれる。この激しさと、人柄に接したときの柔和さが渾然と融合しているのが氏の本質であり、おそらく詩もそのようであるだろう。氏は、梁石日が「終りなき始まり 上・下」で登場させた金時鐘にあつい関心を注ぎ続けていると松原が言っている。一度お話を聞いてみたい。
★★★
細井文衛詩集「二の腕さん」(百人浜書房、二〇〇二年)。私が大学卒業後、二度目に選んだ一九七一年の公務員職場には、いま私が知るだけで三人の偉大な芸術家がいたことになる。一人は現在の我が編集部の画家武藤初雄氏であり、もう一人は元我が編集部の写真家福島明博氏であり、今一人が詩人細井文衛氏である。このところ一年に一冊のペースで詩集を発刊している。第一が「二十年後の朝顔」、第二が「歹」、第三が「風の通り道」、第四が本作の「二の腕さん」である。「風の通り道」までの人生への正面タッチという作風から、本作は狂言タッチである。装丁が豪華になり、意気込みは重いが、作品は意識して軽くしてある。本作の意図を最も象徴する作品は「声援」であり、あらゆる頑張れ発言が適切と思われる場面で、「あ.ぁ草臥れた」と言おうという呼びかけである。勉強中の子ども、マラソンの沿道、営業社員、結婚式場、病院、学校、会議室、立ち呑み路上で「あ.ぁ」と言おうというのであり、日本を変えるかも知れないのである。その他、男女の仲で決定的な「おしまい」の言葉があることを嘆き、世の中が色々科学的に解明されるに連れ神秘な力が失せていくことを嘆く「ちちんぷいぷい」、あなたなしでは生きてゆけないと思いつつ、生きてもいける実感をうたう「器」などコミカルに作った合間に、「メール」では、彼と彼女のメールの送信と受信が同時である意味を喜ぶ。詩を私は美人の部長のもとで会計か何かの役職を与えられて高校時代書いていた。しかし、詩は短く人間を抉り取るがゆえに、作品の理解は難しいことが多い。本作は、詩のその理解不能性傾向から脱却した読者本位の境地に到達したと言えよう。
★★★
紀香のアフガン写真展親しい人々の個展
藤原紀香「アフガニスタン写真展」(東京国際フォーラム)。藤原紀香という国民的人気者が、テロとアメリカの空爆のどちらにも抗議しながら、所属事務所の抵抗を押し切って、二〇〇二年夏、危険の渦巻くアフガンを旅し、一五〇〇枚以上の写真を撮った。写真は雄弁であり、撮影対象となった民衆、こども、街、遺跡は、タリバンとアメリカ軍により傷つけられ破壊された生々しさをリアルに伝える。しかしこの写真展がすばらしいのは、展示作品の解説テープや図録(「カンダクウ 笑顔で」★★★)で紀香自身が、アフガンを語っていることである。図録の「私が出会った数えきれない悲しみと新生への希望……」という文章は、本当に紀香が書いたとすれば、極めて優れた叙情および叙事の作品である。将来は文筆でも世に出るかもしれない。紀香が現地で本当の悲しみを見てきたことが、心にしみるタッチで綴られている。出発時に携帯する鞄に入れた物品、天井に砲弾穴の開いた血まみれのホテルの部屋などに驚愕しつつ、義足や指が吹き飛ばされたこどもたちと交流するのである。鬼ごっこも、ブランコづくりもして。親兄弟姉妹を失った極貧のこどもたちとの別れは辛いが、こどもたちは「カンダクウ(泣かないで、笑って)!」と言って紀香を励ましている。彼女はインタビューに答えて、現地に学校を作りたいと意欲を語っていた。世の動きが速すぎて、忘れやすい現代人に、人間が起こしたアフガンでの出来事をこのような形で記録したこのアクトレスに、心からの敬意を払う。いつかインタビューしたいものだ。
★★★
いのうえなおこイラスト展「すてきな明日のために」(きさら堂)。本誌最年少編集部、井上奈緒子の初個展である。彼女は本誌五〇号から、当面、私の評論のカットを描いてくれている。このカット絵の意表を突いた面白さは、読者から好感をもって迎えられているが、この個展は更に彼女の才能の面白さを良く出したものだった。木に描いた小品だが、色が付くと一段とファンタジーである。対象は婦人靴、車、ティーカップなどであり、その色調の明るさ暗さ、形象の抽象化は、観る者の心をホッとさせる温かさに包まれている。四月に美大を卒業し就職するようだが、いずれ世に出るだろう。それにつけても京都はいい。久しぶりに車でなく叡電で一乗寺駅から会場のCafeまで、北白川疎水を横切ってしばらく歩いたが、静かな落ち着きがなお残り、気分が高揚した。
★
★★
「五人展」(アートスペースフジカワ)。武藤初雄、岸本恵美、中辻修、上田素久、榎本秀利という関西に根を張る水彩画家の共同展。岸本は本誌二号(八五年)にご登場いただいている。その後、安井賞も受賞した実力派である。当然のことながら、どんどんと画風を変化させており、本展ではデッサンの上に少し絵の具を配する画法で、対象の爽やかな発見を観る者に与える。中辻は窓のブラインドの写実作家である。幾度となく作品を観てきたが、ともかく気分が良い。今回は一転ワイン、ウイスキーの瓶の群像または個像である。そして武藤。浜辺の光景、冬日、ドックなどの継続的モチーフととともに、珍しく青地に金色を多用した日本画風の「母の肖像」五〇号が目立った。ミシンと洋裁鋏などおそらく亡き母堂の思い出の品々が対象となっている。誰もがそうであるように、武藤もまた五〇歳なかばになり母を想っている。母とは、顔形も匂いも懐かしいが、身近にあった道具が思い出を象徴することもあるのである。芸風の広がりを喜ぶ。
★
★★
演劇、ジャズ、オペレッタ、落語のライブに酔う
「桂米朝一門会」(堺市民会館大ホール)。市民寄席と名を打ち、昭和五四年から実に二四回目なのである。私の米朝一門詣は本誌四九号に続く。この日は、まん我が「平林」、九雀が「親子酒」、吉朝が「ふぐ鍋」、米朝が「足上り」、南光が「つぼ算」、ざこばが「天災」という豪華メンバーと演目で、じっくりと寄席のよさを楽しんだ。ここではこの度紫綬褒章を受賞した米朝師匠の「足上り」を評論する。往年と比べ声が細くなったが、ますます色気が出たようで、うっとりと話の中に誘い込まれる。米朝師匠と本誌や弁護士会との関係は本誌四九号で書いたが、ここでは米朝師匠が端唄、都々逸がお上手なことを書く。一〇年ほど前、祇園の和風スナックで偶然隣になったとき、堪能させられた。背広姿で絶妙な芸を披露された。お一人できておられ、飲んで唄ったあと、小さなショルダーバックを下げ、ハンチングを被って、ホナ帰りますわと言って出ていかれた。懐かしい思い出である。色っぽい男というのはこういう人のことを言うと思った。その米朝師の「足上り」である。この噺は、昔、圧倒的にメジャーだった芝居、大衆娯楽の雄である芝居と商家の掟を主題とする。この芝居噺のネタは四谷怪談。小屋は本誌前号で報道した焼けた中座である。番頭が、丁稚を連れて勤務中に仕組んで、お茶屋のお内儀、芸妓、舞妓、仲居をはべらしての大豪遊の芝居見物。先に帰らされた丁稚を問い詰めて、事態を把握し、旦那はその番頭の足上げ(解雇)を決めている。そうとは知らぬ番頭が帰ってきて自室の蚊帳の中で先に帰った丁稚に四谷怪談の続きを話して聞かせてやる。突如我々聴衆は怖い怖い怪談に引き込まれる。その語り口の絶妙なこと、語りのテンポもこの場面では数段上がる。不気味な笛、太鼓、三味線の鳴り物も入る。お岩がスッと消え込む様を番頭が蚊帳を使って演じ、「身体が宙に浮いたように見えたやろう」と自慢すると、丁稚が「宙に浮くはずや、さいぜんに足が上がってまんがな」と言いオチになる。同僚の阪田健夫弁護士は大の米朝ファンで、師匠の噺のCD(「特選!!米朝落語全集」東芝EMI)を揃えている。貸してもらって復習して驚いた。本題は六割ほどで、前ぶりの四割で江戸時代の芝居の人気、役者、子役、化粧、衣装、セリフなどを入念に解説し、ひとしきり笑わせ基礎知識を付けてから本題に入っている。また、活字でこの噺の全文を読むと、実に緻密であることがわかるのである。やはり芸術である。
★★★
劇団スーパー・エキセントリック・シアター第四〇回本公演「幕末幻妖伝」(大阪厚生年金会館芸術ホール)。しばらく来ていない間に、中ホールの名が芸術ホールに変わっていた。三宅裕司率いる同劇団のナンセンスコメディである。四〇回公演とは驚いた。文久二年(一八六二年)、勝海舟派遣の千歳丸が上海へ向かったが、乗っていたのは長州の高杉晋作、伊藤俊輔、薩摩の五代才助など勤皇の志士。上海には坂本龍馬が既に渡っており、シーボルトも医業に従事していたという設定である。歴史を調べると同年高杉、五代が幕吏に従い上海に行ったのであり、伊藤は行っていない。伊藤は同年から勤皇派に参加したのでその故事を、坂本は同年脱藩して勝の元に身を寄せたからその故事を、シーボルトは入国禁止令が解けて二度目の来日を果たし帰国したのが同年であると言う故事にそれぞれちなみ、彼らを上海で合流させるという設定を考えたのであろう。座付作家大沢直行は一八六二年という鍵となる年を選んで、史実と虚構を組み合わせた。舟には殺生石という石を積み(殺生石は現在栃木県那須にあり、遣唐使にまつわるからこれも史実と伝説を作家は活用している)、この石が中国にある対となるべきマツタケ状の突起から出る胞子と合体すれば、莫大な財宝、翡翠が手に入る。これを倒幕と新政府の海軍創設のために探索する日本側と、奪おうとする白蓮教集団とのたたかいに、太平天国の騒動もからんで大ハチャメチャ、ドタバタが展開する。舞台が上海とあって京劇の俳優四人も参加して、小倉久寛をはじめ常連とともに力演している。驚いたのは出演のほとんど全役者が側転バク転を自由にこなしたことであった。あの肥満の小倉までもがである。舞台装置もシナリオもそれなりの工夫があったが、やはり一番面白かったのは三宅を舞台回しとする掛け合いの話術である。ナンセンスに大声で笑えることもたまにはいいものだ。客席は活気に溢れた。
★★★
 喜歌劇楽友協会第四三回定期公演「メリー・ウイドウ」(森ノ宮ピロティホール)。原作ヴィクトル・レオン、レーオ・シュタイン、作曲フランツ・レハール、原題Die Lustige Witweのオペレッタである。ご招待を受けて、オーケストラボックスの前のかぶり付で鑑賞した。二〇世紀初頭の作品で一九世紀末の貴族社会を描く。ハプスブルグ家の末期近くは神聖ローマ皇帝からオーストリア皇帝へと領域を狭めていたが、本作品はその皇帝のパリの属国での男女関係とほんものの恋を描く。貴族の女はほとんどが夫に隠れて独身男と恋をしているから、夫の嫉妬心から逃れて遊ぶ妻達の滑稽と、その中での真正な恋の行方にスリルを求めている。平民出身のハンナ(鄭里花、ソプラノ)は想う相手である公使館付秘書官ダニロ伯爵(臼井秀明、バリトン)と結ばれず、親子ほど離れた富豪と結婚したが八日目に夫が死亡して莫大な遺産を得ている。彼女に多くの男が金目当てで迫るが、彼女はダニロを今も深く慕っている。ダニロはハンナと結婚しなかった自分の不甲斐なさを責めながら、自堕落な生活を送り、今も彼女を想っているが、今更ハンナに迫れば遺産目当てと思われるという進退両難状態にある。そのような基本構造を明確にしたうえで、周辺の不倫恋のドタバタをそれに組み合わせる。ドタバタの中で一際目立つのが元踊り子で公使夫人ヴァランシェンヌ(日吉聖美、ソプラノ)とフランス人青年カミーユ(沢田和夫、テノール)との恋である。この四人の声はすばらしく、女性陣のダンス、カンカン踊りなど華やかさも満喫できる。井村誠貴指揮のオーケストラ・エウフォニカ管弦楽団も良い。向井楫爾演出。
喜歌劇楽友協会第四三回定期公演「メリー・ウイドウ」(森ノ宮ピロティホール)。原作ヴィクトル・レオン、レーオ・シュタイン、作曲フランツ・レハール、原題Die Lustige Witweのオペレッタである。ご招待を受けて、オーケストラボックスの前のかぶり付で鑑賞した。二〇世紀初頭の作品で一九世紀末の貴族社会を描く。ハプスブルグ家の末期近くは神聖ローマ皇帝からオーストリア皇帝へと領域を狭めていたが、本作品はその皇帝のパリの属国での男女関係とほんものの恋を描く。貴族の女はほとんどが夫に隠れて独身男と恋をしているから、夫の嫉妬心から逃れて遊ぶ妻達の滑稽と、その中での真正な恋の行方にスリルを求めている。平民出身のハンナ(鄭里花、ソプラノ)は想う相手である公使館付秘書官ダニロ伯爵(臼井秀明、バリトン)と結ばれず、親子ほど離れた富豪と結婚したが八日目に夫が死亡して莫大な遺産を得ている。彼女に多くの男が金目当てで迫るが、彼女はダニロを今も深く慕っている。ダニロはハンナと結婚しなかった自分の不甲斐なさを責めながら、自堕落な生活を送り、今も彼女を想っているが、今更ハンナに迫れば遺産目当てと思われるという進退両難状態にある。そのような基本構造を明確にしたうえで、周辺の不倫恋のドタバタをそれに組み合わせる。ドタバタの中で一際目立つのが元踊り子で公使夫人ヴァランシェンヌ(日吉聖美、ソプラノ)とフランス人青年カミーユ(沢田和夫、テノール)との恋である。この四人の声はすばらしく、女性陣のダンス、カンカン踊りなど華やかさも満喫できる。井村誠貴指揮のオーケストラ・エウフォニカ管弦楽団も良い。向井楫爾演出。
★
★★
「EURO JAZZ」(中之島中央公会堂大ホール)。澤野工房のプロデュース。保存と新機能を融合した公会堂のこけら落とし公演の一つである。私は集会や演説会は数知れずこのホールで参加したし、コンサートも二回聴いた記憶がある。一つは確かPPMだったように思うが、アコースティックの限界なのかやはり音響が良くなかった記憶がある。今度の新機能はそれを改善していて、太い柱の存在をあまり気にさせないいい音が聴けたように思う。さて私はユーロジャズのことは何も知らなかった。聴いての第一印象はこれもジャズなのかという驚きだった。本誌四九号に登場願った吉田理容所の吉田金吾氏は、私の「さんぱつやさん」なのだが、いわゆる音キチで、ご自身でジャズの演奏もしておられるが、その彼がユーロジャズを絶賛するのである。要するに上品なジャズなのである。今回の演者はJean-Philippe Viret TrioとVladimir Shafranov Trioと JosVan Beest Trio with MariellKoemanの三グループである。ピアノトリオばかりだが、個性は際立つ。特に後二者のテクニックはすばらしいものがあった。ピアノは後述するが、それぞれのベースの個性にも驚いた。シャフラノフはニューヨークで活躍したあとフィンランドに帰ったロシア系ピアニスト、ドイツでホワイト・ナイツというアルバムを出し大ヒット。吉田氏からいただいた三枚のアルバム(「Portrait In Music」「LIVE AT GROOVY」「MOVINVOVA !」もよい。力強いピアノ技術で、アメリカジャズの系譜が間違いなく現れている。ビーストはオランダのピアニストで、妻であるボーカル、コーマンを連れて来日。吉田氏からこれもいただいた三枚のアルバム(「Because of you」「From theHeart」「EVERYTHING FORYOU」 も聴いての感想は、ともかく甘く柔らかいピアノタッチで音が滑り流れていく。コーマンの歌声もこれにマッチした清純なボサノバ調。杉田宏樹「ヨーロッパのJAZZレーベル」(河出書房新社 二〇〇二年)によると、ユーロジャズは九〇年代以降に日本で大きく認知されるようになったが、その原因は専ら音楽ソフトの主流がCDになり、制作・流通の簡便性から多くの新興レーベルが現れたからで、ユーロジャズはもともとそこにあったのだそうである。★★★
清兵衛で愛を、
ギャングでアメリカ史を
ホータンで地球の不思議を
「たそがれ清兵衛」。元治二(一八六五)年というから、維新の三年前、今の山形県鶴岡にいた下級武士が、運命に翻弄されながらも家族を愛し、一途な恋情を貫く様を描く。妻に先立たれ、幼い娘二人と痴呆の進む母親を慈しみ地味に生き続ける井口清兵衛(真田広之が重厚に演ずる)。彼は仕事終りの太鼓が鳴ると、城からサッと退出して農作業や内職に励むので、仲間は「たそがれ」とさげすんでいた。文武に優れ、時代の激変をも理解している優秀な清兵衛だが、身分制は厳しく禄高も極端に低く、着物も破れ、よれよれの風体であった。そんな彼にとって、親友飯沼の妹で幼なじみ、酒乱の夫と離別して実家へ帰っている朋江(宮沢りえ好演)の存在は苦しい生活の中の一条の光であった。朋江との再婚を奨める飯沼には固辞していたが、藩にお家騒動があり、破れた家老に仕えた剛の者、善右衛門(前衛舞踏家田中泯が怪演)の抹殺を命じられた清兵衛は、再婚先が決まった朋江に身支度を頼み、必ず生きて帰るので待っていて欲しいと告白する。何の罪もない剣客を切らねばならない理不尽、自らが殺されるかもしれない理不尽の中で闘い、清兵衛は紙一重の差で深手を負いながらも勝利する。家に帰ると朋江が待っており、二人は娘達の祝福の元に夫婦になる。清兵衛がほどなく今度は奥州戦争に巻き込まれ鉄砲で死んだ後、朋江は東京に出て二人の遺児を育てたという。心にしみる作品である。藤沢周平の小品三点を基礎にして山田洋次が脚本を書き、初めての時代劇を撮った。七一歳にして初めての時代劇で何を残し、あるいは今後の出発としようとしたのであろうか。本質的な悪がどこにも出てこなかった寅さんシリーズに象徴される諸作品からの決別である。因習、身分制、藩という暴力装置の、徹底した悪を明確な形で描いている。商業映画としては時代劇の中でしか明確な悪が描けないと考えて、山田が一大決断したと見るべきかどうか(しかしそれならば、本誌四六号で取り上げた原田眞人監督の「金融腐敗列島 呪縛」などは時代進行形で巨悪を描いている)。それにつけても秋の叙勲で勲四等旭日小綬章をもらったことはひっかかることだ。人に位を付けて表彰するなどという制度を山田が受け入れることは、この作品のコンセプトにも反し、優れた作品に瑕がついた感じがしてならない。二〇〇二年作品。
★★★
 「僕たちのアナ・バナナ」(DVD)。原題はKeeping theFaith。二〇〇一年公開だったが観られず、DVDで。本誌四〇号で評論した「真実の行方」で、リチャード・ギア扮する弁護士を二重人格の振りをして翻弄した殺人犯の青年役をしたエドワード・ノートンが出演し監督している。幼なじみの三人(女一人、男二人)の成長してからの恋の物語である。真面目な親友ふたりは、ブライアン(ノートン)がカソリックの神父、ジェイク(ベン・ステイラー)がユダヤ教のラビになって、それぞれの教会に新風を与える人気者僧職として生活していた。ブライアンは禁酒禁煙禁欲の生活に満足し、ジェイクは有力な富豪信者の娘をより取り見取りで結婚の準備をしていた。そこに一六年ぶりに遠くに離れていたアナ(ジェナ・エルフマン)がヤング・エグゼクティブとして現れる。幼いときの魅力が倍加し、輝くばかりのキャリアウーマンに成長した彼女を見て、親友二人は衝撃を受け、直ちに恋心を抱く。アナも生き馬の目を抜くようなビジネスの世界から純真な二人を見て、衝撃を受ける。ブライアンは神父職を捨てようかと、ジェイクはラビ職のためにアナを諦めようかと悩む。しかし皮肉なことに、アナが愛し始めたのはジェイクだった。激しく愛しあいながらユダヤ人でないアナとつきあうことはスキャンダルとなりかねないと悩み、アナを拒絶するジェイク。母親も反対であった。これらの矛盾を解決するのが、三人の基本的な信頼関係と母親の愛であった。マンハッタンはこよなく美しい。まだWTCがあったアメリカンドリームの世界である。
「僕たちのアナ・バナナ」(DVD)。原題はKeeping theFaith。二〇〇一年公開だったが観られず、DVDで。本誌四〇号で評論した「真実の行方」で、リチャード・ギア扮する弁護士を二重人格の振りをして翻弄した殺人犯の青年役をしたエドワード・ノートンが出演し監督している。幼なじみの三人(女一人、男二人)の成長してからの恋の物語である。真面目な親友ふたりは、ブライアン(ノートン)がカソリックの神父、ジェイク(ベン・ステイラー)がユダヤ教のラビになって、それぞれの教会に新風を与える人気者僧職として生活していた。ブライアンは禁酒禁煙禁欲の生活に満足し、ジェイクは有力な富豪信者の娘をより取り見取りで結婚の準備をしていた。そこに一六年ぶりに遠くに離れていたアナ(ジェナ・エルフマン)がヤング・エグゼクティブとして現れる。幼いときの魅力が倍加し、輝くばかりのキャリアウーマンに成長した彼女を見て、親友二人は衝撃を受け、直ちに恋心を抱く。アナも生き馬の目を抜くようなビジネスの世界から純真な二人を見て、衝撃を受ける。ブライアンは神父職を捨てようかと、ジェイクはラビ職のためにアナを諦めようかと悩む。しかし皮肉なことに、アナが愛し始めたのはジェイクだった。激しく愛しあいながらユダヤ人でないアナとつきあうことはスキャンダルとなりかねないと悩み、アナを拒絶するジェイク。母親も反対であった。これらの矛盾を解決するのが、三人の基本的な信頼関係と母親の愛であった。マンハッタンはこよなく美しい。まだWTCがあったアメリカンドリームの世界である。
★★
「幻の大河ホータン」(NHKハイビジョン)。ノンフィクションの名作、世界の自然探検の大作である。タクラマカン(ウイグル語で一度入ったら生きて帰れない場所の意)砂漠に毎年六月下旬から九月の三か月間だけ大河が流れる。謎の大河と呼ばれてきた。驚いた。地球は大きく不思議である。コンロン山脈の雪解け水が最初はチョロチョロとあらわれ、やがて洪水のように流れ出し、砂漠に進出する。しみ込みつつも、水はかなりのスピードで砂漠を横切って行き、横幅も長さも巨大に成長していく。ついにはナンと最大幅八キロ、全長一二〇〇キロの大河になるのである(五〇〇キロでタリム河に合流する)。コンロン山脈が氷点下に入る九月になると、河は砂漠に沈む。地図によると、中国のチベット自治区の北端のコンロン山脈の麓にホータン(和田)というオアシス都市があり、ホータン河はそこを発し、北上し、新疆ウイグル自治区へと向けて流れる。毎年のこととて、「流域」辺境の農民は今や遅しと河の到来を待っている。河が来れば作物が育つ、動物の飲み水となる。来なければ餓死する。河の到来は祭りである。もちろん、そのような河であるから毎年少しずつは河の位置が異なるので、従前の河を前提に「河辺」に建てていた家も、河がずれれば水没するし、毎年人と動物の水死はあとを絶たない。しかしこの水がなければ、砂漠の生活は成り立たない。自然の条理と不条理が同時に現れるのである。撮影隊は砂漠探査車、ヘリコプターで、七〇度を越える熱の中、水を追い、また先回りして水の到着を待ち、人々と河という自然の関係を写す。極めて優れた手法である。しみじみと地球に生きるということの不思議を考え直させる番組であった。★★★
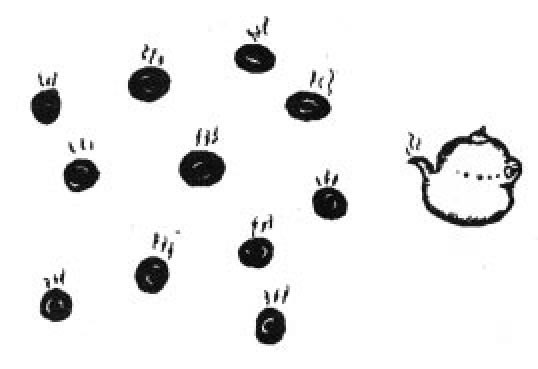 「ギャング・オブ・ニューヨーク」。原題はGANGS OFNEW YORK。マーティン・スコセッシ監督。超大作。描かれたものが一八六〇年代のニューヨークのギャングの敵討ち的勢力争いと見れば、全くつまらないテーマであるが、スコセッシはギャング抗争を象徴または状況説明手段として使って、生成期アメリカの猥雑な混とんと湧きだすようなエネルギー、移民間の壮絶な争い、醜い政治家の実態など、アメリカとその中心であるニューヨークの時代を切り取ったと見るべきであろう。一七七六年に独立宣言したアメリカの建国一〇〇年以内のニューヨークの模様である。一九世紀初頭から飢餓を逃れて大量に流入するアイルランド移民、待ち受けるネイティブと自称する一八世紀からの移民の子ども世代の連中が弾圧、搾取する。一八六一年に起こった南北戦争で、ニューヨークは北部に属するからその兵が募集され、貧しいアイルランド系は多くこれに応募する。自称ネイティブは、黒人排斥主義者でもあるから、北部にいながらリンカーンの奴隷解放政策には反対であり、うすぎたない政治家は自称ネイティブに買われながら、北部の政治家として生きていく。募集では足りないから反リンカーン主義者が徴兵され、暴動を起こし、軍が出動して鎮圧する。どこを取っても混とんと矛盾、犯罪に充ちた街、ニューヨーク。本作品には現れていないが、南北戦争のあとなお本当のネイティブであるインディアン、ジェロニモ指導下のアパッチの最後の反乱が起こるのであり(一八七一年)、アメリカ合衆国が様々な流血の上に建国された、原住民にとっては侵略的、新住民間では内部闘争国家であることが了解されるのである。このような時代の中で、自称ネイティブギャングの首領ビル・ザ・ブッチャー(名優ダニエル・ディ=ルイス好演)が対決のうえ殺したアイルランド系組織の首領の息子アムステルダム(レオナルド・デカプリオ力演)は、成長し、身分を隠してビルの組織に入り、メキメキと力をつけ、ビルに信頼され、ビルの隠された人間的側面にも親近感を覚える。華麗な女スリ、ジェニー(キャメロン・ディアス好演)は幼女の時ビルに拾われ、今はビルの愛人であるが、アムステルダムと愛しあうようになり、それを嫉妬するアムステルダムの親友が、アムステルダムの正体をビルにちくる。半殺しにされながらもジェニーの献身的看護でよみがえり、力を蓄え、父親の子分達を徐々に結集して、最後に対決して徴兵暴動の混乱の中でビルを倒す。目を覆うばかりの血が飛びすぎる作品だが、アメリカの氏素性を直視する価値ある作品と言えるであろう。
「ギャング・オブ・ニューヨーク」。原題はGANGS OFNEW YORK。マーティン・スコセッシ監督。超大作。描かれたものが一八六〇年代のニューヨークのギャングの敵討ち的勢力争いと見れば、全くつまらないテーマであるが、スコセッシはギャング抗争を象徴または状況説明手段として使って、生成期アメリカの猥雑な混とんと湧きだすようなエネルギー、移民間の壮絶な争い、醜い政治家の実態など、アメリカとその中心であるニューヨークの時代を切り取ったと見るべきであろう。一七七六年に独立宣言したアメリカの建国一〇〇年以内のニューヨークの模様である。一九世紀初頭から飢餓を逃れて大量に流入するアイルランド移民、待ち受けるネイティブと自称する一八世紀からの移民の子ども世代の連中が弾圧、搾取する。一八六一年に起こった南北戦争で、ニューヨークは北部に属するからその兵が募集され、貧しいアイルランド系は多くこれに応募する。自称ネイティブは、黒人排斥主義者でもあるから、北部にいながらリンカーンの奴隷解放政策には反対であり、うすぎたない政治家は自称ネイティブに買われながら、北部の政治家として生きていく。募集では足りないから反リンカーン主義者が徴兵され、暴動を起こし、軍が出動して鎮圧する。どこを取っても混とんと矛盾、犯罪に充ちた街、ニューヨーク。本作品には現れていないが、南北戦争のあとなお本当のネイティブであるインディアン、ジェロニモ指導下のアパッチの最後の反乱が起こるのであり(一八七一年)、アメリカ合衆国が様々な流血の上に建国された、原住民にとっては侵略的、新住民間では内部闘争国家であることが了解されるのである。このような時代の中で、自称ネイティブギャングの首領ビル・ザ・ブッチャー(名優ダニエル・ディ=ルイス好演)が対決のうえ殺したアイルランド系組織の首領の息子アムステルダム(レオナルド・デカプリオ力演)は、成長し、身分を隠してビルの組織に入り、メキメキと力をつけ、ビルに信頼され、ビルの隠された人間的側面にも親近感を覚える。華麗な女スリ、ジェニー(キャメロン・ディアス好演)は幼女の時ビルに拾われ、今はビルの愛人であるが、アムステルダムと愛しあうようになり、それを嫉妬するアムステルダムの親友が、アムステルダムの正体をビルにちくる。半殺しにされながらもジェニーの献身的看護でよみがえり、力を蓄え、父親の子分達を徐々に結集して、最後に対決して徴兵暴動の混乱の中でビルを倒す。目を覆うばかりの血が飛びすぎる作品だが、アメリカの氏素性を直視する価値ある作品と言えるであろう。
★ ★★
