「晴子情歌」と「阿弥陀堂だより」文学は人間の心を描くものであることを再発見
高村薫「晴子情歌 上・下」(新潮社 〇二年)。発売とともに大きな話題となったから、それらを印刷物として残しておき、作品を読んでから他のひとの評論を読むように心がけた。大正九年(一九二〇年)生まれの晴子が、昭和二一年(一九四六年)三月生まれの息子彰之に、彼が仕事として選んだ船員として遠洋漁業にいた昭和五一年(一九七六年)の航海の途中三〇〇日に、一〇〇通もの手紙を書く。作品はこの長大な手紙をベースにして晴子の人生と主として昭和という時代を描き、彰之をしてその手紙の内容を反芻させながら、母と自分の人生を考察する様を描く。手紙を軸とした文学は例えば宮本輝「錦繍」(本誌一一号で絶賛)の交換方式など色々あるが、この作品も成功例と言えるであろう。なぜ母が息子に突然膨大な量の手紙を書いたのかは、下巻の最後に母の病気(子宮癌)が明らかにされるから少し納得する思いがある。母は息子に対し、自分をちゃんと語っておきたいと思う心と、息子の今はこのような自分の歴史を踏まえて形成された可能性があると語っていると私は思う。母と母の歴史があったから必然的に息子の人生が規定されたとは言わないまでも、影響が必ず色濃くあったはずよ、その中身を考えてみようよと作者は呼びかけている。時代の痕跡は、ほかならぬ一人ひとりの人間の身体を通してしか存在せず、その痕跡を合計し総合したものが歴史であると作者は述べているのだろう。読者に。私も母を九三年に亡くして以来、母からもっと母の歴史を聞いておくべきであったと年々悔やんでいる。さてこの作品において、晴子と彰之とはどのような歴史をもった親子であったのかを、簡単に素描しておきたい。晴子は、母の実家である東京本郷の岡本家で生まれ、母の死後、父康夫の実家である青森県西北部、津軽地方の筒木坂の野口家に移り、野口家の係累の関係で北海道南西部土場に行き、父について鰊漁のため北海道北西部初山別などにいきつつ、父の死後奉公のために青森県東北部野辺地の大家福澤家に移る。福澤家は元は醤油製造業であり、加えて水産や建築の地方大資本家て国立ガンセンターの部長になっている。さて彰之は、野辺地で生まれ、常光寺で中一から六年間小坊主をし、中学以来漁に親しみ、東大理学部に入学するが、盛んだった全共闘運動にも馴染めず、六八年卒業と同時につきあっていた女とも別れて北転船に乗り、船員となった。船員として彼は年長の仲間から、戦争の悲惨、三井三池闘争の実情を聞き、学生時代の逃避的姿勢に思いをいたしながら、カムチャツカ、マグロ遠洋、インド洋などと航海をするうち、今は三〇歳近くになっている。この年にインド洋で母からの手紙が届くのである。作者は、たくさんの文学者、文学作品 (「嵐が丘」、「失楽園」、「啄木」、「ジャン・クリストフ」、「アンナ・カレーニナ」、「ジイド」、「三島」)を引用しながら、昭和の歴史を描く。重厚である。作者の取材は徹底しているから、漁業、漁労の激しさを微細に描き出すし、その中で船員が楽しむ編み物への蘊蓄も添えている。地方政界の地元利権体質もしっかり描かれている。以上述べたところからも、一級の文学であることはわかるはずだが、一体この文学は何をめざしているのかを次に考察する必要があろう。この作者と出会って久しく、本誌に登場願うこと本号を入れて三度(三〇号記念号で座談会「大阪からの発信―世界へ」、三六となり、衆議院議員を輩出する。晴子は福澤家三男で福澤家としては落ちこぼれの画家である淳三と結婚する。しかし夫婦とは形ばかりであり、性交渉はなく、淳三が他所で作った美奈子を長女として育て、終戦直前の昭和二〇年七月淳三出征中に、晴子は愛情もなく福澤家長男で衆議院議員となる榮の子を宿し、翌年彰之を産み、淳三の長男として育てる。晴子には初山別時代から恋しいと思う男もおり、また帰還した淳三と一時別居し、その間若い船員と付き合ったりしている。ただ淳三の晩年、晴子は彼と友人のように暮らし、淳三の絵、何十枚もの「青い庭」を通して淳三を深く理解できるまでにいたっている。淳三の死亡時、晴子は五六歳であり、この前年から息子に手紙を書くのである。晴子の父、康夫は東大文学部を出、東京外国語学校講師をつとめ、大杉栄を尊敬し、共産党のシンパで、小説も書く人であったが、昭和九年(一九三四年)疲れ果てて、津軽に晴子達を連れて帰り、漁業に従事し、翌年には死亡している。晴子の弟の哲史は東大医学部を出号の巻頭言「震災のあと思うこと」、本号)、主要な作品は、読み、ほぼ絶賛評論してきた。「黄金を抱いて翔べ」(三一号)、「マークスの山」(三二号)、「照柿」(三七号)、「レディ・ジョーカー」(四七号)。作者はこれまでのミステリー、サスペンス作品を捨てて、歴史考察に移ると随所で語っている。その理由を、阪神・淡路大震災の人間にとっての理不尽さに求めている(「現代」八月号)。上述したように、作者は人間の具体的肉体を通した出来事を綴って、歴史を、昭和を語っている。大きな作品の登場である。これに戸惑い、「煩悶、葛藤、心の乱れ見えず」として教条的な歴史観から批判的に評論する論稿もあるが、私はそれを軽蔑する。作者は自然な人間とそれに体現する歴史を悩み苦しみながら描いている。それ自体の価値がわからない人は、文学を読むのをやめればよい。
(「嵐が丘」、「失楽園」、「啄木」、「ジャン・クリストフ」、「アンナ・カレーニナ」、「ジイド」、「三島」)を引用しながら、昭和の歴史を描く。重厚である。作者の取材は徹底しているから、漁業、漁労の激しさを微細に描き出すし、その中で船員が楽しむ編み物への蘊蓄も添えている。地方政界の地元利権体質もしっかり描かれている。以上述べたところからも、一級の文学であることはわかるはずだが、一体この文学は何をめざしているのかを次に考察する必要があろう。この作者と出会って久しく、本誌に登場願うこと本号を入れて三度(三〇号記念号で座談会「大阪からの発信―世界へ」、三六となり、衆議院議員を輩出する。晴子は福澤家三男で福澤家としては落ちこぼれの画家である淳三と結婚する。しかし夫婦とは形ばかりであり、性交渉はなく、淳三が他所で作った美奈子を長女として育て、終戦直前の昭和二〇年七月淳三出征中に、晴子は愛情もなく福澤家長男で衆議院議員となる榮の子を宿し、翌年彰之を産み、淳三の長男として育てる。晴子には初山別時代から恋しいと思う男もおり、また帰還した淳三と一時別居し、その間若い船員と付き合ったりしている。ただ淳三の晩年、晴子は彼と友人のように暮らし、淳三の絵、何十枚もの「青い庭」を通して淳三を深く理解できるまでにいたっている。淳三の死亡時、晴子は五六歳であり、この前年から息子に手紙を書くのである。晴子の父、康夫は東大文学部を出、東京外国語学校講師をつとめ、大杉栄を尊敬し、共産党のシンパで、小説も書く人であったが、昭和九年(一九三四年)疲れ果てて、津軽に晴子達を連れて帰り、漁業に従事し、翌年には死亡している。晴子の弟の哲史は東大医学部を出号の巻頭言「震災のあと思うこと」、本号)、主要な作品は、読み、ほぼ絶賛評論してきた。「黄金を抱いて翔べ」(三一号)、「マークスの山」(三二号)、「照柿」(三七号)、「レディ・ジョーカー」(四七号)。作者はこれまでのミステリー、サスペンス作品を捨てて、歴史考察に移ると随所で語っている。その理由を、阪神・淡路大震災の人間にとっての理不尽さに求めている(「現代」八月号)。上述したように、作者は人間の具体的肉体を通した出来事を綴って、歴史を、昭和を語っている。大きな作品の登場である。これに戸惑い、「煩悶、葛藤、心の乱れ見えず」として教条的な歴史観から批判的に評論する論稿もあるが、私はそれを軽蔑する。作者は自然な人間とそれに体現する歴史を悩み苦しみながら描いている。それ自体の価値がわからない人は、文学を読むのをやめればよい。
★★★
南木佳士「冬の水練」(岩波書店 〇二年)。本誌前号でこの人の短編小説集「神かくし」を評論し色々と書いたが、実は私は大好きなこの作家の行く末に不安を感じたのであった。大丈夫だろうか、生き続けて貰えるのだろうかと。しかし、本随筆集を読んでいささかホッとした。洒脱なユーモアが全編に充ち、心身の疾患とちゃんと向き合ってうまく付きあっていることがわかったからである。本誌北川編集長は、今はこの人は随筆がいいねと言う。同感である。その安心は、全編からも漂うが、書名となった最後の一遍「冬の水練」で、作者が病者にとって水泳の持つ前向きさをしみじみ描いている珠玉の文章から主として来る。その他、猫とのかかわりから生き続ける自分を肯定する「トラのいる十二年」、できる編集者との作家としての「たたかい」を綴る「物置における追憶」、病を得て、生き続けられた感謝を込めて思い出す「麻雀」、超一流でなくとも生き続けることの重要性を描く「医局の孤独」、夢破れて妻子ありとほざいていた通りになった自分を正面から捉える「最後に仕事」、司馬遼太郎や開高健や深沢七郎を偲びつつ旅する「とても小さな旅」、小説家は一般人を相手に言葉の喧嘩をしてはボクサーのパンチのように危険だと思い、医者の患者に対する言葉の重さを考える「医師の言葉」、泣かない赤ん坊はミルクをもらえないという格言の誤りを考察しつつ、禁煙体験を恥ずかしげに語る「やめる」、若月俊一と黒澤作品のなかでの志村喬の言葉を反芻する「七人の侍」、体調が絶不調だったときに若月のインタビュー著書を突撃的にやった思い出に浸る「太宰治の顔」など面白い。
★★★
南木佳士「阿弥陀堂だより」(文春文庫 〇二年)。九五年の作品で、映画化されこの一〇月から封切りされている(小泉堯史監督。後述の映画評論参照)。重厚な名作である。津々と温かさが湧いている。人が心を病んだときどのようにして回復していくのかの一つの試みを作品は実に丁寧に描き出している。誰でも心を病むことがあるが、それがエリートの場合、地位からの脱却が無慈悲に劇的に訪れるから更に苦しみが増すのである。妻である学界で注目されていた大病院の内科医長美智子が人の死を見過ぎて「気」が抜けた状態になって東京から逃げ出したいと思ったとき、新人賞をとりこれから世に出ようという夫である作家孝夫は、自らの故郷、長野の山奥の谷中村に共に移り住む。孝夫は元々農作業をして育った極貧の野の出であり、何より東京での高校時代にすでに背伸びをしないことを学んだ男であった。美智子が医師である自らが病気であること、しかも心の病気であることを受け入れる重要な契機に、美智子の母が登場し、肩の力を抜いてやり美智子を泣けるだけ泣かせてやる場面も美しい。作者は自らが医師であり病者であるがゆえに、心憎いばかりの配慮を作中の人物達に施している。美智子は診療所の嘱託医として稼ぎ、孝夫が家事家業全般を肉体でこなす。経済主体が妻であることは、この夫婦の結婚以来変わらない。そしてこの村には、いくつかの阿弥陀堂のひとつに、堂守のおうめ婆さんがいる。九〇歳を越えて矍鑠と生きている。江戸時代の生活とほとんど違わないという自然の生活、この最もシンプルな生活者の存在自体が夫婦を励ます。余計な刺激のない田舎暮らしは、妻を回復させていく。動物として、生物として。そして作者は医者の真の回復とは何かという次のテーマを用意する。おうめ婆さんの語りを「阿弥陀堂だより」として村の広報に連載していた二四歳の村役場職員小百合ちゃんが肉腫に侵されるのである。この極めて難しい手術に妻は挑戦できるのだろうか、手術中に逃げ出さないか、かたずを呑んで読者を引きつけておいたうえで、作者は美智子の回復ぶりを克明に丁寧に描写していく。小百合ちゃんを救うことを通じて美智子は自分を救っていくのである。美智子は自分をそこまでにした孝夫を深く想う、そして二人は村の自然、おうめ婆さんを想う。人が心を病んだとき、回復に必要な要素を作者は、ストレスからの離脱、気長に回復を待つ周辺の人々の優しさ、自然の中での生活に求め、徐々に回復し恐怖性障害が遠のいたときには、体力と気力に合ったある種の挑戦が重要であると言っている。本誌北川編集長も言っていたが、この作者の作品では、主人公は常に医者であり自己を投影させてきたが、本作では妻を医者に、夫を作家にして、医師兼作家の自己を分割して見せ、成功している。南木さんが開高健を好くことは、「冬の水練」でも何度も語られたが、本作品にも出てくる。「珠玉」は名作だと。都市に生きる多くの人々に一読を進めたい不朽の名作である。
★★★
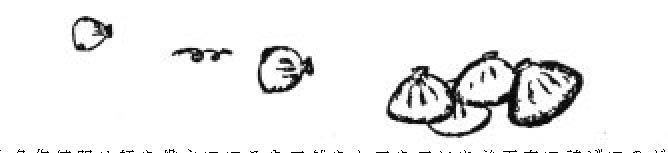
河野多惠子「小説の秘密をめぐる十二章」(文藝春秋 〇二年)。本誌二五号の巻頭言をお願いした氏の、小説の書き方読本。ネットで買ってから試みにジュンク堂を覗いてみたら、同種の本がたくさんあるのに驚いた。スポーツを含むどの分野でもハウトゥーものは書くことが難しいが、精神的所産とも言うべき文学のそれは想像にあまりある。およそデビュー、受賞、文章の呼吸、冒頭から最後まで書くこと、スランプ、テーマ、書きたいもの、才能、ノート、登場人物の名前、標題、導入と終り方、筋、人称、伏線、文章力と進むわけだが、このようなことを該博な知識と経験の無い者が書けば悲惨なものになるであろう事は自明である。本書を読み進めるうち、氏は、これほどの人であったのかとの感銘が私の中から湧き出た。単に私が知らないだけなのであろうが、氏はまがう事なき大家である。上述のテーマを古今東西の作家を素材に、例を挙げながら説き進める。取り上げられる作家は自分のほか、ザーッと上げるだけでも、W・ホイットマン、マーク・トウェイン、N・ホーソン、エミリー・ブロンテ、E・A・ポー、ヘンリー・ミラー、ダフネ・デュ・モオリア、井原西鶴、上田秋成、尾崎紅葉、樋口一葉、泉鏡花、菊池寛、里見、芥川龍之介、谷崎潤一郎、永井荷風、井伏鱒二、島崎藤村、志賀直哉、日夏耿之介、萩原朔太郎、佐藤春夫、林芙美子、武者小路実篤、武田泰淳、丹羽文雄、石川淳、吉行淳之介、阿川弘之、庄野潤三、平林たい子、石原慎太郎、三島由紀夫、大江健三郎、津島佑子、山田詠美、藤沢周に及ぶ。文学史でもある。前述のテーマに沿って進みながら、例えば樋口の「闇桜」をけなし、「うもれ木」を絶賛し、平林の地震小説の三つの出来不出来を比べ、芥川の「羅生門」の末行が玉に瑕であることを詳しく解き明かす。谷崎への言及が圧倒的に多い。その次は芥川であろうか。その二人の「話しの筋論争」の結末が不毛であると批判する。本は図書館で読まず、自分のお金で買えとも言っている。
★★★
石田衣良「池袋ウエストゲートパーク」(文春文庫 〇一年)。瑞々しい、新しい作家の登場である。と言っても、もう単行本数冊、文庫数冊という実績だから私が知るのが遅いだけであろうが。これから華々しく種々の賞を取っていくはずである。六〇年生まれだから、この作品に代表される少年少女の今を切り取って描く作風を三〇代後半で書き始めたことになる。前号で評論した重松清の「定年ゴジラ」が、三〇代前半に定年退職後のサラリーマンを重厚に描いたのと正反対の驚きである。才能のある人は湧いてくるものだ。さて本書は石田の出世作かつシリーズの出発になる重要な位置づけがある。短編四つだが、シリーズの出発である。大沢在昌がはぐれ刑事の鮫シリーズで新宿の今を描くのに対抗してか、石田は池袋西口商店街で果物屋のせがれ、寡婦の母親を助けて店番をするマコトという一見地味なハイティーン少年を創作して池袋の今を描く。大沢は鮫で大人の裏舞台、非合法部分を太い筆致で切り取って新宿という巨大都市とアジアに通底する日本社会の今に迫るが、石田はマコトの感性で少年少女の側からやはり大人たちが作り出している裏舞台、不条理部分を繊細ナイーブに切り取って池袋と日本社会を描く。少年少女は学校の勉強はできないしやらないが、あらゆることを知っており、目的を持つと想像を絶する能力を発揮し、自分の理解した良いことのために(これをも正義感と言えるかもしれない)身体を張るのである。石田の表現は柔らかく、華麗で、少年少女の生態(売春、風俗、薬、武器、引きこもり、グループづくりと抗争、ファッション、食、コンピューター、オーディオ、バイクなどなど)を克明に取材して、該博な外国文学、クラシック音楽知識を参考構造に取り入れながら、物語を紡ぐ。少年たちは仕事を一概に嫌がらないが、「仕事の喜びはポケットに入るくらいだが、その退屈ときたら二トン積みのトラックが必要なくらい」などと石田により表現されている。マコトの信条は平和な池袋への愛である。石田は池袋を素材に日本社会への恋情を文字にしている。
★★★
石田衣良「少年計測機.池袋ウエストゲートパークII」(文春文庫 〇二年)。前作と同じく短・中編四つからなる「マコトシリーズ」である。性転換、ネットの覗き部屋女優、大企業社員であるストーカー、心を閉ざし計測器にモノマニアしているLD(learning disability)少年、エロジジー、新デザイナーズブランド創作者、悪を狙う極悪の強盗団、女子高生監禁など池袋に滞留する現状を素材に、日本の今を描く。少年少女の失業率の高さを告発しつつ、他方大企業を含む「正業」と考えられてきた職業の今日における脆弱さを指摘する。ただ暴力団をヤー公、ケダモノと呼んではいるが、少年グループと暴力団との連続性、死にも至る暴力シーン描写が凄惨であることなど少し私の心にはわだかまりも生じつつあるが、もう少しこの類い稀なる新しい作者に浸ってみようと思う。やはり味付けにはシェークスピアやバッハ、武満徹など文学と音楽を巧みに配している。
★★★