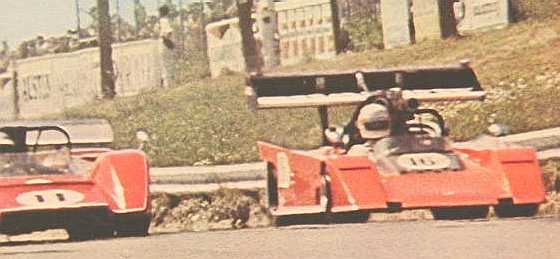| ジョージ・フォルマー ミニ ヒストリー (
The History Of George Follmer )
私はジョージ・フォルマーというとすぐ思い出してしまうのが1968年に日本で開催された「ワールド・チャレンジカップ 富士200マイルレース」、通称「日本カンナム」に物凄いオーバーフェンダーの白いローラT70MKIII
(クローズドタイプのMKIII とは別物でMKII の発展型グループ7カー) で出場した時のことを思い出してしまいます。
1968年当時はマクラーレンでなくては勝てないとまで言われるほどマクラーレンの新旧マシンは強力でありました。
そんな中、ジョージ・フォルマーはまるで(!?)競争力がないと思われるローラT70MKIII
を駆ってその年のCAN-AMシリーズに挑戦続けいたのですから、実力はあるにせよ当時はローカル・ドライバーの印象がたえず漂うドライバーであったと記憶しています。
しかし、そんなフォルマーのローラT70MKIII でありましたが、1968年度シリーズ最終戦「ラスベガス・グランプリ」においてブルース・マクラーレン(マクラーレンM8A)、ジム・ホール(チャパラル2G)、そして、マーク・ダナヒュー(スノコ・マクラーレンM6B)などのリタイヤに助けられたとは言え、デニス・ハルム(マクラーレンM8A)に次ぐ総合2位に入賞したことはまさに驚異でありました。さらに、その後の日本CAN-AMにおいては予選6位、決勝レースでも30周目までピーター・レブソン(シェルビー・マクラーレンM6B)とマーク・ダナヒューに次いで3位を走行するなど侮れがたいスピードを示したりして只者ではないという印象を少なからず私に植え付けてくれました。
さて、そんなカルフォルニア州出身の彼がプロデビューしたのは、25歳(1959年)にフォルクスワーゲンでレースをした時が最初でありました。
アメリカのスポーツカーレースに参加し続けていた1965年シーズン、思わぬ幸運がジョージ・フォルマーに訪れるのです。当時ジム・ホールのチャパラルの活躍により人気を呼んでいたUSRRC(ユナイテッド・ステイツ・ロード・レーシング・チャンピオンシップ)に非力なロータス23ポルシェで参加していたフォルマーは、2リッター以下のクラスで優勝、さらに、当時のルールによりクラス別シリーズポイントの合計が一番多いドライバーに総合タイトルの栄誉も与えられるという変則的な規約のためフォルマーは1965年度のUSRRC総合チャンピオンをも手中に収めてしまったのです。
その後のフォルマーは1966年度からスタートしたCAN-AMシリーズやUSRRCなどをローラT70でプライベート参戦するもののワークスチームのマクラーレンやジョン・サーティーズの準ローラ・ワークスなどの強力チームの前に歯が立たず涙を飲むシーズンが続きました。
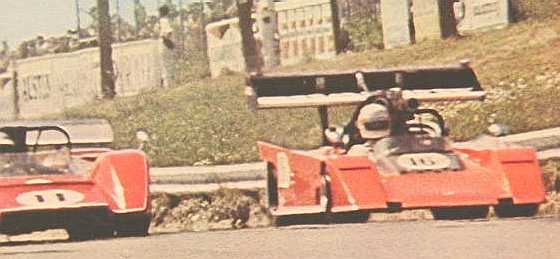
(C) Photograph
by Joe Honda.
TOP : Follmer and his AVS SHADOW
上の写真は、1970年CAN-AM シリーズにおいて話題のマシン“AVSシャドウ(左側)”に乗るフォルマー。
1969年転機が訪れます。SCCA主催のツーリングカーレース通称Trans-Amシリーズに参戦したフォルマーは初めての総合優勝を得る事に成功するのです。そして、インディへの参戦。他分野への挑戦でした。
1972年、ペンスキーチームから参戦したTram-Amシリーズで見事シリーズ・チャンピオンに輝き、さらに、ポルシェ917/10KによるCAN-AMシリーズチャンピオンにも輝いたフォルマーはまさに円熟期を迎えていました。
翌年、翌々年もCAN-AMシリーズで連続総合2位に輝いたもののすでにCAN-AMシリーズはローカルイベントに成り下がっていたことにも影響されてかフォルマーの評価はあまり高いものではありませんでした。
1973年、前年のCAN-AMチャンプ奪取の活躍を盾に憧れのフォーミュラ・ワンの世界にシャドウを駆ってデビュー。デビュー戦の南アフリカ・グランプリに初挑戦ながら見事6位に入賞し、シャドウに初のポイントを獲得させ、同年スペイン・グランプリでは堂々3位をゲットし、彼の評価を上げる事に成功するのでした。
現在ジョージ・フォルマーは、ヴィンテージ・イベントでのビジネスなどに従事し、忙しい毎日を送っているそうです。
ところで初年度1966年から閉幕した1974年までのCAN-AMにおける彼の生涯ポイントはなんとデニス・ハルム、ピーター・レブソン、マーク・ダナヒューに次いで第4位。ブルース・マクラーレンよりも多いポイントを稼いでいるフォルマーはやはり只者ではないと今さらながら私は密かに思い始めているところです。
text report by Hirofumi Makino
|