 15 水滴を完全に取り去ったらヘアドライヤ(大量処理のときにはRCペーパー用乾燥器を使うと便利)の温風をまんべんなく当てて乾燥させる。(以上の処理は、テストでも本番でも同様に行い、けっして省略してはいけない)。
15 水滴を完全に取り去ったらヘアドライヤ(大量処理のときにはRCペーパー用乾燥器を使うと便利)の温風をまんべんなく当てて乾燥させる。(以上の処理は、テストでも本番でも同様に行い、けっして省略してはいけない)。 16 テストペーパーの色調がRWCCフィルタガイドの2と5のカードのどちらに近いかを判定する。もしなけれぱ1、3、または4、6のカードの中から最も近似する色の部分をさがす。判定は昼光がプルーランプで行うこと。
16 テストペーパーの色調がRWCCフィルタガイドの2と5のカードのどちらに近いかを判定する。もしなけれぱ1、3、または4、6のカードの中から最も近似する色の部分をさがす。判定は昼光がプルーランプで行うこと。 17 チヤートの中でテストに近い色が決まったら、その位置の上の数字がYフィルタ、また左側の数字がMフィルターの補正値である。+記号ならばフィルターをプラス、-記号ならマイナスすれぱよい。
17 チヤートの中でテストに近い色が決まったら、その位置の上の数字がYフィルタ、また左側の数字がMフィルターの補正値である。+記号ならばフィルターをプラス、-記号ならマイナスすれぱよい。 18 この例では補正フイルターがYは+20、Mは+20であるがら、ヘツドの数値をそのとおりに補正する。60Y、40Mではじめたので、ヘツドの数値はYが80、Mが60となる。(テストペーパーには、このテータを記入する)。
18 この例では補正フイルターがYは+20、Mは+20であるがら、ヘツドの数値をそのとおりに補正する。60Y、40Mではじめたので、ヘツドの数値はYが80、Mが60となる。(テストペーパーには、このテータを記入する)。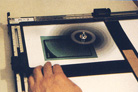 19 補正したフィルターデータで、再度ストライプテスト。そして現像処理・乾燥する。(もしその結果まだ色味が強く、グレーから遠い場合は、もう度ガイドを使ってフィルタを補正。要はテスト段階で灰色になればよい)。
19 補正したフィルターデータで、再度ストライプテスト。そして現像処理・乾燥する。(もしその結果まだ色味が強く、グレーから遠い場合は、もう度ガイドを使ってフィルタを補正。要はテスト段階で灰色になればよい)。 20 テストがぴったりグレーになったとき、フィルタ調節は完了である。ぴったりではないがNO.2の力ードでチェックしたとき補正フイルタが0.5以内のときはその分ヘッドを補正して次の段階に移る。
20 テストがぴったりグレーになったとき、フィルタ調節は完了である。ぴったりではないがNO.2の力ードでチェックしたとき補正フイルタが0.5以内のときはその分ヘッドを補正して次の段階に移る。 21 グレーテストの上に、RWグレーサンプルのNO.7(またはグレースケール2のNo7の部分)を当てがい、同濃度の部分をさがす。その部分に焼き付けられた数値が標準露光秒数である。これをタイマーにセットする。
21 グレーテストの上に、RWグレーサンプルのNO.7(またはグレースケール2のNo7の部分)を当てがい、同濃度の部分をさがす。その部分に焼き付けられた数値が標準露光秒数である。これをタイマーにセットする。 22 ネガキャリアからグレーネガを取り去り、これを一連のネガとともにコンタクトプリンターまたは透明ネ力袋にセット、もし2本目のネガがあるときは、グレーネガだけを追加しておくとそこが2本目のテスト部になる。
22 ネガキャリアからグレーネガを取り去り、これを一連のネガとともにコンタクトプリンターまたは透明ネ力袋にセット、もし2本目のネガがあるときは、グレーネガだけを追加しておくとそこが2本目のテスト部になる。 23 コンタクトを作るとき、135用のネガキャリアでは全体をカバーしきれないので、6×7用に交換する。もちろんネガは入れない。つきにフイルターとタイマーを確認し、セーフライトに切替えてペーパーをセットし、露光する。
23 コンタクトを作るとき、135用のネガキャリアでは全体をカバーしきれないので、6×7用に交換する。もちろんネガは入れない。つきにフイルターとタイマーを確認し、セーフライトに切替えてペーパーをセットし、露光する。 24 コンタクトをとった力ラーぺ一パーを乳剤面を内側にしてドラムに装填する。テストと同一条件にして、手順をまちがえないように発色現像・漂白定着処理を行う。温水による水洗についても同様に行う。
24 コンタクトをとった力ラーぺ一パーを乳剤面を内側にしてドラムに装填する。テストと同一条件にして、手順をまちがえないように発色現像・漂白定着処理を行う。温水による水洗についても同様に行う。 25 裏面もよく水洗したのち、スキージしてドライヤーで乾燥させる。これが標準コンタクトである。コンタクトを点検し、引伸したいネガを選ぶ。このときコンタクトでノーマルにプリントされているネガが適正ネガである。
25 裏面もよく水洗したのち、スキージしてドライヤーで乾燥させる。これが標準コンタクトである。コンタクトを点検し、引伸したいネガを選ぶ。このときコンタクトでノーマルにプリントされているネガが適正ネガである。 26 プリントしたいネガを、135用のネガキャリアにはさんで引伸機にセツトし、ピント・フレーム・絞りを確認しセーフライトに切替える。フィルターと露光時間は、コンタクトを作ったときと同条件でよい。
26 プリントしたいネガを、135用のネガキャリアにはさんで引伸機にセツトし、ピント・フレーム・絞りを確認しセーフライトに切替える。フィルターと露光時間は、コンタクトを作ったときと同条件でよい。 27 本焼きでは露光・現像処理・水洗・スキージ・乾燥をコンタクト作成と同様に行う。これで8X10インチの美しいカラープリントが完成する。別のコマについても、本焼きを同条件で行えぱ、安定したプリントが得られる。
27 本焼きでは露光・現像処理・水洗・スキージ・乾燥をコンタクト作成と同様に行う。これで8X10インチの美しいカラープリントが完成する。別のコマについても、本焼きを同条件で行えぱ、安定したプリントが得られる。| RW products |
|---|
●システム概要&製品一覧
色再現関連製品
●銀塩プリントオーダー用
●自家プリント用
●ポジチェック用
●照明光記録ディフーザー
●QS35用取り込み
●プリンター色再現補正
●フラットベッドスキャナー用
●FUJI DS-300用
●SONY DSC-D700用
●システム概要&製品一覧
吸着システム
●吸着フィルムホルダー
●吸着キャリア
●吸着イーゼル
●システム概要&製品一覧
色のものさし
●Top Page