 1 引伸機のキャリアにネガを入れ、8×10または10×12インチがフルフレ一ムでプリントされる高さとイーゼルの大きさを調節してピントを合わせる。35ミリネガでは、左右いっばいに合わせ、下側に余白ができるようイーゼルをセット。
1 引伸機のキャリアにネガを入れ、8×10または10×12インチがフルフレ一ムでプリントされる高さとイーゼルの大きさを調節してピントを合わせる。35ミリネガでは、左右いっばいに合わせ、下側に余白ができるようイーゼルをセット。 2 ピントルーペでピントを確認。ネガキャリアはガラス製のほうが平面性がよい。引伸レンズの絞りをF8か5.6にセット、このあと引伸機の高さも、絞り値も最終プリントまで変えないことが安定した力ラープリントを作るコツ。
2 ピントルーペでピントを確認。ネガキャリアはガラス製のほうが平面性がよい。引伸レンズの絞りをF8か5.6にセット、このあと引伸機の高さも、絞り値も最終プリントまで変えないことが安定した力ラープリントを作るコツ。 3 力ラーヘツドのYダイヤルは60、Mダイヤルは40にセツト(印画紙の指定フィルタ、Cダイヤルは日)。CPフィルタを使うときはコンデンサ上にのせる。タングステン光撮影の場合はさらに40Y+80Mを追加する。
3 力ラーヘツドのYダイヤルは60、Mダイヤルは40にセツト(印画紙の指定フィルタ、Cダイヤルは日)。CPフィルタを使うときはコンデンサ上にのせる。タングステン光撮影の場合はさらに40Y+80Mを追加する。 4 引伸機に接続した露光タイマー(カラープリントでは正確な露光が大切なので必需品)を10秒間にセツト。一度タイマーボタンを押して確認。準備が完了したら、カラープリント用のセーフライトに切替えてテスト露光を行う。
4 引伸機に接続した露光タイマー(カラープリントでは正確な露光が大切なので必需品)を10秒間にセツト。一度タイマーボタンを押して確認。準備が完了したら、カラープリント用のセーフライトに切替えてテスト露光を行う。 5 テストペーパーをドラムにセツトできる規定サイズ(たとえば4×5インチ)に力ツト。そのテストペーパーを乳剤面(着色している側)を上にしてイーゼルの中央に置き、ストライプテスタをのせる。
5 テストペーパーをドラムにセツトできる規定サイズ(たとえば4×5インチ)に力ツト。そのテストペーパーを乳剤面(着色している側)を上にしてイーゼルの中央に置き、ストライプテスタをのせる。 6 ストライプテスタの回転軸をつまんで、羽根を回転させる。すぐにタイマを押して10秒間の露光を与える。(テスターがないときは、1回目は3秒ごとに覆いながらズラシ露光し、6段階くらいの段階焼きをつくる)。
6 ストライプテスタの回転軸をつまんで、羽根を回転させる。すぐにタイマを押して10秒間の露光を与える。(テスターがないときは、1回目は3秒ごとに覆いながらズラシ露光し、6段階くらいの段階焼きをつくる)。 7 露光済のテストペーパーを、ドラムに乳剤面を内側にして挿入し蓋をする。(注 ドラムには適当位置にガイドをセットし、あらかじめ練習しておくこと。どうしてもセツトできないときは、テープで貼りつける)。
7 露光済のテストペーパーを、ドラムに乳剤面を内側にして挿入し蓋をする。(注 ドラムには適当位置にガイドをセットし、あらかじめ練習しておくこと。どうしてもセツトできないときは、テープで貼りつける)。 8 力ツプに番号をつけ、1前浴(規定の温水)、2発色現像液、3すすき液(規定の温水)、4漂白定着液、の各液重(8X10インチでは100cc)ずつ注入して液温調節し、手ぎわよく液を交換できるように配置する。
8 力ツプに番号をつけ、1前浴(規定の温水)、2発色現像液、3すすき液(規定の温水)、4漂白定着液、の各液重(8X10インチでは100cc)ずつ注入して液温調節し、手ぎわよく液を交換できるように配置する。 9 温水をドラムに注入、30-60秒間処理して排出させる。液温は、たとえば31度Cといったように一定に保つことが処理の秘訣。処理時間も含め、本番を通じて一定であれば0.5℃くらいの違いはほとんど間題にならない。
9 温水をドラムに注入、30-60秒間処理して排出させる。液温は、たとえば31度Cといったように一定に保つことが処理の秘訣。処理時間も含め、本番を通じて一定であれば0.5℃くらいの違いはほとんど間題にならない。 10 発色現像液を注入しドラムを回転させる。ドラムは液を入れると液だまりにたまり、回転によって印画紙が現像される。現像時間は11頁の表を参照。完了10秒前に回転を止めて液を排出させ、完全に液を切る(すべての処理で)。
10 発色現像液を注入しドラムを回転させる。ドラムは液を入れると液だまりにたまり、回転によって印画紙が現像される。現像時間は11頁の表を参照。完了10秒前に回転を止めて液を排出させ、完全に液を切る(すべての処理で)。 11 中間水洗を温水で30-60秒行う。この水洗処理もテストと本番で、つねに一定条件で行うことがコツ。すべての処理をテストと本焼きで同じように行わないと、正しい発色を得ることができない。
11 中間水洗を温水で30-60秒行う。この水洗処理もテストと本番で、つねに一定条件で行うことがコツ。すべての処理をテストと本焼きで同じように行わないと、正しい発色を得ることができない。 12 漂白定着液を注き、ドラムを回転させる。発色現像でできた黒化銀と色素(発色カプラ)のうち銀だけが漂白され、未感光銀とともに定着剤で除去される。残った色素により色画像が構成される。
12 漂白定着液を注き、ドラムを回転させる。発色現像でできた黒化銀と色素(発色カプラ)のうち銀だけが漂白され、未感光銀とともに定着剤で除去される。残った色素により色画像が構成される。 13 ドラムから印画紙を取り出して大きめのバットに移し、流水で3-4分水洗する。裏側の薬液もよく洗う。キズがつきやすいので乳剤面には手をふれないこと。この間にドラムも水でよく洗い、水滴を完全に拭っておく。
13 ドラムから印画紙を取り出して大きめのバットに移し、流水で3-4分水洗する。裏側の薬液もよく洗う。キズがつきやすいので乳剤面には手をふれないこと。この間にドラムも水でよく洗い、水滴を完全に拭っておく。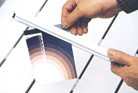 14 印画紙を専用のスキージ(スクイジーともいう)で水滴を完全に取り去る。水滴が付着しているとその部分に斑点状のムラが残るのでていねいに行う。とくに本焼きでは消えないので要注意。
14 印画紙を専用のスキージ(スクイジーともいう)で水滴を完全に取り去る。水滴が付着しているとその部分に斑点状のムラが残るのでていねいに行う。とくに本焼きでは消えないので要注意。| RW products |
|---|
●システム概要&製品一覧
色再現関連製品
●銀塩プリントオーダー用
●自家プリント用
●ポジチェック用
●照明光記録ディフーザー
●QS35用取り込み
●プリンター色再現補正
●フラットベッドスキャナー用
●FUJI DS-300用
●SONY DSC-D700用
●システム概要&製品一覧
吸着システム
●吸着フィルムホルダー
●吸着キャリア
●吸着イーゼル
●システム概要&製品一覧
色のものさし
●Top Page