![]() 特定保健用食品(トクホ) : 厚生労働省が生活習慣病の予防に有用と認めた食品
特定保健用食品(トクホ) : 厚生労働省が生活習慣病の予防に有用と認めた食品
![]() 栄養機能食品
: ビタミン、ミネラルなど14種類の栄養成分を一定量含む食品
栄養機能食品
: ビタミン、ミネラルなど14種類の栄養成分を一定量含む食品
![]() 健康補助食品
: 特定保健用食品に該当しないが、体によいとされる栄養成分の補給を目的とした食品
健康補助食品
: 特定保健用食品に該当しないが、体によいとされる栄養成分の補給を目的とした食品


特定保健用食品マーク JHFAマーク
ビタミンとは、化学反応などの体のさまざまな働きをスムーズにし、体内では合成できない、または合成されても必要量に足りない有機化合物を指します。体内で十分作ることができないため、食物から摂取する必要があり、不足すると欠乏症状が現れ、とりすぎると過剰症が現れるものもあります。
特に大切な働きは、糖質や脂質などのエネルギー源が体内でエネルギーになるための代謝をサポートしたり、体の組織をつくったり、古い細胞を新しくつくりかえる新陳代謝をサポートすることです。
現在、ビタミンとして認められているものは13種類あります。
|
名称(化学名・別名) |
主な働き |
多く含む食品 |
||
|
脂溶性ビタミン |
ビタミンA (レチノール・β―カロテン) |
・皮膚や粘膜を正常に保つ ・視力を保つ ・免疫力を維持する ・抗酸化作用があり、抗がん作用がある |
レバー、肉類、魚介類、卵、緑黄色野菜など
|
|
|
ビタミンD (カルシフェロール) |
・カルシウムの吸収を促進し、骨の発育に欠かせない |
レバー、イワシ、カツオ、マグロ、きのこ類など |
||
|
ビタミンE (トコフェロール) |
・抗酸化作用がある ・血行を促す ・老化を防止する ・生殖機能を正常に保つ |
魚介類、植物油、種実類、緑黄色野菜など |
||
|
ビタミンK (フィロキノン) |
・血液凝固作用を補助する |
納豆、ブロッコリー、ほうれん草、肉類、油脂類
|
||
|
水溶性ビタミン |
ビタミンB群 |
ビタミンB1 (チアミン) |
・糖質をエネルギーに代謝するときに必要 |
豚肉、穀類、豆類など |
|
ビタミンB2 (リボフラビン) |
・脂質の代謝に関わる ・成長を促進する |
レバー、卵黄、肉類など |
||
|
ビタミンB6 (ピリドキシン) |
・たんぱく質の代謝に必要 ・免疫力を保つ |
肉類、魚介類、卵、くだものなど
|
||
|
ビタミンB12 (コバラミン) |
・たんぱく質の代謝に必要 ・葉酸とともに貧血を防ぎ、神経機能を維持する |
レバー、肉類、魚介類、卵、くだものなど |
||
|
ナイアシン (ニコチン酸) |
・皮膚を健康に保つ ・糖質とアミノ酸の代謝をつなぐ働きをする |
肉類、種実類など |
||
|
パントテン酸 (ビタミンB5) |
・エネルギーの代謝全般に関わる ・免疫力を高め、ストレスに対抗する |
レバー、肉類、魚介類、牛乳、豆、きのこなど |
||
|
葉酸 (プテロイルグルタミン酸) |
・貧血を防ぎ、成長を促進する ・核酸やアミノ酸の代謝を促進する |
レバー、肉類、卵黄、胚芽、緑黄色野菜など |
||
|
ビオチン (ビタミンH) |
・皮膚や髪の健康を維持する |
レバー、魚介類、種実など |
||
|
ビタミンC (アスコルビン酸) |
・コラーゲンの生成に関わり、毛細血管や歯、軟骨の結合組織を維持する ・免疫力を高める ・鉄の吸収を促進する ・抗酸化作用がある |
くだもの、野菜、芋類など
|
||
一日所要量、欠乏症、過剰症
|
名称 |
一日の所要量 |
欠乏症 |
過剰症 |
||
|
成人男性 |
成人女性 |
許容上限摂取量 |
|||
|
ビタミンA |
600μgRE |
540μgRE |
1500μgRE |
夜盲症 |
頭痛、嘔吐など |
|
ビタミンD |
2.5μg |
2.5μg |
50μg |
くる病、骨粗しょう症 |
高カルシウム血症、腎不全 |
|
ビタミンE |
10mg |
8mg |
600mg |
血行不良 |
|
|
ビタミンK |
55〜65μg |
50〜55μg |
30000μg |
出血性傾向 |
|
|
ビタミンB1 |
1.1mg |
0.8mg |
― |
脚気、中枢神経障害 |
|
|
ビタミンB2 |
1.2mg |
1.0mg |
― |
口内炎、舌炎、皮膚炎、眼炎 |
|
|
ビタミンB6 |
1.6mg |
1.2mg |
100mg |
口内炎、脂漏性皮膚炎 |
|
|
ビタミンB12 |
2.4μg |
2.4μg |
― |
悪性貧血 |
|
|
ナイアシン |
16〜17mg |
13mg |
30mg |
ペラグラ皮膚炎
|
皮膚のかゆみ、潮紅
|
|
パントテン酸 |
5mg |
5mg |
― |
疲れやすい |
|
|
葉酸 |
200μg |
200μg |
1000μg |
巨赤芽性貧血 |
|
|
ビオチン |
30μg |
30μg |
― |
皮膚炎、白髪 |
|
|
ビタミンC |
100mg |
100mg |
― |
壊血病 |
|
ビタミン様因子とは、ビタミンと同様の働きがあるものの、体内で合成することができたり欠乏症が知られていない微量栄養素のこと
|
名称(別名) |
特徴 |
主な働き |
多く含む食品 |
|
ビタミンP (フラボノイド) |
水溶性 |
・ビタミンCの働きを高める ・毛細血管をじょうぶにする ・血圧降下作用がある |
かんきつ類 そばなど |
|
カロテノイド (ポリエン色素) |
植物に含まれる色素で多種類ある カロテン、リコペン、ルテイン、フコキサンチンなど |
・強い抗酸化作用がある |
植物性の食品 特に緑黄色野菜やかんきつ類、海藻など |
|
イノシトール |
水溶性 ビタミンB群の一種 |
・細胞膜の成分になる |
オレンジ、メロン、グレープフルーツなど |
|
コリン |
水溶性 アミノ酸から合成される |
・アセチルコリン、レシチンの材料になる ・高血圧、動脈硬化を防ぐ |
レバー 卵など |
|
パラアミノ安息香酸 (PABA) |
ビタミンB群の一種 |
・葉酸の合成に必要 ・肌・髪の老化を防ぐ ・腸内の有用菌を繁殖させる |
卵 レバー 牛乳など
|
|
コエンザイムQ (ユビキノン ・補酵素) |
脂溶性 |
・抗酸化作用がある ・糖質をエネルギーに変える ・白血球の作用を高める |
レバー 牛肉、豚肉 カツオ、マグロなど |
|
ビタミンU (塩化メチルメチオニン スルホニウム) |
キャベツから発見された 商品名キャベジン |
・胃酸の分泌を抑える ・胃腸の粘膜の新陳代謝を活発にする |
キャベツ レタス セロリなど |
|
リポ酸 (チオクト酸) |
ビタミンB1とともに働く |
・抗酸化作用がある ・脳の損傷を修復する |
レバー 酵母など |
ミネラルとは、無機質ともいい、栄養学的にはビタミンと同様、体内の潤滑油的な働きをする栄養素です。ビタミンとは違い、単一の元素で構成されています。
|
分類 |
名称(元素記号) |
主な働き |
|
準主要元素 |
カルシウム(Ca) |
骨や歯を形成する 神経の興奮を鎮める |
|
リン(P) |
骨や歯を形成する リン脂質、核酸の成分になる |
|
|
カリウム(K) |
心臓の機能や筋肉の機能を調整する ナトリウムと拮抗して細胞内の浸透圧を一定に保つ |
|
|
イオウ(S) |
皮膚などを健康に保つ 酵素を活性化する 解毒作用がある |
|
|
ナトリウム(Na) |
筋肉や神経の興奮を鎮める 細胞外液の浸透圧を保持する |
|
|
塩素(Cl) |
胃液の成分になる 殺菌作用がある |
|
|
マグネシウム(Mg) |
筋肉を活性化させる 神経の興奮を鎮める 酵素の作用を活性化する 糖質や脂質の代謝を助ける |
|
|
微量元素 |
鉄(Fe) |
酸素を運搬して細胞にとり入れる エネルギーの燃焼に働く |
|
亜鉛(Zn) |
核酸やたんぱく質の合成に働く |
|
|
銅(Cu) |
ヘモグロビンの合成を助ける 鉄の吸収をよくする |
|
|
ヨウ素(I) |
発育を促進する 基礎代謝を活発にする |
|
|
セレン(Se) |
抗酸化作用がある |
|
|
マンガン(Mn) |
骨の形成を促進する 骨や肝臓での酵素の働きを活発化する |
|
|
モリブテン(Mo) |
成長を促進させる 糖質などの代謝に関わる |
|
|
クロム(Cr) |
糖質や脂質の代謝に欠かせない |
|
|
コバルト(Co) |
造血機能に不可欠 赤血球の色素の生成に関わる |
|
|
超微量元素 |
バナジウム(V) |
コレステロールなどの代謝に関わる |
|
フッ素(F) |
歯のエナメル色素を強化して虫歯予防に働く |
|
|
ケイ素(Si) |
コラーゲンの働きを助ける 骨、腱、爪、血管をじょうぶにする |
|
|
ニッケル(Ni) |
尿素の分解を促す 酵素の働きをサポートする |
|
|
リチウム(Li) |
白血球を増加させる 自律神経の働きに関わる |
一日所要量、欠乏症、過剰症
|
名称 |
一日の所要量 |
欠乏症 |
過剰症 |
||
|
成人男性 |
成人女性 |
許容成人摂取量 |
|||
|
カルシウム(Ca) |
600〜700mg |
600mg |
2500mg |
くる病、骨軟化症 |
高カルシウム血症 |
|
リン(P) |
700mg |
700mg |
4000mg |
骨や歯が弱る |
Caの吸収阻害 |
|
カリウム(K) |
2000mg |
2000mg |
― |
|
|
|
ナトリウム(Na) |
10g以下 |
10g以下 |
― |
|
高血圧 |
|
マグネシウム(Mg) |
280〜320mg |
240〜260mg |
650〜700mg |
疲労感、筋力低下 |
下痢、吐き気 |
|
鉄(Fe) |
10mg |
10〜12mg |
40mg |
貧血 |
|
|
亜鉛(Zn) |
10〜12mg |
9〜12mg |
30mg |
味覚異常 |
|
|
銅(Cu) |
1.6〜1.8mg |
1.4〜1.6mg |
9mg |
貧血 |
|
|
ヨウ素(I) |
150μg |
150μg |
3mg |
甲状腺腫、クレチン症 |
甲状腺腫 |
|
セレン(Se) |
45〜60μg |
40〜45μg |
250μg |
老化しやすい |
脱毛、爪の異常 |
|
マンガン(Mn) |
3.5〜4.0 mg |
3.0〜3.5mg |
10mg |
骨異常 |
|
|
モリブテン(Mo) |
25〜30μg |
25μg |
200〜250μg |
|
|
|
クロム(Cr) |
25〜35μg |
20〜30μg |
200〜250μg |
耐糖反応の障害 |
|
|
コバルト(Co) |
|
|
|
ビタミンB12欠乏症 |
|
肉体疲労の人に・・・ビタミンB群をたっぷりとる
ビタミンCで疲労回復
ストレス・イライラのある人に・・・ビタミンC・Eでストレスへの抵抗力をつける
カルシウムで神経系を強化
不眠の人に・・・カルシウムとマグネシウムでイライラ解消
ビタミンB6で神経を休める
食欲不振の人に・・・ビタミンB群でエネルギー代謝を促進
ビタミンA・Uで胃腸の粘膜をじょうぶに
冷え性の人に・・・鉄・マグネシウムで血行をよくする
ビタミンEやナイアシンで血液の循環を促進
目の疲れのある人に・・・ビタミンAをたっぷりとる
ビタミンB2で視神経の働きを高める
しみ・そばかすのある人に・・・ビタミンC効果で美白
ビタミンEで肌を活性化する
乾燥肌の人に・・・ビタミンB2・B6・ナイアシンで皮脂をコントロール
ビタミンEで皮膚の形成を促進
口内炎のある人に・・・ビタミンA・Cで粘膜をじょうぶに
ビタミンB2・B6で粘膜を保護する
タバコの害のある人に・・・ビタミンC・E、β―カロテンで活性酸素の害を防ぐ
ビタミンAで皮膚や粘膜を健康に
飲みすぎ・二日酔いの人に・・・ビタミンCで肝臓の働きを促進
ビタミンB6でたんぱく質の吸収を促進
生理痛の人に・・・ビタミンEで血行をよくする
ビタミンB6でホルモンバランスを改善
ビタミンB1で神経を鎮静させる
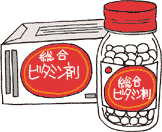
Q.いつ摂取すれば効果的ですか?
A.ビタミン、ミネラル類は摂った食べ物との密接な関連性があるので、食後30分以内が効果的といわれています。水溶性のビタミンは、たくさんとっても利用されなければ、尿や汗とともにすぐに排泄されてしまいます。蓄積できないので、朝、昼、晩と分けてとると効果がとぎれません。一方の脂溶性ビタミンは、脂質に溶けて体内に吸収されるため、食事の前後にとると吸収が早くなります。使われなかった分は蓄積されるため、1日1〜2回にまとめてとっても構いません。
Q.サプリメントを飲んではいけないときは、どんなときですか?
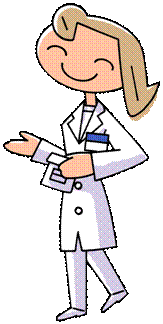 A.アレルギー体質の人は、材料にアレルギー反応を示す素材が使われている可能性があるので、湿疹などのアレルギー反応が出た場合には、飲むのをやめて、自分に合ったものを探してください。また、血液検査や尿検査を受ける日には、ビタミン剤を飲むのをストップしてください。特にビタミンCは、血液中のコレステロールや中性脂肪、尿酸などの数値を実際より低く表してしまうことがあるからです。
A.アレルギー体質の人は、材料にアレルギー反応を示す素材が使われている可能性があるので、湿疹などのアレルギー反応が出た場合には、飲むのをやめて、自分に合ったものを探してください。また、血液検査や尿検査を受ける日には、ビタミン剤を飲むのをストップしてください。特にビタミンCは、血液中のコレステロールや中性脂肪、尿酸などの数値を実際より低く表してしまうことがあるからです。
薬剤師にご相談ください。





