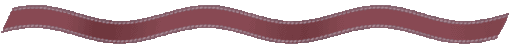
43−86mmインプレッション
(28−70mmズームとの比較)
(2020年6月7日)
43−86mmズームを初めて実戦投入した2016年9月のMAX撮影会です。
| 気がつけば10本以上も広角〜標準系レンズを持っています。雑誌・ネット情報で気になったやつを見かけた瞬間買ってしまった結果です。しかし、各レンズの本当の特徴を把握できていません。今回の新型ウィルス騒動で外出制限のかかったこのタイミングで調べてみました。最初はすべてのレンズをいっぺんに報告しようと思っていたのですが、整理しきれそうにないので、レンズごとに報告することにします。 第1回目は43−86mmズームです。このレンズは2016年の夏、入手し、その年の9月のMAX撮影会で実戦投入しています。その際、想像以上に違いが出たので、詳細を改めて報告したいとお伝えしました。しかし何も対応せず、現在に至っています。今回の外出規制で出来た時間を使ってインプレッションしてみました。 |
マニュアル時代のズームはワンアクションリングと被写界深度の曲線(通称:ひげ)が特徴です。
| 43−86mmは一眼レフ黎明期のズームレンズです。最初の発売は1963年でした。その後数回の設計変更を経て1982年頃まで販売されました。標準ズームということで需要が多かったこと、コンパクトでそれなりの値段だったことから20年近くも販売されました。標準ズームは設計が難しく、コンピュータの能力が貧弱だった50年前は困難を極めたようです。雑誌の受け売りですが、このレンズは50mmを間に挟むこと、ズーム比2倍以上を確保することが命題だったようで、開発担当者は1mm刻みで妥協点を探ったようです。その結果、この中途半端とも思える焦点距離となったのでした。 オレが入手したレンズは外観から最後期のモデルと思われます。レンズ構成を一部変更し、初期モデルの欠点であった解像度を向上させたモデルとのことです。 |
像歪収差の違い

マウスポインタを画像に重ねると43−86mm画像となります(歪みが確認できます)。
| このレンズを語る時外せないのが歪みです。雑誌などでこのレンズの歪みは酷評されてきましたが、今回のテストで分かりやすい写真が撮れました。歪んでいることが分かると思います。43−86mmは飛び出してくるような感じです。ただし、普段、こういう比較はしないと思います。単独で示された場合、気が付かないかもしれません。後の画像を使った計量には使えないと思いますが、通常使用には差し支えないと思います。雑誌で言われる程のものではないかと思います。 なお、色合いやコントラストも違って見えると思います。個人的には43−86mmの方が好きです。この違いについては別項目で改めて触れたいと思います。 |
このサイズでは分かりづらいかもしれませんが、43−86mmはどこにもピントが合っていません(左:28−70mm、右:43−86mm)
| これも面白い比較となりました。撮影距離が違うし、ピントの合っている箇所も異なるので厳密な比較ではありませんが、特徴が上手く出たと思っています。画面周辺部の画質に違いが出ました。43−86mmの周辺は像が流れています。43−86mmは花にピントが合っていない(最短撮影距離の関係)ことも合わせ、結果としてまとまりのない写真となりました。ある意味においてこのレンズを象徴する写真となりました。 |


上の画像を拡大するとボケの状態の違いが分かります(左:28−70mm、右:43−86mm)
| これらは上の写真の拡大です。ボケの比較です。43−86mmは周辺に向かって像が流れているように見えませんか。これはボケではなく、収差です。恐らく球面収差と思いますが、収差の補正をかけないレンズに多く見られます。とくに広角レンズでは被写界深度が深い(ボケが目立たない)分、この収差(像の流れ)が目立ちます。 |
左の画像は渦を巻いているように見えませんか?右の方が自然なボケに見えます(左:28−70mm、右:43−86mm)
| 28−70mmのボケをご覧ください。渦を巻いているように見えませんか。ぐるぐるボケと呼ばれていますが、球面収差の補正をかけ過ぎると発生することが多いようです。一昔前の比較的高解像度のレンズに多く見られるボケです。被写界深度が浅く、少しのずれでボケが大きく発生する標準から中望遠で発生することが多いようです。 この傾向は43−86mmにも当てはまるのですが、望遠側で適切に補正されているのだと思います。絶妙なボケ具合です。恐らく撮影距離も大きく影響すると思いますが、これら4枚の中では一番好きな写りです。この例は43−86mmレンズの特性を生かした撮影方法の一つだと思います。 |
中心付近はほとんど同じくらいの明るさですが、周辺はずいぶん違いがあります(左:28−70mm、右:43−86mm)
| これも面白い結果となった画像です。元々、歪みが出ることを狙って撮った写真ですが、周辺光量が気になる写真となりました。43−86mmの周辺は真っ暗と言って良いかもしれません。他の画像でもその傾向はうかがえますが、この例の場合、真ん中に明るい部位が位置することで傾向が顕著になったのかもしれません。一般的に周辺光量の落ち込みは嫌われますが、これはこれで味わい深い雰囲気です。 因みに歪みですが、門の「ぐし」を見てください。糸巻き型歪みを狙ったのですが28−70mmの方が目立つかもしれません。おそらく歪みは焦点距離だけでなく撮影距離によってもその量が変化すると思われます。 |
||
どちらもWBは太陽光です。43−86mmは黄色く見えます(左:28−70mm、右:43−86mm)
| この画像で気になるのは色の違いです。このレンズは状態が良かったため、レンズの変色がほとんどないと思っていました。実際、仕上がりに不満はありませんでした。しかし、この画像を比べると道路が黄色に見えます。古いニコンはレンズが黄色になると言われていましたが、初めて確認できました。恐らくこの違いは劣化ではなく元々の色ではないかと思います。並べなければわからないくらいの差です。 (余談) 白黒写真が主流だったころ、レンズの色はそれほど重要視されませんでした。ニコンは画質向上を優先させました。その結果、ニコンにはレンズ間の色がバラバラという欠点が生じました。この点を最初に突いてきたのがキヤノンです。すべてのレンズの色をそろえ、カラーフィルムを使ったとき色合いの変化が出ないようにしました。このことはポートレート写真で如実に表れたことからキャノンは最初にグラビア系のカメラマンに評価されたという流れがあります。 |
逆光特性
カーテンの写りは同じようですが、遠くの樹木の写りに差が生じました(左:28−70mm、右:43−86mm)
| 古いレンズはレンズコーティングが未熟だったり、そのコーティングが劣化しているケースがあり、逆光に弱いと言われています。厳密な比較をするつもりで撮った画像ではありませんが、ご覧ください。見た目はほとんど変わらないと思います。逆光に弱いレンズは明暗差が生じる場所(画像の場合カーテンの縁)に光の滲みが出ますが、両者ともほぼ同じです。違いは43−86mmの遠景が光に溶け込でいる点くらいでしょう。28−70mmは情景が辛うじて残っていることが確認できます。 |
| というわけでお伝えしました。まず、結論ですが、雑誌などで言いふらされているような差を感じることはできないということです。紹介した作例もこのサイズでは気付かないかもしれません。ぐにゃぐにゃ、ボケボケを「期待」すると、案外まともな写りで「がっかり」することが多いと思います。喧伝され続けてきた「歪み」「周辺画質」「周辺光量」の悪さを「楽しむ」には周辺にも見せたい部分がある、中心付近を明るくする、直線が多く含まれる被写体を撮ると見えてくるかもしれません。「ボケの汚さ」を強調させるにはピントが微妙にずれている場合の方が分かりやすいようです。思い切りずれている場合は単なるボケになり、条件次第では綺麗に見える場合もあるようです。ダメダメ品を最初から作る人はいません。妥協の産物とはいえ可能な限りの対応はしていますので、通常には何ら問題なく使えるレンズです。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる