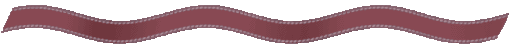
広角レンズの使い分け
(レンズ・インプレッション)
(2018年5月26日)



広角レンズは扱いが難しいのですが、その魅力に取り付かれると抜け出せなくなりますw
| あまり大声で言ってませんでしたが、ここ1年間で広角系を中心に3本もレンズを手に入れました。フルサイズデジカメ2台体制となったものの、レンズの性能がカメラに負けているように感じたからです。ただ、それぞれのレンズを使いこなせていないのが現状です。レンズの癖を知らないからです。そこで、自分なりにレンズの比較をしてみました。 |
| 20mmF2.8 | 24−70mmF2.8ズーム | 24−120mmF3.5ズーム | 28mmF3.5 | |
| 外観写真 | ||||
| 概 要 | この4本の中では一番最後に入手したレンズです。2018年のCP+の中古市で一目惚れしました。フィルターリングの部分にそそられました。 開放F値は3.5。最短撮影距離は25cm。発売開始は1984年12月。ニコンの現在までのマニュアル20mmの最後のモデルで、かつ、現在も販売中です。光学系はそのままAFレンズに受け継がれています。 |
広角系にも関わらず、恐ろしく全長が長いレンズです。知らない人が見たら望遠レンズと思うでしょう。24−120mmズームに不満を持つようになり、2017年末買ってしまいました。 開放値は全域F2.8。最短撮影距離は38cmですが、全長が20cm近くあるので、レンズ先端からの撮影距離(ワーキングディスタンス)は20cm以下となります。 |
所有するレンズで一番数奇な運命を辿ったと思います。2003年に購入し、D100やF80とともに使ったものの、18−300mmズームを手にした後出番はめっきり減りました。しかし、その後D810を購入し、再び最前線へ。手軽に使えるズームとして重宝しています。 24mmにおける開放値はF3.5。最短撮影距離は50cm。発売直後は重宝しましたが、今となっては物足りません。 |
2017年CP+の中古市で購入したレンズです。28mmレンズは高校時代にT社製を手に入れましたが、複雑な機械構造が災いし壊れてしまい、純正が欲しいと思っていました。ただ、今ではズームレンズで代用できると思っていましたが、展示会で見せつけられ、衝動買いしてしまいました。 開放F値は3.5。最短撮影距離は30cm。Sタイプでないので、1980年頃の製造と思われます。 |
1.周辺光量
| レンズに斜めに入った光はレンズの中での減衰が大きいことに加え、枠や筒の一部によって遮られるためフィルム(センサー)に到達する光は中央部よりも少なくなります。これを口径食と言います。さらにコサイン4乗則の影響も加わることで得られる画像はまるでスポットライトに照らされたような描写となります。この影響は望遠より広角レンズの方が大きくなります。このような表現を意図しているのであればともかく、一般的には嫌われる描写です。カメラメーカは改善を進めてきましたが、古い設計ではその影響が残っている場合があります。 それぞれのレンズの周辺光量がどのようになっているか、調べてみました。なお、口径食は絞りを絞ることで改善されます。開放値の異なるレンズを比較するためF5.6での光量も一緒に確認しました。 (コサイン4乗則は後日詳細をお伝えします) |
| 20mm | 24−70mmズーム | 24−120mmズーム | 28mm | |
| 開放 | ||||
| F5.6 |  |
|||
| 評 価 | 周辺の光量が落ちていることが一目で分かります。これを知らずに撮影するとかなりがっかりになると思います。5.6まで絞ればあまり気にならない光量低下となります。 | 2.8まで明るいにもかかわらず開放3.5の旧型品と同じくらいの光量落ちです。5.6で比較するとその差は歴然です。さすが現代のレンズと言いたいところですが、面白みには欠けますね。 | 開放(3.5)でも十分実用的な光量落ちです。ただし、新型モデルに比べると落ちているのが分かります。そこは時代の差ってことです。 | それほど気にならない光量低下です。28mmともなればこの問題は30年前にクリアできていると言うことです。もちろん意識して観察すれば5.6でも光量落ちが確認できますが、通常撮影では開放でも問題ないレベルと思います。 |

| なお、周辺光量が十分確保されれば良いレンズなのかといいうと実は一概に言えません。周辺光量落ちを生かした広角レンズの使い方があるからです。そういう映像作品もたくさんあります。デジタル技術で周辺光量補正も楽になりました。この性能は劣っていても特に大きな問題になることがないことを付け加えます。上左は20mm開放画像(左上画像)を加工したものです。元の画像に比べ画面全体の明るさが等しくなっています。また、上右は某有名映画のワンシーンです。センター付近の明るさを強調することで、幻想的な演出をしています。 |
2.周辺解像度
| 中心からの離隔角度が大きくなると解像度も落ちていきます。これの比較をしてみました。ただしこれも一概に言えません。ボケに関係するからです。周辺解像度を向上させると、ボケが汚くなると言われています。どの辺に落ち着かせるかがレンズ設計の難しいところになります。 | ||
調査は1つのレンズについて構図を変えて2枚撮影し、同じ場所(黄色の枠)の比較をしました。 |
||
| 20mm | 24−70mmズーム | 24−120ズーム | 28mm | |
| 中央 | ||||
| 周辺 | ||||
| 評 価 | 明らかに周辺画質は低下していますが、中央部に比べた場合、拡大しなければ分からないレベルです。20mmと言うことを考慮すれば、中央部から周辺まで安定した画質と言えます。 むしろ気になるのは倍率変動です。同じ位置から撮った画像にもかかわらず周辺と中央部でここまで差が出るとは予想していませんでした。 |
周辺の画質低下は確認できましたが、全く問題ありません。ズームであること、F2.8であることを考えると、4本中一番良い成績と言えます。広角レンズで被写体をあえて端に置くような構図の場合、失敗する可能性がありますが、このレンズは構図関係なく、間違いのない画像を得ることが出来ます。 | 4本の中では一番画質低下が悪かったですね。特に中央と周辺部の差が著しいです。かつてデジイチの黎明期にアンチニコンから徹底的に叩かれた画像がこれです。でも今では「レンズの味」として多くのユーザーが評価する余裕が出来ました。 | 得られた画像だけを比較すれば、一番と言って良い成績でした。加えて中央部での画質も一番良かったですね。これはレンズの性能云々より、焦点距離が28mmで、単焦点レンズという事が大きく作用したと思います。 |
3.最短撮影距離
| 昔から言われるのですが、広角レンズを持ったときは一歩前へ出ろいうセオリーがあります。撮りたいものを強調できるからです。でもそれには一つ重要なレンズの性能があります。最短撮影距離です。せっかく前へ出てもピントが合わなければ意味がありません。そこで最短撮影距離を確認しました。ただし、焦点距離が異なるレンズの比較となりますので、どれくらい大きく写せるかを確認しました。 結果は28mmが一番でした。携帯ガスボンベの大きさは分かるかと思いますが、これは一般的な人間の顔を画面いっぱいに写すことが出来ると考えて良いと思います。ただし、鼻デカ写真的な画像を狙うのであればやはり24mmまで広くないと難しいでしょう。そうなると24mmズームってことになると思います。オールドズームは残念ながら遠すぎです。 |
| 20mm | 24−70mmズーム | 24−120ズーム | 28mm | |
| 最短距離 | ||||
| コメント | カセットボンベの高さは25cm弱ですので、どんな小顔のモデルさんでも顔を画面いっぱいに写すことが出来るくらい近づけます。このときの撮影距離は25cmですが、この距離はフィルム(センサー)面からの距離です。レンズ先端からは15cm程度です。ここまで近づくと、傍目からは異常接近(というより、変態接近)状態に見えます。モデルさんの撮影時は予告などが必要ですね。 | 20mmレンズほど被写体を大きく写すことは出来ません。しかし、撮影距離は38cm確保されています。これでも異常接近かも知れませんが、変態接近ではないと思います。無難な距離です。ただし注意すべきは焦点距離の変動です。最短距離までフォーカスリングを回したときの焦点距離は実質的には26mm程度になります。遠近強調が弱くなります。 | 通常であればほぼ十分な50cmまで近づくことが出来ます。ただし、広角レンズの楽しみを知った人には不満の残る距離です。作例であればカセットボンベケースを画面いっぱいに写せるかどうかが一つの判断になると思います。でもこのレンズで10年前は満足していたんですよねぇ。 | 文句ないサイズで被写体を写すことができます。これで撮影距離は30cm。モデルさんの顔を常識的なサイズで写す場合、50〜60cm離れます。これだったら怖くならないでしょうね。安心して使えるレンズと言えます。 |
4.ボケ具合
| 次にボケ具合を確認してみました。実はボケの良さというものはきわめて曖昧な定義です。レンズの善し悪しを評価する項目は多数ありますが、なかなか数値化出来ない項目であることに加え、人によって評価が異なるからです。一般的に輪郭が綺麗に崩れるのがよしとされています。例えば黒(彩度0)と白(彩度255)の境目は数値が一定間隔で0から255に変化するのが良いとされています。このような変化をしない場合、一般的には嫌われる二線ボケのような形で現れます。また、このことは距離に対するボケも同様で、ピント面から離れるときのボケの変化にジャンプがないようなレンズが良いと言われています。 |
5.歪み
広い範囲を撮ることの出来る広角レンズは角度によっては画像が大きく歪みます。常にNG画像と隣り合わせです。 |
| レンズには多かれ少なかれ像歪特性があります。本来まっすぐのものが曲がって写ってしまう現象です。これは特に広角レンズで目立ちやすく、人工構造物(建物や鉄道)や証拠写真、学術写真を撮る人たちには重要な特性です。鉛直線や列車が曲がってしまう、見取りが正しく記録されない、画像を使った解析が困難になるなどの影響が出ることとなります。集合写真、記念写真でも端の人が可哀想な写りになってしまいます。もちろん、レンズの味として楽しむことも出来ますが、そのレンズの癖として認識しておく必要はあります。 などと心配を先に言いましたが、持っているレンズで大きく歪むのはありませんでした。車庫のシャッターを撮る限りではレンズ間の明確な違いは見いだせませんでした。むしろ、使い方(構図の取り方)の方が重要であることも分かりました。 |
6.まとめ(使い分け)
| とまあ、いろいろ検証をしてみてそれぞれのレンズの特徴を確認することが出来ました。で、結局結論は?タイトルに対する答えが出ていません・・・・。 んーーーー、結局成り行きでしょう。でも一応次のような感じで使い分けようかと思います。 |
 トップページへもどる
トップページへもどる