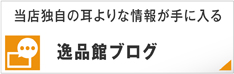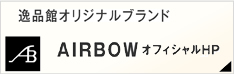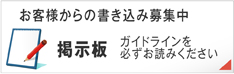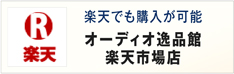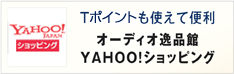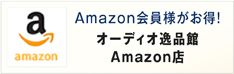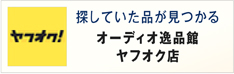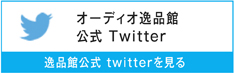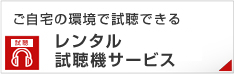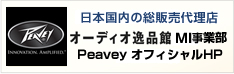生録 ”Live Recording” レポート
オーディオ機器とは、音楽を録音し再生する装置です。もしその装置を開発しようとするなら、「テストに使うための音楽ソース」が必要となります。そして、再生装置の「再現する音楽」に「精度」を求めるなら、「絶対に自分が録音した音楽ソース」を用いなければならないのです。
しかし、オーディオメーカーの設計者が「自分で録音」をしているという話はあまり聞いたことがありません。また、「録音現場に立ち会った音楽ソース」をお持ちになっていらっしゃる、オーディオマニアも、非常にまれなのではないでしょうか?
「音と音楽」の章で、私に「音楽を厳しく教授して下さる指揮者」のご紹介を致しましたが、98年8月30日に行われた「公開練習会」とその「生録」の様子をレポートいたしましょう。(さらに簡便な小ホールを利用した録音と演奏の実験はもっと数多く行っています)
開催場所は「箕面・東生涯学習会館」の、大きさが、縦20m×横15m×高さ10m程度の多目的・小ホールです。
音響特性的には、決して恵まれているとはいえないのですが、「ある程度の残響がある大きな空間」で練習を積まないことには、「実際のコンサートで楽器の音をどのようにコントロールすべきか?」を学ぶことはできません。
音楽を学ぶための練習会。それは「私達オーディオファン」にとっては、「またとない、生きた音楽を学べる機会」なのです。
当日のマイクセッティングをご紹介いたしましょう。

左からSONY/C38B ・ Neumann/USM69i USM69i/拡大画像
当日は、2種類のマイクを使用しました。
|
SONY/C38B(改) | |
|
Neumann/USM69i | |
|
録音機器・AIWA/XK−S9000(改) |
同時に、Victor/KY19とHR−W1/SDモードによる、ビデオ収録も行いました。
その都合もあって、マイクのポジションは、ホールの後方1/3中央。高さは160Cmです。
ご覧頂ければお分かりいただけるでしょうが、SONYのマイクはやや外側向きにセットされています。
マイク正面からの音と、左右のホールの音を取り分けて、ステレオイメージを調整するためです。
USM69iは、二つのカプセルの指向性を「前方中心」にし、それぞれのカプセルの角度差を約15度にセットしました。
本来なら、「モニタースピーカー」を持参して「2本のスピーカーでモニター」すべきなのですが、時間と会場の都合上
割愛しました。
ヘンデル/トリオ・ソナタ テレマン/ビオラ協奏曲
バッハ/2つのVnの為の協奏曲 ヴィヴァルディ/チェロソナタ
モーツァルト/ピアノ協奏曲K−488 ラヴェル/水の戯れ
どうです?
普段着の中にも、「真剣な熱気」が伝わってきませんか?
じつは、逸品館のお客様の中で「公開練習」に参加して、「どうしても楽器をやりたくなって」、豊島音楽教室の門をくぐった人がいるくらいです。オーディオだけではなく「生きた音楽」に接してみて下さい。「大きな収穫」があなたを待っているはずです。
生録とオーディオ装置の音決め
アンプなどのオーディオ機器を作るとき、「音のテスト」は、「音楽」ではなく「音」で行います。
そうしないと「音楽に自分の好みが紛れ込む」からです。
そして、「仕上がりのチェック」は、「まず自分が立ち会った(録音した)音楽ソース」で行い、その後に「いつも良く聴いている音楽ソフト」で最終確認をしています。その過程のどこかで「気になる点」が感じられたら、また「最初からさらに細かくヒヤリングを繰り返して」音と音楽の関係を煮詰めて行きます。
「AIRBOW製品」は言うに及ばず、「TUNED BY 逸品館の製品」もすべてこのような「厳しいテスト」を経て製品化されています。
その過程で「振り落とされた製品」は、もちろん日の目を見ることはありません。
私は「私の音楽への思いと、心からの敬愛の念」でオーディオ機器を作っています。しかして、「バッハはバッハ」であり「モーツァルトはモーツァルト」であって欲しいのです。
最近の音楽は「パロディー」と呼ぶ方がふさわしいほど「オリジナルを軽んじ、改変してしまった演奏」や、「ブルーノートのJAZZ」のように「レコーディング・エンジニアが演奏家の意図とは無関係」に、演奏を大きくアレンジ(客席の音をわざと入れるなど)してしまっている「芸術をないがしろにした興業音楽」も多く見受けられます。
また、「意地悪なあら探しに終始する一部の人間」の「批評・文句」を嫌って、「編集」を繰り返し「傷のない作品」に仕上げられた演奏すら見受けられますが、これでは、まさに「仏作って魂入れず」。「生きた演奏=感動」とはほど遠い「きれいなだけの音楽=本質的な感動のない音楽」になってしまうでしょう。
レストランの「陳列にならべられたきれいなだけの商品」や「お湯をかけたら3分で出来上がるような音楽」。そのような音楽のために「私はオーディオ機器を作ってるのではない」のです。
私など「足元にも及ばない努力を重ね」て「思いのすべて音に託した音楽家」達の「貴重な記録の再現」、「厳しさを優先した音作り」それが「AIRBOWに託した音」なのです。
再生される音、音楽と一体となり「心の隅々まで感動で満ちあふれる」ことを目指して作った音、「優しさ、暖かさを優先した音作り」それが「TUNED UP モデル」です。
それぞれの求めるところは違います。しかし、「音楽を生きた感動としてとらえようとする」部分では完全に一致しているのです。
私はいつも、製品を作りながら思うのです。
一体、いつになったら音楽家の努力に追いつき、「彼等に聴かれて恥ずかしくない音のオーディオ機器」を作り上げられるのだろう?と。
それを「見果てぬ夢」と、うすうす感じながら・・・