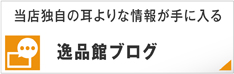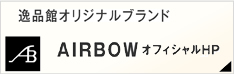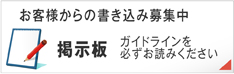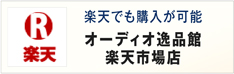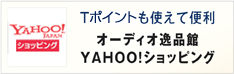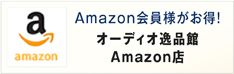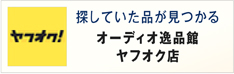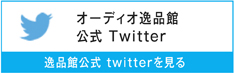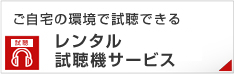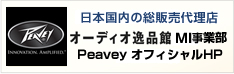97年5月発行・ダイレクトメール記載文章
目次
WINTER-CESの報告
オーディオマニアの定義<第1章>
音と感動の関係<第1章>
<第2章>
<第3章>
再生音楽の定義<第1章>
<第2章>
<第3章>
<第4章>
<第5章>
前回のダイレクト・メールから、ずいぶん間が空いてしまいましたが、一度に多くの考えを吐き出してしまい、思いの外充電に時間がかかったことや、しだいに考えが変化して行くため、まとめるタイミングをずれ込ませてしまったことが原因です。お許しください。さて、今年1月に初めて、アメリカ・ラスベガスのウィンターCESに行きました。まず、そのご報告から始めましょう。
ご存じのようにウィンターCESは、世界最大規模のオーディオ・フェアです。(DVDやマルチメディア・パソコン関係も集約・展示されています)CESにはアメリカ製のみならず、世界各国のオーディオメーカーが出展し、個別にブース(部屋)を設け、展示&デモンストレーション(実際に機器を鳴らしている)を行っています。CESに出向けば、一度に全世界のオーディオ機器を実際に見たり、聴いたり、また開発者と意見を交わしたりできるのです。
確認したかったことは、主に二つです。一つは、産声を上げた新しい「我々」のブランドである、AIRBOWの実力。もう一つは、優れた機器が輸入されずに見落とされていないかということです。なぜなら輸入製品の選定を、すべて輸入業者に任せきりにすれば、経済的な理由(儲けにならない)等の、様々な事由により品目がコントロールされていても気づかない恐れがあるからです。設立時から、販売する商品と、推奨品の選定に徹底的なこだわりを持ち続けている私どもとしては、販売商品に生じた疑問を、自ら確認、解明するのは当然であると判断したのです。
CESの会場は大きく二つに分かれています。一つは「南港インテックス」のような大型の建物に、「仕切り」を立ててブースを区切り展示している会場。これは、毎年、東京の池袋で行われる「オーディオフェア」に似ていますが、その規模はたぶん10倍以上あるのではないでしょうか。この会場の主なテーマは「マルチメディア」。みなさんご存じの「Microsoft」(Windows-Ceを展示)を始め、日本からはおなじみの、<PIONEER/SONY/PANASONIC/etc・・・>が出展していました。
ここで、日本では名も知られていないメーカーが実は海外市場では、とても大規模に商売をしていることに気づきました。なぜなら、彼らにとってみれば「日本市場」は、海外のそれと比べれば、取るに足らない小さなマーケットなのですから「日本での知名度」が上がらなくてもいっこうに構わないわけです。逆に、日本のオーディオフェアを大々的に牛耳っている、オーディオメーカー「SONY・DENON・Marantz・PHILIPS・DIATONE・PIONEER・ESOTERIC・Victor等」のブースには、高級オーディオ製品は全く展示されていません。
日本の著名なオーディオ雑誌で、トップに評価されている機械が、実は輸出されていないのです。なぜでしょう?答えは単純。「海外では人気がなく、売れない」からです。実際に訪れた、海外高級オーディオのブースの出展関係者に聞いてみても、日本のメーカーが高級オーディオを生産していることすら知らない有様でした。
しかし、海外メーカーの誰もが知り、断然評価が高い日本製品がありました。それは、「CECのトランスポーター」なのです。「CEC」はアメリカでは、「WADIAやMARK-LEVINSON」と同列以上に評価されています。CECの日本での価格が45万クラス(TL-1)は、アメリカではワンクラス上の100万クラスに匹敵しますが、それでも同等以上の評価を受けているのです。実際に彼らのブースではCECのトランスポーターが、リファレンス機として、多数デモ用に使われていました。
付け加えると、アメリカで「TEAC」として売られているCDプレーヤー、(最も数が売れる¥10,000程度のクラス)は、そのほぼすべてが「CEC」によってOEM生産されたものであり、アメリカ全土で販売されている、CDプレーヤーの50%以上が「CEC」によって生産されている事実を、あなたは知っておられたでしょうか? これらは、「日本のオーディオ市場での機器の評価」が、「一部の雑誌の管理された情報と、音質(音楽性)の絶対評価が出来ないアンフェアなマニア」により作り上げられた、「正当性を欠くものである」可能性が大きいことを示しているのかもしれません。
この傾向はアメリカにおいても変わらず、顕著でありオーディオ機器の評価が、「価格重視・音質無視」の「メーカー主導型の雑誌による旗揚げ、→それを鵜呑みにする機械マニアが追従」するハード重視・音楽無視の方程式により作り上げられた、正当性を欠く、かなりいびつな状態であることはとても残念でした。
確かに、より高価な装置やより大型のシステムに、心をくすぐられるのは理解できますし、「本当に音のよい装置」は大枚叩いて買う価値があるとは思います。(それを売っているのが、逸品館ですから)それにしても、ある程度の「限度」というものは存在しないといけないと思いますし、また、「フェアな見識」を失ってまで、暴走してはいけないと思います。オーディオメーカーや業者が、オーディオ用という「魔法の呪文」をかければ、何でも価格が高ければ高いほどありがたがられ、希望価格を何倍にもふっかけてよい、等と考えてしまうようでは困りますから。
もう一つのCESのメインであるハイエンド・オーディオの会場は、なんとホテルを一軒借り切って設置されています。どういった形かと言えば、二階建ての高級マンションを想像して下さい、一部屋が約50平方メートル、これが一階に約20部屋、二階にも同じ20部屋があり、小さな中庭を囲むように「コ」の字型にたてられています。これが一つの棟で、中央にある大きな庭を囲むように約20棟たてられているのです。部屋数はざっと400室! 展示メーカーは、約300!! ハイエンドのブースだけでこれだけの数があり、とてもCESのすべてを、たった3日間でくまなく見学するなど不可能なことがおわかりいただけるでしょう。
さらに、オーディオファイル、(日本のステレオサウンドにあたる、アメリカの最有力オーディオ雑誌社)が主催する「HES/ハイ・エンド・ショウ」も、同じラスベガスで同時開催されており、HESにはCESに出展できなかったメーカー、(JEFF-ROWLAND・PAD・他)が約50程出展しています。せっかくラスベガスまで出向いたのですから、目的を果たすためには、それらすべての音を聴き、目を通す必要はあるわけです。足が棒になるほど、歩き回りましたが、結果としてほぼすべてのブースの音を聴き、また興味を持ったブースの主催者とは直接話をすることが出来ました。
その結果、一つ目の疑問点であるAIRBOWの実力は、問題なく、「世界一流(最高)」レベルであると確認できたことをご報告させていただきましょう。これはHESで出会ったスピーカーメーカー、「サイファイ」社の社長が、3月に「逸品館・3号館」を訪れた時に、彼のスピーカー「24K-ジュール」が、AIRBOW/TYPEⅡでドライブされているのを聴き、文字通り「驚嘆」したことからも解ります。
彼は、「私のスピーカーの基本コンセプトは3次元的な立体感を重んじるところにあるが、この3次元的広がりは、私の知る限り真空管アンプでしか得られないと信じていた。しかし、このトランジスターアンプ、(AIRBOW/TYPEⅡ)は、私の認識を覆したばかりか、スピード感、色彩感、広がり感、どれをとっても、アメリカの超一流アンプメーカー(MARK-LEVINSON.JEFF-ROWLAND.MCINTOSH等)の製品を凌駕し、これまでのトランジスターアンプとは一線を画したすばらしいアンプである。また、トランジスターでありながら真空管アンプの音質に迫り、それを超越する事の出来る唯一のトランジスターアンプではないかと思う。」という、最大級の賛辞を残していってくれました。彼は、彼自身の設計による自社製スピーカーでAIRBOW/TYPEⅡを聞いたのですから、このコメントは信頼できます。
次は、残されたもう一つの疑問。隠れた名機の発掘です。答えを先に言うと、「収穫は無し」なのですが、その理由を考えてみました。CES、HESのブースを回り実際に彼らのセッティングで、音を見聞きした所、日本のオーディオ・マニアと、アメリカのオーディオ・マニアでは「音楽の聴き方=装置の使われ方」に大きな相違点があると言うことに気づきました。
アメリカのオーディオ・マニアの大部分は、プロジェクターをはじめとした、各種のビジュアル機器との組み合わせでオーディオ機器を使うか(最近の、MARK-LEVINSON・MCINTOSHのあり方を見ていただければご理解いただけるでしょう)あるいは、広いフロアー(20~40畳のリビング)にお客を招いて、「パーティー」(アメリカ人ほどパーティー好きな国民はいないとも言われていますが)を行うとき、ROCKやPOPSを大音量で鳴らし、文字通り踊り、歌い、騒ぐ、目的のために機器を選定し、購入する場合が多く、日本のオーディオ・マニアのように、一人で静かに集中し、「まるで機械の性能をチェックするように」音楽を聞き込んで行くといった機器の使い方は、彼らの中にあっては非常に特殊なのです。
JBLのおおらかな鳴りっぷりや、アメリカ製アンプの残留ノイズの多さ等も、彼らの使い方では全く支障がないのです。そればかりか、基本的には、図体がでかく(見栄えがして)大きい音(高出力)も出なければ、一般には通用しないのです。これは、最近のインフィニティー/JBL(大きくて安く作るために、東南アジアで生産されており、アメリカで売るよりも日本で販売する方が輸送コストの面などで有利。そのため、日本でも安く販売されている)の設計や、アメリカ製アンプに大出力の製品が多いことなどからご推察いただけると思います。
同時に、相対する嗜好を満たすものとして、「緻密さや定位」を重んじた製品も生産されています。ティールやWILSON等をはじめとする最近のアメリカン・トレンドなスピーカーです。では、「緻密さや定位」を重んじる方向のアメリカ製品が、日本のオーディオ・マニアの嗜好に合うかといえば、決してそうではなく、それらの製品も彼らの好みの音楽である「POPSやROCK」そして「カントリーやJAZZ」を聴くために作られていることが、デモンストレーションに使用されるソフトから伺えました。
各ブースに用意されているソフトは、「電気楽器を多用したPOPS・ROCK」と、「JAZZやカントリー」がほとんどであり、「クラシック」は平均10%~20%以下と非常にウエイトが低いのです。このように、デモ用ソフトから見ても、日本との大きな相違点が感じ取れます。
彼らが日常聞いているソフトをソースにして、製品の音決めをする場合、問題となるのが、彼らが重視している「定位」への要求です。定位感を左右するのは、楽器からの直接音と間接音の関係です。直接音が間接音より多く聞き取れ、より明確になれば定位感は強調されます。しかしこの手法は、彼らが好む音楽(POPSやJAZZ等)では、「間接音=ホールトーン」は絶対必要な要素でなく、楽器の直接音だけでも音楽を成立させることが可能なために成り立ちます。彼らの好みから判断すれば、楽器や人の声をしっかり定位させるためには、直接音の明瞭度を上げ、音の輪郭(くまどり)を強調してもよいわけです。
しかし、「クラシック」においては、彼らが重んじる「定位」は音楽的に重要ではないのです。クラシックのライブコンサートに行かれた経験をお持ちの方なら、おわかりいただけるのではないかと思うのですが、広いホールで楽器を演奏した場合、「明瞭な=目に見えるような定位」は存在しません。確かに、目を開けて楽器奏者を見ながら音を聴けば、楽器が目で見た位置に、明瞭に定位するように感じられます。しかし、これは「視覚情報」と「聴覚情報」が脳の中で合成された結果であり、目を閉じれば「楽器の定位」は、たちどころに消えてしまうでしょう。逆に、有りもしない「定位」を追いかけて、音の輪郭を強調すれば、それが歪みとなり、クラシックにおいて最も重要な要素である、「直接音と間接音(ホールトーン)の関係により形成される、ハーモニー(美しい音の重なり)」は、破壊されてしまいます。
同様に、間接音の量を意図的に、あるいは気づかずに損なえば、(聞こえるか聞こえないかの微細な信号の再生ができない=ボリュームを絞れば音がやせる装置)「広がり感」が欠如してしまうでしょう。
このように、POPSやJAZZ、電気楽器しか聞かず、クラシックをよく知らない人間が「音決め」したなら、直接音重視・間接音(エコー感)軽視の音づくりに偏り、バランスを崩しかねません。結果として、特定の音楽にしか対応できなくなってしまうでしょう。アコースティックな楽器の音、ハーモニーにより形成される音楽(主にクラシック)に用いられる楽器の音=音波は、非常に複雑かつデリケートです。すべての音が、正確にバランスよく再現されなければ、気持ちよく聞こえないばかりか、どこかに特徴的な「癖」をつけて、特定の情報を際だたせる(特定の楽器を聞き取り易くする)よう加工すれば、すべてが破壊されてしまうと言っても過言ではないのです。
ティールやWILSON等のアメリカ製スピーカーで音楽を聴いたとき、「定位」感はあっても、「自然な広がり感」や「音楽的心地よさ」が、欠如しているのはこのためではないかと思います。現在生産されている、アメリカ製のオーディオ機器の多数が、大音量を出せる大型のもの(音がにじんでしまいます)か、あるいは定位を重んじる明瞭な音質への要求を満たすべく設計されており、日本のオーディオ・マニアの要求とは明確なずれが生じていることが推察できます。
我々が、最近のアメリカ製品に納得できない理由は、このあたりにあるのではないでしょうか?
アメリカ製以外のオーディオ製品も、CESに出展し、数多く販売することを考えれば、アメリカのマーケットに合わせた音質への要求を満たす必要があります。たとえば、日本製の「エアータイト」は、高出力の真空管アンプですが、今まで「日本で使うのに、耐久性を犠牲にしてまで、高出力にこだわる必要があるのだろうか?」という疑問を持っていました。しかし、「エアータイト」の主なるマーケットのアメリカでは、アンプは実際に40W以上の出力で使用されます。日本製でありながら「エア-タイト」は、アメリカで最適なパフォーマンスを発揮するように設計されており、純粋には日本向きではないとも言えるでしょう。
では、我々の嗜好を満たせるオーディオ機器は存在しないのでしょうか?
また、現在日本で販売されているオーディオ機器だけを見て、国際的な音質基準を判断してもよいのでしょうか? 答えは、残念ながらほぼ「Yes」です。残念ながらというのは、パソコンがこれだけ進歩する間に、いったい、オーディオ機器がどれだけ進歩したかということを考えると、大きな疑問が残るからです。しかし、それが国際的現実だったのです。
それなら、オーディオ機器は「これ以上進歩出来ないのだろうか?」この疑問には、これから発売する「AIRBOWの新製品」によってお答えしたいと思います。今、申し上げられるのは、「オーディオ機器もパソコンと同じように飛躍的な進歩を遂げることが可能である」と言うことだけです。現在、発売されている、AIRBOWの価格対品質(C/P)は、他メーカーの10倍はある、(AIRBOWは10倍の価格の製品の音質を凌駕する)と思っていますが、いずれ、2000年までには、これを20倍以上に高めることが可能なのではないかと思っています。これは、同じ音質なら、もっと安い機器で実現できるという以外に、「未だかつてない最高音質のコンポを製造できる」ことも示しています。
CESで気づいたことは、もう一つあります。観光旅行ではなく、ビジネスを通じ、生で外国を体験したことは、文化や慣習、様々な違いの中で「音楽に対する感性」が実際にどのように違うのかを、体感させてくれました。たとえば、アメリカ人と日本人の体格を比べれば、いろいろな点で、我々と大きく違っています。人種が異なるので当然のことです。それなら、外観同様、人種により「音」に対する感覚、「聴覚=音の聞き分け」にも差異があってしかるべきなのですが、日本にいては気づきにくいのです。しかし、海外に出れば、これは事実として体感できます。たった3日間の経験でしたが、頭で考えることと体感すること、この差はやはり非常に大きいものでした。
この人種による「聴覚の差異」は、「言語の差異」と密接に関連しているという説がありますが、この「言語の差異」はどのように生まれたのでしょう。暖かな気候の中では、「大きく息を吸って、大きく息を吐く」ことが出来ます。しかし、寒冷地では「小さく息を吸って、発音」しなければ、体温の低下を招くため、小さなエネルギーでより多くの情報を伝える必要が生じます。エネルギー効率を考えると、周波数を上げる(音を高くする・代表的なものは虫の鳴き声や、携帯電話の呼び出し音)ことがよい方法です。子音を強調することにより、小さなエネルギーで明確に言葉が伝わるでしょう。このように、寒冷地では周波数帯域の高い子音を多用する言語が発達し、それに伴っい聴覚も「高い周波数をより聞き分けられる」方向に進化すると考えるのは理にかなっています。
言語により、いつも聞き慣れている、「周波数帯域」が異なるとすれば、言語=地域が異なる人種が、同じ録音を再生する装置を設計する場合、「元に近い=歪みが少ない」と感じる音に差異が生じるのも当然のことでしょう。日本の風土や慣習に適し、日本人の感性に沿うオーディオ機器は、日本人の手により製作することが、ベストであることがおわかりいただけると思います。
「AIRBOW」が、最高水準の音質・性能を実現できるのは、その音質を日本人の繊細な感性に添うよう、日本のユーザーの嗜好を熟知した、音のスペシャリストである販売店の私どもが、十分に吟味し音決めすることを許されているということ、それを生産可能とする日本のオーディオメーカーの優秀な電子技術との融合により、生み出されているからなのです。
最近、私は日本で有数のパソコン通信、「NIFTY-Serve」の「オーディオフォーラム」へ参加を始めました。これはより多数のオーディオ・マニアと意見を交わし、自分自身のオーディオへの認識をフェアなものにするためです。その中で感じたのは、「良い音」や「色づけのない音」への認識に、同じ日本人の中でも、思っていたより以上の、大きな個人差があると言うことです。ある人が「これは良い」と思っていても、ある人は「それは悪い」と感じたり、一つの音、一つの装置に対する好みや、解釈が大きく異なっています。もちろん「音楽の解釈=音楽への指向」自体個人によって大差がありますから、これは当然といえば当然のことなのですが、「ユーザーの求める音」と、「AIRBOWが作り出す音」があまりに大きく異なれば問題です。NIFTYの電子会議室には、私なりに考えた、「音楽とオーディオの関係」に基づく解釈を掲示しました。
その抜粋を掲載します。内容がだぶっていたり、文章のつながりが悪いところもありますが、必要箇所のみ、今後のオーディオ・セッティング、方向決定の参考にしていただければ幸いです。
オーディオという趣味をジグソーパズルにたとえて、オーディオ機器をピース、絵を音楽に当てはめてみましょう。この場合、絵を見るためには、パズルを完成させなければいけません。けれど、絵を見なくても、あるいは完成した絵に興味がなくても、パズルだけを楽しむこともできますし、パズルを買うだけ買って、沢山所有することを目的としてもよいわけです。また、対照的に完成した絵=音楽を楽しむことを愛する人もいらっしゃるでしょうし、音楽家の中には、出来るだけ着色されない絵を完成させることに、心血を注ぐ方もいらっしゃると思います。
しかし、それらをひと括りにして、オーディオマニアと総称するのなら「オーディオマニアはこうでないといけない」、「こういう音を出さないといけない」と決めつける必要はないと思います。確かに、オーディオ装置を、作曲者と演奏者の意図を学び取るための道具として割り切り、また、歴史的な作曲家や演奏家の苦労や勤勉さを知っておれば、ちょっとオーディオをかじったくらいで、さも音楽の良否が判断できるかのように云々している輩に、いい気持ちがしないこともあるでしょう。
では、本当に音楽に対する、知識と教養を兼ね備えた人物でなければ、オーディオセットで音楽を再生してはならないのか? 私は、そうではないと思います。もし、音楽家が本当にそう思うのなら録音を許してはならないはずですし、同様に、作曲家自身以外は、何人たりとも、演奏を行ってはならないことになります。しかし、作曲家も演奏家も、感動に至るヒントを掲示すればこそ、感動を細かく言葉で説明はしないでしょう。「演奏」をどのように感じるか、その自由は聴き手に許されていると思いますし、見方を変えれば「解釈の広がり」とも言えるでしょう。
ある意味では、その曖昧さこそ芸術の本質であり、曖昧さ故に、芸術は深みを増すのではないでしょうか?また、同じ書物から受ける感銘が、年齢とともに深まるように、音楽に対する感性も、聞き込めば聞き込むほど、深まりますから、関心を失わず聴き続ければ、より深く音楽を知り、いずれ、より多くのイメージが受け取れるようになると思います。
もちろん、同じ音楽、同じ再生音を聞いても、感性が異なれば感じ方も変わります。だから、自分と違う意見のぶつかり合いがあったときは、相手を攻撃し、対立するよりも、理解し合うために会話を交わすことが大切ですし、それによって、相互理解を深めることこそ、趣味としての楽しみではないでしょうか?たかが趣味、されど趣味。本質を追究し、本質に至ることが真の目的ではなく、本質に至る過程を楽しむことこそが、趣味の醍醐味、喜びでは ないでしょうか?
高みを目指すには、いろいろな道があり、様々な歩き方があるでしょう。歩いていれば、それで良いと私は思います。
どうせなら、眉間にしわを寄せるより、マイペースでニコニコと歩きましょうよ。
オーディオは、決して急いだり、焦ったりせず、長くゆっくり楽しみたいと、思っています。
音と感動の関係<第1章>
(オーディオ装置による音楽の解釈の違いについて)
私たちが、趣味と呼びこだわりを持つオーディオ。一体オーディオの何が楽しいのだろう?自分なりに考えてみた。
多くのオーディオファンは、例外なく、それで音楽を聴くと思う。では、音楽はなぜ生まれたのだろう? なぜ発明されたのだろう?
人と動物の違うところは、人が言語を持つことだ。たとえば、言葉で「悲しい」と言えば、悲しいと言う情報が伝わる。けれど、悲しみの程度や、種類を説明するのは、難しい。つまり、言語は、デジタル伝送に例えてもよいのではないのだろうか?
では、人の情報伝達法は、言語だけなのだろうか?
たとえば、身振り手振りの仕草や、じっと見つめるだけでも気持ちは伝わる。このように、曖昧な感情や感動を、デジタルではなくアナログ的に、曖昧なまま伝える方法。 その方法の一つとして、我々が発明したのが、音楽なのではないだろうか? また、そういうものを総称して、我々は、芸術と呼ぶのではないだろうか?
では、芸術の中で、音楽のみが持つ特質を考えれば、「時間の流れの中で、双方向性を持つコミュニケーションであること」ではないかと思う。なぜなら、音楽という伝達方を用いれば、多くの人と、感動や感情を瞬時に「共有」することが出来る。文章にして伝えようとすれば、莫大な文字数を必要とする情報を、たった、一音の楽器の音色に凝縮し、奏でる楽器の、メロディーやリズムの変化で瞬時に感動を伝え、なおかつ「同じ時間の中で共有」する事が出来る。それこそが、音楽の本質なのではないだろうか?では、音楽をつかさどる空気の振動=音波とはどのようなものなのだろう?
私たちは、音波によってダイレクトに心を動かされる。例えば、ガラスをひっかくときのイヤな音も、真夏に涼を呼ぶ風鈴の音も、どちらもかなり高い音だけれど、一方は、気にさわり、もう一方は心地よい。このように、音の変化が、一定の感情の変化を導くなら、ある演奏を録音して、再生するときに、ある一定の幅以上に再生音が変化すれば、当然、元の演奏のニュアンスとは違ってしまうだろう。
もし、オーディオが音楽を聴くための手段に過ぎないなら、装置の音質には、大きな変化があってはならない。良い装置と、そうでない装置の差は、感じ取れる感動の深さの差違であり、装置によって、音楽の内容(感動の種類)が大きく変化してはならないはずだ。高音や、低音の量的バランス、広がり感や、奥行き感。ポリフォニック(各パート)の音量バランスや、楽器のはいるタイミング。それらは、すべて、ある一定の幅に収まっていなければ、演奏は変わってしまう。
原音(録音時)にはなかった、音の変化を歪みというなら、歪みは、可能な限り小さくなくてはいけない(メーターでは計れない)。けれど、再生装置によって作り出された音(歪み)がその人にとって心地よいものであれば、それが装置の音楽性? はたして、本当にそう言えるのだろうか?否定はしないが、美しい歪み(美音)も歪みは歪みであり、元の音楽の持つ、本質を損なってしまう。オーディオマニアが陥るパラドクスがここにあるように思う。
自分の装置の音、美音におぼれ、本質を見失っては、音楽(芸術)の持つ真の深みには到達できないのではないだろうか?
再生された、音楽を楽しむのか? 録音された音楽の本質を求めるのか?
もちろん、個人の自由だと思うし、優劣を付ける必要などないと思う。ただ、どこまでが、元々あった音(音楽表現)であり、どこからが、自分が作った音であるのかを、私は知っておきたい。そして、自分が作り出した音を、人に元々あった音楽だとは言わないでいたい。
もし、同じソフトが、装置によって全く違って聞こえるとしたら、どちらかの装置の音が歪んで(美音も含めて)いるのか、双方共に歪んでいるのか、そのどちらかだろう。再生装置による音楽の解釈に大きな違いが現れたなら、それは、その装置が作り出した偽の音楽性(歪み)にとらわれているに違いない。
歴史に残る、名演奏、偉大な音楽家の努力と苦難を思えば、自分の小手先の、細工で作り出した音楽など、実に矮小で、自分勝手な思い上がりであると、最近、私は思っている。
音と感動の関係<第2章>
(どのように原音に再生音を近づけるかの問いに対する答え)
私の場合は、元の音楽を出来るだけ深く学ぶように心がけています。
もちろん、限界はあるでしょうが、直接本人に会いその演奏の意図を確認したり、録音された演奏を再生し、できれば本人に聴いてもらい、その人が行った演奏と、どのような相違点がみられるかを確認するディスカッションの中で、自分自身の音に対する感性(あるいは個性)や自分の欲するもの(再生音)と、与えられたもの(原音)の差違などを見いだして行きます。
その段階では、もちろん再生装置だけでなく、録音装置に至るまでの細かい知識と経験が必要となってくるので、録音に対する勉強も必要でしょう。私の再生音楽に対する考え方は、音楽はイメージの伝達である、と言う仮定に基づいていますから、元々に似た音を出すため(元々イメージされたものを、再生音を通じて再構築する)には、元々行われたことを出来るだけ深く、正確に知る以外に方法はないと思っています。
それで、出てきた音を自分自身だけではなく、広く客観的に出来るだけ多くの人に、あのときの演奏に似ている、と感じてもらえたなら、それがある意味ではベストなのではないでしょうか?
もちろん、テストに使用するソフトは、ジャンルや演奏に関わらず、その演奏が録音された場所に、私自身が居合わせたものを使用できれば、最良であることはいうまでもありません。しかし、そういう機会に多く恵まれないことも、残念ながら事実です。
音楽と、音を深く聞き分ける経験を積み、同時に自分の聴覚の個性を知る。元あった音と、再生時の音の間にどのような差違があるかをより注意深く、聞き分けることが出来るようにトレーニングする。自分の出している音が、どのような音であり、どのような歪み(原音との差違)があるかを、確認できるようになることが、唯一良い音を出すための方法であると、自分では、考えています。
この方法は、とても多くの時間と労力を費やします。芸術が、一朝一夕では完成しないように。
(再生装置=オーディオ機器による音作りを歪み歪みと言われますが、
それぞれの装置の持ち主は、自分の聴感に基づきソフトから
よりよい音楽を取り出そうと努力しているのではないでしょうか?)
それは、その通りだと思います。ただ、自分の装置の歪み=原音との差違を正確に知らなければ、(カラオケでエコーをかければうまく聞こえますが、それは、音を歪ませて、音楽を作り出しているとはいえないでしょうか?それなら再生装置によって、演奏が実際より心地よく聞こえることもあり得るわけです)
演奏のニュアンスが、実際の演奏と大きく異なっていても気が付かないばかりか、実際の演奏より、心地よく聞こえれば、それが素晴らしいという評価に結びつく場合もあると思います。
それは、実際の演奏を理解しようとしているという目的とは、少し違った方向へ向かっているのではないでしょうか?
もちろん、そのような、オーディオのあり方を否定するつもりは毛頭ありません。しかし、自分の装置のことをより深く知れば、より深く客観的にその音楽を知ることもできるのではないかと思うのです。
芸術は、曖昧だから、深みがあると思うのです。でも、曖昧さの中の「真実」のようなものを求め、探しているのかもしれません。そんなものは、幻かもしれないと、感じながら・・・
演奏者と、聴衆。それぞれが、渾然一体となって、高め合いながら、何かを作り上げてゆく。うまく表現できないのですが、音を通じた、その両者のコミュニケーションこそ、音楽なのではないかと思います。私も、専門家であると同時に、単なる一人のオーディオ・音楽愛好家です。音楽を深く知れば知るほど、オーディオも深く知れば知るほど、自分自身の、知識のいたらなさを知ることになり、偉そうなことを言っても、心ではいつも不安でいっぱい、不安を解消するために、より多くの人と率直な意見を交わし、認識を深めたいのです。
また、私自身のこの不安感は、演奏家と全く同じような感覚ではないかと思うことすらあります。なぜなら、自分にとって、オーディオ機器は楽器であり、誤解を恐れず言えば、自分が出す音は、自分自身の演奏に他ならないからです。人の力(録音)と機械の力(オーディオ機器)を借りてはいても、自分の装置から出す音(音楽)は、自分自身の解釈した再演奏であり、それは、ある意味では演奏家の手を離れた、再生装置の持ち主の音楽です。
私の私感では、音楽再生装置を販売するという行為は、ある意味で、音楽の語り部としての責任をも、負うべきではないかと感じています。ですから、良い語り部になろうとすれば、物語に精通し、物語=音楽を自分なりの解釈で、自分の言葉で伝えなければ、本質はうまく伝わらないのではないでしょうか?
それには、思慮深さと、謙虚さが最も求められてしかるべきだと思います。自分の装置から再生される、違う人の音楽。 その本人と、それを愛好する聴衆にその装置の音を確認し、評価されたいのは、音楽家が自分の演奏の感想を、聴衆に求めたいのと同じ気持ちだと思います。しかし、見方を変えれば、自分の装置の音を自分自身の楽しみのために聴くのであれば、再生音楽(演奏)を本物と比べて確認する必要はないと、言えるのかもしれないと思います。
私達は、音楽を聴きたいと思ったとき、コンサートに足を運ぶか、オーディオ・セットのスイッチを入れて、再生音楽を聴くか、そのどちらかの方法しか選べない。仮に、再生音楽が、録音された情報(演奏)を正確無比に再現(解凍・再演)する事だと定義しよう。実際の演奏では、プレイヤーは楽器(ヴォーカルも含めて)の音を変化させることによって、音楽の調子(伝える情報の内容)を変えたり、作り出したりしている。では、もし、再生装置(オーディオ機器)によって音が変わって聞こえるとすれば、再生装置によって新たな感動が付加されることになる。では、どこまでが、元の演奏の感動で、どこからが、装置によって作りだされた感動なのかが、オーディオ機器によって「元の音楽」を聴こうとするときに一番の問題点になる。この仮定に基づけば、録音時になかった音(装置の歪み)や録音時と異なる表現は、すべて歪み(有害なもの)とし、排除・拒否すべきものとして定義しなければいけないからだ。
オーディオ専門メーカー・オーディオ専門店であれば、そして、「音楽」を聴くためにオーディオをやっているというマニアなら、この定義の持つ意味を知っていてほしいと思う。なぜなら、現在販売されている機器の多くは、その機器特有の歪みを持つために、元の音楽(演奏)にその機器の音楽(歪み)を付加するものがほとんどであるからだ。
結果として、元の演奏とは、とても呼べないほど変化した再演奏やあるいは、聞き手(リスナー)の好みに作り替えられた演奏が、より珍重されていると言ってもいいほど、同じディスクが違う音楽に作り替えられて再演されている場合すらある。特定のディスクの、特定のトラックを中心に、オーディオ機器の音を、比較試聴されるなら是非、注意してほしい。あなたが、よい音だと感じ、思っている「演奏」がはたして、本当に「元の演奏」に近いのかどうかを。
装置次第で、下手な演奏もうまくなれば、うまい演奏も下手になる。ただ、音を大きく歪ませる装置からは決して本当の意味での「音楽」は見えてこない。と私は思うし、また、お叱りを受けるのを覚悟で「絶対」であると、断言してもいいと思っている。
(どうすれば、生演奏に近づくのか?
また、再生音楽が生演奏とは、
決して同一になれず、個人によって歪みと感じる部分が違うのではないか?
生演奏=再演奏になり得ないジレンマについてどのように感じるか?)
録音と、再生時に生じる差異。そのジレンマについては、私もとても悩んでいます。たとえば、人のシステムで同じソフトを聞いたとき、やはりそれは自分と同一の音ではありませんし、その人が注意して聞いている部分も自分と違うことが理解できます。つまり、そっくり同じ再生音は絶対に存在しません。コンサートにおいても、客席の人の配置(ポジション)も違えば、それぞれの感性も違うわけですから同じ曲を聴いても、それぞれに感動も違います。
たとえば、私がよく知る指揮者である、チェリビダッケは、非常に深く静かに、速度も遅く指揮する場合がありますが、これは彼が考える、音楽における真実、「音=音楽によって聴衆を深く静かな集中へ誘う」ために必要な方法であるからだと思います。
ですから、チェリビダッケのソフトを再生するとき、一番注意することは、禁欲的=ストイック(不必要に歌わず、静かな集中を生むこと)であることです。
これは、ある意味ではカラヤンとは対照的であるとも思えます。
最近気づいたのですが、システム(再生音)の歪み(装置によって作られた元々ない音)が、かなり減少したとき、同じソフトが、ステレオっぽい音から、生っぽい音へと変化し、その時点ではもはやステレオで音楽を聴いている、という意識ではなくなるのです。さらに興味深いのは、この生っぽく音楽を感じ始める歪みの減少レベル(歪みの総量)には、個人差はあまりなく、一定のラインが引けるのではないかと感じることです。つまり、すべての歪みを消し去ることは不可能ですが、再生音楽中の歪みがあるレベル以下になったときに俄然、純粋に音楽が見えてくるらしいのです。
これは、実際に体験しなければわかりません(現在3号館でデモできます)が、体験すれば、誰にでも理解できるほど劇的な変化です。(ただし、生の音楽を注意深く聴いている人に限ります・比較すべき楽器の音のデータが記憶として必要であるため)このように、私が考え、あるいは感じている再生音楽中の「本当の音楽」とは、ある一定のレベル以下にシステムの歪みが減少した時に感じる、「音楽」を示しているのかもしれません。
非常に抽象的なコメントになってしまいましたが、再生音楽から「本当の音楽」のしっぽをつかんでいる人は、多いはずです。是非、本体までがっちりつかんでほしいと思います。私は、自分がいったいどこまでつかんでいるのか、それもよくわかりませんが、自分が今まで聞き経験した全体的なレベルで判断すれば、最先端に近い場所にはいるのではないかと思っています。しかし、その先にもずっと歪みという山が続いていることがわかります。けれど、その歪みと言う、障害物を一つづつ、つぶしていって、あるいは越えて行けば、もっとクリアーに「元の演奏」が見えるのではないかと感じています。
いくら装置の歪みを消し去っても、同じ音は二つと存在し得ないし、また演奏の感じ方も決して同一にならない。というジレンマに対する答えですが、それは同じ作曲者の同一の曲が指揮者によって異なって演奏されるように、生演奏にも同様に存在すると思います。言い換えれば、この「ジレンマ」こそ、芸術の深まり、広がりだと言えるのではないでしょうか?
ですから、あるソフトの再生音から、その演奏者の音楽感を把握しようとするときは、ステレオから取り出せる音楽表現を越えて、正確に知ろうとすれば、生演奏を聴きに行くのが最もよい、唯一の方法でしょう。なぜなら、生演奏では、楽器の音だけではなく、演奏者自身が発する「気」まで感じ取れるので、演奏の「テーマ」がより明確に感じられるからです。しかし、それが不可能な場合は、演奏者をよく知っている人に尋ねるなどして、演奏者に対する理解を深める他はないと考えています。
長くなりましたが、最後に、言葉はデジタル=定量的かつ正確。音楽はアナログ=正確な形を持たないイメージ。感動のイメージを言葉で正確に表現することは出来そうもありませんし、また、感動は分かち合い、共有こそすれ、定義する必要はないと思います。
ただし、非常に細かく音楽に配慮をしている人のシステムからは、学ぶべきことがたくさんあります。その人のフィルターを通して、「音楽」を「解釈」出来るのです。そのフィルターに「フェアな見識」があれば、それでOKです。では、いったいどこからがOKで、どこからならだめなのか、その線を引くことは出来ないし、必要もないと思います。
再生音楽から、共有すべき感動が現れればそれでOKと思っています。それを、個人的に作り替えて、自分の世界の感動に作り替えることは、私の再生音楽の聴き方とは、少し趣を異にするところがあるかもしれません。
しかし、今までは、結構自分も作り替えて悦に入っていたと思いますが、うるさくなったのは、それだけ、年食った、ってことでしょうかね・・・
再生音楽の定義<第3章>
(正確な再生音を求めるようになったきっかけ)
最初は、文字通り音をほじくり出すことしか考えていなかったんですね。音がたくさん出始めると、その中で、いったいどの音が正しいのか疑問が出始めるわけです。本当にこれでいいのだろうかと。
そうしているうちに、音楽家と知り合い、音楽について深く考えるようになりました。 そうして、最近では、演奏者が集中して楽器の音を出すのと同じように、自分のオーディオ機器の音を注意深く聞きながら、音を整えることを覚えました。楽器を調律し、音楽になるよう、注意深く音を出したり、削ったりしながら・・・
それは、音楽家が演奏するのと全く同じなのです。音源はたとえ人の演奏だとしても、誤解を恐れず言えば、再生される音は、その人の、自分自身の演奏に他なりません。元を知り、それに近づける。その一連の行為と、学習の中で、自然と深く音楽を知ることになる。これが、私が目指し、考える、もっとも趣味性の高いオーディオ道、とでも言えばいいのでしょうか。オーディオに触れながら、音楽を知ることが出来、本当に、幸せだと感じています。
そして、そういう演奏と録音を残してくれたすべての人たちに感謝しています。だって、人類共通の重要財産でしょう?
ソフトがなければ、どんなに高価な機器もただの箱。でも、箱がなければ、ソフトも再生できませんね。
だから、職業としてオーディオに携わるとき、その責任は非常に重いと思いながら、仕事をしています。でも、本人は、とても楽しくやっています。
再生音楽の定義<第4章>
(人が音楽を感じるキーとなる部分は?)
たとえば、「スィング」する。といってもいろいろな方法があるはずです。聴衆を、「スィング」させ、「注目→集中→感動」という流れに引っ張るためには、楽器の音の美しさで「ハッ」とさせるのか、ドラムやベースの「ドキッ」とさせるタイミング=リズムで、引っ張るのか。いろいろな方法があるはずです。
仮に、ステレオ装置の再生音に、明確な輪郭をつければ、リズム感は強調されます。また、真空管アンプのようにエコー感を付加すれば、音が美しく聞こえます。低音を持ち上げれば、低音楽器の量が増えます。このように、再生装置が何かを強調すれば、その強調された部分が持つ「音楽的感動」のみに、縛られてしまい、音楽的な広がり、感動の広がりは、結果的に阻害されてしまいます。つまり、バランスのとれた、うまいはずの演奏が、ラフな演奏、つまりちょっと下手になるわけです。
私流に「音楽」を正確に再現しようとすれば、すべての歪みを減らすことが重要になります。抽象的な表現になりますが、生の音楽をつかさどる、あるいは奏法として用いられる楽器の音の変化、それと同様の変化が、再生時に起これば、それはすなわち歪みです。
「カザルス」という、チェリストをご存じでしょうか? 彼の出すチェロの音は、すばらしく美しく、彼は、鳥がさえずるように、自然体でチェロを奏でたそうです。(残念ながら、私は実際に聞いたことはありません)彼をよく知る、音楽家の話では、彼が一番苦労したのは、ボゥ(弓)が弦とこすれる音を、どうすれば音楽に出来るかという点だそうです。つまりカザルスのチェロの録音に、弦がこすれる音が入っていて、それが気になるようなら、その音を削って聞こえなくするのではなく、それすら、音楽的に心地よく聞こえるようでなければいけない、ということでしょう。だから、バイオリンをはじめとする弦楽器の音がきついからと言って、音をなまらせる方向に走ること(真空管アンプ)を私は好きになれません。
高域の歪みが減れば、こすれ音やきつい音がたくさん出ても気にならなくなります。下手なバイオリンはうるさく、うまい人のそれは心地よく聞こえるでしょう?再生音も一緒です。再生音に、不要な輪郭、リンギング、テレビのゴーストのような歪みが付加されれば高域はきつく、うるさくなったり、逆になまったりします。
(よく雑誌で、装置の組合わせ=歪みの重ね合わせで、独特の音を作り上げることが、オーディオの醍醐味であるといわれていますが、それはどのように解釈されますか、本当に歪みを取れば音はよくなるのですか?かえって日本製のコンポのようにつまらない音にならないのですか?)
同じプロとして言わせてもらえば、彼らの言うことは「疑問の固まり」です。歪みと、音楽の区別すら付かないのではないでしょうか?
雑誌に書いてあることは、ほとんどが、ゴシップか、提灯記事であるとまず、「???」・疑問詞を3つ以上つけながら読んだほうがいいと思います。雑誌の記事を鵜呑みにして、まねなどしないでください。歪みを取ることを考えない人に、歪みを取ることなど出来ません。
それでもステレオから、すべての歪みを取ることなど誰にも出来ないと思います。わたしも、出来るだけ自分のシステムからは、元になかった「嘘の音」=歪みを出さないよう努力しています。なぜなら、そうしないと、全生命を集中させ、チェロを弾いてくれた、カザルスの集中力を感じ取れる境地には、とうてい近づけないと思うからです。
まだまだ、そんなに、立派なものではございませんが、お互いに、がんばりましょう。
再生音楽の定義<第5章>
(オーディオの音を決める私なりの見識)
今までにいろいろなメーカーが一貫して、製作したオーディオ(入り口から、出口まで)で音のよいものはない。という話ですが、オーディオ機器を製作する場合、作り手の感性により、製作する以外に方法はありませんが、できあがった機械は、制作者と同じ感覚で、音楽を聴きわけようとする人、音楽を聞き分ける感性を同じくする人たちを、対象とせざるを得ません。
仮に、曲を録音、オーディオ機器をオーケストラにたとえるなら、同じ曲を演奏するにしても、チェリビダッケ指揮が好きな人もいるでしょうし、カラヤン指揮が好きな人もいるでしょう。しかし、カラヤンのファンのために、チェリビダッケは、カラヤンのまねをして演奏をしません。そこには、潔い彼の「音楽への考え方」が反映されているはずです。
装置も同様に、万人に、その音質がよいと認めてもらう必要はありませんし、またそのような製品は作りようもないと思います。だから、その機械を評価する人もいるでしょうし、そうでない人もいるでしょう。今まで聴いた、多くの装置の中で、自分が作った装置で聴く音楽を、わたしは、「十分美しい」と感じますし「十分感動的」であるとも感じます。
しかし、極論を言えば、それは、他の人から見れば「どうでもいいこと」でしょうし、「とても悪い音」かもしれません。そういえば、ずいぶん自分勝手に聞こえるかもしれませんが、誰でも、自分には、自分の音が一番であろうと思っているはずでしょうし、自分のための音は、自分で出したい、と考えるのが正直なところでしょう。
けれど、認め合い、学び合わずに、他を否定しあっても、なにも生まれないと考えています。私が真空管アンプを批判したのは、真空管アンプでは音楽を聞き分けられない、というのではなく、私が音楽を聞き分けたいときに、私が聴いたことのある真空管アンプからは、生の楽器のような、素早い音の立ち上がりが得られなかったということです。それでは、トランジスター(AIRBOW)は最高かと言われれば、現時点では最良だと言う表現以外にはありません。本当にすばらしいのは、「生演奏」であることに異論はありません。
再演奏は、その人の感性のフィルターを通した「色づけ」のある再現でしかありません。しかし、その「色づけ」が見識のあるものであれば、出てくる音が全く違っても感銘は受けますし、感動もします。現に、私のシステムと、「かなり違う音」が出るシステムがあって、そのどちらもが「音楽を理解できる音」であってもいっこうに構いません。
そればかりか、「自分と違う音が出る」そのシステムから、より「深い音楽への解釈」が聞き取れた時、私は「自分の音楽への理解度の限界」と、「他の感性から見た自分の感性」を知ることが出来るわけです。そして「さらに深いもの」を求めて行きます。
なぜなら、自分自身の聴覚や感性を「唯一・最高」だと、勘違いした時点で成長も止まってしまうのですから。
再生音楽の定義<第5章>
(真空管アンプでは音楽は分からないのか?)
私が,AIRBOWを作り上げてから、気づいたことですが、美音を楽しむという意味では真空管アンプを肯定できます。
また、歪み(データーではありません)の大きいトランジスターアンプより、よくできた真空管アンプの方が、心地よく音楽を楽しめることも事実です。でも、最高に作り込まれた(自分が作った範囲内でのレベル)真空管アンプと、トランジスターアンプを比べた場合、真空管アンプでは音が出る一瞬の立ち上がり、100分の1秒以下のレベルでは、アウトプットトランスの高周波特性が十分でないためか、やはり音に曖昧さ(歪み)が残り、その部分を修正する努力はしましたが、うまくいきませんでした。ただし、このマスキング効果によって音のエッジがなめらかになり、より聞き易く、心地よい音になることも事実です。
では、そのアンプ(真空管アンプ)では音楽が分からないのか? といわれると、そうではなく、真空管アンプでも十分音楽は楽しめます。しかし、その立ち上がりの歪み(遅れを是正すれば)を取れば、音楽がさらによく分かるようになったのです。
つまり、現時点で真空管アンプは、私が音楽を理解しようとした場合において、トランジスタアンプより、適切でない部分が多いと感じています。ただし、アンプのスピードが早ければ早いほど、よいのかと問われれば、それは違います。もし、AIRBOWのように立ち上がりが早く、歪みが少ないアンプやCDの性能を十分に発揮しようとすれば、立ち上がりが早く歪みの少ないスピーカーが必要です。
たとえば、タンノイを鳴らすことを考えると、ロードをかけたウーファーは反応があまり早くありませんから、ハイスピード一点張りで、色彩感に乏しいトランジスターアンプで鳴らすと、高域と低域が分離したように聞こえうまく鳴りません。そのため、タンノイに固有の速度感と、アンプの持つ速度感をマッチさせ、さらに、ホーンの色彩感の多彩さを生かすために、よく出来た真空管アンプで鳴らすのは良い方法だと思います。そして、それでも十分に「音楽を楽しむ」ことは出来るのです。
ずいぶん長くなりました、ここまでお読みいただいたことを感謝いたします。
電子会議室での、会話の中で、自分自身の発言だけを取り上げているため、かなり読みづらい部分や、文章的におかしな部分が多いと思いますが、お許し下さい。また、会話の流れの中で、「テンション」が上がってしまい、「上からものを言う・高圧的」な文章になっていたり、論点がずれたりしがちですが、その点についても、なにとぞご容赦下さい。
ご理解いただきたいのは、「価格」や、「データ」・「理論」だけで、「オーディオ装置の音楽性」は判断できない、ということと、現在の「オーディオ製品」は、カタログに載っているような「理論・データ」通りには作動していないと言うことなのです。
また、現在の「測定器」も測定できない部分が多く、「人間の感性」と「測定器のデータ」は、「一致しない」ことの方が多いと言うことを、ご理解いただきたいのです。むろん、「理論・データ」のすべてに意味がないわけではなく、一方的に偏らず、双方がバランスよく、一致することが望ましいと思うのです。
「人間の感性」については、まだまだ分からないことが多く、現在のオーディオ装置では、まだまだ、人間の感性に追いついているとは言い難いでしょう。ですから、われわれ個人の介入できる部分が、「オーディオ」には数多く残されており、「趣味」としておもしろいのだと思います。
今度も、一点集中ではなく、バランスよく、「システム」全体を広い視野で見られて、長期計画でオーディオのレベルアップと同時に、お客様自体の感性のレベルアップにつながりますよう、良い趣味として、ごゆっくりとお楽しみ下さい。
今後も、皆様のお役に立てますよう、出来る限りの尽力を惜しまぬつもりですが、万が一、配慮が行き届かず、お気づきになられた点がございましたら、何なりとお気軽にお申し付け下さい。