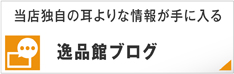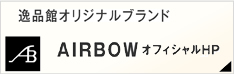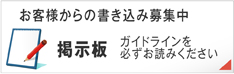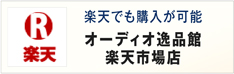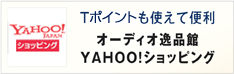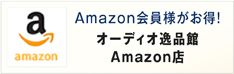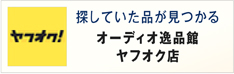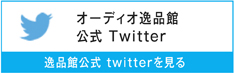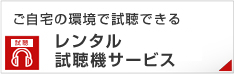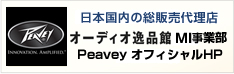98年6月発行・ダイレクトメール記載文章
-
目次
音楽とオーディオの関わり
音楽から得られる感動とは
自分色のフィルター
私が考えるプロの耳
音と感動について考える
自分自身の音作りの限界
音を判別することと、音楽を聴くことの違い
オーディオ選びのポイント
歪みなのか味わいなのか?
ヘッドホンとスピーカーの違い
ホールトーンの役割
測定データーの有効性
デジタルは音楽を進化させたか?
現在主流の測定法の問題点
周波数帯域における相対感覚とパターン認識
リスニング・ルームの条件
ルーム・アコースティックの考え方と整え方
人間のセンサーの働き -
今年もすでに折り返しを迎え、21世紀まで残すところ1000日を切りました。今世紀、私達は様々な科学技術の発明と実用化によって多くの利便を手にしましたが、中でも、通信技術と記録技術の発展やコンピューターの発明は、「情報の記録と伝達」に飛躍的な進歩をもたらしました。
-
もはや私達は距離や時間に縛られることなく、世界中に張り巡らされた電子ネットワークを通じ、瞬時に出来事を知りリアルタイムに思考を交わせるのです。それは、個人や地域で考える時代から、地球規模で物事を考える時代への進化を意味しているのでしょう。かし、どれほど科学が進歩しても、人間そのものに進歩がなければ「歴史は繰り返す」の言葉通り、同じ迷路を回り続けることになるのかも知れません。
-
オーディオもまた科学技術の進歩と共に大きく進化しました。というよりも、オーディオという言葉そのものが、今世紀になって生まれたのです。この音楽を聴くための手段として発明された「オーディオ」は、はたして「音楽」を進化させたでしょうか?
-
最近、私は仕事の合間に「ニフティーサーブ」や「インターネット」の会議室に自分の意見を発信していますが、それは自分の考えをまとめようとする時、時間や場所の制約を超えてより多くの仲間達と話し合える「電子ネット」が大変役立つからです。この「電子ネット」に発信した文章をダイレクトメールのために編集し、一つの結論に到達させることはさして難しいことではありませんが、あえてネット上に発信したほぼそのままの文章をお伝えしようと思います。
-
そのため、これからの文中には断定的、高圧的な表現が含まれたり、「音やオーディオ機器の良否判断」を行ったり、「オーディオと音楽との関わり」や「音楽と自分自身との関わり」について結論めいたこと示唆している場合もあります。しかし、それは必ずしも「絶対的」なのものではなく、「オーディオの考え方の一つ」としてとらえていただきたいのです。 また、文章の内容が今までのダイレクトメールの中でお伝えさせていただいたことと重複する場合もありますが、今一度おつきあいください。多忙を理由に、文中行き届かない表現も多いとは思いますが、なにとぞお許し頂いた上でご参考にして頂ければ幸いです。
-
オーディオの起源を知るためにはまず、音楽の起源を知る必要があると思います。では、音楽の起源とはどのようなものなのでしょう?
-
私は、音楽の起源とは「感動の伝達と共有」にあると思います。自分の中に生まれた「感情」が、体の外側に向かって「音」に形を変えながらあふれ出し、誰かの心に共鳴すれば、それを「音楽」と私達は感じるのでしょう。
-
もう少し解釈を広げれば、私達を生み出した「大地=地球」の鼓動である「自然の音」が私達の心を和ませたなら、それも「音楽」と呼んでもよいのかも知れません。もちろん自然の音に感情は含まれていないかも知れませんが、私達の心を「共鳴させる音」を「音楽」と呼ぶならば、「自然の音」は立派な音楽と呼べるでしょう。
-
しかし、人間が作り出した感情である「喜怒哀楽」を表現する波動と、自然の鼓動である「自然な音の波動」とは少なからず違うように思います。
-
なぜなら、「喜怒哀楽」の感動は非常に主観的な感情であるが故に、受け取る側の個人体験によって聞こえ方にかなりの差異が生じるでしょうし、場合によっては、まったく同じ音を同じ人が聴いても、日によって聞こえ方が変わってしまうかも知れません。
-
もし、そのような音楽を基準として、楽器の音やステレオの再生音の良否判断を計れば、そこには個人的な好みによる主観的な要素が混ざり込むため、絶対性・普遍性を持てないはずです。つまり「喜怒哀楽」を音楽から感じている場合、そういう音楽は「音を判断するための絶対的・普遍的」な基準とはなり得ないと言えるのです。
-
では、「自然の音」ではどうでしょうか? 例えば、「車の走る音」を基準にすることを考えましょう。あなたの家族が、「あなたの車の音」を覚えておられて、その音であなたの帰宅を知るとします。「その車の音」を録音して「音の判断基準」に用いれば、そこには「個人的感情による音の聞こえの差異は紛れ込まない」はずです。つまり「喜怒哀楽」と無関係な音は、ある程度の絶対的基準となり得ると考えられるのです。
-
以前「機関車の音」を録音し、それを出来るだけ「現場と同じ」に再現しようという試みが、一部のオーディオ・マニアの間で「生録ブーム」として巻き起こったことがあります。当時は、「感情のない音を再現すること」にまったく意味などないと考えていましたが、今になって考えれば、確かにそれだけでは意味がなくとも、そのようにして構築された「機関車の音の再現性に優れた装置」で「音楽ソース」を聴けば、その装置が「最も原音に近い音楽再生装置」となり得たはずです。
-
このように、「オーディオ機器」が作り出す「音楽」には、「主観的な側面」と「普遍的な側面」のどちらもが共生しているのです。
-
あなたが「オーディオ機器によって音楽を楽しむ」という行為を、「非常に主観的なもの=個人的な楽しみ」と理解されているなら、「機器の良否判断」は100%あなたの好みに委ねられます。しかし、あなたが「オーディオ機器によって音楽を楽しむ」ということを、「記録された音楽の再現」とお考えなら、「機器の良否判断に音楽を用いる危険性」をあえて指摘しておかねばならないでしょう。なぜなら「再生音が原音忠実=普遍性・客観性を持つ」ためのテストソースには、「個人的好み=主観性の高い音楽というソース」は不向きだからです。
-
私の知る一部の音楽には、あたかも「楽器を自然に鳴らすこと」で「心のバランスを整える=精神の自然への回帰」を成し遂げたと感じられる音楽があります。(ターラやシタール、ガムランなどの民族音楽・カザルスのチェロ・リパッティーのピアノ・その他)
-
このような音楽を「自然のまま」に再現しようと試みるなら、「音楽ではないソース」によるオーディオ機器の音質判断を是非行ってみてください。あなたのオーディオ機器の「原音忠実再現性」が高まれば高まるほど、それらの音楽は深みと輝きを増すでしょう。
-
逆に「喜怒哀楽」の振幅の大きさのみを「再生音」に求めるなら、「原音忠実再現性」が高まっても、「感動の振幅が増大する=あなたの好みに合う」とは限らないのです。
-
この相反する「オーディオと音楽の関わり」の側面を理解しようとせず、「オーディオ機器の判断」を行えば、それはもはや「自分以外の人間には何の意味もない個人的な自己満足」の範囲を出ることはありません。もちろん、「そういった自己満足」がなければ「オーディオに楽しみ」が生まれないことも事実ですが、大切なのは「オーディオと音楽との関わり」を通じて「自分の求める音楽」を見いだすことなのではないかと私は思います。
-
そして、その「自分の求める音楽(感動)」を見つけだすことが、「自分自身の発見」につながるのではないでしょうか。安易な音楽を聴くことで「心が堕落する」とまでは言いませんが、歴史(時間)と共に練り上げられた厳しさと深みのある音楽は、心を健康にし自分自身を高めてくれることは間違いありません。
-
たかが音楽かもしれませんが、「音楽と音楽の歴史」を学び知ることは、すなわち「人間の精神の歴史」を学び知ることなのです。「過去と同じ過ち」を繰り返さないために、来世紀に向かって「正確に音楽を伝えられるようオーディオも進化」しなければならないと私は考えます。
-
私は「音楽」が大好きですが、私を感動させ「生きるために欠かすことの出来ない何かを与えてくれるもの」は、もちろん「音楽」だけではありません。つらいときに友人が掛けてくれる「暖かな言葉」は、すごく大きなエネルギーとなりますし、映画やTVにも感銘を覚えます。何も音楽にこだわらずとも、「楽器」が弾けなくとも、「人を感動させることができる」なら、それだけで素晴らしいと思うのです。
-
では、「感動を覚える」とはどういうことなのでしょう。そして音楽から得られる「感動」とは、どういうものなのでしょう。
-
音楽を聴き「感動した」と一口に言っても音楽が与えてくれるものは、単一の感動だけではありません。人それぞれ「生まれ持った感性」も「育った環境」も違いますから、「何に対して感動したか?」には、各人の主観に基づく相違点があるはずです。
-
また、実際にリスニング・ルームで同一の音楽を再生したとしても、このような心因性要因以外にも、空気のコンディション(気温や湿度)による音質の変化やリスニング・ルームの間接音の影響など、さまざまな物理的な要因により、音そのものも変化しています。
-
このように、同一のソフトを再生しても、そのソフトに対する感じ方はさまざまであり、したがってその評価は「同一の音楽感を持つ人達」にのみ共感を持って受け入れられるであろうという事を忘れないようにしたいと思っています。音楽やオーディオの世界では、自分にとっての「絶対」が、相手にとっての「絶対」ではありえないのです。簡単にいえば、価値観の相違と一致です。たとえば、教会音楽などには、宗教的側面や学問的側面すら否定できませんが、このような音楽と、カラオケに代表されるような娯楽的音楽を混同できるはずはないのです。
-
しかし、もちろんオーディオで音楽を聴こうとする人達は、「音楽が好き」・「音楽に求めるものがある」という部分において基本的には同じであると思いますから、あまり目くじら立てて、「あれは駄目だ」とか「これが絶対だ」とか、喧々囂々と議論を戦わす意味はないと思います。
-
音楽には様々な感動のチャンネルが隠されています。多くの感動を得るには、出来るだけ多くのチャンネルで音楽を感じる必要があると思います。また、特定のチャンネルにこだわりすぎると、「全体」を見過ごす恐れがありますから、多くのチャンネルで音楽をとらえると同時に、すべてのチャンネルの感度は公平であることが望ましいと思います。つまり、「心を素直に開け放って音楽を聴こう」ということです。
-
また、感動のチャンネルは経験によりその数を増やして行きますから、あまりいい印象を持たなかった演奏でも、一度聴いたきりで切り捨ててしまうようなことでは、感動を聞き逃したり、見過ごしたりしてしまうでしょう。しかし、名演というものはその時は好きになれなくても、やがてそれが分かるようになるときまで、どこか心に引っかかっているのかも知れません。
-
オーディオファンの音作りの基本的な姿勢を、聴覚と視覚とを置き換えて考えてみました。
-
ここに白い紙があって、その中央にバラが描かれてるとします。そのバラを絵の具で、「正しくバラの赤に塗ってください」と言う指示があれば、100人が描いたバラの色は二つと同じものはないはずです。
-
この比喩は、100人のオーディオマニアが、同様に「バラ=音楽」をイメージし、それを「正しい赤=その人がこれだと思う音」にチューニングしても、出てくる音がまったく異なってしまうことを意味しています。
-
しかし、どの「音=色」が本当に正しいかどうかは、「本物」とその場で比較する以外に確認することは不可能です。つまり、自分で録音し、それを正確に聞き覚え、録音(機器)現場の音と再生(機器)現場の音を、比較する以外に、「正しさ=機器の音の絶対指標」を判別することは出来ないのです。
-
もちろん、「赤か黄色か」ぐらい「色」が違えば、ほとんどの人はその間違いを指摘できるでしょう。しかし、「赤」の中で「どの赤が一番正しいか?」を判別することは、このような比較を行わなければ、不可能といえるほど困難なはずです。この点に注意しなければ、気付かずに自分の「好み」による音質判断と機械の「良否判断」がすり変わってしまうでしょう。
-
話は変わりますが、ビデオを撮影するときに、薄汚れていたはずの色鉛筆がピカピカの新品に生まれ変わってキレイに写っていることがあります。この傾向は、[CCD]+[デジタル方式]でより強くなりますが、これは録画再生時に細かな中間調が飛んでしまい、色彩の明瞭度(鮮やかさ)が増すためです。そのような映像システムで「名画」を撮影すれば、実物とはまったく違って写ってしまうでしょう。
-
同様なことは、音の世界でも起こっています。限定された情報しか再現しないオーディオ機器は時として、下手な演奏のあらを隠すでしょうし、強調感(誇張感)のある再生装置は、演奏の不備を補って上手な演奏に聴かせることがあるのです。しかし、そのような装置から再生される音楽は、肉眼で見た名画と印刷された名画がまったく異なった印象を与えるように、実演とはまったく違って聞こえているのです。
-
このように好みと言う「歪み」を付加された装置で聴けば、音楽は「本来の演奏」とは「まったく違った演奏」に作り替えられてしまうのです。
-
「好き嫌いによる判断基準」と「原音対比から得られる正確な良否判断」。私自身は、それをわきまえた上で話すことが、オーディオ機器の音質を評論する上での最低限のルールであると考えています。更に、職業(プロ)として正確なアドバイスを心がけるなら、この点を十分に理解しなければ、食い違ったとんでもないアドバイスを行ってしまうことになるでしょう。
-
確かに、オーディオの楽しみには「音を好みに作り替える」という部分がありますが、それが過ぎれば、もはや「それは音楽を聴かせていただく」のではなく、「自作自演の演奏を聴いている」ことになってしまうのです。そうなれば、「音楽」から客観的に学び取れる情報が極度に少なくなってしまうでしょう。
-
「名画」を目の前にしながら、何らかのフィルターがじゃまをして「名画の感動」を味わえないとすれば、それほど「もったいない」事があるでしょうか?
-
しかも、そのフィルターの色は「自分自身」そのものであるのかも知れないのです。
-
プロの音=モニター調の音は、味気ないと言われる場合があります。しかし、私は「音楽=音」を「料理=味」に例えた場合、プロの味とは「素材そのものの持ち味を殺さずそれを更に引き立てる料理法」、アマチュアの味とは「素材そのものより、味付け自体にこだわった料理法」と考えています。
-
また、時として私は「その人の音を聞き分ける能力の是非」を前提として話を進めることがありますが、それは、様々な料理を食べ、食べ物と料理に精通していない、「自称グルメ」が「正しく料理を味見できる」とは考えられないからです。もちろん、彼等は彼等なりに「上手い不味い」を感じてはいるのですが、広く一般的な「味覚感覚」を身につけていなければ、本当の「味覚=味の可否判断」をすることはできないはずです。
-
ソムリエと呼ばれるような人達は、その人物自体が「高感度なセンサー」として機能する事を一般に認められた人達ですが、音楽に関しては、そのようなポジションが見あたらないように思いますし、実際に評論家になるための「楽器の音の聞き分けのテスト」があると聞いたこともありません。まして、経験不足な人達の間で流れる「噂」の信憑性は、いったいどの程度のものなのでしょう?
-
私の考える「耳がよい人」とは、「ある程度正確かつ、一般的に音楽を判断出来る経験豊かな人」を指し、「単に耳が良く聞こえる人」という意味ではありません。音楽やオーディオの音質判断においても、相手が経験不足なら「その人の判断は好みの範疇」を出ず、そのまま鵜呑みにはできないということになります。
-
「オーディオセットの再生音」は生の楽器と厳密に比較すれば、「似て非なる音」と言って差し支えないほどまったく違う音に変化しています。我々はそういうステレオの音からも「音楽」を感じ取ることが出来ますが、演奏された音と再生される音に差異(ずれ)があれば、当然、音を媒体としたコミュニケーションである音楽の内容の差異(ずれ)となって反映されてしまいます。そのため、「自分が聴いている装置の性能限界=生の音との差異」を明確に知っておかなければ、「もとの音楽を正確にイメージする」ことはできません。逆に言えば、自分の装置の「音」に聞き惚れているうちは、「音楽の重要なメッセージ」を聞き逃している恐れがあるとさえ言えるのです。そして、このような独善的な音作りを続けても、再生音楽の世界は広がりを見せてはくれません。
-
ご存じのように音楽は、リズム・メロディー・テンポなど様々な要素により構成されています。現在最も売れている、「小室ミュージック」は、「覚えやすい旋律と言葉を、派手なテンポで繰り返す」という単純な手法により作られていますが、このような音楽は、最初は良くても次第に飽きて行くはずです。それは「音楽表現」に用いられている「感動伝達チャンネル数」が少ないためであると考えられます。
-
感動伝達に使用されるチャンネル数が少なければ、取っつきやすく「わかりやすい」と考えることもできますが、「たんなる娯楽」としてではなく、「更に深く何かを学ぶ素材」として「音楽を考える」なら「チャンネルは一つでも多く開かれている」ほうが「より音楽は深みを持つ」ことは紛れもない事実です。なぜなら、自分の心の経験が増し、「受け入れる側の感動のチャンネル」が新たに開かれたとき、そこに「新たなチャンネル」を見いだすことができれば、「音楽はまた違った感動」を与えてくれるはずだからです。
-
仮に、音楽に使用されているチャンネルを「楽音の変化=音の変化」に限定してみましょう。楽器の一台を「一つのチャンネル」に当てはめたとすれば「楽器の少ない構成」の音楽より「楽器の多い構成」の音楽が、より音楽表現に「多くのチャンネルを使うことが出来る」はずです。更に、もし一つの楽器の音が、いくつかのチャンネルを持てるとすれば、「音楽が内包する感動のチャンネル数」は飛躍的に大きくなるはずです。
-
例えは適切ではないかも知れませんが、仮に一つの楽器が10のチャンネルを持っているとします。楽器が10台になれば、当然チャンネルは10×10の100チャンネルになるはずです。
-
そのためには「各楽器の音がぶつからず整然と混ざり合う」必要があるはずです。つまり、「多くのチャンネルが開かれた演奏」とは、「非常に整ったハーモニーの構造を持つ」と考えることが出来るのです。(楽器の数が少ない、JAZZやPOPSでは楽器の音色の調和よりも、リズムやテンポの調和が優先する場合もありますが、それらの音楽でも使用されている感動のチャンネルが多くなれば、楽器の音がぶつからず綺麗にハモるはずです)
-
逆に、いくら多くの楽器を使っていても「楽器奏者が上手くなかった」り「指揮者が不味」ければ、「音がぶつかって=チャンネルがぶつかって」しまい、聞こえる音は団子になり、チャンネルはお互いにうち消されてしまって、演奏に「多くのチャンネル」が開かれることはありません。
-
話を少し戻しますが、「複数の楽器」を使えば、「複数の音」が生じるので、「複数の感動伝達チャンネルが開く」ということは、比較的容易く理解して頂けそうです。しかし、一台の楽器に「複数の音=複数の感動伝達チャンネル」が開かれるとは、どういうことなのでしょう。それは、楽器の「一音」の音の構造を「倍音のハーモニー」と考えることで説明ができるのです。楽器から音が出るときは、「基本となる音=周波数」が楽器の各部でさまざまに共鳴、反響し、渾然一体となって空中に放射されますが、この共鳴、反響を整然と整えるように楽器をコントロールすることができれば、音波は整然とした形になります。これを、測定器で見れば、「音のエネルギーが高い周波数帯域」とそうでない「音のエネルギーの低い周波数帯域」が交互に現れるのです。そして、ほとんどの場合この周波数帯は、「整数倍の関係」を取ります。これを、「楽器の倍音構造」と呼ぶのですが、綺麗に響いて伸びやかな楽音は、「倍音構造=基本の音が反響して作られる倍音のハーモニー」も美しいのです。
-
つまり、「感動のチャンネルをより多く開く」ためには、「ハーモニー=調和」を重要視する必要があり、ステレオ装置はハーモニーの基本と考えられる「楽器の倍音構造」を明確に再現する必要があるのです。そのためには、「ステレオで偽の倍音=音楽表現」が発生していることを聞き分け、それを取り除く必要があります。私が特に再生音の倍音関係の清潔さ(原音忠実性)を重視しているのはこのような理由からなのです。
-
ご存じのように、クラシックの交響曲は多くの楽器で演奏されます。つまり、多くの感動伝達チャンネルが開かれているということです。それが、「クラシック」が「世界で深く愛好される音楽である理由の一つ」ではないかと思うのです。しかし、いくら「多くの感動のチャンネル」が使われていても「録音・再生」が不味ければ、やはり「リスニングルーム」には「多くのチャンネル」は開かれないでしょう。
-
非常に「ハーモニー」にこだわったお話をしましたが、もちろん「音楽から感動を感じるポイント」は「ハーモニー」のみにあるのではありません。そのポイントは音楽によってもさまざまですし、「聴く人の感覚によってもさまざま」ですから、最終的な音の判断は「その人の好みでよい」と言いきってしまえばそれまでです。しかし、あえて自分自身の独善におぼれずに、人の感性も採り入れられて、ひとつでも多くのチャンネルで音楽を感じる努力をして欲しいと願うのです。
-
なぜなら、再生音により多くのチャンネルが開かれれば、一つの音楽、演奏から更に多くのことを感じることができるでしょうし、もしかすれば、音楽を聴くことによって、あなたがまだ知らない心のチャンネルが開かれるかも知れないのです。そうして「感性を鍛えること」ができれば、より人生は深みを増すと確信します。
-
一つの音楽、演奏から更なる感動を求められるなら、「自分のオーディオセットの音作り」に際して「好き嫌いによる判断=個人的な思いこみのチャンネル」だけでなく、より普遍的な音の要素を取り入れて、更に多くのチャンネルを開くことが重要なのではないでしょうか。
-
AIRBOW製品の音決めに際して、どんなに「細部まで聞き込んで機器を完成させた」としても、セットアップを含め、再生音の音作りを最終的には個々のリスナー自身の判断に委ねる他ないのがオーディオの音楽性の限界だと考えることができます。
-
例えば、生のバイオリンを聴いたことのない人に、バイオリンの再生方法を説明したとしても、バイオリンの再生音の良否判断感覚は正確に伝わりません。このように、音の情報の伝達は、「受け手側の経験」があって初めて成立するのです。私のオーディオのプロとしてのスタンスは、「無駄がなく元の音をストレートに感じさせてくれる音」作りです。そして、自分の思うアプローチでその命題に取り組んでいますが、本物の音を聴いたことがない人には通じない場合も出てくるでしょう。できれば、すべての人に「これは良い」と感じてもらえれば何よりなのですが、追求するためにはある程度の「割り切り」は必要だと考えざるを得ない場合があります。
-
その割り切りとは「アコースティックな音源」と「電気的に合成された音源」、「ワンポイントステレオマイクによる録音」と「マルチマイクによる作られた録音」を区別しなければならないことなのです。
-
私の求めている、「高度な音楽」とは「音の情報の細かい音楽」です。再び料理に例えれば、本当に上手い天然自然の味です。極論を述べるなら、「電気楽器やオーディオ的に作られた作為的な録音」は「合成調味料」以上の存在ではありません。
-
確かにおいしく食べることを楽しむのが目的であれば、どちらでも上手ければよいのであって、天然か合成かにこだわること自体が無意味にも思えますが、もし人にどちらがより上手いか聞かれたら「天然の素晴らしい素材」を上手いものとして推薦するでしょう。
-
「アコースティックな楽器」から出る音と「電気的に作られた音」とでは、開かれている「感動伝達チャンネル数=音の粒子のきめ細かさ」に相当な差があります。また、「それらを料理する」=「機器の音決めをする」場合にも、まったく違う手法を取らざるを得ない場合が出てくるのです。
-
「天然の味=アコースティックな音源」に「合成調味料=電気による歪み」を加えれば、即座に「味=音がおかしくなる」ことでわかりますが、「合成調味料=電気的に合成された音」に、更に「合成調味料=電気的な歪み」を加えても、味が変わるだけで「上手くなるか、不味くなるか」は「聴く人次第」になってしまうのです。つまり、「アンプの音をわざと歪ませて音作りをして」も、電気音楽を基準にするなら「音を歪ませた方が良く聞こえる」場合も出てくるのです。
-
しかし、言うまでもなく、AIRBOW製品の音決めでは「迷わず天然素材の味=アコースティック楽器の原音忠実性」を優先しています。
-
また、「マルチマイク録音のあらを消す」には、「音場空間を濁らせること」以外に方法はありません。なぜなら「装置の空間再現性が正確」に保たれれば、録音時に各々のマイクがとらえた空間がリスニングルームに「正確に重なってしまい=ハーモニーが何十にも重なって」音像がにじんで聴けたものではなくなるからです。しかし、このような音作りをすれば、「確実によい演奏はくすんで」しまいます。それは「素晴らしいハーモニー」の再現性を低下させることになるからです。
-
「良い演奏を更に輝かせるよう」にすれば、「加工して録音された多くのソフトが奇妙な音」になってしまうかも知れませんが、その場合にも、迷わず「良い演奏を更に生かす」ことを優先しています。
-
そのため、「今まで心地よく聴けたはずのソフト」が「以前より良く聞こえなくなってしまう」ということも起こらないとは言えません。しかし、「どのような機器を購入」したとしても「そのような問題」は付きまとうことです。「特定のディスク」や「特定の演奏」を「上手く聴かせる」ことにこだわりすぎることは、「多くの感動を見すごしてしまう」ことにつながりかねず、本当はお薦めできないのです。
-
つまり、お客様のお手持ちのソフトを「すべてそれなりに聴かせる」ようにすることは、結局どっちつかず、「二兎を追うもの一兎を得ず」の諺通り、すべてを駄目にしてしまうでしょう。
-
音を「判別する」ということと、「音楽を聴く」ということは、私の中では違う行為です。アンプやスピーカーの音を判別しているときは、「純粋に楽器の音を聴いている」のであって、「音楽を聴いている」とはいえないのです。たぶん、脳の中でも全く違うプロセスで処理されていると思います。
-
オーディオで音楽を聴く場合には、「音を聴きそれがどのような音なのか判断するプロセス」つまり、「楽器の音」を「記憶にあるデータ」と照らし合わせて、「音を再構築するプロセス」と「脳が感じた音=音波による刺激」から「精神の変化=高揚を生み出すプロセス」のそれぞれを分けて考えたほうが良いと思います。
-
まず最初のプロセス、「音の判別」には、あきらかな個人差=学習効果があるでしょう。このプロセスを鍛えるためには、多くの音のパターンを記憶する=判断基準になる楽音を、沢山聴く以外に方法はないと思います。
-
また、その次のプロセス「音に感応して精神を高揚させる」ためには、「様々な音に感応できる感性のチャンネル」を多く開くことが重要でしょう。そのためには、人生において様々な経験を積むことが必要なのではないでしょうか?
-
私達が本を読むとき、まず「文字が読める」必要があります。次に「言語を正確に理解し、文章の内容を把握」しなければいけません。最後に、「内容を自分の経験に基づき、もっと深く想像」することでしょう。音楽を聴くのも、これとまったく同じではないか?と思うのです。それは間違いなく、とても奥深く難しいことです。「音は耳で聞き、音楽は感性で聴く」きっとそういうことなのでしょう。
-
また、「音」の中の「どの部分」に「音楽」が隠れているのか?「人はそれをどのように音楽」と感じるのか?この問題に対する「深い考察」を抜きにしては、「音楽」を再現できる「オーディオ機器」は構築できないと考えています。
-
私にとって「オーディオ」は音楽を知るための「シュミレーター」であり、「オーディオによるシュミレーション」の先には常に「生の音楽」があるといえます。オーディオセットが見せてくれる「仮想現実化」においての「満足すべきバーチャルリアリティーの完成」が私にとってのゴールではなく、「音楽をより深く知ること」が、オーディオにより深く携わる目的でありゴールなのです。
-
学ぶべき事は、またまだ沢山沢山あります。なぜなら、それは「音楽を深く知ろうとすること」は「人間そのもの」を知ることと同意義であると感じるからです。
-
オーディオ機器を選ぶとき、最も大切なポイントはどこにあるのでしょうか?
-
オーディオセットは音楽を聴くものですから、自分で試聴して本当に気に入った物を買ってこそ、愛着が出るものだとも思いますが、本当にそれだけでよいのでしょうか?
-
私は、少し違うように感じます。私が「道具を選ぶとき」は二通りの方法があります。自分の経験や感覚に自信を持てる場合は、自分の感性と好みで選びます。しかし、自分がその分野で正しい選択をするには「経験不足」だと感じるなら、信頼できる人を捜してその人に選択を任せてしまいます。
-
なぜなら、正しく選択された道具を「信頼」し使い込んで行けば、その「過程」がそのまま、「自分自身の成長」につながるからです。正しく選択された「道具」は使い手を正しく「成長」させてくれるでしょう。しかし、経験が少ないまま、「好みだから」等という理由で適切でない道具を選べば、結果として上達が遅れたり、まったく上達しないということさえあり得るのです。
-
オーディオ機器の選択時には「音楽家の卵が楽器を選ぶ場合」と同様、最初に選んだ道具によって「その卵の成長が大きく左右される」ように思います。
-
このように、我流で続けることは「遠回りする時間の無駄遣い」とも考えられますが、もちろん、その人にとって何が無駄で、何が無駄ではないか?それは本人以外には計り知れません。しかし、「趣味」に見いだす最も重要な要素を「それを続けることで自分自身を高めること」とお考えなら、道具の選択は信頼できるアドバイザーに委ねられるのが最も良い方法だと思います。
-
無論、人間のやることですから「常に最もシンプルにその方向に向かえる」とは限りませんし、そんなことだけを考えれば息が詰まってつまらなくなるかもしれません。
-
しかし、道具の選択時に「目的や目標を明確にしておく事」は、最低限必要な事ではないかと思います。
-
楽器を弾く人ならお気づきでしょうが、アコースティック楽器は奏者によって音が変わります。つまり、楽器から取り出せる音波の波形が変わるわけです。オーディオ・ファンなら誰でも、装置を変えれば音が変わることを知っています。むしろ、積極的にそれを楽しむのがオーディオだとも言えるのです。
-
仮に、入力波形(もとの波形)と出力波形(取り出せる波形)との差を「歪み成分」と定義します。再生時にはオーディオ機器の中で、「もとの波形」にこの「歪み成分」が加わることで、「波形が変わり」その結果出てくる「音が変わる」のです。
-
では、再生される音の「どこからが歪み=もとと違う音」で、どこまでが元々の音なのでしょう?その判断はかなりのマニアでもまず不可能だと思います。なぜなら、それを知るためには、演奏の現場にいて自分で録音し、その音源をマスター(基準)として判断しなければならないからです。
-
現在私は、機器のテストにそのようなマスターを何種類か作成して使用し、また演奏者を交えて再生音を聴いたりしています。しかし、このような音質判断に「音楽」を用いることはよい方法ではないのです。
-
「音楽を聴く」ということは、「演奏者」も「聴衆」も「単に音」を聞いているのではなく、それぞれの主観に基づき、更に「感性と想像力」の助けを借りて、「音楽」を聴いているからです。つまり、「音楽」をテストソースに使うことは「再生音を客観的に判断」する妨げとなるのです。
-
たとえば、音の判別に「主観」が混じり込んでしまうということは、二者択一を迫られた時、「客観的でなければならない良否判定」に、「音楽的に良いかどうか」という「主観的価値」が混ざり込んでくるということなのです。実際にマスターを録音してテストする場合にも「演奏」よりも「楽器のチューニングの様子」をソースに使う方がより早く、正確な答えが出せます。そこには「主観的な迷い」が入らないからです。
-
また、このような「正確な音質判定」を繰り返し、システムの「歪み」を取り除く経験を積むことで、取りきれていなかった再生時の装置の「歪み成分」が「再生音楽の音楽性に与える影響」を知ることもできるのです。
-
また、このテストと並行して「測定器によるデーターの摂取」を行えば、「人間の聴感」と「データーの相関関係」がわかってきますが、誤解を恐れずに申し上げれば「現在カタログに表示されているメーカー発表のデーター」は「音質とはほぼ無関係」です。
-
また、「F特がフラットに保たれているかどうか?」ということよりも、「人間が感じとれる音(楽音)の相関関係がきちんと保たれているかどうか?」ということが正確な音楽再生には大切なようです。
-
オーディオの目的がもし「寸分違わない原音忠実再生」にあるのだとすれば、「スピーカーを使って部屋に音を出した」時点でそれは不可能になってしまいます。無響室でもない限り、スピーカーから出た音はリスナーに届くと並行して複雑な反射を伴い再度リスナーに戻るからです。このような状態では、音の聞こえ方は「部屋の音響特性=ルームアコースティック」の影響を大きく受けることでしょう。
-
更に、録音時にも問題があります。コンサートで音は360度すべての方向から聞こえますが、マイクには指向性が生じており、収録時にその場で聴いている音と、録音された音はすでに違う情報になっているのです。
-
もし、コンサートの音を正確に再現しようとすれば、まず、被験者を模して製作した理想的に精度の高い「ダミーヘッド」を用いて録音し、これまた被験者に合わせて作られた理想的に精度の高いヘッドホンで再生すれば「原音忠実再生」は高いレベルで実現可能なように思います。
-
しかし、マイクが拾った指向性のある情報を、異なった指向性を持つスピーカーで再生し、その情報を部屋の反響でさらに歪ませているのが、今のオーディオです。これでは最初から、「精度」などとはほど遠い再生音になるはずです。「正しさ」の追求には、根本から間違っていると言えなくもありません。
-
反面、ヘッドホンでは「雰囲気」が殺がれると言う側面を否定できません。例えば、リスニングルームの調度品や照明、オーディオ・セットの色やデザイン。「耳(鼓膜)」ではなく、「皮膚」で感じる音。例えば、料理が盛りつける皿によって、上手くなったり不味く感じたりするように、そういう「環境」の雰囲気も「自宅で音楽を聴く」場合には重要だと思います。我々、オーディオ・ファンはきっと完璧なモニターシステムを求めているのではなく、求めるのはあくまでも自分の部屋における「バーチャル=仮想現実」なのでしょう。
-
「正しい音=モニターシステム」あるいは、「楽しい音=仮想現実」。そのどちらを選ぶかは、自由だと思いますが、それぞれの長所と短所をきちんと知っておけば、より良いことは間違いないと思います。
-
クラシックのコンサートは、まず例外なく豊かなエコーのあるホール(教会なども含めて)で行われます。これは、クラシック音楽がキリスト教と共に発展してきたことと無関係ではなく、大勢の民衆を前に少ない演奏者で楽音を隅々まで浸透させようとすれば、反響のあるホールで行うことは非常に理にかなっています。重ねて、当時のヨーロッパでは大きな建物は石造りであったことも、ホールトーンの存在が音楽や楽器の発展・構成に大きな役割を果たした要因でしょう。
-
このように音楽のホールトーンへの依存は、ホールの音響特性があたかも楽器の一部であるかのような、演奏とホールとの密接な関わりを生んだのです。
-
では、ホールが悪いと「それだけで良い演奏が出来ない」ということなのでしょうか?
-
ある意味では的を得ていると思いますが、楽器の音で使えるのは「艶のある流麗な美しさ」だけではありませんから、様々な奏法を用いホールに合わせた表現が出来るはずです。
-
この楽器の表現幅を「楽器の表現チャンネル数」に当てはめてみます。もし演奏家が未熟で「特定のチャンネル」しか使うことができなければ、不得意な音響特性のホールで演奏しようとした時には、「ホールが自分の持っているチャンネルと合わず、頼りの楽器の音がよく響かない」ため、とたんに演奏できなくなるということも起こりえますが、演奏はホールと同時に奏者の資質の問題でもあるわけですから、もしカザルスが奏者なら、ホールが悪くてもきっとそのようなことは起こらなかったはずです。
-
この関係はそのまま「リスニングルーム」と「再生音」の関係に当てはまります。ホールトーンを含む音楽を再生する場合は、リスニングルームの音響特性が非常に重要な意味を持つわけです。部屋での再生音に「自分なりの癖が強く付いている=特定のチャンネルしか開かれていない」場合は、ピタリと当てはまる音楽は上手く聞こえ、そうでないものはまったく聴けないという状態になりかねません。
-
しかし、ホールトーンという音は、「クラシック」において必要な概念であって、「小室ミュージック」など現在最も売れているインスタントな音楽には不必要な場合もあります。ですから、それらの「インスタント」な音楽をウォークマンや、ミニコンポで聞き育った人物がオーディオ・ショップの店員になったとしても「ホールトーン」をきちっと再現できるようにステレオ機器をセットアップできるとは思えませんし、そのようなソフトを試聴時に用いても「再生音のきちんとした判断の指標」にはなりません。
-
我々のようなショップのアドバイザーは、出来ればあらゆる種類の音楽と楽音に習熟し、音楽の一つの頂点である「クラシック」をきちんと理解する必要があるのです。そうでなければ、「先を見越した正しいアドバイス」など出来るはずがないのです。
-
話を戻しましょう。下手な歌でも、エコーをかければ上手くなるように、部屋やホールの美しい響きは、「汚い音」を浄化し「綺麗な音」に変えてくれる働きを持ちます。それは、「ルーム・アコースティック」を整えることが、オーディオ装置の性能を引き出し、「再生音を心地よく聴かせる」ために、欠かせない大切な要素であることを示しているのです。
-
あなたが、よくお読みになる「オーディオ雑誌」には、「それらしき数字」が溢れています。また、オーディオ・メーカーの技術者は、常に「データー」を基準に話をするはずです。この「測定データー」とは本当に有効な数字なのでしょうか?
-
ほとんどの音響技術者は、「データー」が取れたことによって「判ったような気」になってしまい、「データーそのものの検証」がお留守になりがちだと思います。私は化学を専攻しましたが、化学実験では「ある物質の水溶液を定量的に検出しようとする場合」には「ある物質」を「溶かす水」に「不純物」が含まれていてはいけないのです。
-
これをオーディオ測定に当てはめれば、高純度銅線の「音質」を測定しようとする場合には、「それを測定するための装置」には「更に高純度な銅線」が使用されていなければ、「データーの信憑性」は確立できないはずです。更に、測定器の回路も「音質を絶対損ねない理想的な回路」が要求されるでしょう。
-
言うまでもなく、現在のオーディオ測定器は「そのような高精度なレベル」には到達していないと思いますから、「測定データ」はあくまでも「参考程度」の域を出てはいけないと思うのです。そうであれば、オーディオ機器の設計時にも「良い音かどうか?」は「人間が聴いて判断する」以外に方法はなくなります。それでは、「科学にならない」と反論する前に、「電気を計る」のと「音を計る」のが同じ機械で通用するはずがないのですから、「人間の聴感とマッチする=信頼できる測定器」を開発する必要があるはずだと思います。
-
現時点ではまだ、測定器から取り出せる「データー」や「現在の電気や音響に関する理論」では、「音の良さ」を表現するには全く不十分だと言い切ることができるのです。
-
我々の世代に於いて、「オーディオ(音の良さ)」を論じるためには、このような「完全ではない理論」で「すべてを説明しよう」とするよりも、「理論を更に完全にすべく」、補足や改編を加える必要があるのです。「現状にしがみつく」だけでは、「愚かな過ちを繰り返す」だけにしかならないことに気が付くべきです。
-
ようやく「DVDオーディオ」のフォーマットは決まりました。しかし、「スーパーCD」なるもののフォーマットはまだ決まってはいません。約20年前、メーカーはアナログ方式を切り捨てて、デジタル方式へと変遷を遂げました。しかし、一部のマニアは未だレコードを捨てきれず、中古レコードには高価なプライスタッグがぶら下がっているではありませんか。本当にデジタルの導入は、音楽のために良かったのでしょうか?
-
デジタルと、アナログの良否については、私は次のように考えています。
-
最高を求める場合、アナログとデジタルでは、デジタルに可能性を感じています。その理由は、ノイズ、ワウフラッターなど、聴覚的に見たデーター的に優秀であること。人間の耳、ハードとしての構造は、デジタル方式に似ていること。(解剖学的に見て、音を感じる絨毛細胞の1つを1つのビットに当てはめて、人間が音を分析するのに必要な最小単位の時間を最小サンプリング時間に当てはめることができると考えています)しかし、現在のデジタル方式は、様々な問題が未解決のまま残されているために、トータルとしては未だアナログ方式を越えられてはいないと思うのです。
-
デジタルの抱えている問題点とは、理論に技術が追いついていないことが最も大きな要因であると思います。
-
例えば、フォーマットと聴覚の不一致が挙げられます。人間には20KHz以上の「単一のサインウェーブは聞こえません」が、現在主流となっている20KHzから急激に遮断するようなアナログ・フィルターを使ってサンプリングを行えば、10KHz以上の楽器の倍音構造=原音との波形相似を考えた場合、かなり奇妙な形に変化しているはずです。
-
自然界では、20KHz付近の高周波は空気のフィルター作用、反射時のエネルギーロス等により、なだらかに減衰して行きます。このような、OCT/6db程度のなだらかな減衰であれば、「聞き慣れた減衰」なので、人間は「脳で補正して元の波形を想像しやすい」=「聞き分けやすい」と考えられますが、(アナログレコードのRIAA方式のフィルター・カーブがこれに相当します)OCT/36db以上というような、極端に急激な遮断(CDの録音時に用いられるフィルター・カーブです)を行えば、波形相似(相関性)が崩れてしまい、元の波形を上手く認識できなくなるのではないだろうかと思うのです。
-
現在のデジタル方式のフォーマットは、CDの導入時に「本当はコスト的に不可能であった」にも関わらず、それはひた隠しにして「20KHz以上は人間には聞こえない云々・・・」と強引にソニーとフィリップスが決めましたが、にもかかわらずスーパーCDの導入にあたっては、「入れば入った方がよいので100KHzまでフラットに録音できるフォーマットを採用するべきだ」と、「再度ソニーがごねている」にいたっては、「茶番劇」以外の何ものでもありません。しかし、デジタル方式のフォーマット上の音質問題は、ハイサンプリング、ハイビット化でかなり解決へと向かうと思います。
-
次に、スタンダードとなるべき、A/D変換・D/A変換方式が未確立であることが挙げられます。デジタル方式が本当に正しければ、A/D変換器やD/A変換器で音が違って聞こえてはいけないはずなのです。なぜなら、「音が違って聞こえる」ということは、「方式によってデーターが変わっている」ということを示しているのです。
-
これらの問題は、「ただ与えられたデーターと理論を信奉して盲目的」に行われている、「測定的、数学的、理論的な乱れや歪みを減らす努力」が「人間の認識能力」に対して、「確実な方法ではない=有効ではない」ということを示しているのです。
-
このようにさまざまな問題点が山積しているデジタル方式ですが、次のような大きな利点があることも忘れてはいけません。CDの簡便さ、「簡単にある程度の音が安定して出せる」点は、現在ソフトがレコード時代より多く売れていることにより、ユーザーがCDを支持したことを示しています。ソフトが多く売れれば、より多くの人が音楽を聴くことになりますから、デジタル方式導入の第一段階としては成功です。
-
次の段階として、量から「量+質」への変遷が望まれますが、「質を上げる」ことは、「コストの増大」を伴いますから、メーカーの腰は重いでしょう。しかし、「質」を要求するユーザーが一人でも増えれば、メーカーも本気で「質の向上」に取り組んではくれるかも知れません。しかし、オーディオセットの「音質」が向上しない限り、「音楽の進化」はあり得ません。
-
それは、前述したような理由により「オーディオセットが開くことのできる感動伝達チャンネル数」が貧弱であれば、「それに相当する貧弱な音楽」しか「再現できない」というようなことが起こり得るからです。つまり、いかに「名画=名演奏」を「簡単にコピー=CD化」できたとしても、その「印刷技術=録音再生技術」が貧弱であれば「名画の本当の凄み=演奏の凄み」は伝わりはしないのです。
-
次々と生産される「コピー」が、「オリジナル」をまったく伝えることができなければ、当然「本物」と「偽物」の「区別すら付けなくて良い」ような粗悪品が世の中に溢れるでしょう。
-
アナログか、デジタルか?その答えはこれから探ることになりますが、我々はすでに「後戻りはできない」のです。デジタル方式の可能性を信じ、その方式で最高のものを作り出していかなければならないわけです。
-
新3号館のメイン試聴室を「デジタル・コンサート・ルーム」と名付けたのはその「強い意志」の表れであるとご理解ください。
-
現在オーディオ機器を測定する場合の基準波形は「連続正弦波」が用いられていますが、この「連続正弦波」を用いた測定には大きな問題点があるのです。というよりも「連続正弦波」によって「オーディオ機器を測定」し、「それに基づいてオーディオ理論を構築」したことによって現代のオーディオ技術、オーディオ製品は大きな問題を抱えてしまったといえるかも知れません。
-
3号館の引っ越しも無事に終わり、スピーカーのセッティングをしていたときのことです。
-
以前から気づいていたことですが、リスニングポイントとスピーカーの直線距離と角度の関係をきちんと合わせれば、音は正確に広がって、正確な音場再現性が増すのです。
-
リスニングポイントを点として、そこからスピーカーの直線距離を測り1cm以下、できれば数ミリ以下に距離の誤差を追い込み、更にスピーカーの角度の相関誤差を1度以内に納めることができれば「部屋中の音場空間」が飛躍的に改善されます。試しに、デジタル・コンサート・ルームに社員を集めてスピーカーを動かしながら、実験して見せたところ、左右のスピーカーの直線距離5mmの誤差は、全員に音場空間の広がりの差となって認識されました。
-
このときの、距離の誤差5mmを音速に直してみます。音速を340m/秒とすれば、340mは、340000mmですから、これを5mmで割ると、時間にして340000÷5=1/68000秒!。この誤差がすべての社員に判別できたということは、解剖学的に見た人間が音を聴いている最小時間単位2/1000秒とかけ離れた数字になってしまいます。これでは、スピーカーの設置距離5mmの誤差がもたらした「時間的誤差」だけでは、被験者全員が感じた「広がり感の欠如」を正しく説明することはできません。
-
しかし、人間の方向感に大きな影響を持つのは低周波数帯域ではなく、高周波数帯域であることを考慮して考えれば、10KHzの空気中での波長「340×1000/10000=34mm」に対しての5mmの誤差は、約50度強の位相差をもたらすはずです。この事実を考えた場合、人間は時間差以外に、左右の耳がとらえる音波の位相差を認識することができると考える以外には、説明が付かないように思うのです。
-
しかし、「連続正弦波」のみでオーディオ機器を測定すれば、測定波の位相が360度の倍数でずれた場合、位相ずれによる「音の歪み」が反映されず、「歪み(音の汚れ)」は検知できないはずです。ですから、測定には「単発パルス」あるいは「矩形波」を使用するか、時間的にロックをかけて測定する必要があるのです。もちろん、これはアンプを始めすべてのオーディオ機器だけではなく、リスニングルームの音響特性の測定にも、そのまま当てはまります。
-
私が、デジタル方式と共に持ち込まれた、現在主流のフーリエ変換で論じられるオーディオ論に耳を貸さないのは、数式上の間違いがあるという意味ではなく、フーリエ変換によるオーディオ理論の構築は「すべての周波数で完全に位相がずれないこと」が前提であるにも関わらず、「連続正弦波」による測定法では、「完全な位相の管理」を行うデーターを得るためには不十分であると言わざるを得ず、当然「そのような測定データー」をもとにオーディオ関連機器を設計しても、何の進歩もないからなのです。
-
次に、測定器とはまったく違う、人間の知覚の問題が挙げられます。駅や都会の雑踏の中でも、私達は「特定の音」を聴くことが出来ます。例えば「携帯電話の呼び出し音」などはきちんと聞こえます。しかし、この問題を現在の全周波数を均等に重み付けされた、S/Nの測定に置き換えれば、仮に電話の音が雑踏のノイズの総量よりも、ほんの少しでも小さいだけで、認知不能になるはずですが、実際には、電話の音がノイズより更に-20dB低かったとしても我々は電話の呼び出し音を認知できるのです。
-
話を聴覚ではなく、視覚に置き換えて考えてみましょう。一面が白い紙の上に、ほんの少しの赤い点があれば、私達は瞬時にそれを見つけることが出来ます。また、紙一面に沢山の三角が描かれていて、その中に1つだけ同じ面積の○が描かれておればやはり瞬時に、その○を見つけられるでしょう。しかし、もしすべてのデーターを同一の重みで考えるなら、白い紙の上の赤い点も、たった1つの○も「測定誤差」の範囲を出ることはないでしょう。逆にもし白い紙を見せられた時に、「それがどれだけ白いか」を我々は正確には判別できませんが、測定器ならすぐにそれを「定量的な数字」としてはじき出すことができるのです。
-
これが何を意味するかと言えば、我々の知覚は「比較すること」を基本に、判別をしているということを示しています。また、比較対照の差が大きければ、大きいほど(赤と緑の関係)素早くハッキリと認識出来るのです。
-
このように私達の認識には「比較」と「記憶」が重要な働きを持ちますが、このような、人間にとっての「基本的な認知感覚」に基づき「オーディオ理論」や「測定方法」を見直せば、「従来の測定法」と「それに基づくオーディオ理論」に重大な不備があることに気づくことはそう難しくないはずです。
-
よく「小型スピーカーでは低音は出ない」ということを耳にします。これは、ある意味では正しく、ある意味ではまったく間違っています。ほとんどのオーディオ・マニアは、「オーディオ雑誌に書かれている」ように「周波数帯域別の音の大きさ」だけで「人間は音(音の高さ)を感じている」とお考えのようですが、少なくともこの考え方は「まったく間違っている」ことをこれから証明しましょう。
-
もし、楽器の低音が単にある低域周波数だけの成分で構成されておらず、高調波の倍音を含み、人間はそのすべての帯域から音程を判断していると仮定し、次のような実験を行ったとします。
-
小型スピーカーでは再生不可能なある低音域を、ピアノなどの高調波をたっぷり含む楽器で演奏し、小型スピーカーで再現すれば、きちんと音程が聴きとれます。逆に、パイプオルガンで同じ音階を演奏すれば、演奏された音程は大型スピーカーでないと再現できません。
-
これは、高調波=つまり音階よりもはるかに高い周波数が同時発生するピアノに対して、パイプオルガンの音が音階に定められた低い波長の正弦波以外の倍音はほとんど含まない単音により構成されているためだと考えられます。
-
このような経験から、私は人間の音の聞き分け感覚を次のように考えています。人間は特定の狭い周波数バンドではなく、数Hzから50KHz程度のかなり広い周波数バンドの音波をFFTのように、いくつかの帯域に分割し、時間軸上の音波のエネルギー(音量)の変化を認識している。その最小サンプリング時間単位は、少なくとも1/100秒以下である。(2/1000秒程度であると考えられています)ここまでは、肉体的(ハードウェアー)としての音の聞き分けに対する考察です。
-
次に、ハードウェアー(左右の耳)で脳が判別できるデーターに変換された音波は、脳に入りますが、ここからは、脳の内部での音の情報分析方法に対する考察です。
-
一度聴いた(経験した)音波のパターンは、その情報的な重要度(危険につながる情報は最優先されているはずです)によって分類され記憶されています。この記憶順位をもとにして、耳に入った音波はパターン照合されることで、その「音が何であるか?」の判別を速やかかつ、高い精度で行っているはずです。
-
つまり、ピアノのペダルの音は、広い帯域に渡ってそのデーターを記録されているため、小型スピーカーから再生される音でも、「記憶をもとにした音波パターンの復元」が可能となり、認識可能であろうと推察されます。しかし、パイプオルガンの音は「照合されるパーターン」となるべき周波数帯域の音波を含んでいないため「音程として認知されない」と考えることができます。(最近発刊された「絶対音感」という本にこのような音程の認知について詳しく書かれていると思います)
-
また、人間の脳は左右の耳に入った音波を「相互に重ね合わせるように比較」して、音の方向性を感じ取っていると推察されます。例えば、車の運転席側の窓を開け「片側の耳をふさいで」窓からはいる音を聴けば、「自分の車のエンジン音の方向感や距離感」はかろうじて感じ取れるのに対して、「違う車の方向感や距離感」あるいは、「サイレンの音などの距離感や方向感」は著しく阻害され、音源の方向と距離に対する感覚はほとんど失われてしまうのです。(危険なのでまねをしないでください)これは、「記憶」というデーターが、「いかに聞こえに対して重要な意味を持っているか」を示しているのです。
-
話を楽音に戻しましょう。聞こえた音を「記憶のパターンと照合する」場合には、時間と共に変化する楽器の倍音体系、あるいはいくつかの周波数帯域に音波が分割され認識されている可能性が高いので、オーディオ再生時に原音忠実度を増すためには、音波の時間軸上でのエネルギー分布形を近似形に保つ事が重要だと考えています。
-
つまり、「パターン」が似ている事が重要であり、細部までもとの波形とまったく同じである必要はないと考えています。つまり、「良いオーディオ」とは、「上手な嘘をつける機械」人間を上手く錯覚させてくれる装置であるという考え方です。
-
よく、ウエスタンやアルテックなどのかなり以前の「フルレンジスピーカー」の音が良いといわれますが、これを「波形相似」の考えをもとに説明してみましょう。
-
当時のウーファーのコーン紙を爪で弾けば、「コンコン」と音がします。これは爪で弾かれたコーン紙の素材自体が分割振動を起こし「波動モーション」として音が立ち上がり、高周波を伴う音波が発生するためですが、楽器から出る音も「高音域」はほとんどこの「波動モーション」によって音が発生しています。
-
もし、このような「フルレンジスピーカー」を「全周波帯域」のエネルギーで駆動すれば、スピーカーのボイスコイルは高い周波数でも振動するため、先程のような「コンコン」という音が絶えず出ているはずです。この音の総量は、ピストンモーションで出る音に比べて遙かに小さいエネルギーですが、「その立ち上がりの早さ」故に、人間の聞こえには相当大きな影響を与えていると思われるのです。
-
しかし、「連続正弦波によって引き起こされるピストンモード」を基本に設計されている「現在のスピーカーユニット」特に「ソフトドーム型ツィーター」からは、このような立ち上がりの早い音波はほとんど発生しません。
-
これを「波形」に直せば、「正弦波と共にパルス性の成分が発生する旧型フルレンジスピーカー」が、「元々の波形の痕跡をとどめているであろう」と思われるのに対し、「高い周波数のパルスを発生できない現代スピーカー」の波形では「楽器の高い音の判別が困難」になってしまうと考えられるのです。「楽器の立ち上がりの波形」は「旧型フルレンジスピーカー」が現代スピーカーより優れているはずです。そのため、「音楽の聞き分け」に際して、現代スピーカーは旧型スピーカーを駆逐しきれないのではないでしょうか。
-
波形を取り上げての説明は難しいかも知れません。少し角度を変えてご説明いたしましょう。バイオリンやギターから高い音(周波数)が出るときのことを考えてください。弦楽器の共鳴板はスプールスなどの「堅く強度の高い板」で作られています。この「強度の高い板」が「高速で振動」し「空気を跳ね返す=衝撃波を起こす」ことで、これらの楽器は高い音(周波数)を出せるのです。
-
この衝撃波を再現するために、録音し再生時に電気的なエネルギーに置き換えて、ツィーターのボイスコイルを駆動します。ボイスコイルの振動は、「強度の低い、軽くて薄い膜」に伝えられ、「これらの素材を高速で振動」させます。しかし、「強度の低い膜」では「空気の質量(重さ)と粘性(粘りけ)」にうち勝って、楽器から発生したような「衝撃波=パルス成分」を発生することができません。しかし、このような「楽器が起こす衝撃波=パルス成分」こそ「楽器の音を特徴付ける」ため、あるいは「楽音に深みを持たせるため」になくてはならない音なのです。
-
現在、オーセンティックと共同で「波動ツィーター」の製作を急いでいます。年内には間違いなく発売できると思いますが、これは「現代スピーカーが失った波動によるパルスのエネルギー」を「カーボンパネルを波動モーションで振動させることによって取り出し、付加しよう」という試みです。(すでに新3号館では、オープン当初からLIMITⅡと併用して使用していましたから、ご存じの方も多いと思います。)この波動ツィーターを使用することで、スピーカーの明瞭度は恐ろしいほど向上するのです。
-
先程、「ダミーヘッド=人間の頭に模したマイク」を用いた録音を「ヘッドホン」で再現するということを述べましたが、普通なら「ヘッドホン」で音を聴いても、「頭の中で音が定位」するだけで、頭の外に音は広がりません。しかし、「ダミーヘッドを用いたバイノーラル録音」のソフトを「ヘッドホン」で聴けば、「気持ちが悪いほどの実在感を持って、部屋の中に音像が定位」します。
-
実際に「バイノーラルによる再生」を体験してみればわかりますが、「正確に音=音楽」をモニターしたいならこれで十分なはずです。正確無比な記録音楽の解凍を考えれば、自室でスピーカーから音を出すことは、矛盾が多く技術的にも論理的にも正しいアプローチであるとは思えないのです。なぜなら、ヘッドホンと耳の間の空間は、最小のリスニングルームであり、考慮しなければいけない影響(パラメーター)の数も少なくすませられそうだからです。
-
では、何故、「わざわざ部屋の中に音を放射して」音楽を聴かねばならないのでしょう。
-
その理由は、まだ私にもわかりません。本来ならシステムを複雑にし、「音を悪く=データーを劣化」させて聴く必要などどこにもないはずです。しかし、私達は装置を複雑かつ高価にし、自分の部屋を疑似コンサート・ホールにしようという要求を持ってしまうのです。
-
確かに、ホールの客席で感じる、あの身体全体を包み込むような音場感覚だけは、いくら高性能な「ヘッドホン」でも得ることはできませんから、「皮膚感覚」でも音楽を感じたいという欲求を持っているのかも知れません。
-
では、「部屋に音を放射」したときに、「再生音」はどのような影響を部屋から受けるのでしょう。また、「部屋の音響特性」をどのようにすれば、「音楽への悪影響を低減」することができるのでしょう。
-
もし、「部屋の反射」が「悪影響」を及ぼしているなら、「部屋の反射」をまったく消してしまえば、「悪影響」を受けることはなく音楽を聴くことができるのでしょうか?
-
次のような実験をしてみました。通常に録音されたソフトを、「反響の全くない部屋=無響室」で再生するのです。結果は?確かに、スピーカーにかなり近づいて音楽を聴くならヘッドホンに近い感じでそれなりに聞こえます。しかし、スピーカーから離れれば離れるほど、「音がかすかす」になって、まったく聴けたものでなくなりました。
-
やはり、無響室は「リスニング・ルーム」には向いていません。通常の録音のソフトを心地よく聴こうとするなら、「部屋の反響を利用して」聴かねばならないようです。また、このようなことが起こる原因は、「音をとらえたマイクの指向性」と「音を吐き出すスピーカーの指向性」との間に「何らかの差」が生じているためではないか?と考えられます。
-
私はいつも、3号館のステレオはスピーカーの正面ではなく、少し離れた事務スペースから聴いているのですが、ベストポジションで聴くよりもこちらで聴く方が時として、生演奏と錯覚するほどリアリティーのある音が聴けることがあるのです。つまり、スピーカーから放射された音が、様々な反射をともなううちに、更に生に近い感覚の音になるらしいのです。
-
また、ツィーターの設置にしても、普通行われているような正面向きの設置ではなく、ユニットを真上に向けて、球面上の反射板に音を反射させて、360度の無指向性を持たせる方が、広がり感はもちろん、定位感も良くなるのです。逆に、現在広く行われているスピーカーの設置法では、リスニング・ルームに「特定の位相を持った音波のピーク」が発生し易くなり、そのピークが「人間の認識に悪影響」を与える可能性があります。
-
人間の認識はあくまでも相対認識であろうということは何度も述べました。光の三原色が混じり合って「白=無色」になるように、音波(暗騒音=ノイズ)も均一に混じれば人間には「無色」に感じられるのだと思います。もし、リスニング・ルームの音響(残響)特性がこのような「無色」に保たれていればそこに発生した「色=何らかのピーク成分」は認識し易いはずです。つまり、「楽音=音楽」の変化を認識しやすくなるのです。逆に、部屋自体が何らかの「強いピーク=色」を持てば、様々な音楽の認識は非常に困難を極めるはずです。
-
しかし、ほとんどのオーディオマニアはリスニング・ルームの音響特性には「恐ろしいほど無関心」だと思わざるを得ません。「狭い部屋に大きなスピーカー」を押し込んだり「スピーカーの位置決め」をきちんと行っていなかったり、まるで、スピーカーから出る音をよくすれば、「それですべてが解決する」とお考えかのようなお客様が、非常に多いように思えるのです。それは、ルーム・アコースティックについての情報が少なすぎるためなのかも知れません。
-
このように、多くのオーディオ・ファンは「特定な強いピークを持つ音響特性」、あるいは、「数種類のピークがある、まだら模様のような状態」の部屋で「音楽」を聴いていらっしゃるように思いますが、それでは、きちんともとの音楽を再現認識することはとても困難になってしまうでしょう。
-
これらのピークを解決するために次のような製品が最近発売されました。ひとつは、「周波数特性のピークを軽減し、部屋のF特をフラットに保つ」ための「デジタルイコライザー」です。実際に、「デジタルイコライザー」をテストしてみましたが、「CDから取り出したデジタル信号を、イコライジングするためにデジタル演算した」段階で「相当な情報の劣化=細かな音や表情が消えてしまう」を引き起こしました。
-
つまり、「デジタルイコライザー」を通すことで、「かなりの感動伝達チャンネル」が閉ざされてしまったのです。このようなことでは、「多くの感動伝達チャンネルが開かれた音楽=演奏と録音が優秀なソフト」に対しては、「デジタルイコライザー」は使用しない方が良さそうです。
-
他方、部屋の反響音(残響特性)をコントロールするために開発されたDSPは、上手く使えば適度な情報の混乱によってリスニングルームの「無色」を作り出す助けとはなるでしょうが、下手に使えばおかしなピークを持たせてしまい、逆効果となるでしょう。
-
もちろん、こちらの方式でも「使用した際の情報の劣化=感動伝達チャンネルが閉ざされてしまう」の問題が大きく、「演奏と録音が優秀なソフト」に対してはお手上げです。
-
しかし、デジタル方式が更に進歩し、個別の部屋(リスニングルーム)の音響パラメーターをきちんと取り入れて、より細かな補正ができるようになれば、スピーカーの数を2本から5本へと増やし、適当な位置にスピーカーを設置して、後はスイッチを押すだけで「アンプに内蔵のコンピューター」が「測定と補正」をすべてやってのけ、「難しいことは何もしなくても」自宅にコンサート会場を出現させることができるようになるでしょう。
-
では、現時点でのルーム・アコースティックの調整はまったく不可能か?といえば、我々はこれをスピーカーセッティングなどという方法ですでに擬似的に行っているのです。
-
リスニング・ルームの残響特性は「エコーが均一に消える」ことさえ満たせば、「エコーの時間の長短=デッドかライブか?」については、結構、幅があっても構わないと思います。問題なのは、「特定の周波数のエネルギーバランス」が崩れることです。リスニング・ルームに「心地よい広がり感と定位=自然な音場空間」を構築するなら、リスニング・ルームには「ピークを持たない周波数特性」と「ピークを持たない位相特性」が必要とされるのです。
-
実際にオーディオ・ルームでスピーカから放射された音は、どのように反射し、また私達は、「広がり感」や「音の方向性」、つまり「定位」と呼ぶ聞こえの違いは、どのようにして生じているのでしょう。
-
まず、「片方の耳をふさいだ」状態で音を聴いてみて下さい。仮に、電話のベルが鳴ったとします。「電話の音と電話の場所」はすでに記憶されていますから、片方の耳がふさがれていても「電話の音の方向」がわかりますが、これは「単に記憶」によって音の情報が復元されたに過ぎません。その他の音はどうでしょうか?「片方の耳がふさがれた状態」では「音の立体感」は、ほぼ完全に欠如してしまうでしょう。
-
これは、「私達は左右の耳に入った音の相関関係」から「音の方向性や広がり=定位」を感じ取っているという証明になります。また、私達は「低い音より高い音に対して、より鋭敏に方向性」を感じ取りますが、それは、何らかの方法で「左右の耳に入った音波の位相差」を認識することによって可能なはずです。これらのことにより、「部屋での定位感の向上」には「スピーカーから出た音の位相差」をきちんと合わせる必要があることが理解できるはずです。この「左右のスピーカーから出た音の位相(あくまでもスピーカーに入った音ではなく、スピーカーから出た音の位相です)」を合わせ、整えるにはどのようにすればよいのでしょう?それは、実に簡単なのです。
-
まず、部屋の寸歩を計ります。仮に、一辺が6m×4.5m、天井までは2.5mの長方形の部屋にスピーカーを設置することを考えましょう。スピーカーから放射された音はできるだけスピーカーから離れてから反射することが望ましいので、スピーカーのユニット(ツィーター)の位置は、天井と床との中心=床から1.25m。壁からは、6mと4.5mをそれぞれ3等分した位置に設置することが理想となります 。
-
このとき、これらの距離の誤差を数ミリ以下にする ように実測して行うことが大切です。それは、前述し たように、左右のスピーカーの5mmの位置のずれが、 10KHzでは約50度もの位相差(ずれ)になって しまうからなのです。
-
距離を正確に設置した後に、2等辺3角形の頂点に 向け、2本のスピーカーの角度誤差を1度以下になるように設置してください。
-
これで、ほぼ理想的なスピーカーセッティングは、 終了しました。音を出してみれば、でたらめなセッティングをしていたときとは、比べものにならないほど音場空間が広がっていることにお気づきになるはずです。
-
では、なぜこのようなスピーカーセッティングをする必要があるのか?を理論的にご説明しましょう。
-
もし、お客様のアンプに「バランス・ボリューム」があるなら、左右のスピーカーの音量を変えてみてください。そうすることで、スピーカーの中央に定位しなければならない音が「音量の小さいスピーカー側」によると思います。つまり、「音量」は「定位」に関係します。さらに、左右のスピーカーの音量を同一にしておいて、「左右のスピーカーの距離をわずかに(数Cm程度)不均衡」に してください。スピーカーの中央に定位しなければならない音は、「距離の近いスピーカー側」によって聞こえるはずです。つまり「2本のスピーカーから出た音の位相差」が「定位」に影響を与えたのです。
-
更に、スピーカーの距離をずらしたまま、アンプのバランス・ボリュームを調整して「音が中央に定位」するように調整してください。バランス・ボリュームのつまみの位置は、ずいぶんと片寄ってしまうはずです。この実験で、「定位」には「音量差と位相差」が影響を与えること。「音量差」と「位相差」では、「位相差の方が定位に強い影響」を及ぼすことがわかるはずです。
-
録音時に、マイクによって録音された音は指向性を持つことをお話ししました。なぜなら、マイクで空気の振動を電気の振動に変換する部分は「面積を待った膜」で作られているからです。もちろん、この「膜」がなければマイクは「振動を電気信号」に変換できません。また、この「膜=マイク」を「音源に対して直角(多少の誤差は許されます)」に設置しなければ、「マイクのF特などを正確に保ったまま、音を電気信号に変換」することができないのです。このような構造上、マイクは「マイク=膜」に対して直交してくる音波に対しては感度が高く、並行方向から来る音波に対しては感度が低いのです。これは、つまりマイクは、前後方向の音は良く拾っても、左右方向の音は拾いにくいということを示します。
-
このように録音時に指向性を持ってしまった音を、「通常のバッフルを持つスピーカー」で再生する場合を考えてみましょう。このようなスピーカーから出る音は、「マイクと同じような指向性」を持ちます。コーン型やドーム型ユニットは前面に強く音波エネルギーを放射するからです。
-
つまり「マイクがとらえた広がりつつある限定された音場の情報」を、「再生時に、位相の相関関係をきちんと保って、そのまま広がって行くように再生」するには、2本のスピーカーの位置・角度関係を、リスニング・ルームに対してきちんとした「距離と角度の対称性」を持たせて設置しなければ、「音波の位相関係のずれを生じ」音場が上手く広がるはずがないのです。
-
話がかなり複雑になってしまったので、例えは適切でないかも知れませんが、もっと簡略に説明しましょう。2本のスピーカーから出る音を「投影される映像」、リスニングポイントを「スクリーン」とお考えください。2台の投影機(スピーカー)から投射される映像を、「スクリーン=リスニングポイント」にきちんと重ねて、結像させるためには、2台の投影機はスクリーンに対して「距離と角度の対称性」を「正確に保つ」必要があることはお分かりいただけると思います。このとき、もし何かがずれていて「スクリーン上の映像」がにじめば、「部屋のどこから見ても映像がにじんで見える」のは当たり前です。しかし、実は2本のスピーカーによる「ステレオ再生」でもこれとまったく同じ現象が起きるのです。
-
リスニング・ルームにおける2本のスピーカーの位置関係。さまざまな理由があって「理想的な位置に設置」できなくても、一度メジャーで測りながら、2本のスピーカーの位置関係が、可能な限り正確な対称性を持つように調整してみてください。驚くほど、広がり感や奥行き感が改善されるはずなのです。
-
私事で恐縮ですが、今年も慰安旅行は伊勢志摩に行きました。自然に触れるのは約一年ぶりだったこともあり、海の美しさや空気の綺麗さ、緑の瑞々しさなど、目に見える自然のすべてが美しく、愛おしく感じられました。自然に触れることで、都会にいては忘れがちな感動を思い出すことができたのです。
-
私にとって「良い音楽を聴くこと」とは、自然に触れるのと同じ意味を持ちます。年齢と共に、「そういう気持ち」が大きくなってきましたが、それは、「綺麗な景色や星を見たい」と思ったり、「たまには自然の中で生活したい」と感じる気持ちとたぶん同じなのだろうと思います。
-
子供の感性は「素直で美しい」といいますが、それは、「心の感動を感じるセンサー」が、「社会が造りだしたつまらない価値観でゆがめられる」ことなく「公平」に開かれていて、「感動」を「ありのまま受けいれることができるからだ」と思うのです。
-
確かに、人間は経験を重ね、成長すると共に感動を感じるセンサーの数も増えて行くでしょうが、「心のセンサーの感度が偏ってしまえば」受け取れる感動の「情報も偏って」しまうでしょう。そうなれば、せっかく開いたセンサーの多くも「偏ったセンサーからのピークを持つ情報にマスキングされて」その機能を失い、その結果、「自分自身の主観に基づく単一的な見方でしか物事を判断できなくなる」恐れがあると思うのです。
-
例えば、「ダイヤモンド」があったとして、その価値を判断するとき「ダイヤモンドの金銭的価値」を知る前と、知った後ではどのように「感動」が違うかといえば、「知る前は単にダイヤの見かけの美しさ」のみでその価値を判断したでしょうが、「知った後ではそれを所有することによって得られる金銭的価値や・名誉・地位」などという、「ダイヤ本来の美しさとは無関係」な基準によって「その価値感がゆがめられてしまう」可能性があるのです。そうなれば、たとえ「ガラス球」が「ダイヤの原石」より美しかったとしても、「絶対にガラス球に価値を見いだす」ことはできないでしょう。こうなってしまっては、「もはや子供のように素直に感動する」事などできないように思います。
-
しかし、もし「このような人間がゆがめてしまった価値観にとらわれることなく」多くの「感性のセンサーを公平に開く」ことができて、物事の「本質」を素直に感じ取れるなら、「人生は更なる感動と、発見に満ちた有意義な時間」となるでしょう。
-
私にとって、「多くの感動チャンネルが公平に開かれている音楽を聴くこと」はあたかも、大自然に触れた時と同様に「センサーの偏り」を修正し、「心に新たな感動のチャンネル」を開いてくれるのです。
-
ですから、私はオーディオ機器の開発、販売に携わる者の責任として、「可能な限り多くの感動のセンサー(チャンネル)」を開く努力を怠らず、常に「そこから得られるデーター(感動)を公平に重み付けすること」が出来なければならないと思うのです。
-
なぜなら、もし、このような立場の人物が、「特定の偏った感動のセンサー(チャンネル)」でしか物事を判断することができず、「開発者の好みだけで音楽をねじ曲げてしまった」ならせっかくの「名演奏」も「ただの茶番劇」になり、「その音楽を聴くこと」により開かれるはずだった、「心の感動チャンネル」を閉ざしてしまうからです。オーディオ機器により「音楽を取り扱う」ことの「責任」は非常に重いのです。そして、「より多くの人を感動させることのできる音」を作り出すために、開発者がまず知らねばならないことは、「人間とは一体何物であるか?」ということであるのは疑いのないことだと思います。
-
ただ最後に付け加えておきたいのは、ここまでのお話はすべて「私が考える音楽と自分との関係」あるいは、「開発者」としての姿勢であって、「お客様=リスナー」から見たオーディオは違う形であっても良いということなのです。
-
「趣味」を通じて「自分自身を高める努力」をすることはとても大切なことだと思います。私自身も「さまざまなことを音楽から」学び取ることができました。しかし、それはひとえに「同じ音楽を愛する友人」と「良きアドバイス」に恵まれていたからです。
-
今年四月、リニューアルオープンさせていただいた「新三号館」には、「お客様と音楽の出会い」のための「多くの窓(チャンネル)」が開かれています。また、お客様同志、「談話」していただけるスペースもご用意してございますので、是非お気軽にお立ち寄りください。