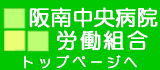|
|

2月13日、洞部落フィールドワーク
~天皇制による被差別部落の強制移転の歴史を学ぶ~ |
2月13日、奈良県橿原市にある洞部落フィールドワークを行いました。この洞部落は、今から 90年ほど前に、〝被差別部落が初代天皇・「神武天皇陵」を見下ろす場所にあるのは恐れ多い〟という理由から、村ごと現在の大久保町に移転させられたという歴史を持つ部落です。「天皇制と部落差別」という、まさに身分制の頂点と最底辺の関係を象徴的に示している場所です。 90年ほど前に、〝被差別部落が初代天皇・「神武天皇陵」を見下ろす場所にあるのは恐れ多い〟という理由から、村ごと現在の大久保町に移転させられたという歴史を持つ部落です。「天皇制と部落差別」という、まさに身分制の頂点と最底辺の関係を象徴的に示している場所です。
フィールドワークは、部落解放同盟奈良県連大久保支部の辻本さんに 案内していただきながら、まず「神武天皇陵」、そして畝傍山のふもとの洞村跡地を散策し、そして現在の大久保町にある「おおくぼまちづくり館」で展示とビデオ上映を通じ強制移転の歴史を学びました。以下、報告です。 案内していただきながら、まず「神武天皇陵」、そして畝傍山のふもとの洞村跡地を散策し、そして現在の大久保町にある「おおくぼまちづくり館」で展示とビデオ上映を通じ強制移転の歴史を学びました。以下、報告です。
「神武天皇陵」へ
まずは「神武天皇陵」へ向かう。きれいに整備された参道を通って陵の正面にたどり着くが、この 通っている参道の場所とて昔は洞村の田畑や住居があった場所のはず。 通っている参道の場所とて昔は洞村の田畑や住居があった場所のはず。
「神武陵」の正面に到着。江戸末期まで、寺の土台の跡で、30センチほどの小山にすぎなかった場所が、初代天皇陵とでっち上げられてから、整備と拡張(被差別部落の移転も含め)を重ねて、現在の姿になった。「ここでは今も身分制が生きつづけている」と辻本さんは語る。正面手前の鳥居から先は勅使(天皇の使者)以上の身分でないと入れないし、さらに奥の鳥居の先へは、天皇と皇后しか入れないそうだ。天皇の即位時や、皇太子の結婚時にも直接の参拝があったが、皇室が海外旅行に行くときにも勅使が安全祈願で参拝に来るとのこと。本当にここに初代天皇が眠っていると思っているのだろうか?おもわず聞いてみたい気持ちにかられる。
洞部落の跡地へ
続いて、「神武陵」の参道から横道に入り、畝傍山に向かって、なだらかな山道を登っていく。このあたりが旧洞部落。
洞村の強制移転は、被差別部落の痕跡を残さないように、徹底的に行われた(墓まで掘り返した)。だからかっての村をしのべるようなものはほとんど残っていない。かろうじて当時使 われていた共同井戸が残っている。 われていた共同井戸が残っている。
さらに上っていくと、江戸時代末期、神武陵をどこかに決める際に、現在の場所(「神武田」=ミサンザイ)よりも一時期、有力な候補地であった丸山に着く。目印の宮内省の石柱が数本立っているが、候補からはずれ、今はひっそりと山中で放置されている。それにしても、「神武陵」になるのとならないのとでは、えらい違いだな、と実感。

おおくぼまちづくり館で歴史を学ぶ
現在の大久保町の古民家を改築して作られ た「おおくぼまちづくり館」。洞村の強制移転の歴史の展示や、洞村の産業であった「下駄表づくり」「靴づくり」の資料展示を見る。大久保支部の人たちを中心にした、強制移転の歴史を伝える取り組みが行政を動かして、この資料館に結実したことに、敬意を強く持った。 た「おおくぼまちづくり館」。洞村の強制移転の歴史の展示や、洞村の産業であった「下駄表づくり」「靴づくり」の資料展示を見る。大久保支部の人たちを中心にした、強制移転の歴史を伝える取り組みが行政を動かして、この資料館に結実したことに、敬意を強く持った。
この部落が、「神武陵」によって、今も昔も日常的に天皇制に向き合っている場所であることがよく理解できる企画でした。
|
| (2010年3月3日) |
|

|