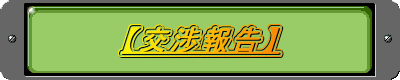
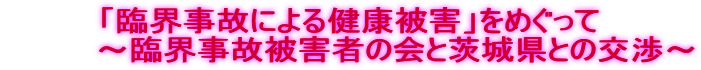
まず第一に、健康診断の基本方針について、とりわけ「健康被害はあり得ない」という前提のもとに健康診断を行う県側の基本姿勢に抗議が集中した。大泉代表は、「健康診断のお知らせ」の中に「健診は放射線の影響を検知することが出来ない」ことを前提として、「周辺住民の日常生活に一般的な助言を行うために当分の間行う」と記されていることに強く不満を表明し、「現に被害を受け、病院通いをしている人たちがいることを県は知っているのか、私たち被害者のことを真剣に考えているのか」と強く迫った。また、「健康被害がないとする根拠を示すこと、健診の内容とその結果を公表した上で、被害者団体、周辺住民とともに、基本方針について改めて検討し直すこと」を要求した。
これに対して県側は、「国の健康管理委員会」が出した結論を唯一の根拠としていることを繰り返すのみであり、県の「JCO事故対応健康管理委員会」としては放射線の健康への影響については、何の検討も行っていないことを明らかにした。
住民側からは、「あらかじめ影響はないと結論づけている健診を誰が受けに行くのか」「現に事故による被害を受けて病院通いをしている人たちがいることを県は知っているのか」「これまでの公害でよくあったように偽患者扱いするのか」などの怒りの声がぶつけられた。
県側は、「被害を訴えて病院通いをしている人数は2〜3名と把握している」「健診は当分の間ではなく、受診者がいる限り永久に続けたい」との回答を行った。
相沢村議は、「被害の訴えを重く受け止めるならば、最低限『健診のお知らせ』にある『被害はない』とする文言を削除するべきでないか」と県側に強く迫った。
大泉事務局長は、健診のデータの公開を求めた。「阪南中央病院の調査では、被曝線量の大きい人程、自覚症状を訴える人が多く、また事故後、身体の調子が悪くなったとの実感を持っている人が多いとの結果が出ているが、県の健診ではこのような問題に対して一切データを公表していない。健診の際にきちんと問診を行っているのかどうか」と追及があった。
これに対して、県側は「自覚症状などの調査は行っていない。問診などで健康不安を訴える者については、健康相談や県が実施している心のケアの活用を勧めている」との回答がなされた。
それでは、「PTSD(心的外傷ストレス症候群)であるというのか」との追及に対しては、『内科医として心の問題だと考えられる』者が若干いたということでフォローを行っており、専門的にPTSDの診断があったわけではない」として逃げの姿勢を見せた。健診のデータについては、調査の上、検討して改めて回答することになった。相沢村議からは、「内科医が心因性であるとするものと、専門家がPTSDであるとするものとの、それぞれの診断基準を明確にした上で、それぞれへの対応の内容をはっきり示して欲しい」との強い申し入れがなされた。
県が事故当日測定した中性子線量の数値が、国の線量評価を大幅に上回っている点についてデータを突きつけて回答を求めたところ、「担当課が違うので回答できない」ということで、原子力対策課から改めて回答するよう連絡することになった。
また、「健康への影響がないとする国の健康管理委員会の報告は、2年以上前のもので、しかも委員会はすでに解散してしまっている。現在では、県のJCO事故対応健康管理委員会が、住民の健康被害の調査について最高の責任を持っているのではないのか。にもかかわらず、中性子の人体影響についての、その後の新しい知見については、何ら検討していないのは無責任ではないのか」とただした。そして、国の健康管理委員会の主査代理であった佐々木正夫氏自身が、学会・シンポジウムや学術雑誌の論文などの場で、「中性子の人体影響評価が未知の領域にある」ことに言及すると共に、「今回の事故の被曝者の末梢血リンパ球の染色体異常の有意な上昇が検出され、中性子の線質係数は予想外に高いことが実証された」とし、また「最近の照射実験からみて低線量域での中性子の生物学的効果は従来考えられてきた値よりもかなり高く、RBE50〜70という値もえられており、国際的基準であるICRPの中性子の実効放射線荷重係数を見直さなければならない」としている事実を資料として突きつけた。
県の側は、「そのような論文のあることを今、初めて知った。対応委員会に持ち帰って検討したい。しかし影響がないとする国の結論を根拠としてやってきたので、国の側ともよく相談してみなければわからない」など、あやふやな答弁に終始した。
交渉を通じて明らかになったことは、県としては、県民の被曝という事実に、真剣に取り組む姿勢が全くなく、国の結論にあぐらをかき、ただ住民の目をごまかすためだけに健診を行っているということだ。現に健康被害を訴えている被曝被害者に対して、どう対応していくのかについても、何ら具体策を持ち合わせていないことが明らかとなった。
しかし、被害者の会から住民の強い不満や不安の声を粘り強くぶつけた結果、健診は毎年継続して実施することが約束された。また「健康被害は出ない」という文言の削除を検討すること、身体異常のデータがあるかどうかを再調査し、公表を検討すること、被害者への補償を検討すること、県の測定データと佐々木論文に対する評価を行うこと等々について約束せざるを得なくなり、次回交渉での回答ということになった。今後とも具体的な成果獲得のために、被害者の会への支援を行っていきたい。